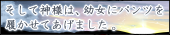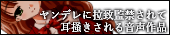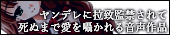セレナーデ ――C-dur――
彼の音楽が私を愛撫する。それだけで私は幸せ。
新学期、春。恋の季節。
だが私は、高二にもなっていまだに恋をしたことがない。それは誰かと両想いになったがないという意味ではない。初恋自体がまだなのだ。友人にそのことを話すと軽いノリで笑われてしまうが、私にとっては深刻な悩みだった。
一度くらい、誰かを好きになるという経験をしてみたい。
そもそも私は、あまり異性に興味がないらしい。友人から「好きなタイプの男子に注目していればいいんじゃない」とのアドバイスを受けて考えてみても、身長、顔立ち、性格、どれもこだわるべき対象ではないように思えて興味が持てない。私は誰でもいいから好きになりたいのだ。それとも、そんな心構えが良くないのだろうか。
そんな私にも、恋している「もの」くらいある。それは音楽だ。自分自身、作曲を趣味としており、作った曲を動画サイトに投稿している。自惚れかも知れないが、高校生にしてはいい曲を作る方ではないかとひそかに思っている。
私が作るのはいわゆるDTM(Desktop
Music)で、シーケンスソフトを使用してパソコンで楽曲を作成する。小中学生の時はピアノを弾きながら作っていたのだが、あいにくあまり演奏が上手でなく、次第にDTMに転向していった。DTMならどんな高度な曲でもパソコンが完璧に演奏してくれるので、その点は安心なのだが、どうしても電子音では表現できない音や雰囲気がある。今は少しでも思い通りの音を出せるように、細かい情報をいじる技能を身につけている段階だ。
家に帰ると、真っ先に動画サイトをチェックする。別にネット中毒だからではない。私の音楽動画に対してコメントが付いたかどうかが気になって仕方ないからだ。クリエイターとして、やはり自分の作品が評価されるかどうかは大問題である。
「来た」
久しぶりのコメント。私はわくわくしながら視線を走らせる。
『綺麗なメロディーなので、一回聞いただけで気に入ってしまいました。よく見たら、僕と同い年なんですね。良かったら今度、僕のページにも来てください!』
へえ、と無意識に呟きが漏れた。同い年なんだ。珍しいと思いながら彼のページへと続くリンクにカーソルを合わせた時、タイミング悪く母がやってきた。
「お父さんが帰ってこないうちに、お風呂入っちゃいなさい」
「えー、あとじゃだめ?」
明らかに不満を含んだ返答が気に障ったのか、母は少しむっとした表情で、
「今すぐよ」
とだけ言って去って行った。今すぐにでも彼のページを見に行きたいところだったが、いかんせん母には勝てない。仕方なく一旦パソコンから離れた。
そして、風呂から上がってパソコンの部屋に行くと、会社から帰ってきた父がパソコンで仕事をしていた。本当にタイミングが悪い。
「お父さん、お仕事、いつ終わる?」
舌打ちしたい気持ちを抑えて訊いてみると、父は目尻を下げて「今日は一時には寝るよ」と訳の分からない返事をよこした。父は私が父を気遣っていると思ったらしい。
今日彼のページに行くのは諦めた。遺憾だ。
翌日、教室で、私は信じられない言葉を聞いた。
斜め前の席の男子が、もう一人の男子にこんなことを言っているのだ。
「昨日さー、僕と同い年で作曲してる人の動画見つけたんだけど、結構いい曲なんだよね。コメントしてきちゃた」
私はちょうど登校してきたばかりで、肩にかけたスクールバッグを降ろすのも忘れて聞き耳を立てる。
「僕も作曲には自信あるけど、あの子に勝てるかって訊かれると微妙なラインだな。まあ負けてはいないと思うけど」
「出た、ナルシ発言!」
「うるさいなあ、クリエイターってのはちょっとくらいナルシの方がいいんだよ」
同い年で作曲してる人だったら他にもいるし……。でも、もし「あの子」が私のことなら、彼は私と同じ趣味を持つ仲間だ。普通に高校生活を送っているだけでは、なかなかそんな人には出会えない。友達になりたかった。
真偽をはっきりさせよう。
「あの、それ何て曲?」
突然会話に割り込んできた私を不審そうに見つめながらも、彼は答えてくれた。
「『独りぼっちの天使』って曲なんだけど……どうしたの?」
それからのことはよく覚えていない。授業も上の空で受け、今こうして帰宅しパソコンの前にいる。
確かなのは、『独りぼっちの天使』が私の曲だったこと、彼がコメントの主だったこと、そして、彼が私に告白したこと。
うん、最後、意味分からない。
思い出すだけでも、胸がむず痒くなるようだ。
『僕と付き合ってください!』
『は?』
『あなたの音楽に惚れました! 何て言うか、ぞくぞくしたんですよ。僕と組んだら、きっと最強の作曲コンビができると思います! どうですか?』
『どうですかって言われても……』
今年一緒のクラスになって初めて彼を知った私にとって、彼は「少し小柄な斜め前の男子」くらいの存在だったのだ。そんな相手の告白にいきなりイエスと答えられるほど、私の恋愛経験は豊富ではない。いや、正確に言えば、無い。
その場では「考えておきます」程度に交わしたが、あまり待たせるわけにはいかない。だが、恋愛経験値ゼロの私には、まだ、その、コイビト、になる勇気がない。だからと言って無視しておくわけにも――。
と、そんな風に堂々巡りをしているうちに、パソコンが立ち上がった。何はともあれ、まずは彼の音楽を聴くことにしよう。
リンクをクリックし、彼のページを開く。まっ先に目に入ったのは、『メタル戦隊メダレンジャー』という曲名。
何だこれと苦笑しつつ、気になるので一番に聴いてみることにした。
金が全てさ
金さえあれば
みんな幸せになれる
刹那の夢を届けにゆこう
バブルが崩壊するまで
メタル戦隊メダレンジャー
メタル戦隊メダレンジャー
サビがこれだ。思わず噴き出した。
彼が歌っているようだが、これがなかなか上手い。しかし、金……。どうやら、この歌の中ではメダル=小銭らしい。
歌詞もメロディーも、プロが作った曲に引けを取らないほどのインパクトを持っている。細かい技術はまだ未熟だが、「印象力」とでも言うべきエネルギーは凄まじい。バックで流れる絶え間ない一六分音符の応酬が、ただでさえ印象に残りやすいこの曲を、さらなる洗脳ソングへと昇華させているようだ。
二番のサビが終わると一転して可愛らしいオルゴール調の音になり、曲調も静かになる。いわゆる大サビというやつだ。
大人は忘れている
もっと大事な煌きを……
「今まで散々金金言っておいて、最後は綺麗に持っていくんだね」
つい突っ込みを入れてしまう私。そのままサビへと続く。
金が全てさ
金さえあれば
みんな幸せになれる
ここで一つずつ音が上がった。何の予告もない、悪戯のような転調。その瞬間、私の中をぞくぞくとした何かが駆け巡った。
無限の夢を届けにゆこう
バブルが崩壊しても
メタル戦隊メダレンジャー
メタル戦隊メダレンジャー
何だろう、この感覚……。
手足が震えているのが分かる。ひどく恥かしい思いをした時のように、全身の血が熱を帯びている。
私は感動していた。
こんなふざけた歌に、感動させられてしまった。
メダレンジャーの余韻に浸る間も惜しんで、私は他の曲を聴きに行く。もっと彼の音楽に触れたい。もっとこの悦びを感じていたい。そんな単純な欲求が私を突き動かした。
そうか、これが恋なのか。
こんなに胸がどきどきして、顔が火照るのだから間違いない。これは恋だ!
彼が今朝言っていた「ぞくぞくした」という言葉の意味が、今なら分かるような気がする。彼もこうして私を好きになってくれたのだ。
彼が私を好きで、私も彼が好き。だとすれば、迷うことはない。
『私も惚れました。付き合ってください』
本音をそのまま書きこんだ。
……。
告白の返事をネットの大衆に晒してしまったということに気づいたのは、その数秒後のことである。
翌朝彼に会うと、彼は微笑んでいるのだかにやけているのだか分からない笑顔で話しかけてきた。小声ではあったが、「昨日は大告白ありがとう」、と。
からかわれているのかも知れない。だが、私はもっと大きな疑問に悩まされていた。
彼氏・彼女の関係になったからと言って、一体何をすればいいのだろう。
私は素直に、自分が恋愛初心者であることを告げ、彼に頼ることにした。気さくそうな彼のことだから、きっと恋のABCも熟知しているのだろうと信じて。
ところが、返ってきた答えは意外なものだった。
「ごめん、僕もこれが初恋なんだ」
「え?」
私と彼は、顔を見合せて笑い出す。
「なあんだ」
「僕たちって、似た者同士なのかもね」
彼が初めて好きになった人間が私だなんて。
私は嬉しさのあまり、人生捨てたものじゃないなどと湧き立った気持ちになった。耳が赤くなっていなければいいけれど。
「で、最初は何したらいいの?」
照れ隠しに訊くと、彼は携帯電話を取り出して、
「まずはメアド交換じゃないかな」
と教えてくれた。そう言えば、まだお互いのメールアドレスも知らなかった。
私たちは、親睦を深めるために共同で歌を作ることにした。テーマは「壮大な愛の詩」。私が歌詞と旋律を手掛け、彼が伴奏をつける。この分担は、繊細な表現を得意とする私と、曲を盛り上げるのが得意な彼の長所を活かしたものだ。
とにかく、まずは私が基盤を作らなければ始まらない。彼のことを想いながら歌詞を考える。
一番伝えたいのは、今まで恋愛感情を抱けなかった私にとって、この気持ちがどれだけ大切なものかということ。本当に、一生恋ができないのではないかと危惧していたくらいだから、そんじょそこらの恋心とはわけが違うのだ。少しくらい誇張してみてもいいだろう。
考えること二時間。ようやく歌詞が出来上がった。タイトルは『今この世界で貴方を愛している奇跡』。……ちょっと中二病っぽいかな?
次に、壮大な愛にふさわしい、シリアスで神秘的な雰囲気を目指してメロディーを作る。ああでもないこうでもないと、旋律を創り壊し組み立てる工程が好きだ。一度始めるとやめられない。
「できた」
時計を見ると、もう朝の六時を回っている。いけない、つい徹夜してしまった。でも、満足のいく歌ができたことを考えると、一夜漬けの疲労でさえ心地よい。
私はUSBメモリーにMIDIデータ(メロディー)と文書ファイル(歌詞)を入れ、颯爽と学校へ、いや、彼の元へと向かったのだった。
彼からメールが来たのはその日の夕食の最中。
『曲聴いたよ! 最高だった! 綺麗すぎて鳥h』
……?
三分後、またメールが来た。
『ごめん、興奮のあまり途中で送っちゃった。綺麗すぎて鳥肌たったよ! こんな歌に伴奏付けられるなんて、考えるだけでぞくぞくしてきた。……それに、この歌詞、嬉しかった。ありがとう。僕も愛してるよ(マジで)』
携帯電話を見つめて一人微笑む私は、きっと家族からは怪しい娘に見えただろう。間違ってメールを送信してしまう彼が可愛くて、にやけが止まらなかった。何より、尊敬している彼が私の音楽を認めてくれたことが嬉しかった。私が渡したMIDIデータを聴いて喜ぶ彼の顔を想像すると、もう愛情としか呼べない歓喜が沸き起こってくるのだった。
それと同時に、私はまだ彼の顔を覚えていないことに気づく。恋人の顔も覚えていないなんてという呆れと、顔を覚えていなくても恋愛感情は成立するのだという驚きをいっぺんに感じた。
彼もそうだと思う。彼はきっと、私の顔を覚えていない。もしかしたら名前さえも。彼にとって、私は異性である前に「音楽」なのだ。それは少し淋しいが、たとえ音楽から入った仲だとしても、いずれ本当の恋人になれるはずだと信じていた。
次の日、彼は遅刻してきた。
授業が始まっても現れない彼を心配していた私は、とりあえず彼の登場に安堵する。しかし、ただの寝坊ならいいが、具合が悪いのなら? すぐ斜め前にいるのに、授業中であるがゆえに声をかけられない葛藤。早く彼と話がしたかった。
「どうしたの、朝?」
授業が終わってすぐに訊いてみた。彼は「ちょっとね」と口ごもり、バッグから何かを取り出す。それは携帯音楽プレイヤーだった。
「伴奏つけてきた」
イヤホンを差し出しながら笑みを浮かべる彼に、私は絶句した。まさか、伴奏をつけるために遅刻してくるなんて。
「ありがとう、一日で作ってくるなんてすごい」
「そっちこそ、一日で歌詞とメロディー作ってきたじゃない」
早速イヤホンを耳にはめ、彼に再生ボタンを押すように促す。ややあって聞こえてきたのは、美しいストリングスの前奏だった。彼は派手な曲が得意だけれど、こんなしんみりとした曲も作れるんだ。感心している間に、前奏はAメロへとつながっていく。フルートの音で表わされている歌のメロディーと、幽玄の美とでもいうべき繊細な伴奏が見事なハーモニーを生み出していた。
「すごい、別の人が作ったなんて分からないくらいマッチしてる」
「やっぱり僕たち気が合ってるんだよ」
彼はそう言ったが、私はそれだけではないと思った。気は合っているかもしれないが、私と彼の曲調は普段は全然違う。それが今こうして自然に合成されているのは、やはり彼の類まれなセンスがあったからだ。彼に対する愛情と憧憬と、そして少しの羨望が胸を締め付けた。
いよいよサビに入る。私はいっそう耳を澄まして聴き入った。
――来た!
ぞくぞくと脳天へ駆け上がる感覚。これが堪らない。彼の曲は必ず私に喜びを与えてくれる。だから彼が好き。彼の音楽さえあれば、私はいつだって幸せになれる。もしかしたら、彼を音楽と同一視しているのは私の方かもしれない。それでも私は彼に恋しているのだ。
音楽の世界があまりに美しすぎて、私は後奏が終わっても現実に帰ろうという気にならなかった。哀しみや痛みがあふれる現実世界と比べたら、純粋な美によって構成される音楽の世界は何と清らかで愛おしいことか。
ある日、私は彼にデートを申し込んだ。普通男性側が誘ってくれるのを待つものなのかもしれないけれど、そろそろ作曲仲間から真の恋人へと関係を進展させたかったのだ。
彼は少し戸惑ってからOKしてくれた。戸惑いの意味が分からなくて不安だったが、目的地を決めたりしているうちにそんなことは忘れてしまった、
行き先は最近オープンした動物園。彼は初め音楽に関するところに行こうと提案したが、私はたまには音楽抜きで、二人の男女として行動してみたかった。割引券を持っていたこともあって、彼は動物園で了承してくれた。
さて、何を着て行こうか。
普段めったに外出をしない私は、ましてやおしゃれなどまともにしたことがない。女の子らしい服など全然持っていなかった。仕方なく、私は新しい服を買いに行くことにした。少しでも彼に女性として好きになってもらいたい一心で。
私が待ち合わせ場所に着いた時には、すでに彼がいた。それも当然、約束の時間を十五分も過ぎていたのだから。
「ごめん、遅れちゃって」
「あと五分待って来なかったら電話しようと思ってた。どうしたの? 道に迷った?」
「そんなところ」
髪型をいじっていて遅れたなんて、申し訳なさ過ぎて言えない……。
「じゃあ、行こうか」
私はうつむいたまま彼についていった。いざおしゃれをして外を歩くと、変な緊張感がある。いや、それ以上に違和感があることがあった。いつもはおしゃべりな彼がなにも言わない。気になって顔をあげてみると、彼は私をガン見していた。
「ど、どうしたの?」
さすがの私も動揺してしまう。彼は一瞬びくっと身じろぎすると、苦笑しながら言った。
「いや、何だかいつもと雰囲気が違うなと思って」
「まあ、今日は私服だし……」
私服、どころではない。初めての女の子らしいおしゃれだ。でも、彼が苦笑しているところを見ると、このファッションには欠陥があるのかも知れない。何がいけないのか、分からないのが怖い。
動物園でのデートはあっけないものだった。デートというよりは、ただの動物園めぐりといったほうが正しいような気もする。私は、彼と手をつないでゆっくりと園内を歩くイメージでデートに来ていた。だが実際には、彼は気になる動物を見つけると私を置いていってしまう。もちろん遠くには行かないが、それでもすぐ隣にいたはずの彼が後ろで巨大なトカゲを見ているのに気付くと、何とも言えない虚無感が私を襲った。そんな子供のような彼も、また可愛いのだけど。
私はその時、愚かな夢見る少女でしかなかった。
動物園から出たころ、空は茜色に染まっていた。同じように赤く染まった彼の姿が、幻想的な危うさを醸し出している。今にも掻き消えてしまいそうな。
「あのさ」
彼は私に背中を向けたまま話しかけた。
「うん」
私は特に何も考えずに相槌を打った。その後に続く言葉も知らずに。
「僕たち、別れたほうがいいの、かも」
「……え?」
思いもよらないその言葉に、私はただ立ち尽くす。
「どうして? 私のこと、嫌いになっちゃったの? それならそうとはっきり言ってよ。理由を聞かなきゃ、意味が分からない」
何がいけなかったの?
動物園? 服装?
いつからそんな風に思ってたの?
私がいけないの?
「僕はきっと、恋をしていなかったんだ」
彼は振り返って私を見た。哀愁と憐憫が混ざり合った瞳だった。
「どういうこと?」
「僕たちの出会いは音楽だったよね。僕は『独りぼっちの天使』を聴いた時、てっきり自分は恋に落ちたんだと思ってぬか喜びしちゃった。その上、告白まで……。でも本当は、ただ単に音楽が好きだっただけなんだって、今日のデートではっきりしたよ。僕は二人の間に恋愛関係を求めてはいなかったんだ。僕は恋人であることを望まれても、偽りの愛しかあげられない。だから」
「別れるんだね」
「……ごめん」
恋することの難しさはだれよりも知っている。好きになれと言われて好きになれるものではないから、彼に何を言ったって、彼が私を恋愛対象として見られないという事実は変わらない。でも、一つだけ確かめたい。
「今でも、私のこと、好き? 恋人じゃなくて、作曲仲間としてなら」
彼はこの上なく優しい表情で微笑んだ。
「好きだよ。間違いなく、世界で一番」
彼は私を最高の友人と認めてくれた。それはとても光栄なことだ。
しかし、私を愛してはくれないのだ。彼の前では、私は女ではなくなるのだ。
恋って、本当に儚いんだね。
真っ暗な部屋で、私はイヤホンをつけてベッドに横たわっている。もちろん聴いているのは彼の曲。愛してやまない彼の音楽。
彼と私は友達になった。今でも関係は続いている。互いの作った曲を聴き合い、アドバイスをし合って高め合う、唯一無二の親友である。
彼はもう、恋人として私を見ない。彼の前では性別を捨て、作曲家としてのみ私は存在する。だが、私は彼への想いを失くしたわけではない。私はまだ、彼に恋している。
それを不幸だとは思わない。実らない恋であっても、恋心を抱くことに意味があるのだ。こんなに誰かを愛せる私は、心の温かい「ひと」なのだと安心できる。恋ができなかったころの自分は、冷たい無機物と何ら変わりのない、つまらない「ヒト」だったのだから。
だからこそ、私を「ひと」にしてくれた彼を、変わらぬ気持ちで愛している。どんなに愛しても、彼が私を愛することはないと知りながら。
代わりに私は彼の音楽に愛してもらうのだ。彼の音楽が――彼が、私を優しく包み込み、抱きしめてくれる。
彼の音楽が私を愛撫する。それだけで私は幸せ。
これは高校文芸部の部誌の引退号に載せた作品です。
執筆当時のあとがきのデータが残っていたので、修正したものを掲載しておきます。
~あとがき~
本気で恋愛小説を書いてみようと思って書いたのが本作です。
「私」と「彼」の名は出さず、その上二人称も使わないという制約を自分に課した、苦しみながらの執筆でした(汗)
僕を知る方は、「私」は僕がモデルだと思われるかもしれません。それは半分正解で、半分はずれです。確かに趣味が作曲で、初恋がまだなのは同じですが、基本的な性格はどちらかというと「彼」の方が僕に近いです。
曲を聴いて「ぞくぞくする」というのは実体験に基づいています。僕にそのような感銘を与えてくださったのは下村陽子さん(主にゲームミュージックを担当する作曲家)でした。とても壮麗な曲を作る方なので、死ぬ前に一度聴いてみてください。(布教布教♪)
あとは、『セレナーデ ――A-moll――』のあとがきでお話ししましょう。それではしばしのお別れです。読んでくださってありがとうございました。
※作中に出てきた『独りぼっちの天使』と『メタル戦隊メダレンジャー』の元ネタは、僕が作った曲です。でも作中に書いてあるほど素晴らしい楽曲ではありません^^;