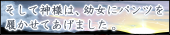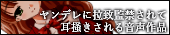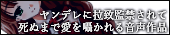マザー・コンプレックス
三十路を向かえて、四季を三回堪能しても、葵には結婚する気など露ほども起こらなかった。
結婚の先に待っているのは、家庭の構築だ。
葵は「家庭」というものを心底から嫌厭していた。
家庭にはいい思い出がない。
葵にとって、家庭は忌まわしい過去の象徴だった。キャリアウーマンとして生きる今からは誰も想像できないだろう。彼女が、古びたアパートの片隅で母の愛を必死に請う、みじめな少女であったとは。
葵の母は、徹底的に娘を否定し続けた。なぜそうなったのかは、葵の知るところではない。物心ついた時から、母は葵の幸福の一切を否定していた。子供にとって、母から受け入れられないというのは、耐え難いアイデンティティの喪失だった。
どんなに頑張っても、私は認めてもらえないんだ。
お母さんを喜ばすには、死ぬしかない。
私なんか死ねばいいんだ。
毎日そんな事を考えていたのにも関わらず、結局葵は死ななかった。単純に死が怖かったのである。死ぬべきなのに死なないでいる自分を臆病者と責め、ならばせめて出世して母を喜ばそうと、葵は必死に勉学に励んだ。しかし、どんな好成績でも、母は冷徹に言い放つのだった。
『こんなんで褒めてもらえると思ったら大間違いよ。あんたは何をやったって駄目。一生幸せになんかなれないんだから』
その言葉に反して、葵は大企業の幹部として活躍している。ただ、母親は葵が入社したての頃にアパートの階段から転落して首の骨を折り、あっけなく急逝してしまった。その時点で葵は、母を喜ばす機会を永遠に失ったのである。現在の地位は、当初の目的からはずれ、自分のプライドのために掴み取ったものだった。
お母さんが愛してくれなくても、私を必要としている人はいくらでもいる。
そうは思っても、他者の愛では母親のそれの代替にはならないというのもまた事実であるらしく、葵はどこか満たされない思いを抱えて生きていた。
そんなある日、上司にある縁談を持ちかけられた。
「私の知り合いの息子さんがねえ、今年でちょうど三十になるのだがね、そろそろお嫁さんをもらおうって事で、お相手を探しているそうだ。君、どうかね」
「は、私ですか」
「君もそろそろ、身を固めないとなあ。晩婚化が進んでいるとは言え、三十三はそろそろ焦るだろう」
「しかし、私はまだ仕事が」
「辞めろだなんて言ってないじゃないか。とにかく、会うだけ会ってみなさい」
上司の薦めをむげに断るわけにも行かず、葵はしぶしぶ見合いを引き受けた。
そんな彼女がそのまま結婚してしまうなど、本人でさえ予想していなかっただろう。
結果から言えば、葵は、上司の知人の息子、長瀬雄太と入籍した。しかも、職を辞して家庭の営みに専念すると言い出した。
その経緯について、葵は「雄太さんは勤勉で思いやりのある、素晴らしい人です。彼のためなら、家事に専念するのも悪くないと思ったのです」と説明している。だが、真相は違った。
葵は姑である長瀬竹に母の理想像を見出したのだった。
数回にわたる見合いで、葵は、絶対にこの小柄な初老の女性を母と呼ぼうと心に決めた。大の大人がそのような幼稚な願望を持つことに恥じらいを感じはしたが、その願望は既成事実として葵の胸に残り、忘れる事はできなかった。
竹の柔和な微笑みや、おっとりしたしゃべり方、さりげない気遣いの仕草こそが、まさに葵が求めていた母性であった。
雄太は葵を気に入り、葵も雄太を嫌いではなかったので、葵がプロポーズに応じさえすれば、結婚は難しい事ではなかった。
結婚生活は幸せだった。
何せ、雄太が出勤している間、葵は義母と二人きりになれるのだから。
舅は数年前に病気で亡くなったそうだ。竹の気持ちを思うと気の毒だったが、葵の独占欲はそれを好都合と捉えた。
葵はよく働き、竹に喜ばれた。
努力に応じて自分を評価してくれる。会社とは違う、人間のぬくもりを持った評価。かつて母からもらいたかった愛がそこにある。
きっと竹も自分の事を本当の娘のように思っているのだ。
そうでなければこんなに親切にしてくれるわけがない。
葵はそう思い込んで、竹を「お義母さん」ではなく「お母さん」と呼んでいた。
だが、もちろん竹の子供は雄太ただ一人だ。
長瀬親子と葵の間には、明らかな溝があった。
それは努力では埋まらない、共に過ごしてきた時間の差だった。
例えば、些細な事だが、夫婦をまとめて「雄太さんたち」と呼んだり、夕方葵と話をしている時に「雄太さん遅いわね」と呟いたりといった具合である。
葵は密かに夫を妬み、何故自分が竹の子として生まれなかったのか、毎日その運命を呪った。
――お母さんの子供は私だけでいいの。
雄太なんか消えてしまえばいい。
そう思っていた矢先、雄太と竹を乗せた車が事故に遭った。
ガードレールを突き破って、海へと転落したのだ。
幸いにも竹は救助されたが、雄太は見つからなかった。
文字通り、雄太は海に消えてしまった。
竹は脊椎を損傷し、寝たきりになった。その痛ましい姿に葵は涙し、その涙で雄太の死を悼むふりをした。
一方で、これからは竹も自分だけを見てくれるという期待があった。
お母さんの狭い世界にいるのは、私だけ。私がお母さんの対人関係を独り占めできる。私がこの人の唯一の家族なのだ、私がお母さんを守るのだ……。
ところが、葵と目が合うなり、竹は「死にたい」と呟いた。
「雄太がいないなら、生きていても仕方がないわ。私もあの子と一緒に死にたかった」
葵は心の中で何かが潰れたような気がした。
「私じゃ駄目ですか? 私がいるこの世界で、生きていこうとは思ってくださらないんですか?」
竹は、微笑んで言った。
「貴女は私の子じゃないでしょう?」
それからの事はよく覚えていない。葵が気づくと、そこには赤黒い血で染まったベッドがあった。そして、足元には、ぐちゃぐちゃに丸まった竹の遺体が転がっていた。
右腕の激しい疲労と、手についた血液が、全てを物語っていた。
葵は、愛する「母」の頭を、金属製のベッドの縁に何度も打ちつけたのだった。
何度も何度も、頭蓋骨が割れて中身が飛び出すまで、何度も。
この人も所詮私の母ではなかったのだ。
やはり私は、永遠に母に愛される事のない人間なのだ。
悲しみや罪悪感は不思議となかった。むしろ、母性の偶像を破壊する事によって、葵のマザー・コンプレックスは消滅したようだ。
竹の遺体は爽快なものだった。
葵は満足の表情を浮かべると、血にまみれた右手で受話器を取り、警察に電話をかけた。
熟女とヤンデレに若干の百合要素をプラスした萌え小説でした。