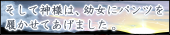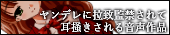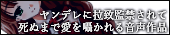『イルミナ』 中3の時書いたラノベ等身大すぎワロタww →企画トップページ
燃え盛る炎の中、崩れゆく紅蓮の世界をただ見つめる者がいた。その目が湛えるものは、愁いかそれとも憎しみか。どちらともつかぬ複雑な感情が、彼の心を過っていく。
全てが一瞬で逝ったはずだ。苦しむことも無く、幸福な時の内に――。
揺らめく炎が彼を飲もうとした。だが、もはやそこに彼の姿は無かった。
第一章 出会い、始まり
夜明けの光が部屋に差し込んだ。小鳥のさえずりが静寂を破り、村に朝の訪れを告げる。木々のおしゃべりが、光を受け止めて煌めく川面が、平和な一日を約束している。
「いよいよですね」
ファレーナは夫に声をかけた。
「ああ、あの子が十五歳になってしまった」
ダールが物憂げに応じる。
アンシェローク老夫妻は夕べ、一睡もしていなかった。いや、できなかったのだ。
「ねえ、あなた、止める事はできないの?」
ファレーナがダールの顔を覗き込んだ。灰色の髪が左右に揺れる。ダールはそれを見つめながら首を横に振った。
「あの子が決めたことだ。わしらが口を出してはならないよ。もちろん、できればずっとここにいて欲しいのだがね……」
全ては十年前、一人の男が現れた事によって始まった事だ。
出身地も身元も不明、そんな彼は、恐ろしい程の魔力とカリスマ性で次々と有能な部下を集め、遂には一国家と変わらぬ軍事力を持つに至った。その間わずか二年。いつしか彼は人々から「魔王」と呼ばれ、世界に君臨する事となる。彼自身は自らをバイゼンと名乗ったが、それが本名であるかは定かではなかった。
バイゼンが姿を現してから五年。彼は、何らかの理由でイルミナ族という種族の村を焼き滅ぼした。たった一つの魔法で、少人数だったとは言え、一つの種族をこの世から消し去ったのだ。しかし、彼は気付かなかった。自分の背後に、一人の少女が立っていようとは。アンシェローク夫妻の言う「あの子」とはこの、イルミナ族の生き残りの事である。
当時十歳だった彼女を、アンシェローク夫妻は養子にした。そして彼女は、のどかな田舎でほとんど悪に触れず育つ。ここからが他人にはなかなか理解しがたい所だが、イルミナ族にはもともと、悪という概念が無かった。その為、一族が滅ぼされた後も、少女は世の中には善人しかいないと信じ続けていた。ダールとファレーナは、何とかして彼女に悪を理解させようと様々な本を読ませたが、結局その効果は、彼女の文章力を高めるのみに留まる。こうして、今日に至るまで、彼女は悪を理解してくれなかったのだった。
「あんな無邪気な子が、旅に出るなんて危険だわ……!」
ファレーナが泣きそうになった、その時。
「おはようございます、おじいさん、おばあさん!」
部屋の入り口から、緊張感のかけらも無い声が聞こえてきた。そこに立っているのは、栗色の髪をした、小柄で肌の白い少女だ。声、顔立ち、体つき、それら全てが、十五歳というにはあまりにも幼過ぎる。立ち振る舞いもどこか子供っぽい。
「まあおかけなさい、メイ」
メイと呼ばれた少女は、素直にダールの言葉に従った。横にちょこんと置かれた荷物がファレーナの心を締め付ける。
「本当に、行くの?」
彼女はやっとそれだけ言った。
「はい! 五年間お世話になりました」
メイは気が付いていないが、そのあどけなさがファレーナの不安を煽り立てるのだ。
「あなたには……まだ早いと思いますよ?」
養母の言葉に、メイは明るく反論する。
「十五歳になったら自由にしていいって、約束したじゃないですか。ね、おじいさん?」
「あ……ああ……」
ダールは妻と養子との板挟みに合って、曖昧な返事をした。
「でもねえ、それは、十五歳になったらメイも大人になっているだろうと思ったからですよ。あなたったら、まだてんで子供じゃない。復讐なんて……」
ファレーナは困ったような顔でメイを見つめる。愛嬌のある――童顔。どう見ても十五歳と言うにはふさわしくない。じろじろと見られて、メイは赤くなった。
「で、でも、約束は約束です! それに、私は復讐のために旅に出るんじゃありません!」
「……え?」
夫婦は同時にきょとんとした。
「バイゼンと話し合いに行くんです。一番苦しんでいるのは、まちがったことをしてしまったバイゼン自身のはずだから。説得して、いい人になってもらいます!」
屈託の無い笑顔。仇さえも哀れむその優しさ。ダールとファレーナは、改めてメイという存在の美しさを思い知った。全ての人間がこんな風ならば、争いなど起きないのに。でも、現実は違う。
「メイ、それは無理だ」
そう教えてやりたかった。けれど、メイの笑顔を壊すのが、怖い。
二人が黙っている間に、メイは荷物を持ち上げていた。
「もう、行かなきゃ」
玄関へ歩き出す彼女に、ファレーナが手を伸ばす。その手を、ダールがそっと押さえた。
「行ってきます」
メイの姿が扉の向こうに消えた時、ファレーナはとうとう泣き崩れた。
「あの子がいない生活なんて、耐えられないわ!」
ダールはただ静かに、妻の肩を抱く。
「大丈夫だよ。あの子は優しいから。私達を悲しませはしない」
そう言う彼の目からも、涙が溢れた。
「絶対、生きて帰ってくる」
今や完全に目覚めた太陽が、哀しくも美しい世界を照らしていた。
いくつかの朝と夜が交互に過ぎた。メイが住んでいた老夫婦の家は相当な田舎にあったが、歩き続けたかいがあり、ようやく町に近付いてきた様だ。
その時、後ろから声がした。
「そこのお嬢さん、悪い事は言わないから、そこに荷物置いてきな」
振り返ると、そこにはぼろ服を着た四人の男が立っている。
「どうしてですかー?」
メイは恐れる事も無く、不思議そうに尋ねた。予期せぬ反応に、男たちは動揺する。
「どうしてって……。とにかく、金か何かよこせ!」
メイはため息を吐き、男達に哀れみの眼差しを向けた。
「そっかー、お金がなくて困ってるんですね? かわいそうな方々……」
その様子を陰から見ている少女がいた。
彼女は見るに見兼ねて、五人の前に姿を現す。
「あんた、何やってるんだ? ちょっと来い」
少女はそう言うと、メイの手を引いて男達の集団から連れ出してしまった。
男達はすでにやる気を無くしていた。だから、
「どうせ、あんなガキ、大した物は持っていなかったさ」
という事で全員納得し、メイと少女は追われる事もなかった。
ある程度行った所で、少女はメイに向き直った。十五センチは身長差がある。
「あいつらは盗賊だぞ。あんた、何のんきにしゃべってるんだ」
「盗賊……って、本当にいるんですか? 本の中だけの話じゃないんですね」
メイが真面目な顔で言った。呆れた少女は思わず溜め息を吐く。
「ここは無法地帯なんだから、あんたみたいな小さい子供がうろついてちゃ危ないの。次からは気を付けるんだな」
そして立ち去った。後ろでメイが、ぼそりと「小さい子供って……。もう十五歳なのに……」と呟いた事には気付かずに。
少女の名はクラリス・エヴェンズ。青い旅人用の服を見れば分かる様に、旅する少女だ。背はそれ程高くないが、後ろで束ねてある長い銀髪と、見る者に涼やかな印象を与える青い瞳が、大人びた雰囲気を作り出している。年はメイと一つしか違わないが、外見はほぼ大人だ。
彼女は今、仲間になってくれそうな魔導士を探している。しかし、自分で設定した条件が難しく、なかなか丁度いい人物が見つからない。
その条件とは、強いがクラリスに従い、また、クラリスが命令しやすい者であること。クラリスはいくら大人びて見えてもまだ十六歳なので、年上の人に命令するのは気が引ける。けれども、十六歳以下で強い魔導士など滅多にいるものではないのだ。
次の日、クラリスが歩いていると、どこから聞き覚えのある会話が聞こえてきた。
「お金ないんですかー? 大変ですね。でも、私もあんまり持ってなくて……」
声のする方に向かうと案の定、栗色の髪の少女が三人の男に囲まれているのを発見した。メイだ。
「またか……」
クラリスの脳裏に、腐れ縁という言葉が浮かぶ。
男達は武器を所持している様だが、クラリスにも剣術の心得があった。彼女は柄に手をかける。クラリスにしては珍しく、助けてやろうという気分になったのだ。
「そこの盗賊ども! やめろ!」
一番目つきの悪い男がクラリスを睨んだ。
「何だお前? 野郎ども、やっちまえ!」
クラリスは深く息を吸い込み、剣を抜いた。重いはずの剣をあたかも軽いかのように振るい、切りかかってくる敵を迎え撃つ。音を立てて跳ね上がる剣。武器を失った敵に手刀を食らわし、瞬く間に倒していく。
息を整えながらクラリスが振り向くと、ヘイゼルの瞳に涙を浮かべたメイが怯えた表情で後ずさりをしていた。
「ひどい……。お金のないかわいそうな人達を、こんな目に合わせて……!」
その言葉が少々気に触って、クラリスは顔をしかめた。
「違うだろ……。私はあんたを助けたの。こいつらは、昨日の悪者と同類なんだ」
途端に、メイの表情が明るくなる。
「そうだったんですか。ありがとうございました!」
ふと、メイはクラリスの左腕に目を留めた。
「あっ、けがしてるじゃないですか! 手当てしなきゃ!」
駆け寄ったメイの手が、クラリスの手に重なる。クラリスはその白さに驚いたが、表情は変えなかった。
「近くに町がある。そこの宿でするよ。生憎、包帯を切らしているんだ」
「私も行きます!」
だがメイは、すぐには歩き出そうとしなかった。倒れている盗賊たちを心配したからだ。
「放っておけ、そんな奴らは」
クラリスが言う。
「でも……」
メイはそっと千リーネ紙幣を男の手に握らせると、小走りでクラリスを追いかけ、一緒に町へ向かった。
宿でも、一部屋しか空いていなかったので、二人は一緒だった。
怪我の手当てをしているクラリスを覗き込む様にして、メイは聞いた。
「けが、痛くないですか?」
「痛くないって事はないけど、大丈夫だ。すぐ治るから」
「良かったー!」
冷静に言うクラリスとは対照的に、メイは安堵の溜め息をつく。が、突然悲しそうに言った。
「私、世の中に本当に悪い人がいるなんて思いませんでした」
それを聞いたクラリスは、思い出した様に顔を上げる。
「ねえ、ずっと気になってたんだけど、あんた何者?」
メイはいつもの明るい声に戻って答えた。
「メイです!」
クラリスは、そういう事が訊きたいのではない。質問を変えてみる。
「どこから来たんだ?」
「この町から南に六日くらい歩いた所にある、名もない田舎町からです。そこは故郷じゃないんですけどね……」
そう言ったメイの心に、イルミナの村の風景が浮かんだ。
「故郷って?」
クラリスは、半ばわくわくしていた。こんなナイーブな人間ができるなんて、一体どんな所だろう、と。
メイは短く答える。
「イルミナの村です」
クラリスは一瞬、時が止まった様に感じた。
実は、イルミナ族は本人たちが思っているよりも、ずっと有名だったのである。
昔、強大な魔力によって勢力を伸ばし、栄えていたイルミナ族。しかし五百年程前、何らかの理由で、同胞同士が戦争を起こし、多くのイルミナ族が命を落とした。
その後、イルミナ族は歴史から姿を消した。彼らは、時の中に魔法を忘れていったのだ。
これが、クラリスの聞いた話である。
今でも、イルミナ族の脅威は忘れられてはおらず、人々の間で噂が飛び交っている。例えば、イルミナ族は食用に竜を飼育するとか、イルミナ族は死人の肉を家族で食べるとか、イルミナ族には角があるとか、そういったものだ。もはや迷信に近い。だが人々は、イルミナ族に対して凶悪な魔法種族というイメージしか持っていなかったので、それらの多くは信じられていた。
だから、さすがのクラリスも平然としてはいられなかったようだ。
「イルミナ族は、魔王に滅ぼされたって聞いたけど……」
彼女は普通に聞こえる様に努めたが、やや声に落ち着きがなかった。
「そうですよ」
メイが言う。逆にこっちは落ち着いていた。
「五年前のあの日、私は薬草を摘みに、村はずれの原っぱに行ってました。そしたら、その原っぱと、村のはしっこにある私の家との間にバイゼンが現れて、村を……焼き払ったんです。私は驚いて村へ駆けもどりました。そこには、背の高い人が立っていて、揺れる炎をじっと見つめていました。そして、私には気付かず、シュッて消えてしまったんです。そういうの、瞬間移動って言うんですよね……」
やがてクラリスには、メイが落ち着いているふりをしているだけだという事が分かってきた。そして思った。メイはただの子供だ。凶悪でも何でもない、世間知らずの女の子に過ぎない。
それに加えて、クラリスはある可能性に気付いた。メイの力を利用するのだ。一般に、バイゼンがイルミナ族を滅ぼしたのは、彼らが自分達の持つ強大な魔力を自覚して、彼の敵に回るのを恐れたからだと言われている。ということは、メイもそれだけの魔力を秘めていると言う事になるはずだ。
メイは年下で、クラリスの条件にも当てはまる。これは、利用するしかないだろう。
「じゃあ、あんた、復讐の旅に出たという訳だな」
クラリスは急に愛想を良くした。
「復讐ですか……確かに、五年前はそう思ってました。でも、今は違います」
メイははっきり言う。
「そんなことしたって、意味がないじゃないですか。イルミナ族は、もう二度と帰って来ないんです。それだったらバイゼンを説得して、いい人になってもらった方が私もうれしいし、バイゼンも幸せですよね」
メイは真面目だった。
クラリスは、そんな彼女を見ていると歯がゆくなった。つい、声がきつくなる。
「あんた、よくそんな風に考えられるな。普通、大切な人を奪われたら、殺してやりたいとくらい思うものだろう。どうして許せるんだ?」
本当は分かっていた。メイが自分より圧倒的に重い過去を背負っている事も、それでも優しさを忘れずに生きてきた事も。だからこそ、それが癪だった。クラリスは、メイの夢想をぶち壊してやりたいという衝動に駆られたのだ。
しかし、
「許してなんかいませんよ?」
クラリスの予想とは違い、メイはきょとんとしただけで、少しも傷付いたりはしなかった。さらに、
「でも、わざと人を殺したいと思う人間なんているわけないじゃないですか。きっと、バイゼンにも何か深い事情があったんです。今ごろは後悔してるかも知れないし。だから、もう一度やり直そうって、言いに行くんです!」
そう当然の様に言ってのけた。
メイは優しい上に、馬鹿だった。
クラリスは思った。本気で人を利用するつもりなら、常に冷静且つ無感情でなければならない。メイへの幼稚な感情は一切捨てるのだ。
「私も魔王に用があるんだ。あんた一人だと心配だし、一緒に行ってやるよ」
メイはにっこり笑う。
「ありがとうございます!」
クラリスは、あまりにも単純なメイに、うっかり笑みを零しそうになった。騙されているとも知らず、のんきな奴だ。そう思っていると、メイがふいに言った。
「でも私、お姉さんの名前すら知らないんですけど……」
これは予想外だった。今ごろ、とクラリスは苦笑する。
「ああ、そうだな。私はクラリスだ。よろしく」
メイとクラリス。全く違う種類の人間。そんな二人の旅が、今、始まる。
スポンサーリンク