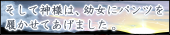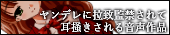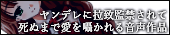『イルミナ』 中3の時書いたラノベ等身大すぎワロタww →企画トップページ
第七章 罪と記憶
クラリスさんに利用されていたなんて……。
「うそ……です」
メイのか細い声が、灯火に照らされた螺旋階段に反響する。
「クラリスさんは、そんな人じゃありません!」
ソアラは憫笑した。
「そうやって、必死で仲間をかばおうとする。無駄な努力はおやめなさい。あなたは裏切られた。これが現実なのです」
「……クラリスさん、どこ行ったんですか?」
「弟さんに会いにいかれましたよ」
ふと、メイの心が凪いだ。クラリスは弟に会う為に私を売ったのだ。それならそれで、私は役に立ったのだから、いいではないか。これでクラリスが喜ぶなら、私も嬉しい。
「諦めが付いたようですね」
そんな彼女の気持ちを察したらしく、ソアラが言った。
「はい! もういいです」
メイは元気に答えた。
「ところでソアラさん、さっきの人、ルシーヌって、アルタにいた時の名前ですよね」
「そうですよ」
「いつも部下の名前を使ってるんですか?」
「たまにです」
「シーク君はどうしたんですか?」
「バイゼン様と喧嘩して、反省室に入れられています」
「二人は、仲いいですか?」
「え……ええ、羨ましいくらいにね。それにしてもメイさん、よく喋りますね」
メイはにっこり笑ってみせる。
「だって、退屈なんだもん」
狂ったのだろうかと、ソアラは振り返った。
むしろ、腹が立つ程健全な笑顔があった。
「メイさん、お分かりですか? この階段の一段一段が、あなたの死に繋がっているのですよ」
「だから、せめて今のうちに楽しくおしゃべりしようとしてるんじゃないですか」
「……」
ソアラは閉口する。
――この子供、ある意味では大物だ。
「長い階段ですねー」
「一番上の部屋へ続いています。バイゼン様は高い所がお好きなのです」
「私も!」
まるで登山でもしているかの様な口ぶりだ。ソアラは遂にメイのお喋りを無視することにした。
最上階には、一つしか扉が無かった。
「バイゼン様、イルミナ族の生き残りを連れて参りました」
ソアラが声を張り上げる。すると、中から若い男の声がした。
「……そうか。入れ」
ソアラは、意気揚々と扉を押した。不吉な音が聞こえる……。
「ソアラ、ゆっくりと開けてくれ。最近、その扉は壊れかけているのでな」
「あ……、失礼致しました」
彼女はそっと扉を押した。完全に開いた時、メイはカチッという妙な音を聞いたが、それを言う前にソアラに小突かれ、中へ入れられてしまった。
「ソアラはもう下がっていい。ご苦労だったな」
「ありがたきお言葉でございます、バイゼン様。では、私はこれで」
ソアラは喜びの色を顔に浮かべて退室していった。もちろん、扉を丁寧に閉める事を忘れなかった。
メイは前を向く。アルタ城の大広間によく似た造りの部屋だった。床や壁は城壁と同じ石でできている。中央を一直線に走る赤い絨毯の先には、遠くてよく見えないが、人影があった。
「メイ、だな? 好きな所まででいい。こちらに向かって歩いて来い」
音響の良い部屋だ。強制的な言い方ではない事までもが聞き取れた。
メイは歩き始めた。男の姿がはっきり見えてくる。すらりとした長身だ。黒いマントがよく似合っている……。
「そんなに近くに来ていいのか? 私はお前の一族を滅ぼした張本人なのだぞ」
「いいの。あなたの顔が見たいから」
漆黒の瞳に、ややウェーブのかかった黒い髪。凛々しい美貌の持ち主である。
そして、肌は雪の様に白かった。
「おい、まだなのか、デランの部屋は!」
クラリスは延々と続く回廊に懐疑心を抱いていた。
「まさか、騙してるんじゃないだろうな?」
「もー、うるさいなァ! もうちょっとって言ってるでしょ? この城はおっきいの!」
ルシーヌは素で叫んだ。
「ほら、着いた! ここよ!」
彼女は声を作ってからノックする。
「デラン様、お客様がお見えです」
「デランっ!」
待ちきれずに、クラリスは扉を開けた。
そこには、クラリスと同じ、銀髪で目の青い少年が立っていた。
「いらっしゃい、姉さん。姉さんが来るって、一時間前に思ったんだ。だから、部屋をきれいにして待ってたよ」
「デラン……」
クラリスは感動のあまり、弟の名を呼ぶ事しかできない。
「さ、入って。ルシーヌは外で待っててね」
「かしこまりました」
二人きりになった姉弟は、しばらく見つめ合った。
デランが元気でいてくれた。それだけで、クラリスの心は嬉し涙を流す。
「デラン、大きくなったね」
体が弱く、小柄だったデランが、前に比べると健康そうな少年に成長していた。今でも傍目から見れば十分弱々しいのだが、クラリスには大きく見えたのだ。
ところが、デランは冷たく言い放った。
「二年もあれば、このくらいにはなるよ。姉さん、二年間も何やってたの?」
クラリスの感動が一気にしぼんでいく。
「あ……、ごめん、デラン……」
デランは拳を握り締めて怒鳴った。
「謝ったって、もう遅いんだ!」
クラリスは頭が真っ白になって、その場に立ち尽くした。
「私の顔に見覚えは無いか?」
バイゼンの問いに、メイは沈黙する。
「では、質問を変えよう。レイールという名を知っているか?」
レイール。古い記憶の中の名前だった。
「知ってる……」
イルミナ族の村がまだあった頃の記憶。
「私とよく遊んでくれた……」
しかし、その名は五歳以降の記憶には無い。
「行方不明になったお兄さん」
最後に会った日の記憶が蘇る。
――「お母さーん、お参り行こ」
五歳のメイが、母親の服を引っ張った。母親は困った顔をして、小さなメイと同じ目線になる様にかがむ。黒髪が床に着きそうだった。
「ごめんね、今日は薬草を収穫しないといけないの」
「行きたいー」
「じゃあ、お父さんと行って」
メイは父親に頼んだ。
「今日は壊れた椅子を直すつもりだったんだけどなあ」
「でも、神さま、汚れてるよ」
「汚れてる?」
父親の童顔が、きょとんとした表情になった。
「母さん、メイが変な事言ってるよ」
「変なことじゃないもん」
母親は、はいはいとメイをいなして、隣の家に連れて行く。
「レイール君、悪いんだけど、ちょっとメイとお参りに行ってきてくれるかな」
背の高い若者が現れた。レイールは、幼い時に両親を亡くし、メイの祖父母を始めとする近所の人々に育てられてきた為、よくメイの遊び相手になっていたのだ。
「いいですよ」
「お兄ちゃん、ありがと!」
メイは彼と手を繋いで、「北の神殿」と呼ばれる祠へと向かった。
それは、普通の家程度の大きさの、象牙色の建造物である。イルミナ族が神の化身と崇めている球状の発光体が祀られているが、一体いつ造られたものなのか、知る者は一人としていない。
二人は中に入って、眩い光を放つ発光体の前に立った。発光体は床から一メートル程のところに浮いており、ちょうどメイの顔の横にあった。
「ほら、ここ見て。何か黒いよ」
レイールは長身をうんとかがめて、メイが指差す先を見る。白く光る球の、普段上からでは見えない部分が、虫に食われた様に黒くなっていた。
「本当だ。何だろう」
彼はそこにそっと手を触れた。
その途端、レイールは動かなくなった。
「どうしたの?」
メイの声も耳に入らない様子で、放心しながらふらふらと立ち上がり、外へ出る。メイは追い駆けた。
「どこ行くの? ねえ!」
メイが服を掴んでも、全く気付かず歩き続ける。彼女は引きずられて転び、泣き出した。それでもレイールは歩みを止めず、そのまま家の方へ行ってしまった。
一人取り残されたメイは、泣きながら家に帰った。
「お父さーん、レイールお兄ちゃんが変になっちゃったあああ!」
泣き方が激し過ぎて、何を言っているのだか不明瞭だった為、父親はとにかくメイをあやす事に専念した。夜になって、薬草採りから帰って来た母親が改めて訊き、初めて何があったのかが明らかになった。
「レイール君、何かあったのかな」
メイの母親がレイールの家を訪ねてみたが、そこに彼の姿は無かった。そればかりか、村のどこを探しても、彼を見つける事はできなかった。
「では、彼は掟を破ったというの……?」
絶対に村の外に出てはいけない。それがイルミナ族最大の掟。従順な彼らは、この五百年間、ずっとその掟を守り続けてきたはずだった。
その後、北の神殿は封鎖され、人々は平和を取り戻した。
あの日までは――。
「あなたが……レイールさん?」
「今はバイゼンだがな」
同じ血を持つ者がイルミナ族を滅ぼしたという悲しみ、そして、もう二度と会えないと思っていた同胞に再会できたという喜びを、メイは同時に覚えた。しかし、口から出た言葉は、驚きを表現していた。
「どうして?」
彼女はバイゼンに歩み寄り、疑問を投げ付ける。
「どうしてみんなを殺したんですか? あんなに仲良しだったのに! 同じイルミナ族ですよ! どうして、どうしてレイールさんが!?」
「そうしなければならなかったのだ」
バイゼンがメイの肩に手を置いて、辛そうに言った。
「本当に悪かった。あの時、全てを終わらせる事ができたと、私は思い込んでいた。お前だけ残してしまって、本当に可哀想な事をした。よりによって、お前を残してしまうとは……」
メイは目の前の長身を見上げる。……首が痛い。何しろ、身長差は四十センチ近いのだ。
「後悔してますか?」
していて欲しい、と願った。そうすれば、期待通りの答えが返ってくるとでも言う様に。だが、バイゼンは首を横に振った。
「後悔する様な罪を、進んで犯したりはしない。イルミナ族には滅びる義務があり、私には滅ぼす責任があった。もちろん、メイ、お前もだ。そして、全てをやり遂げたら、私も逝く」
「そんなにイルミナ族が嫌いなんですか?」
メイが悲しげに呟く。バイゼンは彼女の肩から手を離し、自ら後ろへ下がった。
「何故私がイルミナ族を滅ぼしたのか、お前には知る権利がある。また、知らぬまま、全てを信じながら死にたいと言うのなら、それもいい。どちらか選ばせてやろう。どうする?」
デランのダークグレーのマントが、体と共に揺れていた。
「姉さん、僕ね、バイゼン様の腹心になるんだ」
狂気染みた笑みを浮かべて、彼はクラリスに宣言する。
「今、そのための勉強をしてるとこ。あと少し、あと少しで、僕はバイゼン様のお役に立てるんだ」
パステル調の、ごく普通の少年の部屋に、尋常ならざるセリフが放たれた。それはクラリスの周りを旋回し、ややあって、彼女の耳に入っていく。
「な、な、何で魔王なんかの!?」
「『魔王なんか』って何だよ! バイゼン様は素晴らしい人だ! 優しくて、清廉で、姉さんよりもいい人なんだよ」
デランはクラリスに、汚い物でも見るかの様な眼差しを向けた。
「僕知ってるよ。姉さんは、仲間の女の子を裏切ってここまで来たんだ。もう、姉さんなんか大嫌いだ! バイゼン様は仲間を大切にするよ」
クラリスは反論できなかった。確かに、自分は人間として、良い性格ではない。それは認めるが、愛する弟に嫌われるとは苦しいものだ。
「デラン、あんたの言う通りだ。けど、魔王の部下になるって事は、人殺しになるって事なんだよ。それでもいいのか?」
「いいよ」
実にあっさりと、デランは答える。
「だって僕は、生まれながらの人殺しだからね。あと、どれだけ殺そうと、大した違いじゃない。この予見の力で、悪い奴をやっつけるんだ」
「デラン……」
変わってしまった。デランは変わってしまった。
私の知っていたデランは、もういないのか?
「死ぬつもりはありません。私はレイールさんに、これ以上罪を重ねて欲しくありませんから。でも、真実は教えて下さい」
バイゼンは、ヘイゼルの瞳の奥に、何か強いものを感じた。メイはこの危機的状況において、抗うでもなく、諦めるでもなく、自分の目的を果たす事しか考えていないのだ。
「よかろう。だが、話を聞いたらお前はきっと命を捨てたくなるぞ」
メイは黙然と次の言葉を待っていた。
「お前がイルミナ族だと知った者が、妙な反応をした事は無かったか?」
言われてみれば、クラリスは落ち着きを無くし、ダリアの顔色は悪くなった。
「イルミナ族は絶滅したと思ってたから、驚いたんですよ」
「それが、違うのだ」
目を丸くするメイに、バイゼンは重々しく語りかける。
「普通の人間は、イルミナ族は凶悪な魔法種族だと思っている。そして、それはある意味事実なのだ」
「何で?」
メイは少しむっとした。
「みんないい人だったのに。はっきり言って、外の人達の方がよほど凶悪です!」
イルミナ族には、殺人も追い剥ぎも、偽りも裏切りも無かった。誰もが優しかった。完璧な世界だった。それがなぜ、凶悪と言われなければならないのだろう。
「そうだな。しかし、私たちの知っているイルミナ族の世界は五百年前に創られたものだ。その時イルミナ族は、外の世界との繋がりを断った。だから、外の人々の記憶には、お前の知らないイルミナ族の姿しか残っていない」
「私の知らない……姿?」
「イルミナ族の正体だ」
凶悪な先祖達。それがイルミナ族の真の姿だと言うのか。
「五百年前まで、イルミナ族は少数民族でありながらも大きな勢力を持っていた。他の人種では有り得ない程の魔力を使い、侵略、殺戮、強奪など、悪の限りを尽くしたのだ。まるで、そうする事によって心に空いた穴を埋めようともがくかの様にな」
「イルミナ族は、孤独だったんですか?」
「ああ……。どこから来て、どこへ行くのか。それも分からず、ただ空を見上げていた。悪の道は、当時のイルミナ族に安心感をもたらした。戦ってさえいれば、余計な事を考えずに済んだからだ」
信じられない、とメイは思った。この人は嘘を吐いているのだ。そうに違いない。でも、もし本当だとしたら? 本当に、イルミナ族が昔、暴れていたのだとしたら?
「あの……どれくらい被害が……?」
彼女は恐る恐る尋ねた。
「数え切れない程の人間が殺された。勢力は大陸の五分の一を占めていたという。他にも――」
「もう、いいです」
聞きたくなかった。欲しいのは、嘘だという証拠だ。
「ご……五百年前の事なんて、本当かどうかも分からないじゃないですか。レイールさん、何でそんな、まことしやかに話すんですか?」
ふと、バイゼンが哀れみの目で自分を見ている事に気が付き、メイは居たたまれなくなった。
「信じたくない気持ちは分かる。だが、確実に事実なのだ。なぜそう言い切れるのか、これから話そう。それとも、もうやめるか?」
「いえ」
涙が心のどこかで扉を叩いている。メイは、その扉に鍵をかけるかの如く声を押し出した。
「教えて下さい、全て。イルミナ族の昔話だけじゃなくて、あなたが村を出てから何をしたかも、全部。知れば、少しは罪が軽くなるような気がするから……」
「そうか。お前が望むなら、聞かせてやろう」
バイゼンは頷き、話し始めた。
「五百年前、一人のイルミナ族がある事に気付いた。自分達は何故戦っているのだろう、こんな虚しい生き方をしていていいのか、と。平和を好む人間の方がずっと幸せそうだ。いっそ、汚れの無い美しい人間になってしまおう。彼はそう言って同士を募り、保守派のイルミナ族に宣戦した。こうして、二つの正義がぶつかり合ったのだ。この戦争を、アーク・リッドという。一族は大幅に人数を失った。軍配は革新派(アーク)に上がり、保守派(リッド)の生き残りも彼らに組み込まれた。そして造られたのが、『北の神殿』だ」
北の神殿。レイールがおかしくなってしまった場所。
「あの光る球体を覚えているか?」
「はい」
あそこから、メイとバイゼンの人生は狂ったのだ。
「イルミナ族は、気候に恵まれた住み易い土地に、隠れのまじないをかけた。土地の北に祠を立て、一族全員の力を合わせて、史上最大の魔術を行った。……悪という概念、悪事の記憶、とにかく悪に関する全ての情報を、光る球体として具現化し、封じ込めたのだ。その際、魔法の使い方も一緒に葬った。イルミナ族は悪を忘れ、魔法を忘れ、五百年間の平和と幸せを手に入れた。しかし、いくらイルミナ族でも、永久に魔法を継続させる事はできなかった」
「もしかして、球体が黒くなったのって……」
メイが見つけた黒い部分は、レイールが失踪してからも広がり続け、封鎖される頃には上から見ても分かるまでに大きくなっていた。あれは、魔法が解けかかってきたという事だったのか。
「そうだ。封じていた情報がむき出しになり、触れると同時に私の中へ流れ込んできたのだ。私は全てを知ってしまった。イルミナ族の罪、魔法についての知識、また、外の世界は悪に満ちているのだという事を。今思えば、十六年前、道に迷った冒険家が村に来た時点で、魔法の崩壊は始まっていたのかも知れないな」
「ごめんなさい……」
メイは俯いた。
「何故お前が謝るのだ?」
「だって、私が『神様汚れてる』なんて言わなかったら、レイールさん、こんな辛い思いしなくても済んだのに」
彼女は今にも泣きそうな顔をする。
「私、旅して、世の中には悪いことがあるんだってことを知りました。すごく悲しかった。信じたくなかった。世界が嫌になるくらい……。でも、私はまだ知らないことがいっぱいあるけど、レイールさんは全て知ってしまったんですよね? しかも一気に……。私なんかより、ずっと辛いと思います……。あなたが魔王になった理由が、何となく分かったような気がしました」
「魔王?」
バイゼンの眉がぴくりと歪んだ。
「何だ、それは。『魔王』? ださいな……。そんな単語、幼児向けの絵本くらいにしか出てこないぞ」
「え、でも、いろんな町の人みんなが、レイールさんのこと魔王って呼んでましたよ」
「何……?」
彼はメイから目を離し、何やらぼやいた。
「魔王……。幾ら何でもひど過ぎる……。私は、そんなイメージなのか……!?」
ソカピの絵よりは数倍ましだという考えが、メイの脳裏を過る。さらに、イルミナ族全体が「ソカピ系」だと思われていたら、という恐ろしい想像をしてしまった。
「レイールさん、ショックでしょうけど、続きを言って下さい」
不思議だ。心はずたずたに傷付いているはずなのに、頭が勝手におかしな事を考える。一種の現実逃避なのだろう。
バイゼンは立ち直り、続けた。
「あの後、誰も球体には触れなかったか?」
「はい」
「そうか、それは良かった。とは言え、時間の問題だっただろうがな。魔法の崩壊が進行すれば、球体は形を失い、村に散らばっていただろう」
バイゼンが滅ぼしたおかげで、イルミナ族は罪を知らずに済んだ。果たしてバイゼンの目的はそこにあったのか。メイは聞いてみようとも考えたが、いずれ会話の中で説明される事と思ってやめた。
「私は、我を取り戻した時にはすでに、大切な物だけを持って村の外を歩いていた。帰ろうとは思わなかった。行く当ても無かったが、地理は球体の記憶が教えてくれた。やがて、ある村の近くを通りかかった時、私は一人の少女と出会った。年は十六歳程だった。村の者に追われて逃げ惑っていた少女を、私は安全な場所に隠し、それから尋ねた。どうしたのだ、と」
「私は、父と母を毒殺しました」
少女は真っ直ぐな瞳で言った。
「母が言ったのです。『何、その目は? 殺意でも涌いてきた? いいわ、殺してみなさいよ。もっともあんたなんかにできやしないけど』だから、望み通り食事に毒を盛ってやりました。あの人が望んだ事なのに、どうして私が追われなくてはならないのでしょう」
レイールは黙って少女の眼差しを受け止めている。
「村の人は、私が嫌いなのです。生まれてからずっと。この髪がいけないのですって」
彼女は、夕焼け色の綺麗な髪を指で引っ張った。
「それに、考え方も。ですが、皆さんの考える事は、いつも浅はかで、愚かしい。人の感情など、目を見れば簡単に分かります。皆、汚ない心をしているのです。けれど……」
急に少女の表情が涙で崩れた。
「一番汚いのはこの私……! それが悔しくて、哀しくて。村人が私の事を狂った失敗作だと罵るのも、仕方の無い事……。私はやはり、おかしいのですね。両親を殺しても、何も感じません。人を殺めたら、何か感じられるかも知れないと、期待さえしていたのに……」
涙が光の雫となって零れ落ちる。レイールは、少女を優しくいたわった。
「お前が狂っているのではない。世界が狂っているのだ」
少女ははっとした様に顔を上げた。涙は止まっていた。
「ああ、あなた程心の美しい人を私は見た事がありません。あなたはどこからいらっしゃったのですか? どうか、お名前をお聞かせ下さい」
「名は、捨てた」
レイールはこれまでの経緯を話す。少女は衝撃の歴史に聞き入った。
「私は、イルミナ族の名は捨ててしまいたいと思っている」
「私もです。村での名前は、もういらない。あの、よろしければ、あなたの新しい名前を私に付けさせて下さいませんか?」
「……構わないが」
ぱっと花の咲いた様な笑顔が広がった。イルミナ族の中での暮らしで、人の容姿に対する美意識を持たずに生きてきたレイールにも、類を見ない美しさだという事が分かった程だ。
「少しお時間を下さいね、バイゼン様」
「ああ。……バイゼンサマ? それが私の名前か?」
「そうです。いかがですか?」
「バイゼンサマか、少し長いな」
「……えっ? ち、違います! 『バイゼン』が名前で、それに『様』を付けてお呼びしただけです!」
「あ、そうか」
少女は微妙に天然な青年を、微笑ましく見つめる。
「バイゼン様、私の事は『ソアラ』とお呼び下さい。ソアラというのは、この地域の固有種で、赤い蝶です。村人は、赤は悪魔の色だと言って忌んでいますが、私には自由に飛び回るソアラが輝いて見えるのです。今日から私は自由です!」
「良かったな、頑張れ」
ソアラの目が、一瞬強い望みを訴えた。
「ご一緒させて下さい」
バイゼンは驚きの表情を隠し切れない。
「一緒に来てどうするのだ」
「世界を変えましょう。絶望していらっしゃるのでしょう? この欲界に」
二人は呼吸を止める。互いの心を読もうとして。
「怖いのですね、バイゼン様。世界を変える為に犠牲を出すことが。昔のイルミナ族の様に勢力を持つ事が。ならば、やめましょう。あなたが不幸になるのなら」
バイゼンはためらい、そして、小さく且つはっきりと応えた。
「いや、やろう。こんな世界ではいけないのだ。変えてしまおう、ソアラ」
「この日から、私達は仲間を集め始めた。面白い様に集まった。途中、ある国で元帥だったリカルドと出会い、彼はとても私達を尊敬してくれた様で、国の軍を丸ごと率いて仲間になってくれた。その中にザディーラがいた。モルジェとは偶然山の中で会い、すっかり仲良くなって仲間になった。この三人とソアラは、私の一番の部下となった」
メイはどちらかと言うと、カリスマ性によってではなく、頼り無さによって仲間を作ってきた様なものだ。それに比べて、同じイルミナ族でもバイゼンはすごいカリスマ性の持ち主である。人を引き付けるという点では共通しているのだが……。
「城も建ち、一国家に並ぶ軍事力を持った頃、私はある知らせを受けて遠くの土地に赴いた。その時、近くの貧困街から、並々ならぬ魔力を感じた。私はどうしても気になって、帰りがけにその魔力の主を見に行った。それが、シークとの出会いだった」
「シーク君との?」
バイゼンが、歯に物が当たった様な顔をした。
「メイ、シークを君付けで呼んでいるのか。それはお前くらいだろうな」
「いけないんですか?」
「いや、あの子にはいい経験だ」
メイにはよく飲み込めないまま、話は進められていく。
「私はシークを育てようと唐突に思い付き、城に連れ帰った。シークの絶望感に同族意識を持ったのかも知れない。あの子は非常に優秀だった。魔法においては、ソアラより教え易かったぐらいだ。後継者にしようと思い立ったのは後の事だがな」
「シーク、二万九千三百六十一たす二万五千四百六十八は?」
答えはすぐに帰ってきた。
「五万四千八百二十九。最初に二万五千同士をたしておいて、後から四千三百六十一と四百六十八をたせば、簡単じゃないか。もうやめよう、たし算は飽きた」
幼いシークは才能を持て余している。それが分かっていながら、バイゼンは魔法を教える事に踏み出せないでいた。
「シーク、これから教える事を、決して悪い事に使わないと、約束できるか?」
たった七歳の子供に、魔法を教えてしまぅっていいのか。迷いがあった。
「バイゼンとの約束は、絶対守る」
けれども、シークのきらきらとした顔を見て、それは晴れた。
「よし、では今日から、魔法の勉強だ。魔法の練習の部屋に行くぞ」
「本当!?でも、さっきソアラが使っていたよ、その部屋」
「ソアラが? 変だな」
ソアラが今日のバイゼンの授業に向けて予習しているのだとは、微塵も考えなかった。部屋に行き、
「バイゼン様、早く昨日の続きを教えて下さい」
と言うソアラの授業は後回しにして、シークに教え始める。
一時間、二時間、三時間……。ソアラは待った。イメージトレーニングをしようにも、初日から魔法を発動させ、操るシークが妬ましくて、集中できない。バイゼンも喜んでいる。……私の時より。
――バイゼン様、まさか、今日の私の授業、して下さらないおつもりですか?
バイゼンとシークが実の家族の様にふれ合う中、彼女は部屋を飛び出し、薬の研究に打ち込んだ。それしか、救ってくれそうなものが無かったから。
「そして三年後。ここからは、あの日についての話だ」
あの日。随分と軽々しく呼ぶ。少なくともメイにはそう聞こえた。
「私がイルミナ族を滅ぼした理由、それは――」
耳の奥が熱い。きっと、バイゼンも同じなのだろう。
「一言で言うと――」
早く言って欲しい。でも、まだ言わないで欲しい。混じり合う心が、むしろメイを無心にする。
「イルミナ族が再び昔の様に凶悪になる事を恐れたからだ」
全ての音が、刹那、消えた。
「何ですか、それ。なるわけないじゃないですか! レイールさんだって、黒い部分に触れたからと言って、凶悪にはならなかったでしょう?」
メイは激しい怒りに身を任せて叫んだ。
「それは分からないぞ、メイ。私が大丈夫でも、他の人は違う反応を示すかも知れない」
「じゃあ、みんなを村から連れ出すとか、もっとましな方法があったはずです! 殺すなんて、殺しちゃうなんて、レイールさんのばかっ!」
彼女はバイゼンに殴りかかる。もっとも、メイの力では大した痛みも無く、何回叩いてもバイゼンが表情を変える事は無かった。
「メイ、話はまだ終わっていない」
メイは力無くうずくまった。バイゼンは知らないのだ。真っ黒に焼けただれた死体達。何かを掴もうとしたまま固まっている、骨と炭でできた手。雨に打たれて崩れ去る村。それらを見ないまま、"移動(アテリース)"で逃げ帰ったのだ。
「例え村から連れ出したとしても、イルミナ族が存在する以上、暴走の可能性は残る。いや、暴走しないにしても、その強大な魔力自体がこの世にあってはならないものだと、私は考えた。自然に生まれるはずの無い力だ。私達は、間違って生まれてきたのではないだろうか、と」
「まちがい……」
「そう、間違いだったのだ。私たちがいる限り、世界を滅ぼす事が可能な魔力がこの世に存在する事になる。本人にその気が無くとも、誰か世界を憎む者が何らかの方法でイルミナ族を操ったとしたら? 私達は最強の兵器になってしまう。その前に――」
バイゼンはその先を言わなかった。
クラリスはすがる様な思いで口を開いた。
「分かったよ、デラン。本当に、もう戻ってくる気は無いんだな?」
「うん」
自分がこれからしようとしている事に恐怖心を抱きつつ、彼女はイレイヴを握り締める。
「ごめん、デラン、死んで」
「えっ……?」
一歩、距離を縮めた。
「あんたが悪に染まるなんて、私は嫌だ!」
「姉さん!?」
クラリスの目から、涙がぽろぽろと溢れ、頬を濡らしていく。
「あんたを殺して、私も死ぬ!」
「待って!」
肩で息をしながら、デランが首を横に振った。
「姉さん、ごめんね、僕、嘘ついたんだ」
自然とクラリスは止まった。柄から手を離し、弟を見つめる。
「姉さんの事、今でも大好きだよ。それに、人殺しだって気が進まないよ。それでも僕は、バイゼン様が正しいと思ってる。だから、わざと姉さんに嫌われて、諦めてもらおうとしたんだ。……うわっ」
クラリスがデランに抱きついた。
「ちょっと、やめてよ。僕、十三だよ?」
デランの抗議は完全に無視された。
「何で最初から言ってくれないんだ、デラン」
「だって、姉さんに頼まれたら、僕、決心が揺らいじゃうから」
クラリスは震えていた。
「……泣いてるの?」
そう、泣いている。嬉し泣きだ。涙が止め処なく涌いてくるのだ。
「ね、デラン、帰ろう」
「だからね、僕はここにいたいんだってば。大丈夫、バイゼン様だったら、よほどの事じゃないと殺しは命令なさらないよ」
「家が懐かしくないか?」
できる事なら、デランには普通の少年として、自分の保護下で生きて欲しい。
「魔王の腹心だったら、あんたじゃなくて、別の人が継いでくれるよ」
「それ以上言わないで!」
デランはクラリスを振り払った。
「もう遅いんだよ、姉さん。僕には道が無い。それに、僕を連れ出したら、姉さんも追われるよ? 僕の事はほっといて」
彼の心に故郷への憧憬を感じ取ったクラリスは、大胆にも笑ってみせる。
「構うものか。道が無いなら作ればいい。追われても、デランの為なら私は戦い続けるよ。お願いだから、戻ってきて」
デランが不安げな顔をした。
「僕、怖いよ。とっても嫌な予感がするんだ」
「じゃ、その怖いものさえ無ければ、来てくれるんだな? 大丈夫、私は強くなった。何があっても守ってあげる」
安心して、私に懸けて。魔王なんか忘れて。そう、クラリスは強く念じた。すると、それに応えるかの様に、デランが小さく頷く。
「本当に?」
「本当に」
クラリスは、もう一度デランを抱き締めた。それから、黙って扉を開けた。
「お帰りになられますか?」
ルシーヌが恭しく聞いてきたのと同時に、クラリスは剣を抜き放つ。紫電一閃、目にも留まらぬスピードで斬り込んだ。だがルシーヌは間一髪で身をかわし、藍色の瞳を怒りでぎらつかせる。
「もー、何すんのォ? 許さん!」
彼女も剣を構えた。二人は間合いを取りながら睨み合う。つかの間の静寂。
先陣を切ったのはルシーヌだった。剣を振りかざし、クラリス目がけて跳躍する。クラリスはそれを受け止め、押し返した。鋭い金属音が響く。
激しい斬り合いの中、クラリスはルシーヌに足払いをかけた。バランスを失ったルシーヌは脇腹を切り裂かれ、クラリスの足元に倒れる。
「うっ……、負けないわよ、くそっ」
急所は外れた様だ。クラリスはルシーヌに止めを刺そうと、太刀を振るった。イレイヴが唸りを上げる。
「だめ、姉さん!」
刃先がルシーヌの一寸前で止まった。
「人殺しはだめ! 僕のためでも!」
「デラン……」
クラリスは、剣を収め、ルシーヌを睥睨した。
「これで分かったと思うけど、私の方が強いんだ。デランに免じて命は助けてやる。潔く諦めて、ソアラへの言い訳でも考えておくんだな」
一転して、デランには優しい顔で声をかける。
「さ、行こう。どっちだったっけ?」
クラリスとデランは暗い廊下を駆け巡った。その間、誰にも会う事は無く、やがて正門に繋がる広間に足を踏み入れた。
門番が一人。城がバイゼンの魔法によって堅く守られている為だろう、すっかり油断してぼーっとしている。内側からの敵を想定していない。多分、この城における門番の役割というのは、帰還した仲間を迎え入れる事なのだ。
「姉さん、僕が行く」
デランは門番に向かって闊歩した。
「ねえ、ちょっと用事があるんだけど、開けてくれる?」
「はっ、かしこまりました」
バイゼンにザディーラの後継者として認められた彼は、バイゼンの仲間の中でも上位に立っているらしい。大の大人が少年にへいこらする姿は、見ていて面白かった。
「さあ、来い」
デランは、上司の様な口振りでクラリスを呼んだ。
「はい、デラン様」
クラリスもデランに合わせた。こうして、二人はまんまと城から脱出したのだ。
「ほらな、怖い事なんて無かっただろ?」
城を出て三百メートル程の所で、クラリスが言った。空は白み始め、降り続く雪も姉弟の新たな人生を祝っているかの様だ。しかし、デランは蒼白になって呟く。
「だめ、僕は……」
そして、クラリスが口を開こうとしたその時、
「……?」
彼の肩に、短剣が突き刺さった。
「デ……デラン!」
肩を押さえて崩れる弟。
「何これ!?」
クラリスは慌てて短剣を引き抜いた。次の瞬間、その行為を深く後悔したが、もう遅い。傷口から赤黒い血が吹き出した。
「デラン、しっかりしろ! 大丈夫か!?」
デランは小さく唇を動かし、何かを伝えようとしている様だった。
「何? 聞こえない!」
「……皮肉だよ、姉さん。僕には自分が死ぬとこが見える。これは毒の短剣なんだ……」
クラリスは、短剣が飛んできた方向を振り向く。
ソアラが立っていた。
「なぜですか、デラン。なぜバイゼン様を裏切ったりするのですか? なぜあんな素晴らしい方を差し置いて、そんな女を選ぶのです!」
彼女は本気で悲しんでいる。
「誰も分かって下さらない! バイゼン様がどんなに人間として美しいか! どんなに強く、優しく、温かいか! なぜ分からないのです! どうして!?」
「勝手な事を……!」
クラリスは抜刀し、体制を整えた。ソアラへの憎悪のみを目に宿す。しかし、ソアラは笑って叫んだ。
「クラリスさん、どこへにでも行っておしまいになって。弟の亡骸を抱いてね!」
力強く踏み込んだ。それでも、愛する弟の声は聞き逃さなかった。
「行かないで」
彼女は立ち止まる。
「ソアラなんかほっといて。僕だけを見て。僕のそばにいて。僕はもうすぐ、死ぬんだから……」
クラリスはその願いを聞き入れて座った。ソアラが去っても、その両手は剣を握る為には使わない。デランの手を握る為にこそあるのだと思えてきたのだ。
「ごめん、デラン」
守ってやれなかつた。約束したのに……。
クラリスは深い絶望の海に沈んでいった……。
「メイ、可哀想だが、お別れの時間だ」
バイゼンに言われて、メイは顔を上げた。
「殺して下さい。私達、いること自体が罪なんですよね。お願い、殺して……」
彼女は目を閉じ、静かに思う。
今まで、ありがとう、おじいさん、おばあさん、シーク君、それにクラリスさん。この感謝の気持ちは、ずっとずっと、死んでも忘れないから……。
覚悟は決めていたはずなのに、涙が溢れてきた。愛する人々に永遠に会えない事が、哀しくて仕方無かったのだ。
バイゼンがメイの額に手を置いた。
殺れるか。この私に、罪も無い少女の命を奪う事ができるか。そうやって躊躇している間にも、刻々と時は過ぎていく。
足音が聞こえた。幻聴だろうか。いや、だんだんとそれは、現実のものとなって迫り来る。
「バイゼン!」
聞き覚えのある声。だが、異様な騒音に掻き消されてしまった。
勢い良く開いた扉が、壊れた。蝶番がはずれ、床に打ち付けられると同時に砕け散る。バイゼンもメイも、びっくりして入り口を見た。
シークがぼさっと突っ立っていた。状況を何とか把握した彼は、扉の残骸をまたぎ、走りながら声を張り上げる。
「バイゼン、やめろ! メイから離れるんだ!」
「シーク、どうやってあの反省室から……?」
バイゼンもシークに向かって歩き出した。
「この数ヶ月で背が伸びたし、脚力も上がった。だから飛び上がれば天井の通気口にも届いた。そういう事だ」
「そうか、成長したな……」
「感心している場合か!」
目を細めるバイゼンに、シークが怒鳴った。二人はメイから少し離れた所で向き合った。
「バイゼンが過激な世直しをやめないと言うのなら、俺は戦う!」
「ほう、私に敵うか、シーク?」
メイはすっくと立ち上がり、壁に向かって直進する。
「ヴィエンシル」
音も無く、壁に切れ込みが入った。バイゼンとシークは口論に気を取られて気付かない。メイは何度も"風の刃(ヴィエンシル)"を唱えた。
「ヴィエント」
最後に城壁を吹き飛ばした時、初めて彼らはメイの行動に気を留めた。
「馬鹿な。魔法は使え……」
バイゼンははっとした。自分と同じか、あるいはそれ以上の魔力を持つ者には、このまじないは効かないのだ。
メイは壁の断面の上に立った。吹き込む風が、髪とコートを翻す。
彼女はただ微笑んで、胸の前で小さく手を振った。そして、重心を後ろに移動させた。
地平線が銀色に輝く。
死を感じながら、メイはある一つの風景を思い描いていた。
赤い屋根の小さな家。
もう一度だけ、おじいさんとおばあさんい会いたい……。
「デラン、デラン……!」
クラリスは泣きじゃくった。
「姉さん、泣かないで」
デランはそっと、その歳の少年にしては小さな手で姉の頬に触れる。
「よく聞くんだよ。姉さんの仲間の女の子は死んじゃいない。これから家に帰るんだ」
「えっ?」
遂に混乱したのかと、クラリスはますます強く彼の手を握った。
「姉さんとその子が出会った所から南に行くと、小さな田舎村があるから、僕が死んだらシーク様とそこに向かって。そうじゃないと、今度こそ死んじゃうよ」
そう言うと、デランはほっと息を吐いてクラリスの腕に頭を委ねた。
「見て、姉さん」
薄く目を開き、囁く。
「流れ星、きれいだね……」
デランの視線の先にはエストカルト城があった。その近くで、浅葱色に光る何かが煌めいて、消えた。
「いや、あれはアテリースの……デラン!?」
クラリスは焦った。デランが、焦点の合わない目を閉じようとしている。
「死ぬな! デラン、死んじゃ嫌だ!」
少年の淡い命は、脆く崩れ去っていった。返事をしない。手も動かない。クラリスはまだ信じられないといった様に、デランの胸に耳を押し当てた。ほら、聞こえるよな、心臓の音が。
しかし、彼女の望みは潰えた。
「嘘だ。嘘だろう……?」
クラリスは幾度も幾度も耳を押し当てる。無論、何も聞こえない。デランの髪に、一ひら、一ひらと雪が積もっていく。
この大きな世界の、ある一組の姉弟が、死別した。それだけの事である。
これは、何回も繰り返される死の内の、小さな死にしか過ぎない。
それでも姉は、弟をしのんで、いつまでも泣き続けた。
スポンサーリンク