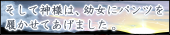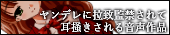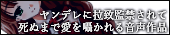『イルミナ』 中3の時書いたラノベ等身大すぎワロタww →企画トップページ
第五章 絆の中での転身
「何故だ! 何故こんな簡単な事が分からないんだ!」
「全然簡単じゃないよ! これが簡単って言うシーク君も分からないよ!」
「嘘を吐くな! 分からない筈が無いだろう!」
「うそじゃないよ、ほんとだよ!」
「いい加減にしてくれっ!」
クラリスはこの数週間、毎日こんなやり取りを聞き続けていた。つまり、シークがメイに魔法を教えようとしても、なかなか理解してくれないのである。
今は雷の低級魔法"電光(トレノ)"の練習中だった。
「こんな大穴開けてどうするんだ。実用性がないじゃないか!」
メイの前には、直径三十メートルの穴がある。今しがた、彼女"電光(トレノ)"が大地に付けた傷だ。幸い、ここはただっ広い荒れ地だったので、何の被害も出さずに済んだ。
「手の平に神経を集中させて、力を最小限に抑えるんだ。何度言ったら分かる?」
「……やってるもん」
メイはすっかりふてくされて、じっと穴を見ている。
「……やってるんだけど、できないの……」
シークは何か言おうとしたが、メイの様子を見て口を閉じた。そして、クラリスの横に座り込んでしまった。
「俺は……こんなにもどかしい気持ちになったのは初めてだ……」
秋の風が二人の耳元を走っていく。
「できないって、辛いんだな……」
「シーク……」
クラリスはシークに深く同情し、自分も腰を下ろした。
「あんたが悪いんじゃない。メイが馬鹿なんだ」
「だが……」
シークはさらに落ち込んで溜め息を吐く。
「あいつに初歩的な魔法を教えた者もいるのに、俺はそいつの足元にも及ばない様だ」
「仕方が無いよ、シーク。その人は有名な魔法の先生なんだから。あんただって、すごく優秀な魔導士じゃないか」
実際に、シークの優秀さは驚くべきものだった。メイを狙って来た強い魔導士との戦いを一手に引き受け、傷一つ無く全勝していた。十五歳という若さで、いや、若いというにも若すぎる年齢で、彼の魔導士としての腕は、高名な魔導士のそれに匹敵する程までに磨かれていたのだ。
「あんたの家族も魔導士なのか?」
クラリスが訊く。
「いや……俺は突発的に生まれてきた魔導士だ。家族の誰にも魔力が無かったから、俺自身、初めは自分の力に気付いていなかった。だが、ある人が俺を拾い上げてくれたんだ。魔法も知識も体術も、全てその人から習った」
「ふーん。いい人だな」
しかし、シークは応えなかった。立ち上がって感覚を研ぎ済ませていた。
「誰か来る……!」
遠くに人影が見える。ベージュの服に身を包んだ金髪の女性。
シークはメイの傍に行って、彼女の様子を伺った。やはりこちらに来る。メイが目的なのか。
「あ、シーク君、さっきはごめんね」
熟練した魔導士だ。口元に笑みさえ浮かべている。
「シーク君……? 怒ってるの?」
「少し黙ってろ」
「……ごめん」
メイは誤解して足元に目を落とした。
「っ……?」
シークが妙な声を出したので、メイは再び顔を上げた。何と、見知らぬ女性が手を振っている。
「えっ、何、あの人?」
「貴様っ、何者だ!」
二人は、違う様で実は同じ意味の反応を示した。
「あーら、あたし、怪しい者じゃないわよ」
そう言うと、女性は困った様な笑顔で近付いてきた。
「ま、忘れてても無理ないわね。ほら、シレジアで会ったおばさんよ、道案内の」
メイの脳が、必死で記憶を探し出す。灰色の目の、親切なおばさん……。
「……ああ、あの時の」
「思い出してもらえたかしら?」
女性はにっこりと微笑んだ。
「マーガレットには会ってもらえた?」
「はい! 魔法を教えてもらいました!」
クラリスは、彼女の微笑から、マーガレットのシンボルマークとも言える、あの笑みを連想していた。
「もしかして、マーガレットさんの妹さんでいらっしゃいますか?」
それを聞いた女性は、手を叩いて喜んだ。
「あ、分かった? そうなの、あたしたちは姉妹なの。年は離れてるけどね。あたしはダリア、才能を発掘するために旅をしてるわ」
ダリアはシークにちらりと目を移す。
「まあ、あなたにはもう、『発掘』も『研磨』も必要ないみたいだけど」
「……」
自分の中身が全て見透かされている様な気がして、シークは何も言えなかった。
「いいナイトをお持ちね、お嬢ちゃん」
「ないと?」
クラリスは、ダリアが何か大きな勘違いをしていると感じたが、面白いのでわざと何も言わなかった。
「あら、あたしったら、まだあなた達の名前、聞いてなかったわね」
三人は、それぞれの名を名乗る。
「みんな、いい名前ねー。私はこんな名前だから、昔よくからかわれたのよ」
どこかで聞いたセリフだった。
「そうだ、この近くに兄の家があるんだけど、泊まってかない? 彼、ルーヴァのお偉いさんだから、いい家持ってるわよ」
「ベッドありますか?」
この愚問は、言うまでもなくメイのものである。
「あるわよ。ふかふかの天蓋付きよ!」
「わあい! じゃあ行きます!」
「……おい……」
他の二人の意思は関係無い。
「んもー、そんなに固くならないで、クラリスさん! あなたもいい顔してるんだから、もっと笑いなさいよ!」
「笑う……」
クラリスには、なぜか懐かしい言葉に聞こえた。ずっと忘れていた事。それとも、禁じていた行為? マーガレットかダリアの様に笑ってみたい……。
しかし、口を突いて出た言葉は冷たかった。
「……今は笑えません。そんな場合じゃないんです」
ダリアは肩を竦めた。
「あら、そう? 笑うっていい事よ」
「クラリスさん」
メイがいつに無く真面目な表情で言う。
「『笑うのは自分のためではない、自分を気遣ってくれる人のためだ』。これ、一族の教えなんです。私、クラリスさんにもっと笑っていて欲しいです!」
クラリスは「悪いけど」と言いかけて、やめた。
「そうだな」
少しだけ笑ってみる。メイの笑顔が頷いていた。
「シーク君もだからね」
クラリスは、シークの代わりに答えてやった。
「メイ、シークが笑わないのは、あんたが魔法を失敗するからだ」
シーク以外の全員が笑った。クラリスの笑顔は半分嘘だ。それでも良かった。本当に笑える日が来るまで頑張っていけば、それで。
「お屋敷だー! お城の次はお屋敷だー!」
『ルーヴァのお偉いさん』ユリウス・アルボルの家は、薔薇園の中にあった。娘の名前がローゼなので、それにちなんで植えられているらしい。彼女もまたルーヴァの一員だと、ダリアは言った。
「でも、あたしはあんまりルーヴァって好きじゃないわ。堅っ苦しくって、正義正義ってうるさくて」
「あの、ルーヴァって何ですか?」
クラリスは、メイが夢だと思っている例の事件に触れない様に説明してやった。
「今のセリフ、兄さんが聞いたら激怒してたわよ。彼にとっては、ルーヴァが全てだから」
ダリアはくすりと笑って呼び鈴を鳴らす。
「兄さん? ダリアよ」
「どうぞ。お入りください」
召使いの男が扉を開けた。
「まあ、我が愛しのお兄様は、妹の出迎えもして下さらないのね」
「申し訳ございません。ユリウス様はただいま仕事中です」
ふんとダリアは鼻を鳴らしたが、気を悪くしたというには悪戯めいていた。
「ベルス、お義姉さんは?」
「ミティーユ様は……お昼寝中でございます。それよりもそちらの方々は?」
ダリアはメイの肩に手を置き、
「あたしが発掘した宝石と」
クラリスの肩に手を置き
「その保護者の方と」
シークの肩に手を置いた。
「その友達よ」
シークは否定しなかった。したら、もっと間違った方向へ進みそうだからである。
「左様ですか。では、あちらのソファーでお待ちください」
四人は、落ち着いたベージュ色のソファーに座った。ダリアの服の色と被っている為、彼女を見た時、他の三人は違和感を覚えた。首と足だけがくっきりと映えてしまっていたのだ。
「彼ね、ベルスっていって、ここの使用人なの。よく滑って転ぶのよ。昔、魔法学校に入りたくて試験を受けた時も滑ったわ! 実は同級生なのよ――」
彼女の話は軽く聞き流された。
「ダリア、若い人達が可哀想じゃないか、お前みたいなおばさんの話を聞かされて」
ユリウスが現れたのは、ダリアの話がいよいよつまらなくなってきた頃だった。
「また随分と変り種を連れてきたな」
ユリウスはメイとシークをまじまじと観察する。
「うーむ、どちらも別の意味で恐ろしい……」
彼は姉や妹と比べるとくすんだ色の金髪で、目の色もやや青味を帯びていた。年は五十代半ばで、紳士的な風貌だ。
「この子達も泊めてくれるでしょ、兄さん?」
ダリアが甘い声を出した。
「構わんが……。こっちの子」
ユリウスはメイを指差す。
「どうせ、姉さんの代わりに『研磨』したいと思ってるんだろう? それはいいが、敷地内ではやらないでくれ。大変な事になりそうだ」
メイやシークの魔力が分かる事からすると、ユリウスも魔導士のようだ。
「はいはい。ところで、ルーヴァの仕事は終わったの?」
「ああ、この年になると、書類ばっかりでつまらんよ。ルーヴァの基地から近いから自宅出勤だしな。毎日スリルの無い生活を送っているのさ。ローゼが羨ましい」
「もう、兄さんったら!」
ダリアは口元をほころばせた。
「さ、君達の名前を聞かせておくれ」
三人はユリウスの要求に応えた。クラリスは、彼が姉や妹と同じ反応をするのを待ったが、残念ながら特に反応は返ってこなかった。
「ベルス、屋敷を案内して差し上げなさい」
「かしこまりました。さあ、こちらへ」
そして、階段の手前でベルスは転んだ。
「楽しかったですね、お屋敷見学!」
メイが夢の天蓋付きベッドで遊びながらクラリスに言った。
「楽しかったと言ったら、ベルスさんに悪いよ」
ベルスは一時間の内に五回も転んでいたのだった。
「あの人、足を調べた方がいいと思う。案外、転びの呪いとかがかかってたりしてね」
「魔法に呪いなんてあるんですか?」
「……少しくらいあるんじゃないか?」
シークは別の部屋にいる。こういう時にいないと、微妙に不便だ。
「名前のせいかも知れない」
メイは閃いた。
「『ベルス』を入れ換えたら『スベル』になりますよ!」
「……関係ないと思う」
そこへダリアがやって来た。
「メイちゃん、魔法、教えさせてくれる? あたし、一度でもいいから、姉さんみたいに先生やってみたかったのよねー」
何もメイを初生徒にしなくてもいいのに、とクラリスは思う。だが、きらきらと目を輝かせているダリアには、何も言う気になれなかった。
「どうぞ。ほら、メイ、行け」
「でも、それじゃあシーク君に悪いですよー」
「いいよ、シークには私から言っとくから」
クラリスは一人になりたかったのかも知れない。メイが出て行った後、なぜかほっとしている自分がいたのだ。
「イレイヴ」
静かに呼んでみる。それは、彼女の剣の名だった。
もとは父親の愛剣であったイレイヴ。無駄な装飾が一切なく、ごく機能的に作られた清楚な剣だ。美しい白刃は女性を連想させる。さすがに血の繋がった親子、重さを取っても、大きさを取っても、クラリスにとっては最高の相棒と言える代物である。
クラリスは地元では名の通った剣士の娘として生まれた。母親は病弱で、難産が予想されたが、何事も無く元気に生まれてきた。銀色の髪を父親から、青い目を母親から受け継ぎ、早くから抜群の運動神経を見せていたクラリス。ところが四年後、残酷な悲劇に襲われた。
母親が死んだのだ。
息子のデランを産んで。
彼もまた身体が弱かった。幼いクラリスは、必死に母親の代わりを務めようとした。いつしか彼女にとってデランは、弟以上の存在になっていた。
クラリスが九歳の年、父親までが病で死んだ。あんなに強かった父が。
クラリスの手には、デランとイレイヴが残されたのだった。
「私が守らなきゃ」
その日からクラリスは大人の強さを身に付けていった。
一方で、デランにも特殊な能力が備わっていた。
予見。
未来を読む事ができる、珍しい性質の魔力。
シーク同様、突発的に生まれてきた魔導士だった。
それが災いして、二年前、彼は何者かに攫われた。クラリスが仕事に出ている間に。
『まおう』
咄嗟のメッセージが、床に焼き付いていた。
十四歳のクラリスは、イレイヴを手に旅に出た。でもある日、自分一人ではバイゼンの許へ辿り着く事さえできないし、対峙したとしても彼の魔法には敵わないだろうと悟った。だから、仲間を――至極子供らしい理由で、扱い易い魔導士を探し始めたのである。もっとも、メイは思ったより使えなかったが。
あれから二年。
もうすぐ……もうすぐデランに会える気がする。
「クラリスさん……?」
「え」
気が付けば、クラリスはメイに見下ろされていた。
「え……な……何……?」
剣を胸に抱いて、カーテンも閉めず、ベッドに横たわっている。
私は……寝ていた!?
クラリスは急に恥ずかしくなって跳ね起きた。
「何……だよ?」
やや声が不機嫌になる。メイの顔が強張った。
「何で怒ってるんですか?」
今までずっと、メイより後に寝てメイより先に起きていたのに。寝顔など見られたくなかったのに。これが本音。完全なる逆恨みだ。
「別に。怒ってない」
そう答えておいた。メイが胸を撫で下ろす。
「晩ごはん、できましたよ」
リビングにはすでに全員が揃っていた。初対面のミティーユ・アルボルは、プラチナブロンドの上品な婦人だった。また、なぜか召使いのベルスもユリウス達と同じ食卓に着いている。この屋敷における彼の地位は、召使いというよりは友達に近いのかも知れない。ダリアの同級生でもあるのだし。
「さあさ、席にお着きなさいな」
メイとクラリスは、ミティーユに言われるまま空席を埋めた。
「じゃあ、食べましょうか」
メイとシークはともかく、アルボル一家やベルスまでもが黙祷を捧げた事に、クラリスは驚いた。
メイとシークは、それが犠牲になった生命へのせめても償いだと言って、毎回やっている。メイの時は然程驚かなかったが、シークの時は正直、目を疑ったのだった。
とにかく、一人だけ何もしないのもおかしいので、クラリスも黙祷した。
「いただきます」
楽しい食事の時間だ。誰が作ったのかは分からないが、家庭的な料理が並んでいて、心が和む。
「兄さん、この部屋に集まっている魔力、とんでもないわね」
「そうだな、第一、クラリスさんとミティーユ以外は、皆魔導士じゃないか」
兄妹の会話から、メイはある事を思い出した。
「ダリアさん、魔法に呪いってありますか?」
ダリアはパンを頬張りながら答える。
「あるわよ。ただし、応用ね。呪文が要らなくなるまで技術を磨いた人になら使えるし、場合によっては作る事も可能よ。ちなみにベルスの転びの呪いは本人の失敗」
「ダリア様……言わないで下さいよ……」
ベルスのぼやきは、ユリウスの補足説明に掻き消された。
「魔王の城にも、人に見つからない様にする呪い……もとい、まじないが掛けられているようだ。私は今、部下に城を探させているのだが、全然見つからんよ」
「でもシークは……」
クラリスはそこまで言って、何でも無いとごまかした。ルーヴァなら、城内の人間を全て抹殺しかねない。シークが嘘を吐いているとは思えないし、彼が城の場所をルーヴァに教えてしまったら、デランの身も危ないからだ。
「ところで、魔法の勉強は進んだかね?」
ユリウスはメイに聞いた。
「はい! 私、"電光(トレノ)"がちゃんとできる様になったんですよ!」
シークが訝しそうに顔を上げる。
「どういう事だ?」
「えっ、クラリスさんから聞いていないの? 私、ダリアさんに魔法を教え……」
メイは言い淀んだ。シークは傷付くだろうか。自分が役に立たないから、先生を辞めさせられたのだと思うだろうか。
「あ……別に、シーク君がいけないんじゃないんだよ? せっかくだから教えてもらっただけなの」
「"電光(トレノ)"……できたのか。ダリアとなら」
シークの一言に、メイは沈黙する。
はっきり言うと、シークの教え方は分かりづらい。最初からできるのが当たり前だと思っている。それに比べてダリアの方は、手取り足取り教えてくれる。できない自分を許してくれる。
そう、まるでマーガレットの様に。
「私、メイさんの魔法が見たいですわ」
場の空気が読めていないミティーユの声が静寂を破った。
「お……おお、私も見たいよ、メイ君」
ユリウスも同調した。
「じゃあ、食べ終わったら外に行きましょうよ、皆さん」
ダリアが笑顔を取り繕って提案する。全員賛成の意を示した。
「はい、出発――あ、無理、寒い」
ダリアは扉を開けた。が、すぐに閉めた。
「外、冷えてるわよ。みんな、上に何か羽織ってきた方がいいわ」
という訳で、一同は一時解散せざるを得なかった。
メイとクラリスは、部屋に戻って自分の荷物からコートを取り出す。
「どうですかー? 似合いますか?」
緑がかった黒のロングコートを着たメイは、何やら嬉しそうだ。
「似合うんじゃない? 色がいいよ」
クラリスは振り返りもせず誉める。この時、彼女は自分のコートが継ぎ接ぎだらけなのに気付き、着るか着ないか迷っていたのだった。
「クラリスさん、どうかしたんですか?」
「いや、どうもしない。ま、コートはいらないよな」
クラリスは、恥を掻くよりはましだと思って我慢した。結果、深く後悔することになるのだが。
外は想像以上に寒かったのだ。
この辺りの土地は、痩せているだけでなく、気候にも恵まれていないらしい。
「これ、十五歳の誕生日のプレゼントとしてもらったコートなんです!」
薔薇園を抜けた時、メイが言った。
「ふーん、誕生日プレゼントなのか。十五さ……えっ、十五歳!?」
クラリスは、すっとんきょうな声を上げてしまった。
「あんた、一体いくつなんだ! 十五歳……なのか?」
驚愕のあまり震えるクラリスを、メイは不思議そうに見つめる。
「そうですよ。旅に出たのが誕生日の日で、それが五月六日、初夏だったから、このコート、おニューなんですー」
クラリスは、言葉ではとても表せない程のショックを受けた。
どう見ても十二、三歳なのに! 顔だけなら十歳でも通るだろうに!
私と一歳しか違わないなんて、信じられない……。
「さ、ここまでくればいいでしょ」
クラリスの様子には気が付かず、ダリアが陽気にウインクした。
「あなたが覚えている魔法、全部見せて。これからの勉強の計画を立てるから」
「はーい、じゃ、行きますよー!」
メイは夕闇に手を広げ、叫ぶ。
「アグア!」
青い輝きと共に、メイはびしょ濡れになった。
「……あれ? こんなつもりじゃなかったんだけどな」
彼女はきょとんとして呟いた。
「何がしたかったの、メイちゃん……? 水の魔法を上に向かって放つなんて……」
ダリアも呆気に取られている。
「私、火の魔法がやりたかったんです」
「それ、フィエゴよ」
「……」
風が吹いた。身を刺す様な冷たさのせいか、メイは眉をひそめる。
「帰りませんか?」
誰もが初めて聞く、彼女の刺々しい声。
「私、見せられる様な魔法は使えないみたいだから。無駄なお時間取って、ごめんなさい」
一人踵を返したメイを、クラリスは呼び止める。
「メイ!」
足を止め、振り向いたメイの瞳には、涙が。
「だって、私……」
それ以上続けられずに、彼女は泣きながら屋敷へ走り去った。追おうとするクラリスをダリアが首を振って制する。
「今は一人にしてあげなさい。後は私に任せて」
「ですがダリア様、私は鍵をかけてきてしまいました。メイ様は中に入れません。入れたとしても、暖炉が点いておりませんし、タオルも用意してございません」
ベルスは現実的な事を伝えた。
「だったらベルス、アテリースで屋敷まで行って、暖炉に火を点け、タオルを用意しなさい」
次の瞬間、ベルスの姿は消え、アテリースの残光が煌めいていた。
メイは薔薇園の中を駆け巡っている時、頭の中で自嘲した。
「困ったな。お屋敷は鍵が掛かってるのに、一人で帰ってきちゃった。ばかなメイ……」
けれども、どういう訳だか、鍵は開いていた。さらに、なぜか暖炉には火が灯っていて、近くのソファーには偶然にもタオルが置いてあった。
「すごく申し訳ないけど、取りあえず温まろう。風邪なんか引いたら、もっと迷惑だよね、きっと」
メイは冷え切った手でコートの留め金を外す。新品の誕生日プレゼントを、早くもこんな目に合わせてしまった。そう思うと、また涙が滲んでくる。
コートの下もぐっしょりと湿っていた。灰色のワンピースが体に張り付いている。メイはそれを脱ぎ、暖炉の近くの椅子にかけた。結局、下着以外の服は全部脱ぐ羽目になった。
「……ばか」
大きめのタオルを体に巻き付けて、メイは暖炉の前にへたり込んだ。明かりに照らし出された肌が通常より白く、むしろ蒼白に見える。普段、自分の姿をよく見ていない彼女には、それがひどく不気味に感じられた。
「……ばかばかばかばかばかばか!」
タオルに顔を埋めて、泣きじゃくる。
「何で私、こんなにだめなの?」
助けられてばかりの、役立たずのメイ。
失敗してばかりの、どじなメイ。
その癖、いつもにこにこしていて、なんだか腹が立つ。一族の教えに従ってはきたけれど、クラリスやシークの目には、ふざけている様にしか映らなかったかも知れない。余計にストレスを与えていたのだとしたら、自分はどう謝れば良いのだろう?
――ああ、力が欲しい!
ふいに、屋敷の扉を開ける音がした。続いて人が転ぶ音。
「あ、みんなが帰ってきた」
一気に気まずさが込み上げた。突然泣き出して帰った自分を、皆はどう思っただろうか。
足音がこの部屋に近付いてくる。メイは身構えて、足音の主を待った。
「……ダリアさん」
優しい微笑を湛えたダリアが、入り口に立っていた。
「あの、ごめんなさい。勝手に……」
「いいのよ、気にしないで」
何もかも知り尽した様な笑みは、メイを少しだけ落ち着かせる。
「もっと温まりなさいよ。遠慮しなくていいのよ」
ダリアが近寄ろうとしたので、メイはタオルをきつく巻き直した。それを見たダリアはため息を吐く。
「ベルスったら、言われた事しかしないんだから」
もちろん、この言葉の意味はメイには分からない。
「ダリアさん」
メイは、急に、決然とした眼差しをダリアに向けた。
「私はろくに呪文も覚えられないし、魔力のコントロールもできません。でも、お願いします。どうか――」
彼女の瞳に光が走る。
「私を戦える魔導士にして下さい」
それが、メイの導き出した答えだった。
それから数日間、クラリスはメイの姿をあまり目にしなかった。魔法の特訓をしているのだとベルスが教えてくれるまでは、その理由も知らなかった。
「ダリア様がおっしゃっていました。メイ様は魔法をいくら使っても疲れないので、一日中やっていられる、と」
完璧に忘れられたシークは、もう先生になる事をすっかり諦めている様だ。気にもせず本をひもとくなどして時を過ごした。
メイはまず、今まで習った呪文をしっかり覚え、次にできるだけ弱く魔法を使う様に練習した。
「メイちゃん、低級魔法は敵を追い払う為のものなの。そんなに強かったら実用性が無いのよ」
「はい」
そして、火の中級魔法"灼熱の炎(フィエブレ)"、水の中級魔法"水の弾(アジュビア)"、氷の低級魔法"冷気(ニエベ)"を新しく習った。
「氷の魔法は水の魔法の基礎がしっかりできていないといけないから、よく復習しなさいね。あと、中級魔法はある程度魔力を込めていいわよ」
「でも、私の場合、込め過ぎるとだめですよね」
「まあ、それはこれから見ていきましょう」
さらに、瞬間移動の魔法アテリースにも手を出した。
「アテリースは技術もそうだけど、一番必要なのは意志。意志さえ強く持って集中すれば、あなたにもできるはずよ。ただし、景色を十パーセントは思い浮かべられないと、そこには行けないわ」
「十パーセントなんて、ハードル低いですね」
「あら、意外と高いのよ。今から兄さんの屋敷の前に行くとして、あの門の周囲の景色、どれだけ思いだせる?」
ある日、ダリアは首を傾げてメイを見つめた。
「どうしたんですか? 私、何か間違ってますか?」
「ううん、そうじゃないんだけどねえ……」
メイはフィエブレを唱えたところだった。赤い閃光が灼熱の炎となって、何も無い大地を撫でる。
「こんなの人に向けたら、絶対死んじゃいますよね。私、強すぎますか?」
「だから、そういう事じゃないってば。その魔法は、そういうものなのよ。何に使うかは、その人次第。私はね、あなたの魔力の気配が全然消えないから困ってるの」
「ええーっ、こんなに頑張ってるのにー。技術が上がってないってことですか?」
メイは未だに移動(アテリース)も守りの魔法(パレ)もマスターしていないのだ。
「技術は格段に上がったと思うわよ。けど、なぜか、何と言うか、独特の魔力の気配が出てるのよねー」
「独特……」
メイにはその理由が分かった。
「たぶん、私がイルミナ族で、他の人とは違うからだと思います」
ダリアが「何族ですって?」と訊き返したので、メイは再度繰り返す。やがて、ダリアの様子が変だという事に気付き、彼女は心配し始めた。
「顔色悪いですよ。大丈夫ですか?」
「ええ、大丈夫……。ちょっと一人で練習してて……」
メイは、暫時ダリアの後ろ姿を見送った後、"灼熱の炎(フィエブレ)"を唱えた。美しささえ感じられる紅蓮の炎。イルミナ族の村を焼いたのは、これより高度な火の上級魔法"劫火(フィエブソール)"なのだろうと、メイは推測した。ただ、あの炎には、邪な何かが含まれていた様な気がする……。
いつしか、季節は冬になっていた。
薔薇園の薔薇には、毎朝霜が降りる。荒れ地まで行くにしても、霜柱を踏んで行かなければならない。
「私、シレジアの方に行ってみるわ。ついでに姉さんにも会いたいし」
ある日、ダリアが言い出した。
「え? じゃあ、私の授業は……?」
メイは不安そうに彼女を見上げる。ダリアは頬を緩めてメイの頭を撫でた。
「あなたはもう戦える。低級魔法でなら人に大怪我なんかさせないから、安心して魔法が使えるわよ」
不安そうだった彼女の顔が、みるみる笑顔に変わっていった。
「ほんとですか? やったー!」
駆け足でクラリスの許に飛んでいくメイを、ダリアは複雑な面持ちで眺めた。
「これでよかったのよね、兄さん?」
基地に出勤中のユリウスに、心の中で問う。
「言われた通り、上級魔法は一つも教えなかったわ。雷の中級魔法"電撃(トレント)"だって。これでいいのよね?」
ふっと肩の力を抜いて、ダリアは荷造りをしに部屋へ向かった。
メイは喜びに胸を膨らませて、ダリアの言葉をクラリスに伝えた。
「アテリースとパレだけはできないんですけどね」
最後に少し悪びれて付け加える。
「へえ、すごいじゃないか」
「……ほえっ?」
クラリスの思いがけない感想に、メイは目をぱちくりさせた。
「ところで、シーク君は?」
「読書だろ。あいつはいつも、魔王に関する書物ばかり見てるんだ」
「ってことは、図書室ですね?」
「ちが……」
クラリスが止める間も無く、メイは部屋を飛び出した。図書室へ走っていき、勢いよくドアを開ける。
「シーク君! 私――」
……ミティーユが昼寝をしていた。
「……なにー? このじかんはわたしのかしきりよー。ここはおひるねべやなのー」
どうやら起こしてしまったらしい。彼女はゆっくりと頭を起こすと、普段の上品さはどこへ行ったのやら、ぼんやりした表情で訊いてきた。
「あっ、ごめんなさい。てっきりシーク君がいるものと……」
「ん……シークくん? ……あ、あのこなら、じ……ぶんの……へ……や……」
再び夢の世界へと戻っていったミティーユを残し、メイはシークの部屋へと向かう。
「シーク君! 私、魔法が上達したよ! 授業も終わりだって!」
シークは本を閉じ、メイの方を向いた。無表情な目付きだ。
「ここまで上手になったのも、シーク君のおかげだよ。シーク君が教えてくれたこと、今では全部分かるよ。シーク君はいつも正しかったんだね。ありがとう!」
それでも、彼は口を閉じたままだった。
「……私、何か悪いこと言った?」
「いや、この本のせいで少し頭が……」
メイはシークの手に載っている本を覗き込んだ。『一流画家の描く魔王の想像肖像画集』とある。メイはそれを受け取ってページをめくった。
その瞬間、彼女の目は点になった。
角と翼が生えた赤い目の老人やら、紫色の髪の先端が蛇になっている幼児やら、訳の分からない怪人が並んでいる。
中でも一番ひどいのは、個性的な画風に定評のあるソカピの一作、『麗しの女王バイゼン』。
魔王は女性であるという説を元にした作品であるが、彼の画風では男女の区別は困難である。しかも、歯は黄ばんでいて牙さながらだし、鼻血を流しながら笑う様は非常に怖い。極め付けに、赤と緑のマーブル地に青とオレンジのリボンをふんだんにあしらったドレスを着ていた。
「……ロムドさん?」
メイは、それだけ呟くと、黙りこくってしまった。
「何やってんの、二人とも」
様子を見に来たクラリスの声を受け、二人は我に返る。
「バ、バイゼンの正体はロムドさんだったんです!」
「……は?」
シークはメイから画集を取り上げて、机の上に置いた。
「出よう、この屋敷から」
「そうだな、ダリアさんも旅に出るそうだし、必然的にそうなるな」
クラリスは賛成した。
「よし、今から出発だ」
「えー、やだ! もう一度だけ、あのふかふかベッドで寝たいよー」
文句を垂れるメイを、シークはきっと睨んだ。
「だめだ! これ以上バイゼンのイメージが壊れない内に城へ行かなければならない!」
シークの剣幕に、メイはびくりとする。
「……ん、分かった」
彼女は渋々、荷造りを始めた。
夕方、仕事から帰ってきたユリウスは、三人の客人はおろか、妹までいなくなっていたので、呆然と立ち尽くした。
「ベルス! せめて私が帰るまで引き留めてはおけなかったのかね!」
「ユリウス様、私はそのような命令は受けておりません」
「むうっ、機転の利かん奴め!」
そんな状態でも、ミティーユはぐっすりと眠り続けていたのだった。
スポンサーリンク