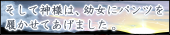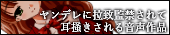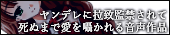『イルミナ』 中3の時書いたラノベ等身大すぎワロタww →企画トップページ
第八章 血に科せられた運命(さだめ)
まだ日も昇り切らない頃に、アンシェローク夫妻は話し合っていた。
「ダール、そろそろ新しい年が来ますね」
「そうだな」
「そろそろメイが旅立ってから八ヶ月が経ちますね」
「そうだな」
「誰かしら、あの子は一ヶ月もしたら帰ってくるなんて言ったのは」
「……私だ」
ファレーナは、数ヶ月間に渡る不眠に苦しんでいた。夜な夜なダールを起こしては、文句を言うのだ。
「ああ、きっとあの子、人攫いに売られたりして、不幸な目に遭ってるんだわ。もしかしたら、もう死んでしまったかも……」
外で、ざくっと雪が潰れる音がした。
「ねえ、あなた、やけに近くで聞こえなかった?」
「屋根から雪が滑り落ちたんだろう」
ファレーナは腑に落ちないといった様子で玄関へと向かう。が、ドアを開けようとすると、何かにぶつかって二十センチしか開けられなかった。彼女はその隙間から外を垣間見、あっと声を漏らす。
「人の手だわ!」
ダールも駆け付けた。
「あの手、どこかで見た様な…」
「そうですね。それにしても、なんて白い、綺麗な手なんでしょう」
夫婦は顔を見合わせた。――メイの手だ。
そうと分かったファレーナの動きは、六十四歳の女性とは思えぬ程俊敏でたくましいものだった。最寄の窓から家を飛び出し、何と十秒後にはメイを抱いて玄関に立っていた。
「メイだわ! 本当にメイだわ!」
「それはいいから、診せろ!」
ダールが診察した所、特に肉体的なダメージは無いという事が分かった。慌てふためいていたファレーナは、急激に元気を取り戻す。
「良かった。じゃあ私、メイと寝ます」
「……は?」
「何だか、安心したら眠くなってきたわ」
彼女はどこから出るのやら分からない怪力でメイを持ち上げ、花歌を歌いながら寝室へと足を運んだ。ダールが気になって様子を見に行くと、ファレーナがメイの頭を撫でながら言う。
「この子、成長するどころか、むしろ痩せたみたい。起きたらいっぱい食べさせなきゃ」
ダールは、ファレーナが親馬鹿で過保護だと、改めて確信した。だが、メイが著しく母性本能及び父性本能を呼び起こす力を持っている事も、また事実だ。彼は複雑な疎外感を覚えた。妻に娘を取られ、娘に妻を取られたような気がして。
久しぶりにイルミナ族の人々に会いに行こうと思い、探検家は出発した。彼らの安全の為に世間には公開していないイルミナの村への地図を持ち、旧友に会える喜びに胸を躍らせ、探検家は進んでいった。雨が降ろうとも立ち止まる事なく。
村の付近で、彼は妙な臭いを嗅いだ。焦げ臭い。よからぬ予感がして、探険家は足を速める。何事も無ければ良いと願ったが、そこに広がっていたのは、地獄だった。
あろう事か、全てが灰と炭でできていた。雨に打たれるだけで焼けた家は倒れ、よく見るとその辺におびただしい程の死体が無造作に転がっている。
何があったのだろう。これがかつての平和な村なのか。探検家は手がかりを求めて歩き続けた。
ふと、子供の泣き声が聞こえてきた。姿を見付けるのに、然程時間は要しなかった。黒い世界の中に、ぽつんとただ一人、少女が膝を突いていたのだ。
最初はかける言葉が無く、遠くから様子を伺った。多くのイルミナ族が黒髪であったのに対して、彼女は栗色の髪をしている。年はまだ十歳にも達していない様に見受けられた。
とりあえず彼は少女に気付いてもらおうと、近寄っていく。
「何があったのかな?」
尋ねても、分からないと泣き叫ぶだけだった。仕方が無いので、探検家は少女の手を引いて村を出ようとした。すると、激しく拒否された。
「だめなの! 村を出ちゃいけないってルールなの!」
「これが村かね?」
「……」
少女は再び泣き出す。
「私の村に来なさい。若者は都会に出ていってしまったが、優しい老人がお前を迎え入れてくれるよ。私には子供が無いから、妻と一緒にお前を引き取ってあげよう。名前は?」
「……メイ」
「そうか、そうか」
探検家は少女を連れ帰った。妻は大喜びした。村の人々も皆、少女の虜になった。
少女の心の傷は少しずつ癒えていき、やがて彼女は本来の明るさを取り戻したのだった。
何だろう。とても暖かくて、気持ち良い。
ここ、天国かな。
メイはゆっくり目を開ける。なぜかそこに、ファレーナの顔があった。
「えー、おばあさんも死んじゃったの……?」
しばらくして、ファレーナに抱かれている自分に気が付いた。彼女は驚いて周りを見回す。――ここ、おじいさん達の家だ!
メイは急に震えだした。何で私、生きてるの? 死ななきゃいけなかったのに!
ファレーナの腕を取り払ってベッドから下りた時、ファレーナが目を覚ました。
「あら、メイ、起きたのね」
彼女は手を伸ばしたが、
「わ、私に触らないで!」
メイに拒絶されてしまい、多大なショックを受けた。
「どうしたの、メイ?」
メイは答えないまま駆け出す。自分の部屋に閉じこもり、隅にうずくまった。
なぜ私はここにいるの? 家族への面会は、科人には許されてないんだよ。それなのに私、無意識の内に"移動(アテリース)"しちゃったんだ……。
「メイ、入るよ」
ダールの声がした。
「だめ! 私に近付かないで!」
メイは立ち上がり、必死で叫ぶ。
「おじいさんは知らないかも知れないから、教えてあげる。イルミナ族って、本当は凶悪なんです!」
扉の向こうは沈黙した。
「怖いでしょう? 私のこと、嫌いになったでしょう?」
「いや、全然」
ドアノブが回った。
「何でですか! 私は危険なんですよ?」
ダールが入ってきた。悲しげに微笑んで。
「私は兵器なんです!」
ダールは迷う事無くメイに歩み寄る。
「私は――」
そして、優しく抱き締めた。
「お前が何なのか、教えてあげよう。お前は私とファレーナの娘だよ」
「違います! 私はイルミナ族です……」
メイはダールの胸に顔を埋めて、涙を流した。決して無くなる事の無い決定的な違いを、彼女は知ってしまったのだ。
「だから何だ。メイはメイだ。私たちの大切な子だ……」
メイはダールにしがみつく。
「でも私達は、いちゃいけないんですよ。レイールさん……バイゼンが言ってました。死ななきゃいけないんです!」
声を上げて泣いた。いつの間にかファレーナも寄り添っていた。
「もっと早くに知らせてやるべきだったね。私達は全て知っていたんだよ。メイが生まれる少し前から、イルミナ族の歴史を」
ダールは抱く力を強め、メイと共に涙した。
「私達はお前を愛している。お前がいなければ生きていけない。お願いだ、死ぬなんて言わないでくれ」
ぐすっ、とメイのしゃくる音が響く。
「……私は、生きててもいいんですか?」
「もちろんだ」
「私達が守ってあげますよ、メイ」
嬉しかった。正直に言うと。
どんな時でも、自分の存在を認めてくれる人がいるのは、幸せな事だ。
罪が許された様な気分になる。
いや、そんな理屈などいらない。
ただ、嬉しいのだ。
メイは心行くまで泣いて、泣いて、泣いた。義理の両親は、その涙を全て受け止め、愛情に変換していった。
平和な日々が、また始まる。
昼になってから、メイは村人達に挨拶して回った。
「おや、メイちゃん、帰ってきたのかい」
「大きくなったなあ。と言ってやりたいところだが、ほんと変わってないねえ」
「ほら、かぼちゃ。プレゼントじゃよ」
多くが年老いた人々だ。または、幼児である。
「メイちゃーん、お帰りなさい」
「今までどこ行ってたのー?」
「家出したの?」
まだ悪など知らない彼らを、メイは非常に愛おしく感じた。
「うーん、どうかな。でもね、旅したってね、悲しいことばっかりだったよ。だから、みんなはずっとここにいて」
それでもいつかは、知ってしまうだろう。何だかとても切なかった。
ある日、ダールが屋根の雪掻きをしていた。メイは思った。魔法を使えば、安全に短時間でできる、と。しかし、そうすると、自分がイルミナ族である事を認める事になる。メイはそれが嫌だった。現に、ダールが「イルミナ族の真実を教えてあげよう」と意気込んだ際にも、首を横に振ったのだ。彼女はダールの姿を見て、無言で応援する。どうせ自分には雪掻きなどできやしないと分かっていた。……ここでも役立たずだ。
突然、ダールがユーモラスな踊りを始めた。
「おっとっとっと……!」
もとい、バランスを崩し始めた。仰向けになって、屋根から転げ落ちそうになる。
――"操土(ティエノン)"を使って。
メイは声を聞いた。そうだ、"操土(ティエノン)"は自在に土を動かす事ができる。その声が誰のものなのか考える暇は無い。
「ティエノンっ!」
ほぼ屋根と同じ高さにまで紫色の光を帯びた土が盛り上がり、ダールの体を受けた。その後は徐々に降りてきて、彼は地面にそっと横たわらされる。
「おじいさん、大丈夫ですか!」
メイが駆け寄ると、ダールは上半身を起こして弱々しく笑った。
「ありがとう、メイ。すごいなあ、こんな事ができる様になったんだね。……ふう、私も年だな」
「よかった、けがはないみたいですね」
こういう事に使うなら魔法もいいな、と思えてくる。一つ気がかりなのは、あの声だ。思い出そうとしても、不思議な事に、どんな声質だったのかさえ不明だった。
「ところでメイ、お前は旅の途中で魔法を習ってきたんだろう? だったら雪をどうにかしてくれ」
メイはダールの顔を見つめる。この人は、私がどれだけ自分の魔力を恐れているのか、分かっていないのだ。できる事なら、イルミナ族をやめてしまいたいくらいなのに。
「あ、悪かった、やっぱりいい」
そんな彼女の気持ちを知ってか知らずか、ダールは自力で雪掻きを再開した。
一年の最後の日、村人達が集まってパーティーを催した。メイはとても楽しかったが、酒が出てくると怒って説教を始めた。それ以外は普通のパーティーだ。子供は早々に寝かされ(もちろんメイもである)、大人は夜が明けるまで遊んだ。
新しい一年の最初の一ヶ月は、楽しく幸せに暮らしたとしか言い様が無い。三角形に切り揃えられたもちを食べ、「キツネハ」と呼ばれるスポーツをし、雪だるまを作った。本当に嫌な事など忘れてしまいそうだった。いつしかメイは、今まで「旅をする夢」を見ていたのではないかと思う様になっていた。この日々がずっと続けばいい。ただの人間として生きていたい。だが、少女の願いは、儚く裏切られる。
二月二日、アンシェローク家を一人の男が訪れた。容姿端麗、金髪碧眼のその男は、白く輝く歯を見せつつ、ファレーナに言った。
「メイ・アンシェロークさんにお会いしたいのですが」
ファレーナは目をしばたく。
「メイにお客様なんて珍しいですね。あの子なら広場で遊んでますよ」
「そうですか」
男が去った後、彼女は一人呟いた。
「素敵な殿方ね。ダールも昔はそれなりに……」
その頃メイは、村の幼児達と季節外れのキツネハをやっていた。
「エルちゃんスマーッシュ!」
「もぎゅー、やられたぁ」
後のセリフはメイのものだが、果たしてこれがサービスなのか本音なのか、彼女以外に知る者はいない。様子を見ていた先程の男は、笑いを堪えながら近付いてきた。
「メイって人、知ってるかな」
「私です」
男の表情が固まる。
「大人をからかうものじゃないよ。俺が探しているのは十五歳のメイだ」
メイは困ってしまった。
「だから、私が十五歳のメイです」
「……そうか」
途端に、男の目付きが変わった。鋭く、厳しく、それは戦士の目である。
「ならば死んでもらおう!」
素早く振り下ろされた剣を、メイは幻でも見るかの様に凝視した。
――"風の刃(ヴィエンシル)"で対抗して。
またあの声だ、と思った瞬間には、すでに呪文を唱え終わっていた。
弓なりに曲がった緑色の光線が、剣を跳ね返す。
「ほう、頭がいいな」
男は少し驚いた顔になった。
「あなたは誰ですか? いきなり攻撃してくるなんて」
幼児達が泣き出し逃げていく中、メイは一人、男と対峙する。
「俺はリカルド。バイゼン様の腹心だ。あの方の御命令で、イルミナ族のお前を消しに来た」
「人違いです」
本人も予期せぬ言葉が口から出た。
「確かに私はメイですけど、イルミナ族なんかじゃありません! ほら、髪だって茶色いし」
「馬鹿か、お前は。そんな言い訳が通用するとでも思うか!」
再度切り込んできた男、リカルドを、メイが放った"水の弾(アジュビア)"が迎え撃つ。あの声に従ったのだ。リカルドは水の力でやや後退した。
「ふ……、そうか、認めたくないんだな。けどな、その並々ならぬ魔力が何よりの証拠。運命からは逃れられないんだよ、メイ・アンシェローク!」
運命からは逃れられない。そう、彼の言う通りだ。
メイは心の奥では気付いていた。あの声が、いや、音声として感じ取ったと誤認していたものが、実は自分の本能的な思考なのだということに。
イルミナ族としての戦闘の知恵。きっと天性の能力に違いない。ただ、呪文がうろ覚えだった頃は、覚醒していなかったのだろう。
私はイルミナ族なのだ。
どこまで逃げても。
どんなに否定しても。
この血は変わる事無く体内を流れ続ける。
生きている限り。
「嫌あああっ!」
メイは前も見ずに走リ出した。彼女の足ではリカルドから逃げ切れるはずが無いのに、何も考えずひたすら走っていた。やがてその足は森の土を踏んだ。
ふと思う。私は何の為に走っているのか。村の人に迷惑をかけない為? いや、違う。これは単に逃げているだけ。尊い自己犠牲でも何でもなく、ただ逃げているだけだ。
私は生きる為に走っている。それが分かった時、残酷なリカルドの声が耳に飛び込んできた。
「そろそろ鬼ごっこはおしまいだ。死ね!」
剣が風を切る音。
――私は死にたくない!
リカルドは、剣を振り切る事ができなかった。
その前に赤い"火球(フィエゴ)"に突き飛ばされ、木に打ち付けられたのだ。
メイが恐る恐る振り返ると、彼は木にもたれ、胸の辺りから煙を出していた。剣はやや離れた所に落ちている。
「大丈夫か、メイ?」
ふいに声がした。後ろを確認しなくても分かる。この懐かしい、低めの声の持ち主は――。
「クラリスさん……」
「待たせたな」
「……」
メイは唐突に泣き出してしまった。安堵と喜びともの悲しさが、あまりにも一気に押し寄せてきたからだ。
「相変わらず泣き虫だな」
シークも現れて、リカルドの状態を見ている。リカルドには悪いが、助かったと思うと嬉しい。だが、
「あの人、生きてますよね?」
そう尋ねた瞬間、
「不覚だったな、シーク」
リカルドがシークの首を掴んで立ち上がった。
「俺は水びたしだったんだよ、あの小娘のせいでな」
「ちっ……」
シークは"電光(トレノ)"でリカルドの手を弾き、着地する。リカルドの服は少しだけ焦げていた。
「城壁の穴から飛び出して、"移動(アテリース)"したんだってな。バイゼン様が探していらっしゃったぞ。この悪ガキが」
「お前の様なナルシストに言われる筋合いは無い」
リカルドは鼻で笑うが、その仕草がすでにナルシストだった。
「ここでお前を殺っても、バイゼン様には分からないよな?」
「それがどうした」
彼は薄く笑みを浮かべる。
「お前、ずっと前から目障りだったんだよ。ちょうどいい、今消してやる」
リカルドが横様に飛び、剣を手にした。シークも瞬時に判断し、太刀をかわしつつ"風の刃(ヴィエンシル)"を放つ。それはリカルドの首筋をわずかに外れ、木々を切り倒した。森の鳥達が、慌てて逃げていく。
そのやかましい鳴き声と共に、クラリスは刺突を試みた。が、イレイヴは虚しく空を掻き、逆に彼女は敵に背を晒す形となった。
「修行が足りないな、女」
リカルドの剣をクラリスはとっさに避ける。しかし、バランスを崩した彼女は相次ぐ攻撃を避ける事ができない。鈍く銀色に光る切っ先が、彼女の脚の肉を切り裂いた。流れ出る鮮血が靴を赤く染め、また靴から滲んで足元に水溜まりを作る。なおも走ろうとするクラリスだが、思うように脚が動かず、転んでしまった。
「シークの前に貴様の息の根を止めてやるよ」
剣を振り上げたリカルドにシークの"電光(トレノ)"が命中し、彼は剣を取り落とす。クラリスはそれを適当な場所に投げ飛ばした。剣はメイの近くで動かなくなる。
「うわっ、えーと、私も何かしなきゃ」
その時、メイの本能がとんでもない事を思い付いた。
「フィエブレ!」
彼女は灼熱の炎で剣を焼き始めた。力を抑制せず、思う存分焼く。すると、たちまち剣が溶け、ただの金属の塊と化した。
「くそ、よくも俺の剣を……!」
痺れが解けて行動可能になったリカルドが、メイに襲いかかろうとする。その背後から、シークは狙いを定めて青と水色の閃光を放った。"流水(アグア)"と"冷気(ニエベ)"を同時に使ったのだ。それらはリカルドの足を大地に捕縛し、かじかませ、動きを封じた。
「どうする、リカルド。諦めて立ち去ると言うのなら、何もするつもりは無い。だが、これ以上俺の仲間に手を出すと言うのなら……」
赤い眼光が、強い思いを秘める。
「容赦はしない」
リカルドはしばらく雷に打たれたような顔をしていたが、数瞬の後、例のナルシスト的な笑みを見せた。
「ふふっ、『仲間』か。そんな儚いものが大切か? 一人じゃ淋しいって事なんだな」
「失せろ」
「足が凍り付けなのにか? 馬鹿を言うな」
シークは彼を無視してクラリスに歩み寄った。
「大丈夫か」
クラリスは苦笑した。
「何とか」
「治してやるから、じっとしていろ」
シークの手から、柔らかい桃色の光が発せられる。
「何してるの?」
メイも二人の傍に寄り添って、クラリスを見守った。
「これは治癒の魔法、レクペラシオン。強い魔力と高い技術が要求され、基本要素の中でも最高の難易度を誇る魔法だ。基本要素の上級魔法を全てマスターし、応用を使いこなす魔導士でも、会得できない場合がある。残念だが、お前には逆立ちしても使えないだろう」
クラリスの傷口がみるみる塞がっていく。
「そんな魔法が使えるシーク君って、やっぱりすごいね」
「……このくらいの傷、治せる者などざらにいる」
照れたのか、シークは不自然に顔をしかめた。その頃には、クラリスの怪我は跡形も無く消え去っていた。
「ありがとう、シーク。もう大丈夫だ」
クラリスが立ち上がって脚を上下させる。
「助けてくれてありがとうございました。二人とも、私の家に来ませんか?」
メイはそう提案した。ふと、不思議な事に気が付いた。
「そう言えば、何でこの村に私がいるって分かったんですか?」
「それは秘密だ。じゃ、案内して」
メイが深く追求しなかったので、クラリスはほっとする。デランの話はしたくなかった。メイも怒っていない様だし、このままずっとデランの事など知らなければいい。そう考えた矢先、
「弟さんには会えましたか?」
と、メイが口にした。
「えっと、それは……」
こいつは全て知っているのだ。知っている上で、私を許容してくれているなんて。
「あ、会えたよ。魔王の元を離れて、自立していったけど」
信じられない。
「あの時はごめん」
「何あやまってるんですか? 家族に会いたいと思うのは、クラリスさんが愛情豊な人だからですよ。気にすることなんて、ないと思います」
メイは真顔で言った。
「私なんかに優しくしないでよ。余計に悲しくなるじゃないか……」
クラリスは右手で顔を押さえて、一粒だけ涙を雫した。
「あんたが怒ってくれれば、私の罪悪感だって、少しは晴れるのに」
「クラリスさん……」
二人は、ゆっくりゆっくり、アンシェローク宅に向かっていった。
「ちっ、面白くないな」
ようやく氷が溶けて自由になったリカルドが、不機嫌に呟く。
「シークの奴、また大切なものを手に入れやがった」
彼の足は紫色になり、じんじんとした痛みがあったが、それでも時が経つと共に、幾分か楽になった様だった。
「あいつはいつでもそうだ。どんどん手の届かない所へ行っちまう。運のいい奴だよ、全く。バイゼン様に拾われてなかったら、落ち零れていただろうに」
立ち上がったリカルドは森を見渡したが、どちらへ行ったら良いのか分からず、かつて剣であった金属のある方向に歩き出した。
「馬鹿魔力(ぢから)だな、さすがイルミナ族だ」
横目でちらりと戦いを共にしてきた友の変わり果てた姿を見、そのまま歩き続ける。
「俺はそろそろ退き時なんだろうか?」
軍人の子として教育を施され、周囲の望むまま入隊し、ついには一国の元帥とまで登り詰めた自分が、なぜあんな年端も行かぬ子供に負けなくてはならないのか。
「完敗だ、シーク」
木々の間から街道が覗けて見えた。リカルドは重い足を引きずって、何とか外に出る。
「やっと出られ――」
その両眼は、右に五、六メートル行った地点に釘付けになった。
「嘘、だろ」
何と、ガイル・トラバース率いるルーヴァの一隊がそこにいた。通常の十五人に加え、くすんだ金髪の中年男性が一人。厳粛な制服を着ており、他の者より偉そうだ。
「アルボル司令官、あの男は、もしや魔王の腹心のリカルドでは?」
氷の瞳をした男、ガイルが言う。
「そうだな、武器は持っておらんが、間違い無さそうだ。捕らえろ!」
十四人の隊員が、リカルドに飛びかかり、取り押さえた。それは一瞬の出来事だった。ガイルは無表情で彼を観察している。
「殺せ!」
リカルドは叫んだ。
「俺は軍人だ。死など恐れはしない。俺を殺せ、ルーヴァ!」
無様だ。本人もルーヴァのメンバーも、皆思った。
「如何いたしましょうか」
ガイルがユリウスに指示を仰ぐ。
「魔王の腹心なら、ザディーラがいるからな。まあ良い、聞き入れてやれ」
「では、私が」
ローゼ・アルボルは自ら進み出た。彼女はもう、れっきとしたルーヴァの一員である。
「どう処されたいですか」
リカルドは数秒の思案の後、剣で、と答えた。
「君の様な美人に殺ってもらえるなんて、俺はラッキーだ。なあ?」
ローゼは返事すらしない。
「ちっ、ノリが悪いな。最期ぐらい、俺らしくキザに決めさせてくれよ」
「あなたの血が平和への糧となる事を喜ぶべきです」
彼女は何の合図も無く、機械的に剣を振り下ろす。
自分の胸が冷たいものに貫かれていく感覚を、リカルドは味わった。あたかもメーターが振り切れたかの様に、度を過ぎた痛みは痛みとして認識されず、ただ彼は、最後に見る光景を堪能していた。
飛び散った血しぶきが、べっとりとローゼの若い顔を飾る。頬に垂れた血液が、赤い涙を思わせた。この女は、俺の為に泣いているのだ。これが死か。これが軍人として最高の名誉なのだな……。
「罪人リカルドの死亡を確認しました」
血の海に立つローゼは、剣にまとわり付く血を、平然とその辺りに振り落とした。
「こら、ローゼ、それはマナー違反だろう。この道は一般人が通るんだから」
「あっ、そうですね。つい癖で……」
彼女は決まり悪そうに頭を下げる。
「お前は近くの川で顔を洗って来い。他の隊員は死体の後始末を!」
そうして、見事な手際で、死刑執行の跡が消されていった。
「ほら、ここが私の家です!」
メイは「ただいまー」と叫びながらドアを開けた。ダールが出迎えてくれる。
「お帰り。おや、その人達は?」
「旅の仲間です。この人はクラリスさん。こっちがシーク君」
ダールは何やら大袈裟なリアクションをとり、クラリスに社交辞令を述べ、シークと握手した。
その上、いつの間にかファレーナが茶と菓子を運んできて、接客のムードを作っていた。彼らは四角いテーブルの周りに椅子を置き、座る。
「ところで、さっき子供の泣き声が聞こえたんだが、何かあったのかね?」
メイはにこやかに答えた。
「あ、不審者に襲われたんです」
「不審者ああっ!?」
「でも、この二人がやっつけてくれましたよ」
ダールとファレーナは目を剥いて怒り出した。
「クソ不審者め! うちのメイに何て事を!」
「変態だわ! ルーヴァに突き出してやる!」
「……?」
メイが退いていると、クラリスが耳打ちした。
「あのさ、この人達、不審者イコール痴漢だと思ってない?」
「ちかん?」
「まあいいけど……」
落ち着いたところで、メイは話を切り出した。
「私、分かったんです。イルミナ族から逃げちゃいけないんだなって。だから私、もう一度旅に出て、バイゼンを説得してきます!」
九ヶ月前と同じだ。同じ表情、同じ声。ただ、今の彼女には、少しだけ強さがある。
「シーク君、知ってた? バイゼンは、世界が満足いく状態になったら、命を絶つつもりなんだよ」
シークは黙っていた。
「私は、バイゼンがやめてくれないと嫌です。強制的な世直しとか、死ぬとか、殺すとか。だから、もう一度行ってきます」
ダールが徐に頷いている。一方、ファレーナはヒステリックに髪を振り乱した。
「いやですよ! もう旅なんて許しませんからね。お願いだからやめてちょうだい!」
脅す様な目だ。メイは潤んだ瞳で見つめ返した。
「ファレーナ」
ダールが妻に優しく語りかけた。
「子供はね、いつかは親の許を離れていってしまうものなんだよ。ずっと手元に置いておきたい。永遠に自分のものであって欲しい。けれども、指の間を擦り抜けて、新しい世界へと飛び去ってしまう。そういうものなんだよ」
しばしの沈黙の後、ファレーナは小さな声で
「分かってるわ」
と言った。
「いつまでもメイを縛っていては、可哀想ですものね……。私、諦めます。ただし、怪我なんかしないで。お願いだから」
彼女は弱々しく微笑み、それからわっと泣き出して、自分の部屋へ駆け込んだ。ダールの言う事はいつも正しい。それがまた悔しかったのだ。
「さて、メイがイルミナ族として生きてゆくと言うのなら、私が知っている全ての事を教えてやろう」
ダールが改まって手を組んだ。
「ひょっとして、あなたが『イルミナ族の真実』を書いたD・アンシェロークさんですか?」
「そう、あれは私の著書だ」
クラリスは手を打って喜ぶ。アルタで知ったメイの姓アンシェロークは、いつかの山村で読んだ本に書いてあった姓と同じだったのだ。道理で、どこかで聞いた事があると思った訳だ。
「君はあの本を読んでくれたのかね? あの本はネーミングがいまいちだったらしく、ほとんど売れなかったんだよ。メイの為にも、イルミナ族はもう危険では無いと伝えたかったのだが……。クラリスさん、よくぞ見つけてくださいました」
「はあ……どういたしまして」
ダールは昔の冒険話でもするかの様に、生き生きとした表情を三人に向けた。
「さ、お聞きなさい。私の長年の研究から分かった、イルミナ族の物語を」
スポンサーリンク