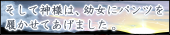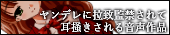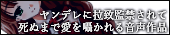第六章 散りゆく輩(ともがら)
雪が降っていた。
銀世界を行く三つの人影が、丘の上でふと立ち止まる。
「見えるか。あれがエストカルト城だ」
シークは他の二人に注意を促した。
「あれが……」
あそこにデランがいるのだと思うと、クラリスの心は疼く様に熱くなる。
眼下に広がる静かな町。その奥に自らの姿を顕現させる、紺碧の城。
「夜の色だ……」
メイの表現は、言い得て妙だった。城壁の石材は濃紺の空、そして、振り撒かれたかの如く散らばる細やかな白い斑点は、満天の星さながらである。
「ついに、行くんだね」
彼女はごく自然に言った。しかし、
「いや、まだだ」
というシークの返事につまづいてしまった。
「どうしてー? 早く行こうよ」
「まずは俺がバイゼンに会って、お前達と話し合ってくれるように頼んでくる。それまで待っていろ」
クラリスが鋭く質問した。
「頼んでくるって……。シーク、あんた、魔王とどういう関係なんだ?」
シークは、ゆっくりと彼女に向き直る。
「聞いても、俺を信じ続けるか?」
「どういう事?」
戸惑うクラリスの代わりに、メイが答えた。
「当たり前だよ。今まで一緒に旅してきて、シーク君がいい人だっていうことはよく分かってるから」
シークは二人の仲間を交互に見つめ、やっと決心して口を開いた。
「俺は、バイゼンの後継者として育てられてきたんだ」
「後継者……」
メイは大して気に留めなかったが、クラリスの方はそうはいかなかった。
「あんたは魔王の息子なのか?」
「息子? 魔王の?」
やめてくれ、と苦笑するシーク。
「バイゼンは三十三歳、十五歳の子供がいる様な歳ではない。それに、あの人は女になんか興味ないんだ。ついでに言うが、『魔王』と呼ぶな。ださ過ぎる。いくら何でも、バイゼンが可哀想だろう」
「まあ……、そうだな。癖になっててやめられないけど」
クラリスは納得させられた。
「それにしても、何で魔王の後継者のあんたが、城を出て旅なんかしてるんだ? 義理の親に嫌気が差したのか? 反抗期か?」
「馬鹿を言え。俺は今でもバイゼンの事を、父とも兄とも慕っている。だからこそ、バイゼンを救う為に城を抜け出したんだ」
「どういうこと? バイゼンは病気なの?」
メイが訊いた。
「病気か……。確かにな。もっとも、その病は良心故のものだが。バイゼンは、世界を変える為に覇気を振るっている。一方で自分がした事に対する罪悪感によって、常に心を痛めているんだ。そんなバイゼンの苦しむ姿を、俺はもう見たくなかった」
「やっぱり! バイゼンはただの悪い人じゃなかったんだね!」
感激して喜ぶメイとは反対に、クラリスは疑いの念を抑え切れなかった。
「けど、私は許さないよ、シーク。私達姉弟を引き離した魔王を、絶対に許す事なんかできないよ。さあ、教えな。魔王を救う事と、私達を城へ連れてく事とは、どういう繋がりがあるんだ?」
シークは目を合わせずに呟く。
「イルミナ族が必要だった」
「えっ……?」
メイの目に、驚きの色が浮かんだ。
「私、今まで一度もシーク君に、イルミナ族だって言ってないよ?」
「イルミナ族は特徴的な種族だからな。言わずとも知れた事だ」
「ふーん、そうなんだー。それで、どうして私が必要だったの?」
クラリスがシークを睨み付けた。
「あんた、メイを利用しようとしてたんだな?」
自分の事は棚に上げている。が、シークはその事を知らないので、気まずそうに顔をしかめた。
「俺が説得しようとしても、バイゼンは聞いてくれない。だが、イルミナ族なら、恐らく聞いてくれる。そう思ったんだ」
「バイゼンは、イルミナ族が嫌いなんじゃないの?」
メイの問いに、彼はまた目を逸らす。
「真実はバイゼン本人が教えてくれるだろう。俺の口から言うべき事ではない」
不安げなメイの顔が見上げていた。
「そんな顔をするな。俺は今から城へ向かう。きっとバイゼンなら、お前達を通してくれるはずだ」
「……うん」
「俺が迎えに来るまで、ここにいるんだ。いいな?」
「うん」
立ち去ろうとするシークに、クラリスが尋ねる。
「城の周りの町は何なんだ? 魔王に支配されているのか?」
振り向き様、シークは笑ってみせた。
「魔王の部下の家族という事で迫害されてきた人々の町だ。バイゼンはいたずらに植民地を作ったりはしない」
そう言うと、"移動(アテリース)"で消えていった。
十七年前の事だ。
ある貴族が、旅先で非常に魅惑的な女を見かけた。彼女は艶やかな黒髪に、妖美な赤い瞳を合わせ持っていた。貴族はその珍しさに惹かれ、その土地に何ヶ月も留まった。そして、遂に結婚を申し込んだ。
女は喜んで受け入れた。実は、女も貴族を心密かに愛していたのだ。彼女は男に従って故郷を後にした。
やがて、彼女は美しい双子の兄妹を生んだ。母親の血を色濃く受け継ぎ、目は赤茶色だった。夫婦は、きりりと整った容貌の二人を愛で、大切に育てた。子供達は才能に恵まれ、健やかに成長していった。
だが、いつしか、貴族の男は妻を愛せなくなっていた。以前夢中になった赤い瞳が、気味悪く思えてきたのである。
双子が六歳になった年、夫婦は子育ての事で言い争った。
「あの子達はここで私が教えます! 学校になどやらないで下さい!」
「黙れ! あいつらはシレジアの学校に入れるんだ!」
「学校に行ったら、瞳の色をからかわれてしまいます! お願いですから、どうか、ここに置いて下さい!」
女は、自分の幼い頃の屈辱を子供にまで味わわせたくなかった。だから、必死で頼んだ。
しかし、
「いい加減にしろっ!」
男が
「あなた……」
女を
「お前ら親子三人、みんな赤い目をして、気味悪いんだよ!」
殴った。
女の赤い瞳から、涙が零れ落ちる。
「昔は、私のこの眼を愛してくださったのに……。どうして……」
彼女は部屋にこもって泣き続けた。
それから幾日も経たない内に、最大の不幸がやってきた。男が見知らぬ女を屋敷に連れてきたのだ。
「あなた、その人は……?」
「私の妻だ。お前こそ何だ、何故ここにいる?」
「わ、私は……」
女の体は震え出し、手で押さえた口からは嗚咽が漏れた。
「私は、あなたの妻ではないのですか!?」
「ああ、私はお前の様な妖しい女は知らないな」
「このっ……」
人でなし? 嘘吐き? 気持ちを言い表せる言葉が無い。
「今すぐここから出て行け。二人の怪物と一緒にな」
「怪物ですって? あなたの子供なのですよ! よくもそんな……!」
その時、双子が現れた。小さな手に荷物を抱えている。
「お母さま、メイドさんがね、外に行きなさいって」
少女が言った。
「母上、あの女の人は誰?」
少年は、父親の隣の女性を見やった。そして、子供心に、今何が起きているのかを理解した。
「行こう、母上」
「そうよ、気にしちゃだめ」
少女も勘付いたようだ。女は双子の手を取り、囁いた。
「そうね、行きましょう」
行く? でもどこへ?
女が思い付けた場所は、一ヶ所しか無かった。
主人の庇護を失い、馬車に乗る事さえできなくなった親子の移動は、自らの足に頼るほか無い。幼い子供を連れての旅は、極めてゆっくりだったが、数ヶ月後、三人は汚い町に着いた。
「なあに、この汚いとこ?」
「お母さんの生まれた所ですよ」
「ふーん」
故郷には辿り着いたものの、女はどんどん生気を失っていった。もはや彼らの生活は成り立たなくなっていたのだった。絶望した女は兄妹を連れて滝に向かった。
「お母さんはもう駄目です。ごめんなさい、死なせて……」
双子は哀しげな顔になった。
「お母さま、行かないで!」
「僕たちを置いていくつもりなの?」
女が涙ながらに提案した。
「では、お母さんと一緒に来ますか?」
双子は固まった。やがて、少女が口を開いた。
「私、いくよ。お母さまが一人じゃかわいそうだから」
「僕は残る。僕には、まだやりたいことがあるから」
少年は泣きそうな目をしていた。女は静かに息子の髪を撫でた。
少女が少年に別れの言葉を送る。それは、信じられない程軽い調子だった。
「さびしくなるね。一人で生きるのって大変だよ。頑張ってね。じゃ」
女は少女を抱き締め、青い滝に身を投げた。
不思議な事に、微笑んでいた。
少年は独りになった。
一人の男が手を差し伸べるまでは。
夜になっても、シークは戻ってこなかった。メイはすでに雪の無い所で寝ている。
クラリスは一人でいたが、風の声に飽きて、メイの横に座った。ちなみに彼女は、ユリウスの屋敷を出てからこっそり買ったダークブルーのコートを着ていた。
「いよいよだな」
もしも城でメイに何かあったら、嫌だ。
最近、メイが自分にとって愛(う)い存在になってきたという事に、クラリス自身気付いていた。
足手まといでも、利用価値が低くても、いつも一生懸命なメイの姿に心を打たれてしまったらしいのだ。
「この私が、ね」
まさか、デラン以外の人間を気にかけるなんて。メイには何か、普通の人間には無いものがあるのかも知れない。
「あんたに会えて良かったよ」
そう言った時、クラリスは人の気配を感じた。
「誰!?」
「あら、なかなか鋭い方ですね」
夕焼け色の髪の美女が――ソアラが後ろに立っていた。
クラリスは無意識の内に立ち上がり、イレイヴの柄を握る。
「何であんたが? シークはどうしたんだ?」
ソアラは天使の眼差しでクラリスに微笑みかけた。
「怒らないで下さい。私は何も、あなた方を襲おうと思って来た訳ではないのですから。ただ、シークは少し甘かったのです。あの子は今、反省室に入れられています。だから私が代わりに来たのですよ」
クラリスは青い眼光を保ち続け、天使の眼差しに抵抗した。
「まだ疑っていらっしゃるのですね。よくお考えになって下さい。私はバイゼン様の腹心。あなたなど、いつでも簡単に殺せるのです。でも、私はあなたに何もしていない。あなたが私を攻撃してさえ来なければ、私は何もするつもりはありません」
「……用件は?」
ソアラの目に、クラリスは負けそうだった。相手は睨み合おうとはしていないはずなのに、どうした事だろうか。微笑みが、怖い。
「メイさんを城に連れて来て下さい。そうすれば、あなたをデランに会わせて差し上げましょう」
「それだけ?」
「いえ、続きがございます。バイゼン様がおっしゃいました。デランの姉には、メイの命の保障は無いと伝えておいてくれ、と。そうでなくては騙す様だから、と。問題は、メイさんの命か、デランとの再会か、どちらに重きを置くかですね」
鼓動が高鳴る。メイか、デランか……。
「私に選べと?」
「選ぶ?」
ソアラは半ば嘲る様に繰り返した。
「あなたには、選ぶ必要など無いでしょう? 最初からメイさんを利用しようと思って連れてきたのではないのですか? 少なくとも、前のあなたの目はそう言っていました。それに、クラリスさん、あなたは城に来なくても構いませんが、メイさんには絶対来ていただかなくてはなりません。あなたが条件を飲まないのなら、今ここであなたを殺して、メイさんを攫っていきますよ。無駄な死をお望みですか?」
凍てつく様な夜風が、クラリスの肌を刺す。それなのに、首筋に冷や汗が流れた。
「あ……あんた達なんて、信じられるか! 第一、何でデランと私を引き離したあんた達が、私を城に招くんだ? メイだけでいいんだろ? そんなの戯言だ!」
「まあ、戯言だなんて。ひどい事をおっしゃいますね」
赤い髪が戦(そよ)いでいた。
「デランを連れ去ってしまったのは、バイゼン様の数少ない失敗の一つなのです。もっとも、半分はあなたのせいですけれど、クラリスさん」
「私の……?」
クラリスは、一瞬思考を止めてしまった。
「そうです。バイゼン様がデランの家の近くにいらっしゃった時、あなたはいつも外出していました。貧しい家に幼い少年が一人。それならいっその事、自分が引き取ってあげようと、あの方は思われたのです。しかし、デランに姉がいるという事が分かったのは、城に着いてからでした。一度この地を訪れた人間には隠れのまじないが効かなくなる為、帰すに帰せなくなってしまったのです」
大陸で一番美しいのではないかと思われる微笑を浮かべて、ソアラは語る。
「バイゼン様は、それは大変気の毒そうにしていらっしゃいました。だから、せめて今回二人を再会させてあげようと、それがあの方のお考えです。そして、私がメイさんと争わずに城まで連れて行くには、あなたの協力が欠かせません。お分かりいただけましたか?」
クラリスに思考が戻ってきた。
何を迷う事があるだろう。私はデランを取り戻す為にここまで来たのではないのか。デランとイレイヴだけが、私の全てではなかったのか。
……いや、今となっては、そうではないのだ。このいたいけな仲間を捨てる事などできない。こうなったら、ソアラを――。
「随分と弱くなられましたね」
剣を抜きかけたのと同時に、ソアラが言った。
「前のあなたは、そんなではありませんでしたのに。もっと強く、狡猾で、弟一筋でしたのに。何があなたを変えてしまったのでしょう?」
クラリスの手が止まる。
私は弱くなったのか……?
「初心にお戻りなさい、クラリスさん」
クラリスは、メイと組んだ日の決意を思い出した。
『本気で人を利用するつもりなら、常に冷静且つ無感情でなければならない』
いつの間にか忘れていたようだ、この事を。
私の本当の目的は、デラン。
デランただ一人。
「メイ、起きろ」
クラリスはメイを叩き起こした。震えているのは心のみだった。
「ほあー、まだ夜じゃないですかー」
「城に行くぞ」
途端に、メイの目がぱっちりと開く。期待と不安が混じり合った光が煌めいた。
「シークは城の方で待ってる。案内はソアラさんがしてくれるよ」
「ソ、ア……?」
横には、数ヶ月前に自分を殺そうとした女の顔が、雪明りに照らし出されていた。
「ソアラさん!」
「この前はごめんなさいね。謝りますから、許してください」
人のいいメイは、ソアラを信じて頷いた。
「では行きましょうか。こちらです」
三人は寝静まった町の中を進む。メイには、その一歩一歩がどれだけ危険なものなのか、知る由も無かった。彼女はただただ、バイゼンを救ってあげようと、それだけを考えていた。
そして、彼女達は、城の前で足を止めた。
固く閉ざされた門。紺碧の壁。辿り着きし目的の地。
メイの運命も、また、クラリスの運命も、この中にあるのだ。
「ソアラです。お開けなさい」
徐に扉が開く。
「お帰りなさいませ、ソアラ様」
中から、まだ幼さが残る面立ちの女が顔を出した。二十代前半といったところだろうか。オレンジ色の頭髪をポニーテールにしており、藍色の瞳が可愛らしい女性だった。三人が中に入ると、自動的に扉が閉まった。
「ご苦労様、クラリスさん」
ソアラはクラリスに微笑みかける。
「彼女は私の部下のルシーヌ。そろそろ門番の交代がありますから、彼女がデランの許へご案内します。私達はここでお別れですね」
「お別れって……?」
メイはクラリスを見つめた。
「クラリスさんは一緒じゃないんですか? 私、一人なんですか?」
クラリスは彼女を無視する。
「クラリスさんっ!」
だが、クラリスは黙ってルシーヌと行ってしまった。
「クラリス……さん……」
クラリスにもクラリスなりの用事があるのだろうとは思うが、やはり淋しい。メイは、何か冷たい物に触れた様な気持ちになった。
「さあ、もう逃げられませんよ」
突然腕を強く掴まれ、彼女ははっとした。ソアラが笑っていた。
「城の中では、バイゼン様以外魔法が使えません。あなたは無力です」
ソアラはメイの腕を掴んだまま歩き出した。
「あなたはこれから殺されに行くのですよ」
二人の靴の音が、鬱々と響く。階段に向かっている様だった。
「お気付きになりませんか?」
紫色の瞳がメイを捉えた。
「あなたは、クラリスさんに利用されていたのです。出会ってから、ずっと」
再び、雪が降り始めていた。
スポンサーリンク