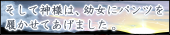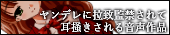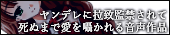『イルミナ』 中3の時書いたラノベ等身大すぎワロタww →企画トップページ
第十一章 夢の終焉
刹那、メイの体は宙に浮き、壁に打ち付けられた。
氷の槍が彼女の腹部を貫いている。
メイは虚ろにそれを見つめ、その場に崩れ落ちた。
「メイ!」
クラリスが抱き留めた時には、すでに意識が無かった。三人の視線は、暗闇から現れた一人のルーヴァ隊員、ガイル・トラバースに注がれる。
「まあいい、この子供は最初から始末する予定だった」
彼はメイをかばうクラリスに歩み寄っていく。
「何を……?」
そして、無言で槍を引き抜いた。
メイの華奢な身体から、大量の血が流れ出た。鮮血はクラリスの腰と床を真紅に染め上げる。シークは急いで回復魔法(レクペラシオン)を唱え始めた。
「助かるか?」
クラリスが心配そうに尋ねる。
「分からない。最善は尽くすが」
そうシークが答えた時、地響きと共に城が揺れ出した。とうとう、階下での戦いに耐え切れなくなったようだ。
もはや自由に身動きが取れない為、ガイルは魔王抹殺の指令を諦め、アテリースで脱出した。
クラリスは冷や汗をかきながら呼ぶ。
「私達は!?」
バイゼンが三人に腕を回して、光の力を利用した集団瞬間移動(ルス・アテリース)を行った。四人の姿が光と共に消え去った二秒後、城は倒壊した。
三月の雨はまだ冷たい。
ソアラは泣き濡れた森を歩いていた。
「バイゼン様……」
私のたった一つの愛。
真っ暗な心の中で、眩し過ぎる程に煌めく想い。
私が本当に欲しかったもの。
あの方の為なら死ねる。いつでもその覚悟はできていた。
でも、私が死んだら、この気持ちはどこへ行くのだろう?
消えて無くなるのか。
この遥遠なる時の中に、忘れ去られてしまうのか。
彼女は顔を上げた。城まで、まだ二キロもある。
次の瞬間、遠くからではあったが、ソアラは絶望的な光景を眼にした。
紺碧の城壁がひび割れ、理想社会の象徴でもあったエストカルト城が砕け散ったのだ。
「バイゼン様……」
前と同じだ。守りたい愛を、その対象を、またしても失ってしまった。
約二十年前、ソアラが六つか七つの頃。
彼女は偶然、花の種を拾った。名は知らぬ花だったが、紅の蝶(ソアラ)がよく蜜を吸いに来る花の種であった。友達がいなかった彼女は、それに「バイゼン」という男性名を付けて植木鉢に蒔き、毎日話しかけながら世話をした。
やがて、花はつぼみを付けた。ソアラは花が咲く瞬間を見届けてやろうと、一晩寝ないで花を見続けた……つもりだった。「つもりだった」というのは、彼女が途中で眠りに落ちてしまったのである。起きてみると、花が植木鉢から抜かれていた。驚いた彼女は母親のいるキッチンへと向かった。しかし、母親は食卓で待っていなさいと、それしか言わなかった。
いつに無く優しく、母親は皿を運んできた。
「はい、今日のごはんよ」
皿の上には、丸ごと炒められた花(バイゼン)が載っていた。
それ以来、ソアラは何も愛せなくなった。
唯一バイゼンだけが、彼女の心に愛をもたらした。彼を愛する事によって、ソアラは自分にも人間らしい温かい心があるのだと確認する事ができた。
それなのに。
バイゼンがいなくなったら、ソアラは愛の無い冷たい人間に逆戻りだ。きっとソアラは壊れてしまう。壊れて狂って、飛べなくなるだろう。
「クラリス、メイは生きているか?」
バイゼンが瀕死のメイを抱き抱えるクラリスに聞いた。
「取りあえず息もしてるし、脈もあるけど……。あれだけ失血していると、安心できないな。それに、何だか体温が下がってきてる」
シークが気を利かせ、パレで雨を防ぐ。
「バイゼンはイルミナ族を絶滅させたいんじゃなかったのか」
「分からない。いや、メイが分からなくさせたのだ」
バイゼンはメイを哀れみの眼差しで見た。
「メイは体を張って私を救ってくれた。自分を殺そうとしたこの私を。可哀相に、いつも犠牲になるのはメイだ」
もう、何もかもやめてしまいたい。彼はそう思いつつあった。
百メートル程先に、何か赤いものが見えてきた。その色は美しく独特で、例えるなら夕焼けの色だ。
「……ソアラ……?」
バイゼンはシークのパレを突き破り、最も忠実で献身的な腹心に駆け寄った。
「ソアラ、しっかりしろ、ソアラ!」
ソアラは大地にその身を任せていたが、愛する主人に名を呼ばれ、わずかに首をもたげる。
「ご無事で良かった……」
「喋るな、今、治してやるから」
けれども、彼女は哀しげに微笑んで首を横に振った。
「多分、これは毒でしょう。私は助かりません。あなたが生きていて下さっただけで、私には十分です」
自らの天質により、遅れて来たクラリス達の目と、血まみれのメイから全てを読み取ったソアラは、心の底からメイに感謝したのだった。
「この薬をメイさんに……」
バイゼンは、差し出された右手をそっと両手で包み込む。今にも消えてしまいそうな弱々しい命。世界を変えようと一緒に歩んできた仲間の死が近付いているという事を、嫌でも思い知らされた。
「逝ってしまうのか、ソアラ。まだお前の役目は終わっていない。終わっていないのに!」
泣いているのか泣いていないのか、雨に濡れた頬からは判断できない。それでもソアラは嬉しかった。バイゼンがもっと自分といたいと思ってくれている。それが男女間の愛情でなくても、少しも構わなかった。ただ、だからこそ切なくもあるのだ。愛しい人を置いて、もう二度と会う事のできない隔たりの向こう側に去らなければならないなんて。
告白しよう。感情の海の中、ソアラは突然思い立った。
「バイゼン様……」
しかし、唇から漏れたのは、やっと聞こえる程のかすかな声だった。そうして初めて、彼女は自分が屍(もの)になりかけている事に気付く。
紫色の瞳は、光を読む事をやめていた。
雨の音も風の声も雷の叫びも、全ての音が消えていた。
感じられるのは、大切な人の存在だけ。
右手を包み込む温もりだけだ。
まだ死なないで、私の体。
この気持ちを伝えるまで。
「愛しています」と、それだけでいいから。
待って……。
――バイゼンが次の言葉を聞く事は遂に無かった。
「ソアラ?」
彼女の手が力を失い、バイゼンの手から滑り落ちる。形のいい手の平から、小さな薬のガラス瓶が転がり出た。
後は何も動かなかった。
冷たい雨が降り続く以外は。
メイは夢を見た。
少年のような顔立ちの父親と、美人と言って良い容姿を持つ母親が、数メートル先を歩いていく。
『行かないで』
だが、メイの体は動かない。追いかける事もできず、両親の後ろ姿を見ているしか無いのだ。
母親がこちらを向いて笑いかけた。
『ヒーローになるのでしょう?』
メイは泣き叫んだ。
『なれないもん、私なんて! 私もそっちに行きたいよっ!』
父親も振り返った。
『この先には何があると思う?』
メイは考えた。
両親の微笑みの後ろにあるものは何だろう? 答えが出たのは、数秒後だったかも知れないし、数時間後だったかも知れない。
『何もない』
そう言った瞬間、辺りは真っ暗になった。
メイが目を開けて最初に見たものは、マーガレット・アルボルの心配そうな顔だった。もっとも、彼女が自分に魔法を教えてくれた先生だと理解するには、十秒かかったが。
「メイが起きたよ!」
マーガレットは歓喜の声を上げた。どたばたと足音がして、クラリス、シーク、バイゼン、さらにはダリアまでもがベッドを取り囲む。
「あの、これは一体……?」
メイは上半身を起こしたが、眩暈がして額を押さえた。
「無理するな。あんた、二日間も眠ってたんだから」
クラリスに言われて、メイは二日前の事を思い出した。確かバイゼンと会って、それから……。
「あ、あれ?」
彼女はパジャマの裾をまくって、氷の槍に貫かれたはずの部分を確かめる。
「けが、治ってるー!」
「シークが治してくれたんだ。って言うか他人(ひと)の前でそんなはしたない事するなよ……」
「いつの間にか、服も変わってるー!」
「あんた、マーガレットさんの家に、下着とパジャマ、忘れていったらしいよ。っていうか、人の話聞けよ……」
メイはやっとアルボル姉妹がいる事を不思議に思った。
「ここ、どこですか?」
クラリスは今までの経緯を話し始める。
ソアラが帰らぬ人となった後、バイゼン達は取りあえず、彼女の遺体と共に、雨とルーヴァから逃れる為、適当に思い浮かべた場所へ移動(アテリース)した。そこで、偶然ショッピングをしようとシレジアへ向かっていたマーガレットとダリアに会った。彼女達はクラリスの話を信じ、シークとバイゼンを受け入れて、マーガレットの家にかくまってくれた。メイの容態は悪化していたが、ソアラの薬を飲ませ、温かなベッドで休ませたら、何とか落ち着いたという訳である。
メイは軽く俯いて、涙を零した。
「そっか、ソアラさん、死んじゃったんだ。それに、大勢の人がお城の下敷きに……」
なぜこんなにも、現実は冷たく人間を突き放すのだろう。この一年というもの、悲しい事ばかりが起こる。
「新聞だ。読みたかったら読め」
シークが差し出した新聞を、メイは無言で受け取った。
『魔王、遂に失脚
先日、三月一日、ルーヴァ元司令官ユリウス・アルボル氏(二日付けで司令長官に昇格)率いるルーヴァ隊が、魔王バイゼンの拠点である城を発見、攻撃した。城は激しい戦いに耐えられず、崩れ落ちた。
ルーヴァ第十二隊元隊長ガイル・トラバース(二日付けで司令官に昇格。隊長から司令官への昇格は異例だという)は、「城の中にはまだ魔王とその仲間がいた。魔王は仲間を大切にする性格である為、一人で移動魔法を使ったとは考えにくい。恐らく、瓦礫の中に彼の亡骸が埋まっているはずだ。だが、まだはっきりとは死を断言できない。今後も注意が必要だ」と述べる。彼はルーヴァきっての切れ者で、今回、魔王抹殺の特命を受けていた。
念の為、魔王とその仲間三人は指名手配されている。(下の絵参照。連絡はルーヴァ本部及び各支部まで)』
四人の似顔絵を見て、メイは泣きやみ、それどころか笑い出した。
「だれですか、これー! レイールさん、全然顔が違う! クラリスさん、何か髪型が変わってる! ううん、それよりも泣きぼくろなんかないし、くちびるはもっと薄いよー。シーク君、顔怖すぎ! これ私かな、やけにきれいな顔してるけど……」
彼女の笑いは止まらない。
「何でこんなに違うんですかー? 一ヶ月も一緒にいたのに。これなら外歩いても捕まりませんね」
「バイゼンはガイルって奴に一瞬見られただけだから」
クラリスは失笑していた。
「メイの顔の洗練されてなさって、絵じゃ表し難いしな。そうすると、そつの無い美少女になってしまうんじゃないか? 私達に情が移らない様に、私たちの顔はあまり見ない様にしてたのかも知れない」
「でも、ローゼさんとは仲良かったですよ」
途端に、場の雰囲気が暗くなる。
「……え、私、何か悪い事言いましたか?」
「新聞の二面を見てみろ」
メイは新聞をめくった。
『正義の為に散った戦士達』
実に二百五十三名の戦死者の名が挙がっている。その中にローゼ・アルボルの名があった。
「あっ……」
再び涙が滲んできた。そんなメイに、シークは包み隠さず事実を教える。
「俺達と一緒にいたルーヴァは、ユリウスとガイル以外、皆死んでいる」
「そんなっ……」
その時、彼女の腹の辺りから、「ぐー」と間抜けな音が鳴った。メイは一瞬固まり、腹を押さえた。
「何で……。何でこんなシリアスな時におなかなんか……! 私って最低!」
ダリアとマーガレットは顔を見合わせた。
――仕方が無いわよね、二日間何も食べてないんだもの。
――そうだね、朝ごはん持ってきてあげようか。
鼻をすするメイの前に、肉じゃがが運ばれてきた。
「ほら、お食べ。バイゼンさんが作ったんだよ。この人は料理が上手でね」
「……ありがとうございます」
メイは一口、二日ぶりの食べ物を口にする。
「おいしー。おふくろの味ですねー……」
十五分間、メイが黙々と肉じゃがを食べるのを皆が見ていた。
「ごちそうさまー」
メイは食べている内に機嫌が直ったらしい。幼い笑顔を見せる。
「メイ」
バイゼンが、今日初めて彼女に声をかけた。
「二人きりで話がしたい。マーガレットさん達には、しばらく席を外していただきたいのだが……」
「では、用が済んだら呼んで下さいな」
二人のイルミナ族を置いて、四人の部外者は退室していった。
「話ってなんですか?」
メイが無邪気に聞く。彼女はいつでもそうだ。心の中に疑念が無い。というより、人を疑う事自体知らないのだろう。
「あの時、何を考えていたのだ?」
「あの時って……?」
「私をかばって攻撃を受けた時だ」
メイは首を傾げた。
「別にあれ、受けようと思ったわけじゃないんです。レイールさんが危ないなって思って、突き飛ばそうとしたら、ちょうど当たっちゃって……。特に何も考えてませんでした」
「そうか、ありがとう、メイ」
深い沈黙が訪れる。メイはバイゼンの顔をじっと見つめ、次の言葉を待った。
やがてバイゼンが口を開いた。
「これからどうするつもりだ?」
「そんな急に言われても、困りますよー」
膝に置かれた手を見ながら、メイは未来の自分を想像する。ふいに先程の夢が浮かんできて、彼女はそれを振り払わなくてはならなかった。
「そうですねー。まずはおじいさんとおばあさんの家に帰って……。ずっとそこで暮らしてもいいし、また魔法を習ってもいいな。道はいくらでもあります!」
言い終って顔を上げると、バイゼンが今にも泣きそうな表情でこちらを見ている。
「道など無い、私達には」
「……?」
「すまない」
バイゼンはメイの首に手をかけて、強く締め付けた。
「っ……!?」
呼吸よりも、頭に血が行かない事の方が辛い。必死でバイゼンの指を緩めようともがくメイだったが、数十秒で意識が薄れ、ベッドに倒れ込んでしまった。
「本当にすまない。私はお前の未来を奪わなくてはならないのだ。これしか道は無い……!」
力を失いかけたへイゼルの瞳に、悲愴な涙が光る。バイゼンは顔を背けた。こんなものを目にしたら、手を離してしまう。あと少しだ、あと少し耐えられれば……。
だが彼は、良心的な私情に負けた。気が付くと、彼の手はメイの首から離れ、小さな肩を揺さぶっていたのだ。
メイはしばらくむせていたが、すぐに目を開いた。
「メイ、怖い思いをさせて悪かった。もうしない。いや、私にはできないという事がよく分かった」
メイは動悸と頭痛を感じつつも、起き上がってバイゼンを慰める。
「いいんですよ。ね、レイールさんはこれからどうするんですか? まさか死ぬなんて言いませんよね……?」
「最初はそのつもりだったが、私は生きなくてはならなくなった」
バイゼンは思慮深く言った。
「お前を生かす以上、私にはお前を守る義務がある。お前が道を踏み外す事なく、明るい道を歩いていける様に。だから、私も生きることにした」
メイがにっこり笑って、彼の手を握った。
「ありがとうございます! 長生きしましょうね!」
「……うん」
未だに五歳のメイの面影が残っていて、レイールと呼ばれる事も容認し、つい昔の口調に戻ってしまうバイゼンである。幸せだった過去が帰ってきた様で、心が温かくなった。
「マーガレットさん達に入ってもらおうか」
「はい」
バイゼンが入り口まで行ってドアを開けた。
「おや、話は済んだのかい?」
マーガレットの声がする。
「実は私も話があるのだ。さ、入ろうか」
メイが起きた直後の様に、五人の老若男女がベッドを取り囲んだ。マーガレットとダリアはベッドに腰かける。
「単刀直入に言うけど、メイちゃん、もう一度、あたし達の授業を受けたくない?」
ダリアが手短に用件を伝えた。
「いいんですか?」
「もちろんよ。あなたはまだ呪文の力に頼っているわ。それじゃあ一人前とは言えないもの」
メイの頭をくしゃくしゃと撫で、マーガレットは宣言した。
「お前さんを世界一の魔導士にしてあげるからね」
「ほああ、目標おっきいですねー!」
突然バイゼンの脳裏を、冷酷な眼差しで廃墟と化した町の中心に佇む華奢な破壊者の姿が過る。それが光の球体から得た記憶なのか、それとも自分の妄想なのかも分からない内に、彼は口を挟んでいた。
「私もやる!」
全員が怪訝そうに彼に注目した為、バイゼンは言い直した。
「イ、イルミナ族ならではの問題点などを解決するのだ。光の力の使い方も教えてやりたいし」
「おおっ、トリプルティーチャー!」
メイは全然意味を考えずに、謎のカタカナ語を叫んだ。その後でふと気が付く。
「でも、迷惑じゃないですか? ユリウスさんって、マーガレットさん達の兄弟なんでしょ?」
「あんな人とは縁切ったわ。だから大丈夫よ」
ダリアが胸を張って答えた。
またメイは気が付いた。
「私がいないと、おばあさんが心配です。アテリースで通うっていうのはどうですか?」
「いいが…。この家の景色を十パーセントも思い出せるかい?」
マーガレットの問いにはバイゼンが答える。
「私が絵を描こう。十分待っていただきたい」
そう言うと、彼は外に出て行ってしまった。
「バイゼン、紙と色鉛筆を忘れているぞ!」
シークも後を追った。
メイは退屈しのぎに新聞を開き、続きを読む。平和の訪れを賛美する文があちらこちらに飛び交い、彼女を不安にさせた。バイゼンが失脚したから平和になった、という考えは余りにも安直過ぎるのではないか。平和の中にも争いがあるのだという事を、また、争いの中にも平和はあったのだという事を、人々は忘れようとしている。これでは真の平和など望めないのに。
十分後、バイゼンとシークが戻ってくると、クラリスが人差し指を口の前に立てて近寄って来た。彼女はベッドの方をしゃくる。メイがすやすやと眠っていた。
「疲れたのだろう。いくら傷がふさがっているとは言え、一度は"氷の槍(ニエベント)"が貫通した体だ。今はそっと休ませてあげよう」
新聞を畳みながら、マーガレットは囁いた。メイは読んでいる途中で眠りに落ちたらしく、紙面の中央が頭の形にへこんでいる。
「こんな感じでよろしいだろうか?」
バイゼンがマーガレットに絵を見せた。マーガレットは口に手を当てて、驚きの声を押し殺す。
「お上手だね、バイゼンさん。これを十分で! 本当に元魔王なのかい? お前さん、画家になれるよ」
「実は……駆け出しの頃は絵を描いて生活していたのだ」
その事は、シークでさえ知らなかった。
次にメイが目覚めたのは、翌日の朝だった。早春の陽射しがきらきらと輝いている。もうじき本格的な春が来るだろう。
「みんな、どこかなー」
彼女は部屋から出て、屋内を歩き回った。案の定、頭の中の地図はすっかり消えていた。
一つ、冷たい風が吹いてくる扉があり、興味をそそられたメイは中に入ってみた。
「……えっ……」
木製の棺の中に、眠れる美女が横たわる。
「ソアラさん……」
保存状態が良く、生きていた時と変わらぬ姿だった。それでもメイには、彼女が目覚める事は二度と無いのだとはっきり分かった。
「起きていたのか。もう体はいいのか?」
後ろから入ってきたバイゼンが声をかけた。メイは手足を動かして確かめる。
「治ったみたいです。肉じゃがパワーですね!」
「そうか、良かったな」
彼女は再びソアラの方を見た。
「お葬式はいつですか? 私も出たいです」
バイゼンは意外そうな顔をする。
「今日だが……。お前を殺そうとした相手だぞ。それなのに参列してくれるのか?」
「はい。薬で助けてくれたのもソアラさんだし……。私、ソアラさんが天国にいけるようにお祈りしたいんです。お墓はこの近くに作るんですか?」
「埋葬はしない。もっとソアラにあった方法を考えてある。さあ、まずは朝食にしよう」
今日の朝食はたまご焼きと味噌汁だ。やはりバイゼンの手料理である。
「クラリスさんは、ソアラさんのお葬式に行きますか?」
「私は……」
クラリスは口ごもった。心の中ではソアラの死を喜んでいる様な気がして、彼女は自分にぞっとする。
「悪いけど、やめとく……」
実はソアラと自分は似ているのだと、クラリスは気付いていた。盲目的にバイゼンを敬愛したソアラと、盲目的にデランを溺愛した自分。ソアラの行動は全てバイゼンの為のものであり、デランを殺したのもそうだった。そう考えると、憎みたくても憎めなくなる。自分がソアラの立場なら、同じ事をしただろうから。
それでもやはり、デランの事を思うと許せないのだった。
ラグティアの岬で、式は行われた。バイゼン、シーク、メイの三人のみの小さな葬儀だ。
花を手向けた棺を閉め、マッチで火を点ける。火は棺を包み、激しく燃え上がった。火の粉が舞い、青天に溶けていく。その一粒一粒が死者の魂なのかも知れないと、メイは思った。
「ソアラは自由に飛ぶ蝶に憧れていた。だから、全てを灰にして大空に振り撒くことにしたのだ」
バイゼンは言った。
遺体が燃え尽きるまで、三人は銘々に祈りを捧げた。
そして、夕方が来た。
残りの力を振り絞るかの様に、赤い太陽が強く輝いている。
「さようなら、ソアラ……」
バイゼンが遺灰を掴んで、風の流れと共に空へ投げた。
世界を変えようとした美貌の女性――しかも、その美貌に頼らずに歴史を創った哀れな女性は、夕焼けの中に消えていった。
誰よりも人の心の汚点を嫌い、誰よりも己の冷たさを恐れた彼女は、死をもって「自分」という呪縛から解き放たれたのだ。
バイゼンが最後の一掴みを投げようとした時、シークが彼の手を止めた。
「どうしたのだ?」
「いや……」
シークは言葉を選びつつ、鈍感な保護者に伝える。
「きっとソアラなら、一緒にいたいだろうから……。それは持っていよう、バイゼン」
小波の音が、かすかに聞こえてきた。
次の朝、バイゼンは今後の予定について、皆に話した。
「私はこれから、残された部下達の収拾をつける為に旅立とうと思う。週に一度はアテリースでここに戻ってきて、メイの魔法を見るつもりだ」
「それなら俺も連れて行ってくれ」
シークが頼んだ。
「いいのか、私などに付いてきて。お前にはもっと相応しい道があるのではないか?」
そう言うバイゼンも、どこか嬉しそうだった。
「私も考えてたんだけど……」
クラリスは徐に切り出す。
「一人で旅に出る事にしたんだ、剣の道を極める為に。だって、私にはイレイヴしか残ってないから……」
彼女は脇に愛剣を抱えていた。
「そっか、みんな、それぞれの道に旅立っていっちゃうんですね」
寂しげに呟くメイに、アルボル姉妹が笑いかける。
「大丈夫だ、お前さんの面倒は私達が見てあげるよ」
「そうよ、いっしょにがんばりましょう」
メイはしゃんと背筋を張って、元気良く答えた。
「はい!」
朝食後、彼らは外に出た。バイゼンとシークが並んで他の四人に向き直る。
「私達はまず、モルジェを迎えに行く。マーガレットさん、ダリアさん、世話になった」
「じゃあな」
二人はアテリースの光に包まれ、どこか分からない場所へと去っていった。
「私、まだ、さよならも言ってないよ!」
戸惑って手を伸ばすメイの肩に、クラリスが片手を置く。
「一週間もしたら会えるだろ」
「クラリスさんは?」
メイは不安そうに尋ねた。クラリスは、そんな彼女を優しく抱いた。
「あんたは、私のかけがえの無い仲間だ。近くに来たら、絶対寄ってくから」
「……待ってますね」
「ああ」
ずっと馴れ合いを続けていたかった。でも、修行に仲間はいらない。一人でないと甘えてしまうから。そうやって、これ以上弱くなるのが怖いから。
私は元の冷たさが恋しいんだよ、メイ。
クラリスは理性でメイから離れ、街中に紛れ込んだ。その銀髪が見えなくなるまで、メイは手を振っていた。急に、「大好きなクラリスさん」も沢山の人間の中の一人に過ぎないのだと強く感じ、涙で視界がかすんだ。もう、二度とクラリスに会えない様な気がして。
「じゃ、私も帰ろっかな」
メイはこっそり袖で涙を拭いた。
「明日、朝ごはんを食べたら、また来ます。で、魔法の勉強をして、晩ごはんには家に帰るんです。学校に通うみたいでいいでしょ? これからもそうしましょうよ!」
「分かったよ、行っておいで」
マーガレットの了解も得て、彼女は"移動(アテリース)"の準備をする。ところが、何かを忘れているのだ。何を忘れているのか考えていると、ダリアがさりげ無く訊いてきた。
「メイちゃん、家の絵は持った?」
メイは慌てて取りに戻った。
「ほあー、危ないとこでしたー」
今度こそ、彼女は"移動(アテリース)"を唱えた。
この一年間、一体どれだけの涙を流しただろうか。
悲しい事が多過ぎて、狂ってしまいそうにもなった。
それでも私は、今、こうしてこの世に生きている。
自分の後ろに道を作りながら歩む事を許されている。
これは、とても幸せな事なのかも知れない。
――嬉しいな。
メイは浅葱色の柔らかな光に包まれた。
そして、未来という名の大空へと飛翔した。
残された光の粒が、煌めいては消えていくのだった。
スポンサーリンク