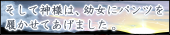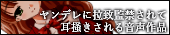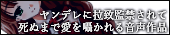『イルミナ』 中3の時書いたラノベ等身大すぎワロタww →企画トップページ
第十章 ルーヴァの理(ことわり)
部屋はしんと静まり返っていた。壊すのが惜しいほどの静けさは、やがて哀しみに変わる。
「やっぱり、イルミナ族が生まれたこと自体が、悲劇の始まりだったんですね」
メイはそう呟いた。
「私はそんなつもりでこの話をしたんじゃ――」
「分かってます。だからこそ、私には悲劇を終わらせる役目がある。自分の存在意義を再確認できました。ありがとうございます」
何者かが玄関の戸を叩き、アンシェローク家の重い空気を振るわせた。
「あっ、私、でますから」
立ち上がろうとするダールを制し、メイが退室する。途端にダールはため息を吐いた。
「私は心配です。あの子が、義務とか運命とか、そういったものに捕らわれて行く様な気がして。お二人さん、どうかメイを守って下さい」
その時、メイが戻ってきた。
「あの、ルーヴァの人が、おじいさんに挨拶したいって……」
彼女の隣に立つ人物を見て、クラリスとシークははっとした。
「ユリウスさん!」
「……二人もここにいたのか。久しぶりだね」
心成しか、ユリウスの声が無機質に感じられたのは、気のせいだろうか。仕事用の声なのか、屋敷にいた時の彼とは雰囲気が違う。
「何ですか? まさか、うちの妻が呼んだんじゃないでしょうね?」
ダールは口走った。先程のファレーナの言動を思い出したのだ。
「いえ、お宅のお嬢さんに依頼したい事があるのです。少しいいかな、メイ君。こっちにおいで」
メイはユリウスに連れられて外に出る。十五人のルーヴァ隊員を目にした時、理由は分からないが、心のどこかが鋭く疼いたのを感じた。
「我々はある人物から有力な情報を得た。それを活かす為には、君の力が必要なんだ。そう、イルミナ族の力が」
「私がイルミナ族だってこと、ダリアさんから聞いたんですか?」
今では懐かしい、自分の血筋など気にしていなかった頃に、何気無く話してしまったのだった。
「あの……私がイルミナ族でも、気にしないでくれてます……よね?」
さっきの態度が引っかかる。
「ははは、当たり前じゃないか」
ユリウスが明るく笑い飛ばした。
「魔王の城で、光の魔法を使って欲しいのだよ。出発は明日の朝でいいから」
「私、光の魔法なんて使えません」
「何だね、使えないのかね。君を探す為に我々は情報網を張って、アンシェローク家に君がいるかも知れないと突き止めたのに」
ユリウスは、あからさまに嫌な顔をした。
「ちょっとおじいさんに訊いてきます」
メイは家に入ってダールに尋ねる。
「さっきの話の中に出てきた、光の力とか闇の力とか、そういうのを操る魔法について、何か知っていたら教えて下さい」
よくぞ聞いてくれましたとばかりに、彼のダークブラウンの瞳が輝いた。
「光も闇も、実は同じものなんだ。プラスのエネルギーとマイナスのエネルギーだと考えてくれればいい。呪文はルスクリダとオスクリダ。それらを単独で使う事は、魔法を知って一年も経っていないお前には難しいだろう。でも、プラスやマイナスの力を他の魔法に帯びさせる事は可能だ。すなわち――」
次第にメイが無表情になっていくので、ダールは焦った。
「炎の上級魔法"劫火(フィエブソール)"に光か闇の魔法を加えれば、それはものすごい炎となるわけだ。その場合は、『フィエブソール』の前に『ルス』か『オス』をつけて唱える。傾向としては、光はより聖なるものに、闇はより邪なものに、その魔法を変えるらしい」
「あの、難しくてよく分かりません……」
見かねたシークが口を挟む。
「要するに、光の魔法ルスクリダと闇の魔法オスクリダの最初の二文字『ルス』と『オス』を、使いたい魔法の名前に付けて唱えれば簡単、と言ってるんだ。分かったか」
「あ、そういうことか! ありがとう、教えてくれて」
教えたのは自分なのに、と落ち込むダール。メイはそれに気付かず、外に出て行ってしまった。
「私にも使える方法が分かりましたよ。でも、何で光の魔法を使う必要があるんですか?」
ユリウスは難しそうに頭を掻いていた。
「君は、魔王の正体を知っているのかね」
「はい」
メイはどきどきしながら返事を待つ。
「……なら、秘密にしておこう」
「えーっ、何でですかー! ? そんなのずるいですよー」
「何か『いい事』が起こるのだよ。それは後のお楽しみだ。仲間にも内緒だぞ」
「じゃ、一つだけ約束して下さい」
一番大切な事を。
「城でルーヴァは何をするつもりなんですか? 戦おうとしてるんですよね、バイゼンと。でも、それはムダなことです。なぜなら、私達がバイゼンを説得して、魔王である事をやめさせるんだから。武力はむなしいんです。だから、戦わないで下さい。約束できないなら、光の魔法なんか使ってあげませんよ」
決してその眼差しは恐ろしくも強くも無い。むしろ優しすぎて犯しがたい眼差しである。それはユリウスに一時の沈黙を与えた。
「は、はは、何を勘違いしているのだね。実は我々も話し合おうと思っていたのだよ。安心したまえ」
「なあんだ、そうだったんですか」
ふとメイは、ガイルと目が合った。彼の目を見ていると、なぜかとてつもない恐怖を感じる。彼女はさっと顔を背けて扉の向こうへと逃げた。
「司令官、よろしかったのですか」
メイがいなくなった後、ローゼが父親を問い詰めた。
「あの少女に光の魔法を使わせるのは、城が帯びる闇の力を打ち消して、私達が城内で魔法を使える様にする為ではないのですか。あのような嘘を吐いて、ルーヴァの正義を裏切ることにはならないのですか」
ユリウスは娘の肩を軽く叩く。
「ローゼ、お前はまだ若いから、分からないかも知れないな。だがな、これだけは言っておく。魔王さえ倒せれば、世界は平和になるのだよ。その為の犠牲が少女との約束一つなら、安いもんだろう?」
「それはそうですが……」
「分かってるんなら、それでいい」
どうか娘には、ルーヴァの正義を信じていて欲しい。あれこれと多様な正義を認めていたのでは、ルーヴァの仕事は務まらない。そして、他の正義の方が正しいのでは、と少しでも考えてしまったその時から、ローゼは不幸になる。一つの正義のみを信じていられる事が、どれだけ幸福で安心な事なのか、ルーヴァ歴三十年の彼はよく知っていたのだった。
「ルーヴァの人達、私達と一緒に行って、バイゼンと話し合いたいんだって」
部屋に戻ってきたメイが、クラリスとシークに伝えた。
「ルーヴァって正義を守るヒーローなんでしょう? これで安心ですよねー」
「そうだな」
クラリスも頷く。ただ、シークは一人、腑に落ちないという顔をしていた。
「ルーヴァが守るのは俺達の正義ではない。奴らの正義だ」
彼が窓の外を見やると、何とルーヴァが人の家の前で野宿の準備をしている。
「見ろ、常識も欠けている」
ダールは、ふて寝してしまったファレーナの代わりに、夕食を作り始めていた。
「いつ出発するのかい、メイ?」
「明日の朝だそうです」
ダールの質問を受けたメイは、そう答えた。
「何ですってー!?」
勢いよくドアが開き、ファレーナが顔を出す。
「何でもっと早く言ってくれないの、メイ。それなら私、今夜、大ごちそうを作ってあげますよ! さあ、どいて、ダール」
ファレーナは夫を突き飛ばし、台所を奪い取った。
「何がお好きですか、クラリスさん? シーク君は? メイはフルーツシチューでしょ?」
フルーツシチューとはいかなるものか。シークはそれが気になって仕方が無かった。
「じゃ、私は味噌汁ごはん、お願いします」
クラリスが真顔で注文するので、ファレーナは苦笑いを浮かべる。
「ええと、クラリスさん、それはごちそうじゃないと思いますよ」
「そ、そうなんですか……」
未だに貧しい食生活が抜けないクラリスだった。
パーティ。それは特別な集い。心と心が通う時間。
今、アンシェローク家で行われているのは、いわゆるお別れパーティである。
シークはフルーツシチューを観察した。果物の形にくり抜かれた野菜がシチューの中に入っている。本物の果物が入っているのを少しならず期待していた自分が恥ずかしくなって、彼は一切それに手を付けなかった。
クラリスはフルーツシチューを食べながら、ぼんやりと部屋の飾りを仰いだ。父親を亡くしたばかりの頃、他人の家を覗いて、幸せな家族を眺めては、彼らを馬鹿にしていた事を思い出す。――「ほら、デラン、ごらんよ、あの間抜けな笑顔。あの子、親がいなくなったら、きっと生きていけないね」――その反面、自分もデランがいなくなったら生きていけないと思っていた。それが今、弟を失った自分は、こうして別の光の下に生きている。もう敵討ちなどいいから、せめて残った光だけは守りたい。その思いを抱いて。
ガイルは外からアンシェローク邸を覗いた。
「愚かしい」
近くにいたローゼが近付く。
「何故ですか? 微笑ましいではありませんか」
メイがシークにフルーツシチューを薦めていた。もちろん断られたが。
「感情を持つ事は罪だ。感情など持つから、人は争うのだ。そうは思わないか」
ローゼは黙り続けた。
「唯一感情を許されるのは、完全なる正義を知る者のみ」
そう言い残して、ガイルは去っていく。
「それは神ですか?」
ローゼは呼び止めたつもりだったが、ガイルの耳には届かなかった。
いつか聞いた。神は全てをお許しになる、と。
「でも……」
ルーヴァは許す事を知らない。
では、私達の正義は、完全なる正義ではない?
ローゼははっとして、馬鹿な事を、と自嘲しつつ家から離れた。
お人好しの少女メイは、フルーツシチューをもりもり食べる。一杯、二杯、まだ食べる。
「そんなに食べて大丈夫か」
シークが見守る中、メイは苦しそうにウインクした。
「ほら、もしかしたら、おばあさんの手料理が食べられるのも、これが最後かもしれないから」
「最後って、お前……」
彼女は食器をテーブルに置き、少しだけ憂えた様子で微笑んだ。
「バイゼンを説得できなかったら、今度こそ殺される。だから、今のうちに食べるんだよ。全部食べないと、おばあさんがかわいそうだし」
そしてまた食べる。
「おい、明日出発なんだぞ。無理するな。いつもの二倍は食べているじゃないか」
「うん、そう言えば、おなかが痛い」
「お前、食べるからには戻すなよ」
――神と馬鹿は紙一重である。
出発の朝が来た。
ダールとファレーナは涙ぐんでメイの手を握る。
「ああ、メイ、必ず無事に帰ってきてちょうだいね」
「もしお前に何かあったら、私達の寿命が五十年は縮むよ」
五十年。一体彼らは何歳まで生きる予定なのだろう。
「はい、おじいさん、おばあさん。大丈夫ですよ、私には頼もしい仲間が付いてます! それに、ルーヴァの人達も」
仲間達はすでに集合していた。もう行かなくてはならない。
メイは叫ぶように言い放った。
「……さよなら!」
次、生きて帰ってくるまで、家族の事は忘れよう。それがメイの誓いだった。一度も振り向かず、ひたすら仲間の元へ走っていく。アンシェローク夫妻は、その姿を成長の証として見送った。
ところが、なぜかユリウスが立ち替わりでやってきた。
「多分……、もう会う事は無いでしょう」
夫妻は訳も分からないまま、差し出された札束を受け取る。ユリウスは一礼し、彼らの前から姿を消した。
その金が何を意味するのか、二人が知る事は永遠に無いだろう。
十六人のルーヴァと三人の少年少女。この奇妙な一行は、最短コースでルーヴァの基地へと向かった。朝早くから夜遅くまで歩き通す為、クラリスやシークはともかく、メイはくたびれて動けなくなる事もしばしばだった。そんな時は、ローゼがメイを背負って歩いた。
「ごめんなさい、迷惑かけて」
「いいですよ、筋トレになりますから」
彼女は、メイと出会った山村での出来事を思い出していた。悪であるはずの山賊をかばい、彼らの為に涙を流した少女。この世に生きる全ての者を愛し、許す事のできる、比類無い存在。優しさで正義は守れない。それでも、人間にもっとも重要なのは優しさではないのか。ガイルもユリウスも、この件に関して納得のいく説明を与えてくれそうには無かった。
二十二日後、基地に到着した。
「ほあー、立派な建物ですねー」
メイの感想は、いつかと違って適切ではない。大きさは立派だが、外壁はモノトーンでつまらないのだ。
唯一美術的価値があるとすれば、創始者ルーヴァ・フェリスの像である。ルーヴァ・フェリスは、約百五十年前この世に生を受けた魔導士で、その強さは史上最強、また、非常に正義感の強い女性であったと言われる。今や彼女の正義は大陸の基準となっており、彼女のカリスマ性がいかに強かったかを示していた。
メイは列から抜けてルーヴァ・フェリスの像を見に行った。それ程美人ではないが、その自信に満ちた表情と均整の取れた体が、見る者を惹きつける。像が立っている石碑には、こう記されているのだった。
『正義を守れ』
様々な解釈があるであろうその言葉を、ルーヴァの隊員達はどの様に受け止めているのだろうか。
「ちょっと、何やってるんだ、あんたは」
すぐにクラリスに見つかり、引き戻されてしまったメイは、未練がましい目で像を見つめる。
「あの人、ヒーローなんですよね、クラリスさん」
「だから?」
「かっこいいなー」
「あっそ。将来の夢、ヒーローにでもしたら?」
「はい! そうします」
クラリスは噴き出した。
数分の後、建物から何百人もの隊員が送り出された。どうやら一緒に付いて来るらしい。
「ユリウスさん、戦わないんですよね?」
メイが訊くと、司令官ユリウスは「念の為だ」と答えた。
「休んでいる暇は無い。行くぞ」
メイ達は列の先頭近くに立たされ、周りを隊員に囲まれている。必然的に押されて歩く形となった。
「はめられたな」
シークが眉をひそめた。
「ルーヴァだからと思って、ある程度は信用していたが……。メイ、お前、何を頼まれた?」
メイが口を開こうとすると、ユリウスが後ろから警告を発した。
「それは秘密だったね、メイ君」
「言動も監視されている、というわけか」
シークはおとなしく歩き続ける。これだけのプロの魔導士を相手に逃げ切れるとは、とても思えなかった。
「何か、みんな怖い……」
まるで幼児の様に怯えるメイに、クラリスが何か声をかけてやろうとした時、前にいる女が、こちらを顧みて囁いた。
「大丈夫さ」
シークは初めて彼女の存在に気が付いた。彼女こそは、一年前ルーヴァに捕らえられたバイゼンの腹心、ザディーラだったのだ。気が付かないのも無理は無い。魔導士が溢れているこの状況では、さすがのザディーラの魔力も紛れてしまう。さらに、以前はロングだった飴色の髪が、今はボブカットになっていた。ただ、猫の様な風貌に変わりは無かった。
「お前が案内役か」
「まあね」
彼女は少しも悪びれず、顔を前に戻した。しかし、城への案内をするというのは、バイゼンへの裏切り行為である。シークの心は一瞬怒りに燃えたが、次の瞬間には冷却装置が働いた。もうどうしようも無い。今はただ、ルーヴァがメイとの約束を守ってくれる事を願うばかりだ。
メイもシークもクラリスも、ルーヴァと手を組んだ事を深く後悔した。
三日後、長蛇の列の先頭は、エストカルトの城下町を見渡す丘に立っていた。二ヶ月前、メイ達がその土を踏んだあの丘だ。
美しい紺碧の城と小さな民家の集合体を、暗雲の空が包み込む。まだ昼なのに、日の光はわずかにしか届かない。天候を読める者でなくとも、近い内に天が大泣きする事くらい予測できた。
「灯台下暗し……。まさか、こんなに近かったとはなあ」
ユリウスはしみじみと口にした。
「できれば、ここから光の魔法をかけて欲しいんだが、できるかな?」
魔法をかけると言っても、城は遥か二キロメートル先にある。
「やめた方がいいと思います。ヴィエントなら遠距離ですけど」
「うむ、さすがにイルミナ族でも無理かね」
「多分届きます。その代わり、いくつかの家の屋根が吹っ飛ぶでしょう」
ユリウスは眉を吊り上げた。
「構わん、やれ」
「えー……」
「やるんだ」
メイは仕方無く町全体を守りの魔法(パレ)で覆い、"光の突風(ルス・ヴィエント)"を唱える。
「お前、何を――」
シークの声は轟音に掻き消された。凄まじい強風が町の上空を駆け抜ける。メイの不完全なパレでは、予定通り全ての建物を守り切る事はできず、結局いくつかの屋根が飛んでいった。その風が城に達した時、白と黒の光が混じり合い、いがみ合い、そして消え去った。
「突撃だ!」
ルーヴァ達は"移動(アテリース)"で町の中に侵入する。同時に、それは戦いの始まりでもあった。
「約束が違うじゃないですか!」
息巻いたメイは、ユリウスの冷酷な目に声を失う。
――この人、正義(ルーヴァ)の為なら何でもやるんだ……。
「城を見ろ、メイ。城を見るんだ!」
ふいに腕を掴んだシークにつられて城に視点を動かした時、彼女の足は土から離れた。次にその足が踏んだのは、城の入り口の堅い床だった。
「逃げられたか……」
隊員達が城下町に乗り込んでいく中、ユリウスはザディーラに向き直った。
「情報提供ありがとう、ザディーラ君」
ザディーラは卑屈な笑みを口元に浮かべる。
「さんざん拷問しておいて。これであたいは自由なんだね?」
「ああ、ご苦労だったね」
ユリウスが顎をしゃくると、隊員がワイングラスとボトルを取り出した。
「これはアルボル家秘蔵のワインだ。君の新しい門出を祝って、一献進呈しよう。まさか、ザディーラともあろう者が酒に弱い、などと言うことはあるまいな?」
ユリウスは赤い液体をグラスに注ぎ、ザディーラに手渡す。彼女は挑戦的な目付きで、それを一気に飲み干した。
「どうだ、うまいだろう」
「ワインにしては変わった味だけど、いけるよ」
「そうか、これは毒なんだがなあ。君は、心根ばかりか舌まで狂っているようだね」
一瞬、ザディーラは戸惑いの表情を浮かべたが、事態を理解すると烈火の如くいきり立った。
「そんな! 騙したな! 正義を気取るルーヴァが、聞いて呆れるよ。この悪魔め!」
残っている隊員が、命令さえあれば彼女の命を奪えるように待機していた。
「弓矢や剣などを介して血液に混じれば数分で死に至るが、飲んだ場合は死ぬまでに八時間くらいの猶予がある。その間にソアラの首を持ってくれば、解毒剤をやろう。晴れてお前は自由だよ」
「どうせあんたら、あたいを放って戦いに行っちまうんだ! ソアラがここにいるかだって分からない……」
ザディーラは急に黙り込んだ。
「この魔力……。ソアラの奴だ……」
「なら話は早いだろう。行け」
ザディーラは短剣を手に取り、舐める。これは殺しの前の習慣だ。
「待ってなよ、あんたら」
それから颯爽とソアラの気配がする方向へと走っていった。
ザディーラが森の奥へと去った途端、ユリウス達ルーヴァの面々の口からは忍び笑いが漏れる。
「健気だな。最初から解毒剤など存在しないというのに。さ、我々も行こう」
数人のルーヴァ隊員は、司令官と共に戦場へ"移動(アテリース)"した。
メイは突然の変化に驚いて目をぱちくりさせた。
「アテリースは自分にしか使えないんじゃなかったのか?」
クラリスがシークに問う。
「見えている所へなら行ける。もっと言えば、それぞれが景色を想像できる所へなら」
説明が終わると、急に三人は静かになった。
「どうしたらいいの、私たち……?」
メイは城を見上げて呟いた。中から爆発音や叫び声が聞こえてくる。
「バイゼンを説得しよう。その為に来たんだからな」
シークは冷静に言った。
「どこにいるか、分かるの?」
「ああ。場内には三百人程のルーヴァと二百人程のバイゼンの部下がいるが、その中でもバイゼンの魔力は異質だ。……行くぞ」
メイとクラリスはシークに続いて門をくぐる。
中では壮絶な戦いが繰り広げられていた。訓練された魔導士の戦闘は、常軌を逸するのだ。壁や床は無造作に傷付けられ、早くも落命した者の肉片が散乱している。
飛び交う閃光がシーク達の行く手を阻んだ。彼は自身と仲間をパレで包み込み、安全を確保する。
「やだよ、見たくない……」
メイは手で視界を遮った。それを見たシークが怒鳴る。
「さっさと歩け! そんな事を言って甘えている時間は無い!」
泣くかな、とクラリスは思ったが、メイは泣かなかった。それどころか、今までに無く毅然としてさえいた。
「そうだよね。こんな戦い、早く終わらせよう。まずはバイゼンと会わなきゃ」
たとえバイゼンの説得に成功しても、戦いが終わるとは限らないのだが、ここはあえて指摘しない事にする。三人はそれ以降、無言で足を進めた。
ローゼは翻弄されていた。同僚と二人がかりでも、バイゼンの部下を倒す事ができないのだ。魔王と呼ばれる人物の部下だけあって、相手の男は魔法を使うタイミングを熟知している。
「この悪党が!」
焦りと苛立ちは、ローゼ達の判断力を鈍らせた。相手が放った"灼熱の炎(フィエブレ)"が二人の脚に喰らい付いた時、彼女達は何の対処もせず、それを夢の中の出来事の様に受け止めていたのである。意識が現実に追い付いた時には、肉の焼ける臭いが鼻を突き、重心を失って傾きかけた身体を、鮮やかな"風の刃(ヴィエンシル)"が切り裂いていた。
ローゼは腕が無くなった同僚の名を呼ぶが、返事は返って来ない。相手も必死だった。正義を守れなかったことは残念だが、この様な結果に終わっても不自然ではないだろう。私達は等しく人間なのだ……。
彼女は目を閉じる寸前、ガイルの枯れ草色の頭髪を見た様な気がした。
「隊……長?」
だが、声は冷たくローゼを突き放す。
「心に迷いがあるから、そうなるのだ」
助けてはくれない様だ。彼女は力無く、血の絨毯に頭を預けた。
敵か、あるいは味方の足が、もう二度と動く事の無いルーヴァ隊員の体を踏み越えていった。
ソアラは出張先で三人の要人を殺め、意気揚々と帰ってくるはずだった。しかし、何か言い様の無い胸騒ぎによって、その予定は変更された。今、彼女は上機嫌とは程遠い心持ちで城の近隣の森を駆けている。
「久しぶりだね、ソアラ」
待ち構えていたのは、かつての同僚ザディーラだった。二十メートル先の木陰から、音も無く姿を現す。
「あなたはルーヴァに捕らえられたのではなかったのですか? よく生きて帰ってこられましたね」
ソアラは皮肉抜きで感心した。が、ザディーラが目を細めて笑っているのを見て、顔色を変えた。
「何を企んでいるのです」
「実はあたい、バイゼン様を裏切っちまったんだ」
ソアラの美貌が凍り付く。
「裏切ったというと、具体的にはどういう事なの?」
彼女は敬語を棄てていた。オレンジ色ではなく、本当に赤い夕焼けの色をしたストレートの頭髪が、怒りに戦(そよ)ぐ。
「そうだねぇ。ルーヴァをここまで案内したのはあたいだし、闇の魔法について口伝てしたのもあたいさ。きっと今頃乱――」
先刻までザディーラの首があった空間を、"風の刃(ヴィエンシル)"が薙いだ。危ういところで死を免れたザディーラは、呑気に口笛を吹き鳴らす。
「なぜバイゼン様を裏切ったの? リカルドの大軍の中で埋もれていたあなたを、あの方が抜擢して下さったのよ。その恩を忘れたの!?」
ソアラの心は裏切り者への憎悪で一杯になった。もう、殺す事しか考えられない。
「あたいはただ、自由に生きたいだけなんだ! その為にあんたの首を貰うよ!」
始まるべくして、その後伝説として歴史に残る戦いが幕を開けた。
先駆けて、ソアラは"雷撃(トレント)"を放った。"操土(ティエノン)"によって作り出された土の壁が、ザディーラを守る。ソアラは"氷の槍(ニエベント)"で壁を打ち砕くが、すでにザディーラが跳躍した後だった。連続してザディーラはソアラの足元を"風の刃(ヴィエンシル)"で狙った。ソアラは軽やかに舞い、それをかわしつつ"水の弾(アジュビア)"を唱える。それはザディーラの"火球(フィエゴ)"と衝突して、霧となり四散した。
辺りを白く覆ってしまった事は、両者にとって不覚だった。"突風(ヴィエント)"で霧を払う内に、二人は同じ結論に達した。
「魔法じゃ勝負がつかないね」
「剣で決着をつけましょう」
二人の女は短剣を手に取り、睨み合う。ふとザディーラが口にした。
「あんたを殺る前に言っとくよ。あたい、リカルドの下で働いていた頃、仕事はそこそこで辞めて、後は気ままに生きようって思ってたんだ。それなのに、バイゼンがあたいを指名した! あの男はつくづくひどい奴だよ。あんただってそう思うだろう?」
「なぜ?」
彼女は遊んでいたのだ。
「せっかく綺麗に生まれてきたのに、肝心のバイゼン様が見向きもしないんじゃあね」
ソアラは震える声でやっと叫んだ。
「よくもそんな下劣な事を……!」
二人は接近する。剣と剣が交わり、互いを払い除け、再度交わる。冷たい金属の音が静寂の森に染み渡り、馴染んでいく。
ソアラの短剣がザディーラの頬を裂いた。同時にザディーラの短剣がソアラの腕を裂いた。両者は互角だった。刃物が彼女達の肌を撫で、傷で何かを描く。それは悲しみかも知れないし、強さであったかも知れない。もしくは命の輝きか。いずれにしても、深く儚いものを。
ザディーラには痛みに耐え得る忍耐力が欠如していた。徐々に集中力を失い、与える傷より受ける傷の方が多くなっていった。
そして遂に、ソアラにねじ伏せられた。私は死ぬのだ、殺されるのだと言う事がやっと理解できたのも、この時である。
「いやだ! 死にたくない! 殺さないで! お願いだ、刺さないで! いやだああーっ!」
狂った様に泣き喚く彼女に、ソアラはただ一言、
「許さない」
と、それだけ告げた。
短剣を心臓の真上に定め、慣れた手付きで裏切り者を突き殺す。ソアラの天使の様な顔が、返り血を浴びて妖しく彩られた。ザディーラは必死で生きようとしていた。だが、すぐに表情を失い、彼女の存在は虚無の世界へと葬られたのだった。
雨が一粒、また一粒と降り始め、やがて豪雨となる。天空を稲妻が走った。雨はしたたかにソアラの体を打ち、血を洗い流してくれる。そうすると、傷がはっきり見えてきた。深い傷もあるが、それよりもバイゼンの許へ駆け付ける事の方が重要だ。ソアラはふらふらと立ち上がり、力の入らない脚で歩き出す。
この時、彼女は知らなかった。ザディーラが戦いの前に自分の短剣を舐めた際、その刃に微量ながら毒が付着していた事を。その毒は、すでにソアラを蝕んでいるのだ。
シーク達は混乱に乗じて楽に進む事ができた。シークの完璧なパレは、いかなるものをも跳ね返す。道を塞ぐ者があっても、無理矢理進んでしまえば良かったのだ。
上階に行くに従って、戦士の数は減っていった。ルーヴァは下の階で食い止められているらしい。四階には誰もいなかった。そして、五階の廊下。
「バイゼン……」
捜し求めていた長身の男が姿を見せた。
「待っていたぞ、シーク。それにメイ」
クラリスがバイゼンと会うのは初めてだ。彼女は、厳しい顔つきのたくましい男性を想像していた。だが、目の前の人物は、むしろ家庭に置いた方が自然な程、優美だった。それでも、圧倒的な存在感とカリスマ性を持っている事は否めない。また、彼が魔王と恐れられている事も。クラリスは、きっと自分はデランの事で彼に対して怒りを覚えるだろうと思っていたが、不思議と何の感情も起こらなかった。
「そちらの方は?」
「クラリス・エヴェンズ。デランの姉だ」
シークに紹介されて、クラリスは居心地悪く俯く。
「……そうか。それはすまなかったな」
「そんな事より、この二人と話を。その為に人のいないここで、戦いにも行かずに待っててくれたんだろう?」
「それは少し違う」
バイゼンはやや顔をしかめた。
「この城は、戦場となるには脆い。隠れの魔法で守るから大丈夫だと油断して造ってしまったのだ。お前達の存在に気が付き、こちらから出向こうとも考えたが、下に行けばルーヴァが私目がけて強力な魔法を放ち、城を破壊する。だから、シークを信じてここで待っていた。それだけの事だ」
メイがバイゼンを非難する。
「レイールさん、城なんか壊れてもいいじゃないですか。部下だけを戦火にさらすなんてひどい!」
「いや、メイ、城が崩れたら、下敷きになって、より多くの人間が命を落とすと思ったのだ」
「その話はもういいから、バイゼン、俺の話を聞け!」
シークはいらいらと叫んだ。イルミナ族の会話は、どうもずれていて付いていけない。
「バイゼン、いっそこのまま城を捨てて、普通の家族の様に暮らさないか?」
バイゼンはしばらくシークを見つめていた。
「それがお前の望みか。では、ルーヴァを連れて来たのもお前なのか?」
「それはザディーラだ。俺達は、ルーヴァに利用されただけだ。どんな事をしていても、バイゼンは俺の家族だからな。裏切ることなどできない」
二人の言葉のやり取りが急に途切れた。閑静な場の中で、次に動いたのはメイだった。
「レイールさん、私、あれからまた考えました」
微笑を湛えて優しく語りかける。
「確かに世界って、私達が思い浮かべてたのよりずっとめちゃくちゃで、レイールさんが『汚いな』って思うのもよく分かります。でもそれは、私達がイルミナ族の世界しか知らなかったから。外の世界は私達が生まれるずっと前から、この形で回っていたんです。これが本来あるべき人間の姿なんじゃないのかなって、私は思います。ちょっと汚くて、だけどきれいなところもある。それが人間なんですよ。私達、イルミナの村にいた頃の幻想を押し付けてるんじゃないでしょうか?」
「押し付けて……」
バイゼンは彼女の言葉を繰り返した。
「はっきり言いますけど、レイールさんのやってきたことって、全部ムダです。傍目には乱暴にしか見えないし、余計な恐怖と憎しみを人の心に植え付けちゃったし」
メイは思い切って口に出す。
「人間、このままでも十分美しいです。ほんとですよ。よく見て下さい。汚いところばかり見てるから、何も認められなくなるんです。もっと、いいところを見てあげて!」
その時、町の方で何かが爆発する音がした。
「まさかルーヴァは、町まで滅ぼそうと言うのか!」
バイゼンは、床から百三十センチの位置に備え付けてある通気口から外の様子を伺う。シークとクラリスが彼を見守る中、メイは他にも通気口が無いかと振り返った。
彼女は息を呑んだ。
たった二メートルしか離れていない所で、完全に気配を消した者がバイゼンの背後を狙っている。水色の光が、その者の腕の周りを旋回し、やがて強い輝きを放ち始める。
メイはとっさにバイゼンを押し退けた――。
スポンサーリンク