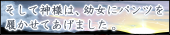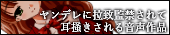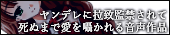※専門家でも何でもない、一介の大学生が授業で作成したレポートです。この文章を「参考文献」にしたり「引用元」にしたりしても、あなたの論文の信頼性を高めることはできません。ご注意ください。
また、後半の考察は一介の学生の意見でしかありません。ご留意ください。
2012年5月10日
原子論は哲学たり得るか
現在、哲学と科学は異なる学問として捉えられている。では、哲学と科学の中間に位置しているように見えるレウキッポス(B.C.435頃)、デモクリトス(B.C.420頃)らの原子論は、哲学と言えるだろうか。そもそも、哲学と科学は本当に性質の異なる学問なのだろうか。
まず、哲学とは何かを明らかにしたい。
最初の哲学者と呼ばれるタレス(B.C.585頃)は、従来の思想家にはない探究態度を持っていたために詩人とは区別された。
詩人、例えば紀元前8世紀のホメロスは、叙事詩を通して世界の在り方や「人間はどう生きるべきか」という生き方の規範を提示していた。しかし、神話的な思想には合理的な根拠がないため、それが本当に正しいのかどうかを検討することができない。
それに対して、自然現象が神々の気まぐれではなく法則に従って起こっているということを発見したタレスは、自分の主張について合理的な根拠を示し、他者が批判的に真偽を検討できる状況を整えた。
論理的な正しさを重視し、反論を受け付ける。それが哲学の始まりだった。
しばしば、哲学は自然現象の探究から始まり、後に人生の在り方について考えられるようになったと言われるが、それは誤りである。
「万物の始原は水である」というタレスの哲学は、以後脈々と受け継がれる「万物の始原を前提とする自然観」の発端でもあるが、ただ単に自然法則を見出そうとしたわけではない。タレスの属するミレトス派では、自然は「生ける自然」として捉えられていた。無生物も含めた万物が魂(生命、プシュケー)を持っているという物活論においては、万物の始原とは生命の原理、動の原理であり、万物に宿る神的な原理であった。
タレスは、自然の在り方を探究することによって生命の在り方を、究極的には人間の生き方を知ろうとしていたのである。
タレスは人間のよりよい生き方を知るために、この世の全体的な知を論理的に探究していた。
この態度が、哲学を哲学たらしめるものであると考えるべきだろう。
タレスが確立した論理的な探究態度は、学問の発展に大いに貢献した。
タレス以降、ミレトス派、ピュタゴラス学派、イオニア自然哲学、エレア派などが、過去や同時代の学説の真偽を論理的に検証し、問題点に対して対案を出したり、時には一部取り入れたりしながら発展を遂げた。多元論、原子論もその流れの中で誕生した。
エレア派は、ゼノンのパラドクスなど、人間の感覚と論理的に真実であると考えられることの間の食い違いを指摘し、ものに動きがあること、大きさがあること、数があることを否定したが、これらは人間にとってはあるようにしか思えないものだった。このことが原子論のヒントとなった。
つまり、エレア派に反論しようとする中で、
「物体は不可分なもの(原子)の集まりなので無限に分割できるわけではない」
「あるものだけでなくあらぬもの(空虚)もあり、原子はその中で運動する」
という考え方を思いついたのである。
また、パルメニデスによる生成消滅の否定は自らの思想にも取り入れ、
「原子は形と大きさ(一次性質)に無限の多様性があるが、色や感触などの感覚的性質(二次性質)についてはいかなる性質も持たないので、永遠不変で生成消滅もしない」
と主張した。
我々が感覚している現象は、原子の形、配列、向きが物理的多様性に変換された結果である。魂についても魂の原子を想定し、すべての現象は空間における原子の配置で説明される機械的なものであると考えた。
レウキッポスとデモクリトスの説には、原子には感覚的性質がないと主張しているのにもかかわらず、原子が形と大きさという感覚の対象となり得る性質を持っていることを前提としていたり、原子がそれ以上分割できない原因を硬さ(密度)という感覚的性質に求めていたりして、論理的に未熟な面がある。
しかし、原子論の最も重要な主張はそこにあるのではない。彼らがアナクサゴラスの多元論のように原子に感覚的性質を認めたとしても、おそらく原子論の本質は変わらないだろう。
原子論の最大の特徴は、世界を機械的な原子の集まりとして捉えた点にある。
最初の哲学者タレスが前提とした、万物に宿る生命性、神性、言い換えれば尊厳を、原子論は否定する。
原子論においては、人間が価値を見出している生命や美などは現象でしかなく、真実においては無価値である。そもそも、何かに価値を見出す心の動きさえも、原子の機械的な動きから生まれた無価値な現象だ。
デモクリトスは倫理学の書物も書いていたが、本当に原子論に徹するならば、この世に「~すべき」「~してはならない」ということは一つもない。何事にも価値はないのだから。
プラスの価値もマイナスの価値もないとすれば、原子論者が生きる上で問題とするのは「どうすべきか」ではなく、「どうしたいか、どうすればそれができるか」である。
人の幸せを願うことも、人の不幸を願うことも、禁欲を望むことも、皆等しく無価値な現象であり、そこに優劣や善悪はない。感情や欲求に価値がないということは、それらを抑圧することにも意味がないため、原子論者は欲望のままに生きるだろう。
自分の感情に価値がないと知っていても、人は無感情になるわけでも快を感じなくなるわけではない。錯覚だとしても無価値な快に喜べるうちは、望んだ現象を計画的に引き起こそうとするのが、原子論者の生き方であると私は考える。
タレスは人間のある「べき」姿を明らかにして「善い」生き方を知るために、この世の全体的な知を探究していた。
それに対して原子論者は、人間にはある「べき」姿などないという結論を出した上で、自分の望みを実現できる可能性を高めるために、あるいは知的好奇心を満たすことそれ自体を目的として、原子でできたこの世界の法則性を探究しているのではないだろうか。
原子論は、タレス以前から続いてきた規範的な生き方の探究を捨ててはいるが、「人生の目的のためにはどうするべきか」という観点は捨てておらず、この世のすべてを知ろうとする態度も変わっていない。違うのは、何を人生の目的に据えるのも自由であるという点だけだ。
規範的な生き方を探究しなければ哲学でないとすれば、原子論は哲学ではない。事物に霊的な価値や尊厳があると信じている哲学者からすれば、善悪を信じない原子論者や科学者は自分たちとは相容れない存在に見えるだろう。
しかし、この世の真理を探究するという点においては、哲学も原子論も科学も同質なのである。