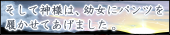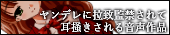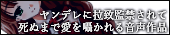プロローグ
そこは戦場だった。日本兵はほぼ全滅。民間人が銃で敵兵を撃ち払おうとするも、力の差は歴然としている。次々と大人が倒れ、非力な子供でさえ遺された銃を手にせざるを得ない状況だ。
そんな緊迫した空間に、何の前触れもなく透き通った歌声が響き渡った。声質はまだ幼い。人々は何かに取り憑かれたかのように動きを止め、恍然として表情を緩める。
やがて歌い手は、一人の青年を従えて姿を現した。
年の頃は十歳前後。黒のショートドレスを身に纏い、長い黒髪を惜しげもなく風にゆだねる姿は神秘的ですらあった。その天使のような美しさを前にして、全ての人間が戦意を喪失し、武器を放棄してその場に立ち尽くす。そして呟いた。
――「萌え」、と。
世歴(せいれき)一九九九年。
第三次世界大戦の真っただ中で、その少女は歌っていた。
「見てパパ、軍が帰っていくわ」
少女は軽やかに振り返って、後ろにいた眼鏡の青年に微笑みかけた。
「かぐやの歌を聴いて『萌え』ないやつはいないよ。この調子で世界を救おうな」
青年はまだ十歳の娘を持つには若すぎる。パパというのは愛称で、むしろ兄か歳の離れた友人であると捉えた方がしっくりくるような風貌だ。
かぐやと呼ばれた少女は、頷く代わりに青年の腕に抱きついた。白い首筋と滑らかな黒髪が優美なコントラストを描く。
「私が世界を救うのよね。私が戦わないでって歌えば、みんな言うことを聞いてくれる。これってすごいことよね。でも、パパ。たくさんの人が苦しんでいるのにこんなこと考えるなんて、私は自惚れ屋かしら」
不安げに見上げる真っ黒な瞳を見つめながら、青年は優しく言った。
「自惚れなんかじゃない。俺なんか本気で、かぐやは天が遣わした天使なんじゃないかって思ってるよ」
「パパったら。発想がファンタジーね」
呆れたように肩をすくめ、少女は青年から離れる。子供が母親の亡骸にすがって泣いているのが目に留まった。見渡しても見渡しても瓦礫の山。戦争が始まる前は幸せだったであろうこの街も、こうなってしまっては元通りには戻らない。
「私が戦争を終わらせる」
自分に言い聞かせるような少女の声に、予期せぬ反応があった。
「だめだ!」
そう叫んだのは、先ほど死んだ母の傍らでむせび泣いていた少年だった。歳は少女と同じくらいに見える。その手には銃が構えられていた。
「戦争さえあれば、ぼくも兵隊になれるんだ! あいつらみんなぶっ殺してやる! あいつらのお母さんも殺してやる! みんな殺してやる! こんな世界、ぼくがみんな殺してやる! だから戦争は終わっちゃいけないんだ! 戦争を終わらそうとするお前なんか――」
「え?」
少女には少年の言葉が理解できない。戦争が終わったら、誰もが私を称えて喜んでくれるのではないの? 何故この少年は私に銃を向けて――?
「かぐや!」
青年が駆け寄るのも間に合わなかった。
「ここで殺してやる!」
これは一つのエピローグ。
そして、新たな物語が始まる。