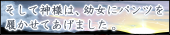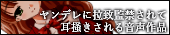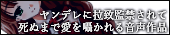第四章 ほし
次に僕が目を開けた時、カーテンの隙間からは朝日が差し込んでいた。時計を見ると五時半。今日は土曜日だが、平日休日分け隔てなく六時に起きている僕にとっては、少し早い起床くらいの感覚だ。でもまだ頭痛もするし、しばらく横になっていようかな……。
そう言えば、寝る前と着ている服が違う。布団から手を出して袖口をしげしげと見つめていると、横から声がかかった。
「貴方の服は、東条胡都が着せ替えていたわ」
「うわっ」
今まで全然気がつかなかったが、高野さんがベッドの隣の椅子に座って僕を見ていた。本当に存在感の希薄な人だ。すぐそこにいると分かっていても、幻を見ているような気分になる。とりあえず基本的な挨拶をしておこう。
「ええと、おはようございます」
「おはよう」
にこりとも笑ってくれないよ……。この人とどのように接するべきなのか、皆目見当がつかない。彼女のことはほとんど知らないのだ。何者で、どこから来たのか。いちご柄のパンツが好きということしか知らないと言っても過言ではない。
「まずは謝罪させて」
「どうして高野さんが謝るんですか? 僕はむしろお礼を言いたいのに。昨日は助けてくださってありがとうございました」
しかし高野さんはほんのわずかに顔を曇らせた。
「昨日のノクターンの侵入は私の責任。だから謝罪する」
驚いて身体を起こす。勢いがよすぎて、ずきりと頭に痛みが走った。
「どういうことですか。高野さんはノクターンの関係者なんですか? そもそも何でスタジオピンクの場所を知ってたんですか」
一息に質問を浴びせると、僕は背中側にあるベッドの柵にもたれかかった。やはりまだ本調子ではない。熱を出している時特有の嫌な寝汗が、外気に晒されて冷える。
高野さんは淡々と話し始めた。
「私はどこの組織にも属していない。そして貴方の敵ではない」
「それじゃあ高野さんは何者なんですか」
白を基調とした静かな医療室に、透き通った声が響く。
「単刀直入に言えば、宇宙人よ」
……そっか。宇宙人なのか。宇宙人だったら超能力くらい使ってもおかしくないよね。納得納得。
「驚かないのね」
無表情で見据えられると、睨まれているのに似た印象を受ける。もしかして驚いてほしかったのだろうか。
「もともと宇宙人はどこかにいるって思ってましたし。それに、僕は昨日一日でアニメを超える経験をしてきたんですよ。信じます」
「そう。なら話しやすいわ。これから私が言うことは荒唐無稽に聞こえるでしょう。でも全て真実よ」
僕は少し緊張して、高野さんの話に耳を傾けた。
「始めに、スタジオピンクの場所がノクターンに知られた経緯について話すわ。もしかするとこれが一番信じられないかも知れない」
信じられないって、一体どんな壮絶な過去が……!?
「おととい、手書きの地図を見つけたら捨てるように頼んだわね。それは、私がスタジオピンクまでの道のりを書いたメモのことだったの。私が道端に落としたのを、ノクターンの人間が拾ったのだと思われる。ごめんなさい」
……え。
「落し物が原因だったんですか?」
「私は真実しか言わない」
しょぼっ。
「そもそも何でスタジオピンクの場所を知ってたんですか。今だってこうしてスタジオローズにいますし……」
「見たでしょう、私が壁を通り抜けるところを。私は自分自身と私に隣接する物体を不可視な霊体にする『ゴースト』という力を持っているの。ゴーストを駆使すれば、尾行・侵入・探索は至極簡単なものになる。私に行けないところはないわ。この星に来てから五十年近くが経ったけど――」
ちょっと待て、今何歳だ。
「――私はずっと食料や生活用品を盗み続け、不法侵入を繰り返してきた。以前貴方の部屋に住んでいたというのは本当だけれど、それは寝食に利用していたということであって、不動産会社と契約していたわけではない。貴方が住み始めたとは知らなくて、出会った時は正直かなり焦ったわ。動揺を悟られないように必死だった」
冷静沈着にしか見えませんでした。
「私のことは他の人には言わないで。ばれたら問題になる」
「えっと、宇宙人さんですから、治外法権が適用されるかも!」
「問題は捕まることじゃない」
渾身のフォローは、高野さんの能面顔の前にあっけなく撃沈した。
「ゴーストになれば、捕まったとしても逃げられる。地球人の持つ物理的攻撃手段は私には通用しない。それよりも、私は私たちの存在を知られることを恐れているのよ」
「たち?」
「地球上にはもう一人、私の主(あるじ)でカタリ様という方がいる。カタリ様は私と違ってゴーストになることはできないし、そもそも自分が宇宙人だということもご存じないの。私にとって最も優先すべきことは、カタリ様の平穏な生活を守ること。宇宙人が地球にいると知られたら、カタリ様にまで調査の手が回るかも知れない。だから絶対に私のことは誰にも言わないで。……今日ここに来たのは謝罪のためだけじゃない。貴方にはゴーストが効かないから、うかつに他言される前に口封じに来たのよ」
脅しとも取れる言葉を投げかけられながらも、僕は高野さんを怖いとは思わなかった。純粋に『カタリ様』を想う気持ちが、真剣な眼差しから伝わってくる。その様子は、むしろ微笑ましいとも呼べる気がした。
「カタリ様って、高野さんにとってとても大切な人なんですね」
僕がそう言った時、高野さんは初めて大きな表情の変化を見せた。何と口元を上げて微笑んだのだ。
「カタリ様は私の全てだから」
表情に乏しい彼女の顔をここまで動かすなんて、カタリ様は偉大な人なのかも知れない。
「貴方にはもう少し話につき合ってもらう。ここからは、先日貴方に言おうとしてやめた話の続き。貴方には聞く権利と義務があると判断した」
高野さんは微細な動作で居住まいを正して、抑揚こそ欠けるものの、流暢な言葉遣いで僕に語り始めた。
「私の故郷の星――ルルティナでは、『力』を持つ者に特別な役目が与えられる。力は幼児期の終わりごろに覚醒し、覚醒した者は力の種類によって役目を振り分けられるの。ルルティナ全土を支配するのは女王の役目。女王の力は純粋で神聖な力。女王の声に含まれる力に触れると、ルルティナの民は問答無用で萌える」
「それって……」
「そう、貴方たちがMPと呼称する力と同じよ。ルルティナの女王は萌えをもって星を統括する。民は女王に絶対的な愛を向け、幸せに暮らしているわ」
萌えによる世界征服がすでに他の星で実践されているとは恐れ入る。ここまで来たら、MPが他の星にもあると考えるよりも、高野さんと共にMPの要素が地球にやってきたと考えた方が自然だ。
「女王の力を持った女王候補は姫と呼ばれる。そして、一人の姫に一人ずつ、女王の力を受けても萌えず、ゴーストのように特別な力を持つ『騎士』が存在する。姫は姫の役目を、騎士は騎士の役目を果たさなければならない。私は姫として生まれたカタリ様の騎士となり、以来ずっとお仕えしているの」
つまり、騎士の人生は全てお姫様に捧げられるということ。高野さんがカタリ様を何よりも大事に思っていることにも納得できる。
「姫たちは女王を決めるその日まで、城に幽閉され続ける。女王以外の者に民が萌えてしまったら規律が乱れるから。姫の純粋な力はルルティナにおいて重要なエネルギー資源と見なされていて、姫たちは専用の装置で力を搾取されながら狭い世界を生きるの。カタリ様はいつも寂しがっていらっしゃった。騎士は、孤独な姫に唯一与えられた味方のようなものだと私は思っているわ」
高野さんがカタリ様を想う気持ちと、僕が東条さんを想う気持ちは、ひとりぼっちの主人を支えたいという点で一致していた。
「女王の任期は五百年で、任期が切れる前日に、次期女王を選ぶための儀式が執り行われる」
「ご、ごひゃくねん……!?」
「地球人から見たら私たちは長生きで、力も強いようね。でも、驚くようなことではないわ。違う惑星で生まれた両者がこんなに酷似していることの方が奇跡的なのだから」
千年も生きるんだったら、ルルティナには仙人みたいな人がたくさんいそうだなあ。僕の脳内では、ルルティナは白く長いひげを生やしたおじいさんだらけの星というイメージになってしまった。
「儀式で姫たちは互いに戦わされる。そして、最も強い者が次の女王となり、敗者は再び力を搾取される日々に戻るの」
「そんな……女王になれなかったら死ぬまでこき使われるってことですか?」
高野さんの表情が少しだけ苦々しくなった。彼女の表情の変化の中では大きい方だ。それだけ姫の境遇に心を痛めているということだろう。
「そうよ。でも、女王になれたからと言って幸せになれるわけじゃない。女王は民が能天気に萌えている間にも、一人で政務をこなさなければならないの。吟くんも、東条胡桃を見ていれば分かるでしょう? それがどんなに孤独なことか」
東条さんは言っていた。MPを使うと周囲の人がみんな萌えてしまってまともに話もできないと。一度でもMPを使った相手には、くるたんとしての彼女が強く印象づけられる。MPを使っていない時でも、その人は東条さんを萌えの対象として見るようになるだろう。
萌えまくる人々に愛嬌を振りまきながら、本心では冷めた目で彼らを見ている疎外感は、何度想像してもぞっとする。そんな疎外感を五百年も抱え続けるなんて。それじゃあ姫として生まれた時点で幸せになれないじゃないか。
「幼いカタリ様の夢は、自由になることだった。だから私はその願いを叶えたの。カタリ様をゴースト化して一緒に城から抜けだし、パクってきた宇宙船に乗って、私たちはルルティナを飛び立った」
すごいことするなあ……。でも「グッジョブ!」という言葉がこれほど似合う行動もない。僕にはそんな度胸はないから尊敬する。
「その頃の私は、行く当てもないのに、カタリ様を幸せにするのだと意気込んでいたわ。青臭いとは思うけど、私は今でもそれについては後悔していない。後悔するのはもう少し先のこと。私はルルティナとよく似た環境である地球を発見し、地上に降り立とうとした。けれど途中でコントロールが利かなくなり、宇宙船は墜落してしまった」
「大丈夫だったんですか!?」
「宇宙船は落ちる途中で燃え尽きてしまったけど、私とカタリ様はゴースト状態で着地したから外傷はなかったわ。墜落した先は雑木林だった。私はカタリ様の無事を確認すると、水や食べ物を探しに出かけた。……それが最大の失敗だった。私が戻って来た時、そこにカタリ様はいなかった。近くの孤児院の青年がカタリ様を見つけて連れ帰っていたの」
あれ、その話、どこかで聞いたことあるような……。
「必死の思いでカタリ様を探し出した私は、カタリ様が記憶を失っていたことを知った。落下のショックで、自分は死んだと思い込んでしまったのでしょうね。ルルティナの姫としてのカタリ様は死んだ。孤児院の青年とも仲良くしていらっしゃって……私は身を引いたの。私といる限り、カタリ様はルルティナの関係者になってしまう。カタリ様が新しい人生を歩み始めるには、私は不要。そう考えて、私はしばらく地球を放浪していた。第三次世界大戦が始まって、戦場の歌姫のうわさを聞くまでは」
カタリ様は――。
「歌姫かぐやはカタリ様の二度目の人生なの」
高野さんはカタリ様と一緒にいたい気持ちを抑えてまで彼女を姫の身分から解放しようとしたのに、結局カタリ様は女王の力を使い始めてしまった。
僕はその続きを知っている。
「私はカタリ様が行くところについていき、陰ながら戦禍からお守りした。カタリ様も色川拓也も、戦地がどれだけ危険かをいまいち理解していないようだった。世界を平和にすることに夢中だったのね。でも、そんな無邪気さがまた愛しくて、私は『かぐや』を止めはしなかった。でもその結果、カタリ様は、私の目の前で……」
高野さんはそこで一瞬口をつぐんだ。ふと、一見無表情に見える彼女の顔に辛そうな影が差しているのに気づく。僕は続きを言おうとする高野さんを制止した。
「その先は、僕、知ってますから」
かぐやさんは錯乱した民間人に撃たれてしまったが、それは高野さんのミスではない。想定できないことだった。それでも高野さんは後悔してやまないのだろう。
「カタリ様がお目覚めになった時、一番喜んだのはきっと私。私であってほしい、と言うべきかしら。色川拓也は『かぐや』による世界平和を諦めてはいなかったようだけど、カタリ様は色川拓也の息子の純人と恋をして、ただ自由を求めていらっしゃった。私は今度こそカタリ様に幸せになっていただくために、色川純人とアプローチを取って駆け落ちを提案したの。彼、何て言ったと思う? 『俺はかぐやさえいれば、世界が滅んだって気にしない』ですって。私は色川純人を信じて、カタリ様との結婚を許した」
お義父(とう)さんみたい。
「駆け落ちは成功したけれど、カタリ様は私のことを知らないから、全て色川純人のおかげだと思っている。カタリ様の幸せは私の幸せでもあるけど……少し悔しかった」
無表情で本音を吐く高野さん。無機質な所作の割には人間らしい人だ。
「これでカタリ様についての話はおしまい。色川拓也はカタリ様が宇宙人だと信じていて、今でも密かに宇宙人探しをしているから、貴方には下手に『宇宙人はいると思いますよ』なんて言ってほしくなかったのよ。……ただ私が思い出話をしたかったというのもあるけれど」
もしかしたら高野さんは寂しかったのかも知れない。地球に来てからちゃんと会話をしたのは色川社長の息子さんくらいなんじゃないだろうか。その孤独も全てカタリ様のためとは言え、辛くなかったわけがない。存在を隠さなくてもいい人間が増えてよかったと素直に思う。
「それから貴方の話」
「僕?」
「ルルティナでは、姫と騎士の人数に乱れがあった時、それによって起こる混乱を終息させるために『調律者』と呼ばれる役割が生まれる。桁外れの身体能力を持ち、女王の力も騎士の力も無効化する最強無比の是正者。本来なら、そう説明できる。でもこの星では、何故か貴方に調律者としての力が宿ってしまったの」
「何故か」を強調されたような気がしたが、もともと抑揚のない人なので気のせいかも知れない。
「調律者はその役割上、力を持つ者を集める性質がある。だから貴方は私と出会い、東条胡桃と出会い、ノクターンの少女と出会った。ディーヴァからこんなに力のある者が生まれるなんて、地球人とルルティナ人の遺伝子は相性がいいみたいね。でもそれは、それだけ貴方がルルティナ人の身体能力を受け継いだディーヴァと出会いやすいということなのよ。貴方は力を無効化するけれど、身体的にはとても不完全。だからこの話を聞いてもらったの。せめて知識だけでもあれば、心構えはできるから」
僕が不思議な力を持つ人々と出会ったのは、偶然ではなかったということか。それなら、今まで気づかなかっただけで、普段からディーヴァの誰かとすれ違ったりしていたのかも知れない。東条さんとの出会いをきっかけに、次々と表面化してきただけで。
「あともう一つ。始めに私は犯罪を犯して生活していると言ったけれど、少し言い訳させてちょうだい。力には恒常型と意識型の二種類があるの。意識型が自らの意思で発動させる能力であるのに対し、恒常型は発動している状態がデフォルト。力を抑えるのはとても難しい。ゴーストは恒常型の力で、私は今でも長時間姿を現していることはできない。だから働けないの。決して怠けているわけではないのよ」
姿を現すのに努力が必要だなんて……。そしたら誰かとお話しするにも苦労するだろう。表情や言葉の抑揚に乏しいのも、会話の経験が極端に少ないせいなのかも知れない。一人では生きていけないような小さい頃から、高野さんはゴーストだったんだ。
ん? 小さい……?
そこで僕はぱっと重大なひらめきを得た。
「高野さん、東条さんの病気ってもしかしてルルティナ星から来てたりしませんか?」
「病気?」
「幼児のまま成長が止まっちゃった原因の病気ですよ。東条さんの成長はもう望めないんでしょうか」
ルルティナ人の遺伝子か、高野さんたちが地球に来た時に持ち込まれた異星のウィルスが病気のもとなら、対処法を知っているのではないかと思ったのだ。
しかし、帰ってきた答えはあまりに残酷なものだった。
「それは病気のせいじゃないわ。東条胡都が不老の薬を東条胡桃に投与したせい」
「……え?」
「彼女自身もその薬で若さを保っている。東条胡桃は薬の副作用を病気と勘違いしてそのように言っているのでしょうけど」
東条博士が、意図的に東条さんの成長を止めた……?
ショックを受けたその時、突然ドアが開いて、東条博士が入ってきた。噂をすれば影。
「あら、起きてたのね。調子はどう?」
そう言って僕の額に手を当てる。この人が東条さんの成長を止めた張本人だと思うと、面倒を見てもらっているのにもかかわらず怒りが湧いてきた。ミツルさんいわく、彼女はナルシストのぺドファイル。自分が幼かった頃の可愛らしさを留めておこうとでも思ったのだろうか。ひどいエゴだ。東条さんは何も知らず博士を慕っているのに。
「十時間も寝てたくせに、全然熱下がってないじゃない。朝ごはん食べたら、今度こそ薬飲んでもらうからね」
博士のすぐ近くに高野さんがいるけど、やはり全然気づく様子はない。あ、今通り抜けた。
「あなたが寝てる間に服着せ替えといたけど」
「はい、お世話になりました」
博士は何故かにやにやしている。
「あなたの身体は小学生並みね」
「……」
あああああ変態変態変態っ!
もうほっといてほしい!
寝る前に泣いていたことについて何も言われないだけましだと考えるべきか。いや、やっぱり変態だ。
「また後でご飯もってくるから、それまで大人しく寝てなさい」
僕の反応を楽しんでから、博士は部屋から出ていった。
昨日の時点で僕は東条博士の考え方に反対だったが、この数分で彼女への好感度は劇的に暴落した。あの人は人間の尊厳を軽視しすぎだ。いつか痛い目に合えばいい。はっきりと口にする勇気もなく心の中でそんな暴言を吐いている僕も卑怯だけど……。
「社員が活動を始めたようね。私はそろそろおいとまさせてもらうわ」
高野さんは衣擦れの音を全く立てずに立ち上がった。
「貴方との会話はとても快適だった。ゴーストのことを気にしなくていいんだもの。今日は楽しかったわ」
「いえ、こちらこそ」
高野さんはレアな笑みを浮かべて壁まで歩いていく。
「またお話しましょう、吟くん」
そして壁の向こうへ吸い込まれるように消えていった。
午後になると大分気分がよくなったので、ついにテレビを見ることにした。
もう同じ過ちは繰り返さない。テレビのスイッチは真ん中にあらず! 真ん中のはダミーだ。押したら最後、大量のボタンが出現して人間を混乱させる。右下のこれが本物だ!
緊張に震える指先でスイッチを押すと、一瞬にして画面に色がともった。
“『なんだただのクロマニョン人か』アニメ化決定!”
おおっ、いきなりアニメのCM。
“人気ライトノベルがついにゴールデンタイム登場!
主人公「俺は人類最後の生き残り。休眠冷凍から目覚めた二十万年後、そこは四種類の獣人が覇権を争う女だけの世界だった」
鳥っぽい女の子「なんだただのクロマニョン人か」
主人公「ハーピィ族の女王に魔神として呼び覚まされた俺は、持ち前の頭脳で大活躍! でもこれでいいのか? 違う、本当の幸せは愛だ! 俺は全種族の女王にフラグを立てる旅に出る!」
蛇っぽい女の人「坊や、いいこと教えてあげましょうか」
ウーパールーパーっぽい幼女「こう見えても妾(わらわ)は大人じゃ!」
人魚っぽい少女「……好きにすれば?」
鳥っぽい女の子「ハーレムって何ですか?」
地球の命運をかけた四つ股が今始まる!
SFラブコメスペクタクル『なんだただのクロマニョン人か』、九月から放送開始!”
どーん!(効果音)
何かすごそうなアニメだな。でも、クタオにはちょっとなじみにくいかも。ゴールデンタイムでハーレムって……。
呆けていると画面の右上に「コール受信:東条胡桃」という文字が表示された。続いて、ど真ん中に大きく、
「応答しますか? はい いいえ」
え、応答しますかって言われても、何これ。どうやって選ぶの?
よく見ると棚にリモコンがあったのでボタンを押してみた。エアコンが起動した。
さらによく見るともう一つリモコンがあったのでボタンを押してみた。カーソルが「いいえ」の方に動いた。コールの意味は分からないけど、東条さんが相手なら答えは決まっている。僕は「はい」で決定ボタンを押した。
ぷつりと画面が入れ換わり、東条さんの姿が映し出される。
「おおっ、乃木坂! もう起き上がっていいのか?」
どうやらこのテレビはテレビ電話としての機能も持っているらしい。さすがにトップアイドルだけあって、東条さんのテレビ映りは最高だ。まるですぐそこにいるかのように感じる。
「うん、いっぱい寝たから、熱も下がってきたよ。脚の怪我も大したことないみたいだし。心配かけてごめんね」
「まったくだ。お前はボクの下僕である限り、ボクの許可なくどこかにいっちゃったりするなんて許されないんだからな! ……もっと自分を大切にしろ」
ぷいっとそっぽを向いて怒ったように言う東条さん。よく考えてみたら、僕は下僕になった次の日に拉致られてその次の日はベッドの上。何て不甲斐ない。東条さんが怒るのも当然だ。
「僕、もっといい下僕になれるように頑張るよ。今『スーパー下僕道』っていう参考書を読んでるんだ。きっと読み終わったころには立派な下僕になってるからね!」
「あはっ、なんだそのギャグ! 地味におもしろいな」
東条さんは何故かけらけらと笑い始めた。スーパー下僕道という書籍名のせいで冗談だと思われたのだろうか。僕は著者の名誉のために鞄から実物を取り出して東条さんに見せた。
「ギャグじゃないよ。ほらこの本! 下僕の何たるかがこと細かに記されたすごい本なんだ。下僕が足をなめるのはご主人様の健康状態を確かめるためなんだって。僕もいつか東条さんの足を――」
「おい」
東条さんは、困ったような、憐れむような眼差しを僕に向ける。
「それは『僕下の階の下僕』っていうマンガから派生したジョーク商品だぞ?」
「えっ」
僕は思わず本を取り落とした。
ジョーク商品!? 精巧に作りすぎだっ!
「ゆーめいなマンガなのにそれを知らないってことは……やっぱりお前、クタオだったんだな」
「……」
テレビの臨場感がこれほど厭わしい時はない。東条さんは画面の向こうから静かに僕を見ていた。怒っているようには見えない。でももちろん喜んでいるようにも見えないのだ。
「ごめん、隠そうとしてたわけじゃないんだ」
切りだすタイミングを逃していただけ。決して東条さんをに嫌われるのを恐れてだましていたのではない……そう自分に言い聞かせる。
ふっと、東条さんは口元を緩めた。
「いいよ。会ったときからそんな気はしてたんだ。乃木坂は、萌えに慣れてないとゆーか、ちょっとみんなからズレてる感じだったからな」
「許してくれるの?」
萌えのリーダーである東条さんにとって、クタオは敵のはずなのに。
「許すもなにも、気にしてないぞ。クタオだとかオタクだとか、そんなことで人間の価値は決まらないってボクは思ってるから。でも、乃木坂が萌えがキライなら……ボクの下僕やってるのは、苦痛だよな。ごめん、無理矢理下僕にしたりして」
「そっ、そんなことないよ! 僕はクタオだけど、萌えって幸せだと思うし、平和も願ってるし、何より東条さんの力になりたいんだ!」
東条さんは上目遣いで僕を見て、不安げな声で尋ねた。
「ほんとに? ムリしてない?」
「うん。っていうか、僕、東条さんの下僕リストラされたら泣くよ」
「そうか……ならよかった!」
東条さんが笑顔になってくれてほっとする。彼女が悲しそうな顔をしているを見るのは心が痛い。
「乃木坂に報告することがあるんだ。雪菜がボクたちのなかまになって、世界平和計画を手伝ってくれるんだって」
「藤巻さんが?」
「うん。ノクターンがボクの力を利用しようと狙ってるから心配で放っておけないって」
「せっかく裏社会から出られたのに……」
「ボクもそういったんだけどな。そしたら一つおねがいがあるっていうんだ。高校に通わせてほしいって。だからボク、今から虹高に行って校長せんせーにMPかけて、雪菜を裏口入学させようと思うんだけど、どー思う?」
どう思うって……それはMPの悪用に他ならないけど……。藤巻さんの境遇を考えればそのくらいしたって許されるよね?
「やっちゃえやっちゃえ!」
「だよな! きゃははっ」
赤信号みんなで渡れば怖くないの精神である。
「ところで、当の藤巻さんは今どうしてるの?」
「まだパパと話し合ってるよ。問題が山積みらしいんだ。ディーヴァはみんな超能力者になったんじゃないかーとか、だれがスタジオピンクの場所をバラしたんだーとか、着物の女はけっきょく何者だったんだーとか。ディーヴァは今日から探し集めていろいろ確かめることになったよ。ノクターンのやつらはスタジオピンクの場所が書いてある紙をひろったんだって。でも社員の中にそんなメモしてるヤツはいない。情報ろーえいだ、スパイがいるのかもって、パパ血相変えて怒ってた」
そういうことか、と僕は心の中で頭を抱えた。カタリ様と高野さんが残していった謎と痕跡はあまりに多すぎる。僕はこういう疑問を上手くごまかして、カタリ様を守らなければならないのだ。
「でも、いちばん問題なのは、ボクのアンチがいるということだっ! まったくけしからん! ボクは、世界を平和にしようとがんばってるのにぃ……」
東条さんのアンチ団体――イノセンス。
今までただ人々に萌えられるためだけに尽力してきた東条さんには、このことはショックだったに違いない。しょんぼりと項垂れてしまった。かわいそうに。何か声をかけてあげなきゃ。
「東条さ――」
「いやいや、もっと明るいにゅーすを言おう!」
立ち直りが早すぎて何も言えなかった。ごめん。
「あしたは神聖アキバ帝国建国はっぴょー記者会見をひらくんだ。生放送で全世界同時配信だぞ」
「え、まだ発表してなかったの? 建国ライブは来週の日曜日でしょ?」
「何カ月も前からはっぴょーしてたら、ネットが大荒れしちゃうだろ。一週間まえくらいがちょうどいいんだ」
なるほど。東条さんほどの人気者となると一般論が通用しない。
「世界中が歓喜に包まれるだろーな! テレビを通すとMPの効き目はうすれちゃうけど、それでも世界中の人間を萌やしてみせる!」
「僕、テレビから見守ってるよ」
「うんっ」
やっぱり活き活きとした東条さんが一番だ。この笑顔を守るのは僕の役目なんだと思うと、誇らしいような申し訳ないような、くすぐったい気持ちになる。
「あっ、ひとつ注意しとくけど、クラスメートかだれかにライブ行かないかって誘われても、うんっていうんじゃないぞ。お前にはとくとーせきが用意してあるからな」
「特等席!? すごい、ありがとう」
「礼には及ばん。さてとっ、そろそろ学校に行って雪菜のにゅーがく手続き取ってくるか」
東条さんは座っていた椅子からぴょんと降りた。その何気ない動きさえ洗練された身のこなし。全ての動作に人を引きつける魅力のある人なんて、彼女以外にいるのだろうか。
「じゃあな乃木坂。あさっては月曜日なんだから、それまでにカゼ直しとけよ」
クールに手を振って画面から消える。通信は僕の方で切っておけということらしい。
……テレビ電話ってどうやって切るんだろう。
リモコンの存在を思い出すまで、僕の前のテレビはずっと誰もいない東条さんの部屋を映し続けていた。スタジオピンクの時と同じ、白黒仕立てだった。
***
岩口県のとある小さな町に、乃木坂純(じゅん)・乃木坂愛と名乗る夫婦がいた。
彼らの住む小さな家に、ゴースト化した高野透が降り立つ。彼女は純を探し出すと、一人でいるところを見計らって姿を現した。
「うわっ!」
「……そんなに驚かなくてもいいでしょう」
「あ、やっほー、透さん」
純はおちゃらけた様子で手を振った。童顔と矮躯が相まって、少年のような印象を与える容姿だ。――いや、実際に、彼の肉体年齢は二十代前半を保っているのである。
透は仏頂面で懐から袋を取り出し、純に差し出した。
「いつもありがとうね」
「勘違いしないで。カタリ様のため。貴方のためじゃない」
それは透が定期的にスタジオピンクに行き、東条胡都の不老薬をごく微量ずつ拝借して、ある程度の量にまとめたものだった。
「カタリ様の寿命に見合う分だけ貴方には生きてもらわなければならない」
「分かってるよ。大事に飲ませていただきます」
純はポケットの中に袋を入れ、「それで」と本題を切り出した。
「ついに吟に言っちゃった?」
「言った」
「まさかあのことは……言ってないよね?」
「言っていないわ。貴方が色川拓也の息子であることも、カタリ様が吟くんの母親であることも」
純は安心しつつ寂しがるように眉を下げて、感慨深げに呟いた。
「ついに吟、いろいろ巻き込まれちゃうんだな」
「巻き込まれるのではない。吟くんは自ら世界を動かすの」
透の言葉を聞いて、純は膝を打った。
「吟が家にいた時は、メディア見せないようにして必死で家に縛りつけようとしてたけど、やっぱり自由にさせてやるのが一番なんだって、今になって納得したよ。俺だって危険を冒して愛と結婚したわけだからさ」
「そうね。確かに貴方の教育方針には問題があった。保健体育の教科書の一部を墨で塗りつぶしたり」
「見てたのか……」
「見てた」
にこりともしないで言われると、ひどく責められているような気がして、純は逃げ出したくなる。
「だってぇ、やっぱ自分の子供にはいつまでも純粋であってほしいし~」
「それは親のエゴイズムよ」
「ですよねー」
――とん。とん。とん。
向こうの廊下から、ゆったりとした足音が聞こえてきた。純が透に目くばせすると、彼女は条件反射のようにゴースト化する。質量も温度も消えた透に、気配などというものは存在しない。
「純ちゃん、誰か来てるの?」
滑らかな黒髪を揺らして歩いてくるのは、白いネグリジェを着た乃木坂愛である。彼女は盲目であるためか音声に敏感なのだが、純朴な性格なのでごまかすのは簡単だ。
「いいや、誰もいないさ」
しかし、この夜だけは違った。
「そう……。でもね、何だかとても会わなければならないような気がしたの」
姫と呼ばれた頃の名を捨て、平穏な主婦として生きる彼女は、何も見えない瞳で透を見つめていた。
***
次の日の十時ごろ、藤巻さんがお見舞いに来てくれた。東条さんの時と違って、東条博士はあっさりと面会の許可を出してくれたそうだ。藤巻さんなら風邪を移されても問題ないと、適当に判断したのだろう。
「乃木坂さん、お邪魔しますね」
控え目な様子で部屋に入ってきた藤巻さんは、初めて見る普通の服装だった。パステルカラーを基調とした清楚なコーディネート。いや、彼女の話では黒服だって一般的なファッションらしいけど、田舎育ちの僕としては今の格好の方が落ち着く。
「お体の具合はいかがですか?」
「もう熱も微熱くらいになったよ」
一日ぶりに会った藤巻さんは、改めて思うけど儚い感じのする女の子である。吹けば掻き消えてしまうようにさえ見える。この体のどこに金属の鎖を引きちぎるような力があるというのだろう。ただ、華奢な体躯の中で、胸だけは量感を持っていた。彼女はスタイルがいいのだ。。
「私、東条さんのおかげで虹間高校に編入できることになったんです」
「よかったね! でも、こんなことを訊くのはあれなんだけど、その……べ……」
「勉強についていけるのかってことですか?」
言いづらいところをつないでくれた。
「学校に通ったことはないのですが、一応ノクターンの一員として大学卒業までの学習はしてきました。たぶん大丈夫です」
「そっか、余計なお世話だったね」
「いえ、高校とノクターンでは教えるものも違うでしょうから、変なところでつまずくかも知れません。その時は乃木坂さん、私に勉強を教えてくださいね」
そんな頭のよさそうな顔で教えてって言われても、逆に自信をなくしちゃうよ……。
「ああ、明日が楽しみです。私、ずっと憧れてたんですよ、学校に通うこと」
幸せいっぱいの微笑みから、彼女の喜びが伝わってくる。それだけに、「ただの高校生」ではないということが惜しい。
「カラプロの計画になんか首突っ込まないで、高校生だけやっていればよかったのに」
僕がそう言うと、藤巻さんは肩をすくめて微笑みを苦笑いに変えた。
「私は家族にも憧れてましたから、カラープロダクションのみなさんにそれと近いものを感じてしまったんです。東条さんはとてもお可愛い人。色川社長は厳しいけれどお父様のように優しくて。世界のどこかにいるディーヴァたちは、私にとっては姉妹のようなもの。どうしてもそんな『家族』を放ってはおけなかったんです。せっかく乃木坂さんに助けていただいたのに、申し訳ないとは思うのですが……」
「ううん、藤巻さんがそれで幸せなら、僕は応援するよ!」
変に罪悪感を持ってほしくなかったのであえて明るく振る舞うと、藤巻さんも暗い雰囲気を払拭し、晴れやかに頷いてくれた。
「ありがとうございます! 実は、私がカラプロに協力しようと思ったのには、もう一つ理由があるんですよ」
「ん? 何?」
「乃木坂さんのお役に立ちたくて」
口にした本人はいつもの聖女スマイルで悠然としている。けど今、すごく思い切ったこと言ったよね?
「あ……ありがと……」
僕は気恥ずかしくなって目線を下に向けた。
「乃木坂さんは、私に自由と未来をくれたんですよ。もっと胸を張ってください」
彼女はそう言ってくれるけど、やっぱりちょっと落ち着かない。もじもじしていると、藤巻さんが助け船を出してくれた。
「そろそろ東条さんの記者会見が始まりますね。テレビ、つけましょうか」
さすがに長年あの角谷さんの支配下にあっただけあって、気配りが上手だ。藤巻さんがテレビのスイッチを入れると、ちょうどニュース番組をやっていて、『くるたんの緊急記者会見 このあとすぐ!』という字幕が右上に出ていた。
まもなく生放送が始まった。
「とゆーわけで、みんなっ、神聖アキバ帝国の国民になってボクをいっぱい崇めてねー!」
神聖アキバ帝国の概要を一通り説明し終えると、東条さんは建国ライブの宣伝を始めた。
「一週間後の二十日には、建国ライブを開催するよ! 気になる会場は、国際都市縦浜の『縦浜オリハルコンホール』! ちけっとはお早めにね! さらに、二十二日にはカデニアに大しゅっちょー! 外国のみんなも、首都サンデシアのミレニアムタワーでボクの歌声をたんのうして下さい! ライブに来られないひともご安心を。ライブはぜーんぶ全世界同時中継だよっ! みゅーん」
ざわざわと記者たちから感嘆が漏れる。僕も藤巻さんも感知できないが、きっと今MPを使ったのだろう。
「みんながくるのを待ってるよー! うにー!」
ゴリっと音がして、画面に人の足が写った。どうやらカメラマンが悶絶してカメラを取り落としたらしい。
相変わらず、東条さんはトップアイドルだ。
記者会見が終わった後は、神聖アキバ帝国についての特集が延々と放送されていた。僕たちには見る必要のないものなのでテレビを切る。藤巻さんは僕の体調を気遣って退出しようとした。
「あ、乃木坂さん。言い忘れてました」
ドアの前で立ち止まり、僕を振り返る。
「私の本当の名前、分かりましたよ。角谷白雪っていうそうです。でも、これからも藤巻雪菜と呼んでください。白雪だなんて、私には綺麗すぎて恥ずかしいです。……それに、この名前はお母様からいただいた唯一のものですから」
「うん、分かった」
いつか藤巻さんとお母さんが和解できる日がくるといいな。
「それでは、お大事に」
彼女の後ろ姿を見て気づいた。おとといのような薄幸な感じが、もう吹き飛んでいるということに。
僕は夕方家に帰った。風邪はほぼ完治、銃創も生活に支障のないレベルにまで落ち着いていた。あの時の僕はちょっと撃たれただけでショックを受けていたが、このかすり具合からすると、藤巻さんはよほど手加減してくれたみたいだ。彼女に恐れをなしていた僕が、今や彼女の幸せを願っているなんて、不思議な感じがする。
冷蔵庫に入れてあった開封済みの牛乳は、腐臭こそしなかったものの生で飲むのはためらわれたので、ホワイトシチューにしてじっくり熱を通してから食べた。
それから何時間か精神安定剤代わりに勉強して、寝た。
次の朝学校に行くと、珍しく他のクラスメートたちがすでに登校していた。
「おまいら神聖アキバ帝国の国民証もらう?」
「もらうに決まってんだろ常識的に考えて」
どうやら神聖アキバ帝国の件で話をするために、みんな早めに来ているらしい。
「よぉ、乃木坂」
「あっ、おはよう」
遅刻ギリギリのイメージがあった池田くんも、今日は早く来ていたようだ。やたら真面目な顔で寄ってくるから何事かと思いきや、切り出された話は平和な内容だった。
「俺さ、ファンクラブ会員三桁内の特典で、建国ライブのチケット手に入りそうなんだ」
「へえ、よかったね!」
最初はそれだけかと思ったのだが、話には続きがあった。
「でさ、思ったんだけど、このチケットで乃木坂にナマのくるたん見せてやりたいなって」
「え?」
「だからさ、チケットやるから、お前俺の代わりにライブ行ってこいよ! こんな機会でもなきゃあ、いつまでもクタオのまんまだろ?」
いや、それは申し訳なさすぎる! 東条さんに特等席を用意してもらっていなかったとしても、僕にはそこまでしてもらって平気でいられるほどの図太さはない。申し出を断る旨を伝えると、池田くんはとても残念そうな様子で腕を組んだ。
「真面目なヤツだなー……。分かった。じゃあライブのDVDが出たら、学校のパソコンで見せてやっからな。ほんと、くるたんのない人生なんて、俺ぁかわいそうで見てらんねぇよ」
何で僕の周りはこんなにいい人ばかりなんだろう。じーんとしてきちゃった。
「ありがとう」
「なーに、くるたんのファンとして、布教運動は当然のことだぜ」
こんなことがあってからクラスを見渡すと、数日前とは全く違う風景に見える。ひそひそ声なんか気にならないし、何だかとってもいいクラスのようだ。高揚した気分で席について、自然と耳に入ってくる栗本さんの楽しそうな声をバックに勉強していると、担任の先生が小走りで教室に入ってきた。
「転校生が来たけど先生もう授業に行かなきゃならんから、後は栗本仕切っといてくれ! じゃあよろしく!」
「ええええぇちょっ先生!」
当然のごとく、クラス中から困惑の声が上がる。まあ、何も知らなかったら状況は飲み込めないだろう。新学期早々編入だなんて明らかにおかしいんだから。
栗本さんに促されて教室に入ってきたのは、制服を着た藤巻さん。生徒の多くが私服を好む中で、藤巻さんは完璧に制服を着こなしている。清楚な彼女は、太陽のように人の目を引く栗本さんと並ぶと、白い残月のようである。藤巻さんは色川社長厳選の美人であり、クラスでは悪目立ちしてしまうかも知れないと心配だったが、栗本さんがいれば上手く溶け込んでいけそうだ。
「今日からお世話になる藤巻雪菜です。よろしくお願いします」
藤巻さん、表社会デビューおめでとう! 僕は心から拍手を送った。
昼休みは、栗本さんが藤巻さんを自分のグループに誘ったため、みんなが彼女たちの周りに集まってわいわいはしゃいでいた。逆に僕の孤立具合はいっそう顕著になった。僕と藤巻さんは会ったことのない人間という設定なので、馴れ馴れしく話しかけることもできない。藤巻さんもそれを分かっているから、僕のことを見ないように意識している。
一人でお弁当を食べること自体はそれほど苦ではない。僕に孤独を感じさせているものの正体は、周囲のにぎやかなおしゃべりだ。一人だけ独りで浮いているのが孤独なのだ。やっぱり僕は臆病なクタオなのだと、嫌でも思い知らされるから。
「乃木坂くん」
「……ふぇ?」
タコウィンナーを口に放り込んだ時、フレンドリーな栗本さんの笑顔が勢いよく視界に飛び込んできた。
「今日はキリエたちと一緒に食べない? みんなで食べた方がおいしいよ!」
「……」
その優しさが責任感や建前から来るものだとしても、僕は嬉しかった。
「んー!」
ウィンナーを頬張ったまま何度も頷く僕を見て、栗本さんはくすりと笑った。
栗本さんという架け橋を渡って、僕はクラスメートの島に少しずつ足を踏み入れていく。そしてその島は、僕が思っていたよりもずっと暖かい空気に包まれていた。
だが……その人口密度のせいか、栗本さんの隣りに座っていた佐々木くんが貧血を起こしてしまった。まさか、クタオと席を共にしたストレスのせいじゃないよね!?
栗本さんのグループで昼休みを過ごして、一つ分かったことがある。
栗本さんはクラスの人気者で、いつも人に囲まれているにもかかわらず、どことなく人と距離を取っているようにも見えるのだ。
その理由がまさかこんなにすぐ分かるなんて思ってはいなかったけど。
「乃木坂くんは、クタオだよね?」
放課後、二人きりの教室で突然栗本さんはそう言った。帰ろうとしたところを呼び止められて、最後の二人になるまで待っていたのだが、まさかいきなりそんなことを言われるなんて……。
「怖がらないで。キリエは乃木坂くんを責めてるんじゃないんだよ。むしろその逆」
両手の指と指を突き合わせ、長い睫毛を伏せて彼女は告白する。
「あのね、キリエもほんとはクタオなの」
「えっ」
だって、どこからどう見ても完璧なオタク撫子なのに。
栗本さんはフリルのついたのメイド服の裾を握りしめ、僕の目をまっすぐ見た。と言っても僕の方が背が低いから、若干見下ろされる形になる。
「メイド服は手っ取り早くオタクに見せかけるためのカムフラージュ。キリエの家はメイド喫茶やってるから、メイド服には困らないんだ。他にも、みんなと友達になるためにアニメ見たりラノベ読んだり……でも本質はクタオのままなの。萌えなんてウケ狙いの虚しい作りものにしか見えないんだもん」
人との距離感は、オタク撫子の演技をしていることから生まれていたのか。
「だからなの? 僕に気を使ってくれていたのは」
「うーん、そんな感じかな。キリエ、ひとりぼっちの寂しさはよく知ってるから。乃木坂くんにはそんな思いさせたくなかったんだよ」
てっきりクラスを円満にするという義務を果たしているのだと思っていたけど、クタオのよしみだったんだ。クラス会長として以上に親切に接してくれていた理由も分かる。
「いつもありがとうね。栗本さんのおかげで、クラスに馴染めそうだよ」
彼女の心遣いに効果があったことを伝えて喜んでもらうつもりだったのだが、意外なことに栗本さんは不安げな顔を見せた。
「乃木坂くんが寂しくない程度にでいいんだよ? あんまり馴染んだら、乃木坂くんまでオタクになっちゃう。乃木坂くんには今のままでいてほしいな」
僕は、栗本さんが望んでいるのは僕がクタオらしさを抑えてクラスに参加することだと思っていたから、返ってきた言葉には意表を突かれた。
「乃木坂くんは、東条胡桃のライブ、行かないよね?」
僕は表向きには東条さんとは何の関係もないクタオなので、彼女の気持ちを考えなくとも答えは一つしかない。
「……うん」
「だよね! 乃木坂くんはキリエの仲間だよね!」
本当に嬉しそうだ。クタオは少数派だから、少しでも仲間がいると安心できるんだよね。その気持ちは分かるけど……。
実際は萌えの女王の下僕であることを考えると、だましているようでいたたまれない気持ちになった。
栗本さんと別れた後、こっそりと東条さんと合流し、スタジオローズへと向かった。ライブの日までに、僕にもやらなければならないことがあるらしい。車の中で大まかな説明を受ける。
「乃木坂にはライブが始まるまでボクのそばにいてほしいの。でも一般人がボクにひっついてたら、オリハルコンホールの関係者が不審に思うでしょ? だから、乃木坂にはひとつ演技をしてもらうね。ボクが神聖アキバ帝国建国に際して雇うことにした秘書、それが乃木坂の役!」
「秘書の演技って? スーツ着たりするの?」
「ううん、女装」
えええ――と声に出したいところだが我慢した。確かに、正体を隠すには性別を変えるのが有効だ。それに文句を言うのはわがままだよね。そう自分を納得させる。
「もちろんそれだけじゃなくて、ボクのスケジュールはぜーんぶ把握してもらうよ。つまり、乃木坂♂(オトコ)は下僕で乃木坂♀(オンナ)は秘書なの! ね、いいアイディアでしょ?」
「う、うん」
東条さんは僕をからかっているわけではなく、本当に名案だと思って言っているようなので、下手に突っ込むこともできない。この作戦は僕のためのものなのだから、むしろ感謝しなくてはいけないのだろう。
スタジオローズに着くと、待ち構えていたミツルさんがすごい勢いで僕を引っ張っていった。戸惑いがちに見上げると、目がらんらんと輝いている。
「最初見た時からずっと可愛い服着せてあげたいと思ってたのよー。こんなに早く願いが叶うなんて、あたしったらツイてるわぁ」
「えっ、もう女装するんですか」
「胡桃ちゃんは女装したあなたを見てからいろいろ設定考えるって言ってたわよ」
「でも心の準備が」
「ふふっ、あたしに任せておけば大丈夫よ」
更衣室に放り込まれ、僕は――。
目の前にいる少女は、頼りなげな様子で僕を見つめ返していた。
ベビーピンクのエプロンドレスに身を包み、黒いタイツの足元には可愛らしい赤い靴。髪型は緩やかなウェーブのかかったロングで、うさ耳のついたカチューシャをつけている。
鏡の中の僕は、すがすがしいほど女の子だった。
前々から僕の体は発展途上で女々しいと気にしていたけど、まさかこれほどだったなんて……。体のことは時が解決してくれると信じていた僕だが、だんだん自信がなくなってきた。
「可愛いわぁ、もう芸術の域に達してるわよ」
「これなら絶対みんな女の子だって思うよ!」
ミツルさんと東条さんに絶賛されて、嬉しくなくもない。とても複雑な気分。
「よーし、乃木坂♀の設定できたー! これ覚えてね」
手渡されたメモ用紙を見ると、そこにはこと細かに「わたし」の設定が記されていた。
名前:銀杏
年齢:女の子に歳を聞いちゃだめですよ。
誕生日:二月十七日
サイズ:身長156センチ B74・W60・H78 43㎏
特技:おもいだす
「え、これ僕のこと調べて書いた?」
「ううん、てきとー」
それにしては妙に真実度が高いんだけど……。誕生日がぴったり合っているのは奇跡としか言いようがない。
「僕、ぎんなんって名乗ればいいの?」
「ぎんなんじゃないよ、いちょうだよ! 乃木坂の下のなまえはギンでしょ。だから色の銀をなまえに使ってみたの! ふふーん、われながらいいセンスっ」
なるほど。東条さんからもらった名前、大切にしよう。
「それならこれもつけましょう!」
ミツルさんが僕の首につけたのは、いちょうの葉の形のペンダントトップをあしらったチョーカー。秘書がこんなにおしゃれでいいのかと疑問に思ったが、トップアイドルの秘書ならこのくらいでないとむしろ不自然だと説明された。
その後、東条さんの提案で、この格好のまま色川社長にも顔を見せることになった。色川社長は僕が女装して東条さんのライブに付き添うことは知っているらしいので、今さら恥ずかしがることもない。
「失礼します」
社長室のドアを開けると、色川社長と目が合った。そのとたん、彼はやたら真剣な形相でデスクから身を乗り出した。
「き、君はっ……!」
「?」
「あ……ああ、乃木坂くんか」
何故かがっかりされてしまった。
「すみません、お邪魔でしたか?」
慌てて謝る僕に、色川社長は突然こう言った。
「なあ乃木坂くん。美少女は最高だと思わないかい?」
「はい?」
面食らう僕に構わず、色川社長は持論を展開し出した。
「人間の価値が容姿で決まるとは思わないが、やはり萌えの頂点には美少女だろう。人は本能的に美しいものを好み、守ろうとする。それは遺伝子レベルで美が求められているからではないかね」
色川社長は改めて僕を見て、一つ深いため息をつく。
「君のその姿が少しかぐやに似ていたものだから、ディーヴァを作っていた時のことを思い出してしまってね。いやあ、全くもって惜しい。君が女の子ならスカウトしたいところだよ」
「え……あ、すみません、男で」
「なに、気にしないでくれ」
額を抑えてうつむく社長。何と、彼はそのまま嗚咽を漏らし始めた。もう何が何だか。
まさか僕が女の子でないことを悲しんで泣いているわけではないだろう。きっとストレスがたまっているんだなと思って、僕は社長の背後に回って肩に手を置いた。
「お疲れでしょう。肩、叩いて差し上げますね」
それが例え僕の四倍以上生きている剛腕実業家であっても、泣いている人を放って立ち去ることはできない。昔親にしてあげたように、色川社長の凝り固まった肩を叩いていると、彼はいくらか落ち着いたようだった。
「実はね、ディーヴァがなかなか見つからないのだよ。私がDQN(ドキュン)ネームをつけたせいで、皆改名してしまったらしい」
「どきゅんねーむ? 何ですか、それ?」
「おや、もう死語なのかな。私も年を取ったものだ。簡単に言うと変な名前のことだよ。朱雅亜(しゅがー)とか、紫那紋(しなもん)とか」
うっ、それは確かに改名したくなる……。
「私にとっては、すべてのディーヴァが娘のようなものだ。三歳までしか接していなくとも、一人一人ちゃんと覚えている。他の子も雪菜のように虐げられていたらと思うと、ろくに眠ることもできなくてね。ああ、こんなことなら手放すのではなかった。本当だったら今頃私には、孫がいたっておかしくないのだが……みんな私から離れていく」
考えてみれば、色川社長は家族運のない人だ。真心込めて育て上げたかぐやさんと実の息子さんには駆け落ちされて、ディーヴァたちは消息不明。きっと東条さんも忙しくてあまり遊べないんだろうな。萌え業界の大物だから、敬遠されてしまって友達も少なそうだし……。
孤独な老人の影が、暖かな夕陽に照らし出される。
「私のしてきたことは、間違っていたのだろうか」
僕は手を止めて少し考えた。何が正しくて何が間違っているかなんて、軽々しく口にできるものではない。でも、これだけは言える。
「僕には世界平和以上の夢は思いつきませんね」
「……そうか」
僕は肩たたきを再開した。こんなことをしたって彼の大切な人々の代わりにはなれないけれど、少しでも社長の心の隙間を埋めることができたらと思って。
四月二十日。ついに建国記念ライブの日がやってきた。
前日から現地入りしていた僕たちは、縦浜オリハルコンホールで最後の調整を始める。
オリハルコンホールでは以前に何度もライブをしたことがあるので、館員さんたちは東条さんやミツルさんとは顔見知りだ。逆にニューフェイスの秘書(僕)は物珍しいらしく、手が空いていると頻繁に話しかけられた。
「ワンマンなくるたんに秘書さんがつく日が来るとは思わなかったな。名前何て言うの?」
「いちょうです」
「いちょうちゃんかぁ。よろしくね」
またある時は、若い男性に呼び止められた。
「君、かなり若いよね? いくつ?」
十五だなんて本当の年齢を言うわけにはいかない。一応秘書として働く社会人という設定なのだ。
「女の子に歳を聞いちゃだめですよ」
「あっはっは、こりゃ失礼。じゃあ代わりにスリーサイズ教えてよ」
「バスト74、ウエスト60、ヒップ……あ」
しまった、つい設定メモ通りに答えてしまった。相手はと言うと、冗談のつもりだったのに返事をされてしまって困惑している。当然だ、年は答えなくてスリーサイズは答えるなんて不自然すぎる。
「……っ、何言わせるんですかもう!」
演技にぼろが出ないうちに頭を冷やそうと、僕は空気を吸いに廊下に出た。そこで、テレビ局の人らしき集団に出くわした。
「あのー、くるたんの関係者の方ですか?」
「秘書です」
「舞台裏を取材させていただきたいのですが」
あらかじめ東条さんから言われていた通り、僕は丁重にお断りした。
「ああーっ、潜入失敗です!」
レポーターの残念そうな声が聞こえるけど気にしない気にしない。
開演十五分前になり、僕は東条さんから客席に行くように指示を受けた。
「二階の最前列のまんなかが乃木坂の席だよ。あとはシゴトのことなんか忘れて、ボクの歌を楽しんできて!」
今日の東条さんのドレスはいつもと違って短く、裾からふわふわのかぼちゃパンツが覗いている。もちろんミツルさんによるコーディネートである。彼女は月と星を合体させたような髪飾りの位置を整え、不敵な笑みと共に真っ暗な舞台を見据えた。
「さあ、しょーたいむの始まりだ」
客席に向かう途中で、僕は会ってはならない人に遭遇してしまった。
「うわー、トイレどこだよぉ、始まっちまうよぉ、トイレどこだよぉ」
池田くんがトイレを求めて廊下をうろうろしていた。正しい選択をするなら、ここは顔を隠して素通りするところなのだろうが、トイレを探す人を見捨てるなんて人でなしのやることだ。何より池田くんには恩がある。
「お手洗いはそこの角を左に曲がった階段の上ですよ」
できるだけ女の子っぽい声で、脇から教えてあげた。
「うおっ!?」
池田くんはびくっと振り返ったが、僕の顔はよく見ずに「あざーっす!」と叫んで左に曲がっていった。彼にとって緊迫した状況でよかった。女装しているとはいえ、さすがに顔をじっくり見られたらアウトだ。
僕の席の隣には、藤巻さんが座っていた。彼女は舞台セッティングには立ち合わず、直接こちらに来ていたのだ。
「おつかれさまです、いちょうさん」
うっかり本名で呼んだりしない辺りに、彼女の優秀さを感じる。僕だったらきっと一度は間違って、どもりながら言い直すと思う。
僕も藤巻さんも、東条さんの歌を生で聴くのは初めてだ。心地よいクッションに腰を降ろし、期待に胸を膨らませていると、やがて客電が落とされ、夢の舞台が幕を開けた。
てれってれってれー♪
てれってれってれー♪
前置きなしに曲が始まる。ホリゾント幕にだけ青が灯っていて、依然舞台は暗いままだ。だがこれは演出。前奏が激しくなるところで、一斉にライトがつく。
――どんっ!
伴奏の音と照明効果が相まって、僕たち観客の心を一気に躍動の舞台へと引き込む。
華やかな光に照らし出された東条さんは、可愛らしく振り付けをこなしながら、天使のロリ声で電波な一曲目を歌った。
おぼえたての九九を パパにおしえてあげました
パパはおとなのくせに とってもよろこびました
おとなはなんでも知ってるんでしょ
どうしてそんなによろこぶのかな
答えはきまっているよ
ボクがかわいいスターだから!
コースター ブースター ボクすたー☆
マイスター モンスター ボクすたー☆
世界でいちばん ボクすたー☆
事前に東条さんに教えてもらった話では、この歌は彼女のデビュー作で、当時八歳の東条さんがメロディーと歌詞を手掛けたものだ。その時、東条さんは自分のスター性をどの程度理解していたのだろうか。ただの小学二年生が書いていてもおかしくない詩の内容であるところに、逆に巧妙さを感じる。八歳と言う年齢だからこそ、自分をスターと称しても非難の対象にはならず、可愛らしさを強調できたのだ。
「不朽の名曲、『ボクすたー☆』でしたーっ! きょうはみんな、来てくれてありがとー! それからテレビの前のみんなも、見てくれてありがとー! こんなにたくさんの人がボクのこと応援してくれてるんだね。ボクはりきっちゃうよ! みーん」
「萌えー」
観客一同、早くも東条さんのMPに当てられている。MPが効かない僕も、歌を聴いてますます東条さんに惹かれた。彼女はMPなんかなくたって最高のアイドルに違いない。
数曲元気な歌を歌って客のテンションを上げたところで、東条さんはぽんと異色な歌を投入した。
「続いてっ、涙腺崩壊アニメ『ラビットデイズ』のエンディングテーマ、『ひとりぼっちの僕らは』を歌いまーす! しんみりした曲だから、みんなも静かに聴いてね」
「おお……」
この歌は人気が高いようで、客の反応が一味違った。
前奏が始まり、辺りが清らかな空気に包まれる。萌えに徹した今までの曲目とは違い、この曲はシリアスで繊細な哀しみをはらんでいる。東条さんのロリ声でこの曲風に合うのか? 数秒後に僕は、一度でも彼女の歌唱力を疑ったことを恥じることになる。
僕の羽根は氷でできていた
凍てつく空を飛んでいたら
いつの間にか大きくなりすぎて
歩けなくなっていた
ひとりぼっちの僕らは出会い
氷の羽根を溶かして
飛ばなくても 歩けばいいと
手を取って歩み始めた
いつか僕らは別れ告げるけれど
今はそばにいて
愛しい日々が過去になっても
ぬくもり思い出せるように
これが六歳児の声帯から出る声とはにわかには信じられない。電波ソングを歌う時のような蛍光色の声色ではなく、水彩絵の具を水に溶かしたような柔らかい歌声だ。声質そのものは幼いままなのに、神聖な威厳さえ感じられる。歌い方一つでこうも変わるなんて。
僕は天才を目の当たりにしていた。
やがて僕らは別れ告げるけれど
今はそばにいて
優しい日々が過去になっても
歩き続けていけるように
いつか世界は終わり告げるけれど
今は泣かないで
孤独な日々が僕らをつなげて
新たな世界を紡ぎだす
最後のサビのリフレインには涙が止まらなくなった。胸を締めつける切なさの正体が「救い」であるような気がして。東条さんの歌声が、僕の魂に宿る一切の哀しみを抱擁し、泣かないでと鎮めてくれるような、そんな安らぎを覚えた。
歌が終わった時に聞こえたのは、拍手ではなく、涙交じりの「ありがとう」だった。
――ああ、感動するってこういうことを言うんだ。
その後はほとんど明るい曲で、たまにバラード調の歌も交えながらライブは進んでいった。そしてついに、最後の曲の番が来た。
「いよいよ、さいごの曲になってしまいました。今から歌うのは、神聖アキバ帝国の国歌『パックス・アキバーナ』です! ではではっ、ミュージックスタート!」
争い絶えぬ大地に
萌えいずる愛の新芽
泣いてる子も 泣かせた子も
いたいのいたいの飛んでけ
みんなで平和になろうよ
願えば 望めば きっと叶うから
パックス・アキバーナ
全てが萌えに包まれたなら
パックス・アキバーナ
みんな笑顔でいられるよね
萌えは世界を救う
聴衆の歓声がこだまする。
「アンコール! アンコール!」
彼女はまさにスター。世界を彩る星だった。