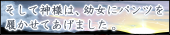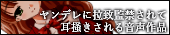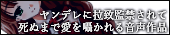第三章 のぞみ
気がついたら、僕は床に転がっていた。
頭が朦朧として、慢性的な息苦しさを感じる。意識はあるのに感覚がない。まるで身体と精神を引きはがされてしまったようだ。
あの男の人は?
もしかして、抵抗の甲斐あって肩から落ちることに成功したのだろうか。なら早く立ち上がらなくては――とそこまで考えて、僕はいつの間にか気を失っていたのだと気づいた。この虚脱感はその後遺症なのだろう。ひどく眠い時の気分に似ている。
ぼんやりとした中で初めに伝わってきた感覚は、体温を奪う石床の冷たさだった。次に、手足を縛られていることを知る。手首の鬱血に苛立ちながら首をもたげると、鉄格子の窓の向こうに紫がかった夕焼けが見えた。どうやら意識がなかったのは一時間程度のようだ。その間にこの見知らぬ薄暗い部屋に放り込まれたということらしい。移動時間もあるから、ここに来てからそれほど時間は経っていないと思う。
つい昨日まで普通の高校生として生きてきた僕は、まさか自分がこのようなアニメ的ピンチに見舞われるなんて考えてもみなかった。予習もイメトレもしていないから、ここがどういった類の部屋なのかも分からない。さしずめ監禁室といったところか。起き上がる気力もないので顔だけ反対方向に向けると、得体の知れない拷問器具がずらりと並んでいた。うん、予想以上だ。
冷静になって情報を整理しよう。スタジオピンクに襲来した人たちの言葉から考えると、東条さんを狙っている団体の名前はおそらくノクターン。こんな手荒なことをするのだから、少なくとも非合法組織には違いない。その組織に、僕は今監禁されている。
ノクターンは、僕が東条さんの行方を知らないことを承知した上で僕を連れてきた。とすると、目的は何だ? あのOp.4と名乗った人は、僕を「萌えない中学生」と呼んだ。MPが効かないことが論点となるのだろうか。でも、拳銃の女の子にもMPは効いていなかった。もしかしたら、そういう人は僕以外にも結構いるのかも知れない。それならわざわざ僕を連れてきたのは何故? とりとめもない考察を続けていると、僕が東条さんにとって特別ではなくなってしまうのは嫌だ、なんて、場違いなわがままが脳裏をよぎった。
東条さん、無事だといいなあ……。
冷えた空気が身に染みる。スタジオピンクの衣装部屋で、ブレザーを鞄に入れてしまったことを激しく後悔した。思わず呟く。
「寒い」
その声は自分でもびっくりするほど幼弱だった。声変わりがまだなので、小学生がダダをこねているようにも聞こえる。しかしここには、生徒のためにストーブを点けてくれる先生も、一緒に震えてくれる級友もいない。そのはずだった。
「寒いですね」
透き通るような綺麗な声に、不安と期待を同時に抱く。声は足の方から聞こえた。転がったままでは声の主が見えないため、ひじを使って上半身を起こす。
灰色の石の壁を背に、黒い服を着た少女がへたり込んでいた。その両手首は頭の上で鎖につながれている。目が合うと、少女は優しい顔で僕に薄く微笑みかけた。
Op.1さんがそこにいた。
「えっ、あっ」
「安心してください。私はこの通り、あなたに危害を加えられる状態ではありませんし、そのような意思もありませんから」
確かに、今ここにいる彼女は全く無害であるように見える。見た目は儚げな美少女だから、拳銃さえ持っていなければ怖くはない。運動神経はものすごくいいのだろうけど、今は何故だか拘束されている。
「どうしてあなたがこんなところにいるんですか?」
「お仕置きですよ」
つらい体勢のはずなのに、少女は何でもないかのように笑ってみせた。
「東条胡桃を捕獲できなかったことに対するお仕置きと、着物の女性に勝てなかったことに対するお仕置き。私はお母様に嫌われているからよくお仕置きされるけれど、こんなにも真っ当な理由でこの部屋に入れられたのは久しぶりです」
話を聞きながら、僕はほっとしていた。よかった、東条さんは無事に逃げられたんだ。もしまた高野さんに会うことがあったら、うんとお礼を言わなくちゃ。僕は捕まってしまったが、東条さんを逃がすことができたのは、ひとえに彼女がOp.1さんを足止めしてくれたおかげなのだ。
「あの……捕まってる身分で申し訳ないのですが、いくつか質問しても構いませんか?」
意外にも、Op.1さんは嫌な顔一つしないで快諾してくれた。
「あなたを襲った張本人がこんなことを言うのもおこがましいですが、まだ歳若いあなたを巻き込んでしまったことを、私は心苦しく思っています。できる限りお答えしますよ」
この人いい人だ。僕は感謝しながら、最初に一番気になっていたことを尋ねた。
「僕はどうして連れてこられたんでしょうか。きっと何の役にも立たないと思うんですけど……」
「もうお分かりではないのですか? あなたが特別な人材だからです」
「特別?」
「東条胡桃に萌えない人間なんて、滅多にいるものではありません。私とOp.4は、東条胡桃に萌えないことを買われて今回の東条胡桃捕獲ミッションに抜擢されました。私は生まれつきなのですが、Op.4については、事故で頭部に損傷を負って以来、愛や萌えという感情を失ってしまったそうです。てっきり、東条胡桃に萌えないのは私たち二人だけだと思っていましたが……。お母様は、カラープロダクションがあなたに萌えない技術を施しているのだと考えて、Op.4にあなたを連れてくるよう指示したのです」
『お母様』というのは、通信機の先にいた人物のことなのだろう。つまり、彼女たち凄腕のエージェントに命令できるほどの地位を持ち、僕をここに連れてくるように指示した人物ということだ。
「残念だけど、僕も生まれつきですよ」
「そうですか。でも、あなたが特別なのはそれだけではありません。ルネサンスが効かなかったのは、あなたが初めてなんです」
「ルネサンス?」
そう言えば、東条さんの部屋でもそんなことを言っていた。薬品か何かの名前だろうか。疑問に思っていると、Op.1さんは少しためらいながら説明してくれた。
「信じていただけないかも知れませんが、私、物体の時間を巻き戻すことができるんです。再生(ルネサンス)というのはノクターンがその力につけた名称で――」
ふいにOp.1さんは話を止めて、戸惑うような、ほっとしたような顔で僕を見た。
「あの、驚かないんですか?」
意外だった。裏社会で働いていると言っても、やっぱり変な目で見られるのは嫌なのだろうか。その辺りは普通の女の子と変わりないのかも知れない。僕は彼女を等身大の話し相手のように感じて、こわばっていた表情を緩めた。
「昨日からびっくりすることばかり起こって、何だか慣れちゃいました。ルネサンスもそうですけど、着物の人が壁を通り抜けてきたりとか」
「あれはカラプロの技術ではないのですか?」
「違います。……たぶん」
我ながら曖昧な回答だ。東条さんは知らないと言っていたが、色川社長が秘密裏に超能力開発をしていた可能性を考えると、はっきりとした答えは出なかった。
「だから僕は何も知らないし、あなたたちに何か要求されてもきっと応えられないし、そしたら僕は……」
用済みだ、とか言われて殺されちゃう?
僕が一番恐れていたことを察して、Op.1さんは安心させるように微笑んだ。
「大丈夫ですよ。ノクターンは東条胡桃の萌えの原理と、萌えに抵抗する方法を探っています。あなたは重要な資料なんです。だから乱暴に扱ったりはしません。安心してください」
安堵が体中に広がっていくのが分かった。しばらくは命の安全は保証してもらえるらしい。一つ懸案事項が減ったので、僕はもう一つ気になっていたことを尋ねた。
「あの、『ノクターン』が何なのか教えてほしいんですけど」
Op.1さんは何故か怪訝そうな顔をする。
「あんなに東条胡桃の近くにいて、知らないということはないでしょう?」
「あれっ? 知ってて当然のことなんですか? やだな、僕世間知らずだから……」
自分の無知を恥じてごまかし笑いをすると、Op.1さんはますます浮かない顔をした。どうしたのだろうか。
「ノクターンは裏社会の軸とも言える組織です。裏社会は世界中の経済情勢を支配する場であり、大企業とは切っても切れない縁にあります。カラープロダクションだって例外ではありません。ノクターンと協力していた時期もありましたが、かつて先代Op.1に組織から抜け出す資金を与えたことが判明してからは、対立関係にあります」
「へぇ。僕の知らないところで、世界って動いてるんですね」
何だか感心してしまった。しかし能天気な僕とは反対に、Op.1さんは悲しそうに目を伏せる。
「何も知らない方を巻き込んでしまうなんて……」
「あ……」
やっと彼女が落ち込んでいた理由が分かった。彼女は東条さんの近くにいた僕を裏社会の人間だと判断し、『お母様』に報告した。きっと東条さんは、すでに裏社会でも影響力を持っているのだろう。だが僕は一般人同然の素人だった。Op.1さんは日ごろから、せめて一般人だけは危険に晒さないように立ち回っていたのではないだろうか。他のノクターンの人、例えばOp.4さんがそんな配慮をするかと言われれば疑問だけど、彼女だったらむしろその方が自然な気がした。
「僕だって、東条さんの下僕になった瞬間から裏社会の人間になったんです。気にする必要なんてありません。覚悟してなかった僕が悪いんです」
「……」
フォローしたつもりだったが、気まずい沈黙が流れる。どうしよう。そうだ、また何か質問すればいいんだ。
「えっと、あなたのお名前は?」
これしかネタがなかったんだ。
「Op.1とお呼びください」
「いえ、本名の方です」
せっかくだからちゃんと訊いておこうと思ったのだが、彼女は何故か困ったように首をかしげた。背中の中ほどまであるストレートの髪が、腕の後ろで揺れる。
「本名、ですか。長いことOp.1――作品番号一番と呼ばれてきましたから、それを名前と認識していました。本名は分からないんです。あえて申し上げるなら、藤巻雪菜(ふじまきゆきな)。これもお母様からいただいた仮の名ですが、Op.1よりは人間らしいでしょう?」
自分の本名も分からないなんて、裏社会は大変なんだなあ。
「じゃあ、藤巻さんって呼んでいいですか?」
彼女は不思議な言葉を聞いたかのようにきょとんとしたが、やがて柔らかな笑みを浮かべた。
「いいですよ」
そこで僕は調子に乗って、また同系統の質問をしてみた。
「藤巻さんはおいくつですか?」
「十五歳です。今年で十六歳になります」
「あ、僕と同い年ですね」
「はい?」
しまった。ノクターンの中では僕は中学生ということで通っているのだった。
慌てて言い直そうとしたら、勢いで体が動いて、脚の傷が床と擦れる。痺れるような痛みに顔をしかめたが、すぐに気づいた。こんなところを見せたら、藤巻さんが気に病んでしまう。案の定、彼女は心配そうに僕を見ている。
「傷――」
「だ、大丈夫ですっ」
無理に取り繕った爽やかな笑顔は、藤巻さんの罪悪感を助長させただけだった。
「あなたを撃つ時に使った弾丸にはルネサンスの力を纏わせてあったので、本来ならあなたの傷はすぐに治るはずだったのですが……ごめんなさい」
本当に申し訳なさそうな顔で謝られてしまった。どうしてこんなに心優しい人が裏社会でエージェントなんてやってるんだろう。絶対向いていないのに。
「敵の傷まで治そうとするなんて、立派じゃないですか。そんな顔しないでください」
「裏の仕事を担う私がそのような配慮をしたところで、偽善でしかありませんよ。分かってるんです。私はルネサンスに甘えているだけなんだって」
事情は知らないが、裏の仕事が嫌でもノクターンを抜けることは許されないのだろう。ミスをしただけで監禁されるのだから、組織を抜けようとすれば殺されてしまうのかも知れない。極論を言えば、本当に何も傷つけたくないなら殺されてしまえばいい。それなのにのうのうと生きて裏の仕事を続ける自分の行動を、藤巻さんは偽善と呼ぶのだ。それを「偽善じゃない」と言ったところで、何の慰めにもならないのは分かっていた。だから、代わりに別のことで彼女を元気づけようと思った。
「藤巻さんがいてくれてよかったです。一人だったら、心細くて泣いてました」
彼女は、作り笑いかも知れないけど、それでも悲しそうな顔をやめて笑ってくれた。
「私も、あなたとお話しできて嬉しいです。いつもは一人ぼっちですから」
場の空気が和んだその時、扉の向こうから二人分の足音が聞えてきた。硬い靴底と冷たい石床の質感がリアルに想像できて、鳥肌が立つ。藤巻さんが張りつめた表情で呟いた。
「お母様と……朝比奈さん?」
「とりあえず僕、寝たふりしてますっ」
僕はとっさにいもむし状態に戻った。いつまで寝てるんだと怒られる可能性もあるけど、怖い人といきなり対面したら心臓が止まりそうだ。藤巻さんと何らかの会話をするだろうから、それを聞くことを準備運動としよう。
足音が止んだ。鉄製のドアが開く音がした。鉄製のドアが閉まる音がした。足音が近づいてきた。……怖い!
「くるたんを逃しておめおめと帰ってくるなんて、いいご身分だねぇ」
声質からして、中年の女性のようだ。高慢で冷徹な印象を受ける。
「申し訳ありません。ですが、帰還命令を出したのはお母様です」
「はん。あのまま戦っていたらお前は負けていただろう? それを考慮してやったんじゃないか。文句あるかい」
「……いえ」
「ほんと、見てるだけでイライラするよ」
鎖がこすれる音と藤巻さんの呻き声が聞こえたので、心配になって薄目を開けた。
黒いスーツを着た女の人が、藤巻さんの髪を一房つかんで頭を持ち上げている。藤巻さんは唇を引き結んで耐えていた。それともう一人、その様子を生温かい笑みを浮かべて傍観している五十代の男性。彼の方は穏やかな気性のように見えるのだが……。
「まあ、あたしはお前がどうなろうと構わないんだけどね。貴重な作品(オーパス)を減らしたとあっちゃあ、ここまで築き上げてきた信頼がパアになるからさ」
藤巻さんは黙って下を見ている。髪に隠れて、表情はうかがえない。
「あーあ、こんな役立たずじゃなくて、くるたんがいたらねえ」
女の人が藤巻さんの頭を壁に打ちつけて手を離した。鎖の音と、壁と後頭部がぶつかる鈍い音が響く。ひどい。これはお仕置きじゃない、虐待だ。
「ああ、そうそう。朝比奈さん、こいつがくるたんに萌えないガキだよ」
目をつぶったのは結構ギリギリのタイミングだった。見つからなかったのは奇跡に近い。
朝比奈と呼ばれた男性は僕の方にやってきて、顔を覗き込んだ。
「寝てますね。つまらないな」
それで満足して帰ってくれればよかったのに、彼はまだ僕の顔をじろじろ見ている。うう、今起きてるってばれたら気まずすぎる。
「何だかこの顔、気に食いませんね。正式にイノセンスを設立したらこき使ってあげましょう」
こき使う? イノセンス?
「朝比奈さん、その人をどうするおつもりなんですか?」
僕と同じ疑問を持ったのか、藤巻さんが訊いた。すると、朝比奈さんはよくぞ聞いてくれたとばかりにべらべらと喋り出した。穏やかな雰囲気が一変し、やや子供っぽい情熱家という本性があらわになる。
「ぼくの今回のミッションにおいての一番の目的は、東条胡桃の芸能活動を止めることだったんですよ。人が自分の望みを素直に叶えようとする世界こそ、ぼくの理想です。望みが対立するなら、強者が弱者を組み敷けばいい。倫理なんかにとらわれず、望みの強さだけ強くなればいい、そんな世界を創りたい。そのためには東条胡桃の平和活動を止めなくてはならないんです。今日東条胡桃を捕獲できたら、芸能活動も止められたし、ノクターンの方で萌えの力を利用することもできたんですけどね。もう向こうも拠点を移動してしまったでしょうから、彼女をノクターンの手中に収めるチャンスはありません。そこでぼくは、個人的にイノセンスというアンチ東条団体を設立することにしました。ノクターンと協力して東条胡桃の萌えに対抗する方法を探りつつ、もっとアグレッシブに東条胡桃を辞めさせる行動を起こすつもりです。その子には、弱者としてぼくの望みにつきあっていただきますよ。身体調査もしますが、それ以上に、萌えずに東条胡桃に近づける彼はイノセンスにふさわしい人材ですからね!」
溢れんばかりの情熱――むしろ狂気とも言える気迫が伝わってきた。慣れていない僕や藤巻さんは圧倒されたが、女の人は何度もその話を聞かされていたようで、うんざりした様子で彼に告げる。
「夢を語るのもいいけど、そろそろOp.1のお仕置き始めたいんだ。さすがに朝比奈さんに見られるのはあれだから、出ていってもらえないかい?」
「おっと、これは失礼」
朝比奈さんは頭を下げて退出しようとした。その際に、諦めの入った表情でお仕置きを待つ藤巻さんと目が合う。彼はふっと表情を崩した。もしかして慰めてあげるつもりなのだろうか。
しかし、その口から出てきた言葉は残酷なものだった。
「ああ、君のことを助けようとは思いませんよ、Op.1。君は望みを持とうとしないでしょう? 逆らいたければ逆らえるだけの力があるのに、角谷さんの言いなりになって仕事をこなすだけ。ぼくは、そういう人間が一番嫌いなんですよ」
藤巻さんは黙りこくってしまって、何も答えない。
朝比奈さんは皮肉な笑みを浮かべた。
「では、せいぜい角谷さんの望みを受け止めてあげてください」
角谷というのは『お母様』の名前なのだろう。朝比奈さんが部屋を去ると、角谷さんは拷問器具の山の中からナイフを持ち出してきた。もっと恐ろしげな器具があるのにあえてそれを選んだのは、より直接的な感触を得たかったからだろうか。
「さあて、お楽しみといきましょうか。くるたんを手に入れられなかった恨み、きっちり晴らさせてもらうからね」
含みのある笑みを浮かべると、彼女はいきなり藤巻さんの喉元にナイフを突き立てた!
「っ――!」
藤巻さんは目を見開いてびくびくと震えている。白い首からは噴水のように血が溢れて、彼女の胸を濡らしていった。しかしそれも束の間。血の勢いは収まり、藤巻さんは動かなくなる。
……死んだ?
「あっはっは、母殺しの気分は最高だ」
角谷さんは意味不明なことを言いながらナイフを抜き取った。すると、輝く光が藤巻さんの上半身を包み込んだ。――これがルネサンスの力。ちょうど東条さんの部屋の窓が直った時と同じように、藤巻さんの首が元通りになる。あんなに広がっていた血液も、跡形もなく消えていた。
「どう? しょっぱなから殺されるとは思わなかったでしょ」
角谷さんは何でもないかのように軽口を叩いている。本当に楽しそうにしているものだから、腹の底から怒りが湧いてくる。何も出来ない自分がどうしようもなくもどかしい。
藤巻さんは荒く息をつきながら角谷さんを見上げた。
「どうしてお母様はそんなに東条胡桃にこだわるのですか? お母様の彼女に対する執着は、組織のためと言うよりご自身のためのように思えます。昔からそうです。くるたん、くるたんと、うわごとのように繰り返して……」
角谷さんは自分の短髪をいじりながらいい加減に聞いていたが、ふと真顔に戻って呟いた。
「いつかは言おうと思ってた。今がその時なのかもね」
深く息を吐いて、彼女は言った。
「お前は作られた人間だ」
藤巻さんは返す言葉もなく角谷さんを見つめた。
「お前はくるたんだったかも知れないバイオロイドだ。まあ失敗作だけどね」
「どういう……ことですか」
「くるたんは、カラープロダクションが世界征服のために生み出した人工生命体なのさ。詳しくは分からないけどね、美人さんのクローンを元に作ったってことだけは知ってる。カラプロの連中が美女の細胞を求めてあたしを訪ねてきたんだ。あなたのお母さんの細胞を使わせて下さいって。若い頃の母さんは美人で有名だったからね。大金と引き換えに、あたしは寝たきりの母の細胞を売った。そして、その細胞からお前が生まれたのさ」
つまり、藤巻さんは東条さんと同世代のディーヴァなのか。ならもしかして、ルネサンスはMPの仲間? 超能力は偶発的なものではない? しかし今はそんなことよりも、カラプロによって人工的に生み出されたディーヴァが、こんな仕打ちを受けて生きていることがショックでならなかった。
「あたしが母さんと不仲だったことは知ってるね」
「はい。私を見ると昔を思いだして腹が立つと、よくおっしゃっていましたから」
「そのあたしが、どうして母さんのクローニングを許可したか。それはね」
角谷さんは一度言葉を切った。その先を言ってしまうことに、ためらいがあるようだった。藤巻さんの姿が母親と重なって見えたのかも知れない。
「あたしは、母さんを好きになりたかったんだよ」
彼女は、母親に言えなかったことを、母親の分身に告げた。
「バイオロイドには人を強制的に萌えさせる力が芽生えるって話だった。あたしはまだ若くて、夢を見てたんだねきっと。あたしを憎んだ母さんを好きにはなれなくても、リセットされた母さんなら、それも萌え萌えな母さんなら、二人仲良くやり直せるんじゃないかって、今考えたら馬鹿な期待をしてたんだ。本当に馬鹿だった」
MPの力がなければ母親を愛せないほど、この人は母親を嫌いになってしまったんだ。好きになりたいのに好きになれない辛さは分からないでもないけど、だからと言って。
「結局お前は出来損ないで、ただ母さんに似ているだけの目障りなガキになった。お前が六歳の時だったかな、お前をこうやって刺し殺そうとしたのは」
だからと言って、藤巻さんを虐待していい理由にはならない。
「その時、ルネサンスが発動したんだ。いやらしい生への執着だよ。さっさと死んでしまえばいいのに生き返るもんだから、あたしゃ思いついちまったんだ。こいつなら最強のエージェントになれるって」
「それで私をノクターンに……」
「お前はあたしを失望させた罪を償わなくちゃいけないんだよ。あたしにとって、くるたんは憧れなんだ。あんな可愛い子を、母として、娘として、愛していきたかった。その夢を台無しにしたお前を、あたしは許さない!」
角谷さんはナイフで藤巻さんの胸や腹を滅多刺しにし始めた。狂ってる。どうしてそんな虚しいことをするの? 他に道はあるはずなのに。
「もうやめてください!」
僕は思わず顔を上げて叫んでいた。だが後悔はしなかった。何か言ってやらないと気が済まない。意志表示の弱いクタオな自分を変えようって、誓ったばかりなのだから。
角谷さんは手を止めて僕に歩み寄った。その間に、藤巻さんの身体はルネサンスで癒えていく。引き裂かれた服も再生していた。
「お前、起きてたんだね。狸寝入りとはいい度胸してるじゃないか。名前は?」
ここで本名を答えたら終わりな気がする。とっさに思いついた名前を言った。
「池田……池田綿三です」
ごめん池田くん。
「メンゾウだって? まあ、偽名ならもっと普通な名前言うだろうけどさ、変な名前だね」
「僕の名前なんてどうでもいい。藤巻さんをいじめるのはやめてください! 東条さんみたいな力がないとか、お母さんのクローンだとか、そんなのは藤巻さんの責任じゃないじゃないですか!」
殴られてもいいと思った。覚悟もできていた。しかし、意外にも角谷さんは怒らなかった。代わりに、どこかしょげたような、不服を帯びた顔をした。まるで不当な理由で親に叱られた子供のように。
「逆恨みなのは承知の上さ。それでもあたしはこいつを憎み抜く。愛せないなら徹底的に憎むしかないんだ。中間は、無理だよ……。いいじゃないか、どうせ怪我はすぐ治るんだし」
「身体の傷は治っても、心の傷は残ります」
「何も知らないくせに、道徳の教科書の受け売りみたいなこと言うんじゃないよ」
僕の言っていることは綺麗事だ。それは自覚している。対人関係は理屈でどうにかなるものではない。でも、僕は東条さんの下僕。『誰一人犠牲にしない、世界で一番平和な世界征服』の第一歩として、まずは綺麗事を貫く努力を払う!
とは言え、もともと臆病な僕は、早くも角谷さんの冷たい目に負けそうになっている。この震えは寒さのせいだけではない。手に嫌な汗をかいて背中の後ろですり合わせていた時、今まで黙っていた藤巻さんが静かに言葉を紡いだ。
「お母様は、それだけ由紀子さんを想っているのですね」
角谷さんはものすごい形相で彼女を睥睨すると、容赦なくナイフを胸に突き刺した。藤巻さんはぐったりとしたが、すぐに傷は消え、行き場を失ったナイフが音を立てて床に落ちる。上げられた藤巻さんの顔を見て、角谷さんは声を荒げた。
「そんな綺麗な表情(かお)するんじゃないよ! お前もあたしを憎んでいるくせに!」
藤巻さんは聖女のような微笑みを湛えて首を横に振った。
「いいえ、私はお母様を愛しています。例え何をされても、あなたは私のお母様だから。子供とはそういう生き物です。――お母様も、そうでしょう?」
角谷さんは一瞬だけはっとした様子を見せた。目を剥いて何か言いたげに口を開いたが、拳を握りしめ、そのまま踵を返して歩き出す。彼女の中で何かが起きたのは確かだった。扉の前で立ち止まり、ぽつりと一言。
「……手洗いに行ってくる」
その声は心なしか喉に詰まったような響きだった。
角谷さんが去り、足音が完全に聞こえなくなると、藤巻さんは僕を見た。
「池田さん、私に力を貸して下さいませんか?」
その目には決意に満ちた強さが宿っている。この部屋で出会ってから、優しくしてくれたり虐待されたりしているところばかり見てきたけど、この人は本来強いのだということを実感した。
「どうするんですか?」
「ここから脱出します」
そう言うと、藤巻さんは平然と鎖を引きちぎって立ち上がった。……えっ!?
「びっくりしましたよね。ここまでの筋力があるとはお母様も知りません。何故だか生まれつき怪力なんです。わ、笑わないでくださいね」
少し恥ずかしそうに横を向く藤巻さん。笑いはしないけれど、腰を抜かしそうだ。
藤巻さんは襟のファスナーを下げて、首の付け根を露わにした。そこには金属でできた首輪が付いていた。
「これは爆弾です」
「爆弾!?」
「組織を裏切ったことが判明したら、頭部を爆破されます。いくら私でも、脳をこっぱみじんにされてまでルネサンスを発動できる自信がありません。そこであなたの力をお借りしたいのです。あなたには多大な負担をおかけするかも知れませんが、成功の暁には、必ず無事に虹間までお送りします」
答えは決まっている。彼女を救いたい気持ちはずっとあったのだ。
「僕にできることなら、お手伝いします」
「ありがとうございます」
藤巻さんは、角谷さんが置いていったナイフで僕の手足を縛る縄を切りながら、作戦の説明をした。
「池田さんにはまず、私の首をレーザーカッターで切っていただきたいんです」
「え? 何ですか、もう一度お願いします」
「私の首をレーザーカッターで切り離してください」
「……えええぇぇっ!?」
僕の耳壊れたっぽい。
「首が再生する前に爆弾を取り外してくだされば、晴れて私は自由の身です。そしたらあの窓から脱出しましょう」
「そんなっ、首なんて切っちゃって、藤巻さんは大丈夫なんですか?」
「怪我をした時に発動するルネサンスは本能的なものです。意識がなくなってもちゃんと治りますよ。ほら、お母様に首を刺されても生き返ったでしょう? 安心してください」
手足が自由になっても立ち上がろうとしない僕へ、彼女は気遣うように手を差し伸べた。
「私みたいに血にまみれるのは、嫌ですよね。それは分かってるんです。でも、こればかりは協力していただかないと、あなたを助けられません」
人の首を切る。
僕がこの手で。
……怖い。
でも迷っている暇はない。早くしないと角谷さんが帰ってきてしまう。
「僕、やります。やるならパパっとやりましょう!」
「ありがとうございます。本当に、ありがとうございます」
藤巻さんは数ある拷問器具シリーズの中から、刃のない剣の柄のようなものを持ってきた。これがレーザーカッターか。
「このスイッチを押すとレーザーが発射されます。かなり小型に改良されていますが、威力は世界一の製品です。光が当たったところは焼き切れてしまいますから、扱いには注意してください」
簡潔な説明を終えると、藤巻さんは横になって襟を開いた。胸の谷間が少し覗いているが、今の僕たちにはなりふりを構っている時間なんてない。
スイッチに指を添え、照準を定める。
「痛いのは嫌ですから、一気にお願いしますね」
「っううううっ――」
叫びたい衝動を押さえ込み、震える手でレーザーを発射した。目をつぶってしまいたいのは山々だが、軌道が外れて頭を切ってしまったら大変だ。血を噴いて切れていく首を見ながらの作業はつらかった。極度の緊張のせいで、感情以前に自然とぽろぽろ涙が出てくる。
それは長い時間のように感じられたが、実際にはほんの数秒のことだった。頭部が切断された首から急いで爆弾をはずす。爆弾をはずすことに必死だったので、切断面がどうとか、そういったことは不思議と目に入らなかった。
爆弾をはずした直後、藤巻さんの首がつながった。僕の身体にべっとりとついていた血も瞬時に消える。彼女はぼんやりと首筋に手を這わせ、そこに金属の輪がないことを確認すると、感嘆のため息を漏らした。
「成功ですよ!」
喜ぶ藤巻さんの傍らで、僕は茫然とへたり込んでいた。目からは止めどなく涙がこぼれ続けている。そんな僕を見て、藤巻さんはふわりと僕を抱きしめた。
「ごめんなさい。無垢なあなたを血に染めてしまって、ごめんなさい。怖かったですよね。でももう大丈夫。池田さん、安心してください」
戦いとは無縁な甘い香りがした。そして、柔らかな胸の膨らみに、何となくお母さんを思い出した。まあ、お母さんよりも大きい気がするけど……。僕のことを中学生だと思っているから気にしていないんだと思うと、急に申し訳ない気持ちになってきた。
「あのっ、僕、本当は池田綿三じゃないんです。乃木坂吟って言います。それで、その……高校一年生です……すみません……」
藤巻さんのきょとんとした顔に、さっと赤みが差す。彼女は慌てて僕から離れた。
「しっ、失礼しました!」
「僕こそ、今まで黙っててごめんなさい。それに、僕は怖くて泣いてたんじゃないですよ。藤巻さんが無事に治って、ほっとして涙が出たんです。だから気にしないでください」
「ほっとして……」
彼女はその言葉に何らかの感慨を感じたようだった。胸に手を当て、優雅に笑いかける。
「ありがとうございます」
何に対して言われたお礼なのかはよく分からなかったが、彼女が喜んでくれたならそれでいい。
それから藤巻さんが立ち上がり、僕も倣って立ち上がった。初めて彼女と並んでみると、ほとんど目線の高さに差を感じない。僕たちは同じくらいの身長らしい。
ふいに、藤巻さんが小さく「あ」と声を漏らした。
「どうしました?」
「同い年なら、ため口で構いませんよ」
「分かりまし……分かった」
僕の言葉に満足したように頷くと、彼女は鉄格子をぐいっと曲げて、大きな隙間を作る。鮮やかな力技にちょっと感動した。
「さあ、脱出しましょう」
藤巻さんの口調は、これがデフォルトらしい。
僕は彼女にうながされて窓枠によじ登り、隙間から外に出た。身体が小さくてよかったと思える貴重な瞬間だ。藤巻さんが出てこようとした時、角谷さんが部屋に戻ってきた。
「お前たち!」
「……さようなら、お母様」
藤巻さんは勢いよく窓から飛び降りた。部屋の中から女の人の怒号が聞こえたが、無視して一緒に走り出す。
「ここは次成(つぐなり)県のもくば駅付近。もくばエクスプレスに乗れば、虹間駅まで三十五分です」
「僕、ポケットの中に財布持ってるよ。たぶん二人分のお金はあると思う」
「決まりですね」
駅付近なら追っ手も目立ったことは出来まい。希望が見えてきた僕たちの前に、黒いジャージを着た男の人が立ちふさがった。
「Op.4……」
「よう、Op.1」
片手をポケットに突っ込んで、もう片方の手をフランクに振っているOp.4さんからは、全く敵意を感じない。普通に街中で知り合いと会ったという感じだ。
「私はあなたとは戦いたくありません。そこをどいてください」
「あー、それ同感! 俺もねーちゃんとは戦いたくねえや。戦ったって勝ち目ないし。でも命令なんだよねー。言われたとおりにしないと俺が怒られちまう」
全く緊張感のないヘラヘラした態度からは思考が推し量れない。いきなり撃ってくるかも知れないよと藤巻さんに注意しようとしたら、それより先に銃が飛んできた! ……え、弾じゃなくて、銃?
「やばい、おーぱすわんにじゅうとられちまった」
演技じみた声で、彼はそう叫んだ。続いて、耳につけた小型通信機を地面に叩きつけ、また白々しく声を上げる。
「うわーやめてくれー、やっぱりおれじゃかてなかったよ」
そして通信機を踏みつぶした。彼が足を上げると、そこにはジャンクになった通信機があった。
「これでよし。俺はOp.1に負けました、と」
「ふふっ、あなたらしいですね」
藤巻さんは楽しそうに微笑んでいる。始めからこうなることが分かっていたかのようだ。
「お別れの前にさ、少し俺の話聞いてよ」
「何ですか?」
「俺さ、Op.1のこと、ずっとうらやましいと思って見てたんだ」
依然としてヘラヘラしたまま彼は語り始める。
「俺は誰にも萌えないし、人を殺しても悲しくない。俺って自由人に見えるけど、感情の範囲が狭いんだよな。だいたいヘラヘラしてる感じ。それに比べたらねーちゃんは、命令には従順だったけど、喜んだり悲しんだり表情は豊かじゃん? 他のオーパスがギスギスしてる中で、ねーちゃんだけは何かが違った。お前には、ノクターンなんかじゃなくてもっとふさわしい居場所を見つけてほしいって、何となく思ってたんだよね。だから今日は俺にとってもいい日なんだ。これで話は終わり。あ、その銃はやるよ。俺からのはなむけだ」
藤巻さんは夜色の拳銃をじっと見つめてから、腰の金具に固定して上着で隠した。それから彼女は、真剣なまなざしでOp.4さんを見上げた。
「Op.4、私たちと一緒に行きませんか?」
「ははは、俺はいいよ。お前と違って人の心を持ってねーから」
「……そうですか」
彼女は少し寂しそうに肩を落としたが、すぐに心を切り替えたようだ。精一杯の笑顔で別れを告げる。
「お元気で!」
「ねーちゃんもな!」
僕たちは、再びもくば駅への道を走りだした。
***
母さんは軍の英雄だった。
けれど母さんは、英雄たる自分を嫌忌していた。
――私は人殺しなの。人殺しのくせに、人並みに幸せになろうだなんて思ったから、罰が当たったんだ。
父さんは終戦の年に母さんと結婚して、五年後に殺された。母さんを恨むカデニア人による犯行だった。母さんはそれを天罰と呼んだ。そして、幼い私に怒鳴りつけた。
――あなたは生まれてはいけない存在だったのよ。今すぐ私の前から消えて!
母さんは誰よりも自分を憎み、そして自分の血を疎んだ。あたしはどうしようもなく悲しくて、哀れな母さんを憎むこともできず、ひたすら泣いていたように記憶する。殴られても文句は言わなかった。子供は親の暴挙を正当化するものだ。
しかし成長するにつれ、母性の幻想は薄れていった。こんな人のために苦しむなんて、もうまっぴらだ。そう思った時ふと気づく。
こんな気違い女に存在を否定されたって、気に病むことないじゃないか。それなのに、どうしてこんなに苦しいの? あたしが母さんに執着しているから? そんなはずはない。あたしは母さんなんて大っ嫌いだ! そう自分に言い聞かせた。どんなに求めても手に入らないものは、いっそ嫌いになってしまった方が楽だと知っていたから。
でも、あいつに「愛している」と言われた時。
一瞬だけ、母さんに愛されたような気がした。
あいつは母さんじゃない。それは分かっているけど、あたしはずっと待ち望んでいたのかも知れない。
あの顔で、あの声で、あたしを認めてくれる存在を――。
***
僕たちはもくばエクスプレスに乗っていた。ところどころに木馬に乗った幼女の萌えイラストが描かれた、可愛らしい電車だ。この幼女どこかで見たことあるなーと思っていたら、『くるたんのおもちゃばこ』に載っていたイラストくるたんだった。こんなところまで東条さんカラーに染められているなんて、さすがの一言に尽きる。
「私、もう自由なんですね。まだ実感が湧きません。でも、ずっと憧れでしたから……人生で最高の気分です」
流れていく景色を幸せそうに眺めながら、藤巻さんが言った。その服装は、もちろん例の黒服だ。機能的なデザインで、いかにも戦闘に向いている感じの。
「ねえ、藤巻さん。その服とっても目立ってない?」
幸せ気分に水を差すのは忍びないが、どうしても気になってしまう。
「あら、ご存じないですか? 最近アニメで戦闘ものブームがあったでしょう。その影響でこういう服が流行ってるんですよ。動きやすいので仕事着にしていましたが、一般的なファッションです。安心してください」
なるほど。僕の今どきのファッションに対する知識の少なさを痛感した。あまり外出をしないクタオだから仕方がないのだけれど。でも、もう一つ問題が。
「僕の脚の怪我、さっきからちらちら見られてる気がするんだ」
「何か訊かれたら、『破壊少女メガキモス』の将太のコスプレだと言いましょう」
「将太っていつも脚怪我してるの?」
「不定期に皮膚を突き破って脚から角が生えてくるキャラクターです。登場シーンの大半は出血しています」
「ええっ、なんか怖い」
僕なんかよりも、裏社会生活を送ってきた藤巻さんの方がずっと萌えに詳しい。ノクターンの人も萌えをたしなんでいるんだね。ちょっと意外。
今の会話に関連して、前々から気になっていたことを訊いてみた。
「藤巻さん、『安心してください』って口癖?」
「ああ、言われてみると……」
藤巻さんは自分の言動を振り返っているらしく、五秒くらい考えていた。
「確かにそうですね。ミッションで襲われた人たちによくそう言っていましたから、癖になってしまったようです」
苦笑しながら軽やかに微笑む。ああ、こういう人を癒し系って呼ぶのかな。狂乱の中で、一人の聖女が人々をなだめている様子が目に浮かぶ。優しい彼女の微笑みに、多くの人が救われたことだろう。
現在の心配事がなくなったので、まったりと過去の話をすることにした。
「どうして今日逃げ出そうって決意したの? すごく勇気のいることだったと思うけど……」
これは純粋な疑問だ。前もって準備していたならまだしも、普通は急に逃げようと思ったりはしない。今まで『お母様』に従っていた彼女が、どうして今になって旅立とうと思ったのだろうか。
「実を言うと、限界だったんです。これ以上いじめられていたら、私はお母様を憎んでいました。愛する気持ちが負の感情に負けないうちに、お母様から逃げたかった。子供なら、親を好きでいたいじゃないですか」
予想外な、しかし藤巻さんの性格から考えれば当然の答えが返ってきた。寛容な彼女が限界まで追いつめられた背景には過酷な仕打ちがあったことは明らかで、微笑ましいとは言えないが、彼女の懐の温かさを象徴した言葉である。
藤巻さんはさらに続けた。
「それに、あなたがいたから」
「僕? ああ、爆弾をはずす人間がってこと?」
つまり、チャンスさえあればいつでも逃げようと思っていた、と。自分で訊いておきながら、それは何か違うと感じた。本当の答えは、今度こそ予想外だった。
「それもありますけど……どうしてもあなたをお助けしたかったんです」
僕のため?
会ったばかりの僕のために、危険を冒してくれたの?
「私の傷を気にかけてくださったのは、あなたが初めてなんですよ」
この上なく綺麗な笑みを浮かべて、藤巻さんは言った。
電車ががたごとと揺れながら、僕たちを安心できる場所へと連れていく。
虹間駅に着いてからすぐに公衆電話に向かい、東条さんに電話をかけた。ちなみに僕は携帯電話を持っていない。もともと実家が貧乏だった上に、僕の一人暮らしが家計に与えた打撃は測り知れず、とてもではないが携帯電話を買う余裕などなかったのだ。虹高に通わせてもらえるだけでも感謝しているが、現代社会において不便だというのは否めない。
『はーい、くるたんでーす! どちらさまですか?』
つながった! 懐かしい東条さんの営業ボイスだ。メモ帳はブレザーの中だったので、電話番号を覚えていたのは幸運だった。知らないおじさんが出たらどうしようかと思ってハラハラした。
「僕だよ、えっと、乃木坂です」
『のぎさかーっ!?』
耳をつんざくような、悲鳴にも聞こえる歓声を上げて、電話の向こうの東条さんは僕を質問攻めにする。
『今どこにいる? ケガはないか? 何があったんだ?』
「へっくしゅ」
『?』
監禁室も寒かったが電車の中も冷房が効きすぎていて、風邪を引いてしまったのだ。本音を言うと、その辺にでも寝転がりたいくらいだるい。
「虹間駅にいるよ。何があったかは後で話す。とりあえず、東条さんと合流したいんだけど」
『だいじょーぶなのか? 今から虹間駅に迎えをよこす。待ってろ』
「あ、僕以外にもう一人保護してほしい人がいるんだけど、いい?」
『だれだ?』
「えっと、ディーヴァの一人? って言うか、さっき拳銃持って窓割った人って言うか、いや、でもほんとは悪い人じゃなかったから一緒に逃げて来たんだよ」
『よくわからないぞ……』
「ごめん、複雑な状況なんだ」
『んー、乃木坂が信じるなら、ボクも信じる! ディーヴァっていうのも気になるしな。そいつも迎えに行こう』
「ありがとう」
電話を切ると、新たな穴が開いたテレフォンカードが戻ってきた。それに何となく充足感を覚える。
「どうなりました?」
後ろで僕を待っていた藤巻さんに問われて、迎えが来ることを告げた。
「大丈夫ですか? 顔が赤いですよ」
「たいしたことないよ。へくしゅっ」
「完全に風邪引いてるじゃないですか。ベンチで座って待っていましょう」
藤巻さんに連れられて待合所に行く。人混みが僕たちを紛わせてくれたおかげで、僕の怪我に気づく人はいなかった。時計を見るともう七時を回っている。今日の晩ごはんどうしよう。
一息つくと、藤巻さんはぽつりと不安事を漏らした。
「東条さんは、私のことを受け入れてくださるでしょうか」
確かになあ……。スタジオピンクでは、侵入・破壊・略奪・逃走を一通りやってきたわけだから、フォローする余地もない。それでも何とか元気づけようとする。
「大丈夫。東条さんは僕を信じるって言ってくれた。藤巻さんが無事に社会復帰できるように、きっと応援してくれるよ」
「乃木坂さんにそう言っていただけると安心します」
気休めでしかないような言葉で、彼女は安心してくれた。「安心してください」が口癖の藤巻さんだけど、本当に安らぎを求めていたのは彼女自身だったのかも知れない。それが今こうしてほっとしてくれていることが、僕には嬉しかった。
十数分ほどして現れたのは、人混みの中でも目立つミツルさん。っていうか彼は公共の場でもピンクフリル金髪リーゼントサングラス姿なのか。勇者だ。
「誰ですかあの人っ」
藤巻さんが必要以上に警戒しているのには笑ってしまった。
「東条さんの専属スタイリストだよ」
「本当ですか? 乃木坂さんに何かあったら私――」
「本当だからその銃しまってぇ!」
訝しがる藤巻さんを何とか落ち着かせて、ミツルさんのもとへ向かう。
「吟ちゃん! 無事でよかったわぁ。さあ、一緒に帰りましょう」
ミツルさんは満面の笑みで僕を迎えてくれた。それから気を張っている藤巻さんにも目を向けて、にっこりと笑いかけた。
「あなたのことはあたしたちが全力でサポートするわ」
「……ありがとうございます」
「そんなに固くならないの! 大人は子供を守るもの。あなたはもっと子供らしく気楽にしてていいのよ」
彼の容姿からは想像もつかない頼もしさに触れて、藤巻さんは一気に緊張を緩めたようだった。ミツルさんの大人としての矜持には、見習うべきものがある。僕も彼のように立派な大人になりたい(外面的なことはまた別として)。
「さあ、外で車が待ってるわ。行きましょう」
傍から見たら、僕たちは立派なコスプレ集団に見えたことだろう。
目的地はスタジオピンクではなかった。
「え?」
「当り前でしょ、一度ばれた場所をアジトになんてできないわ。すでにスペアの施設に全ての機能を移し終えたところよ」
なんて迅速な処置。
「これから行くのはスタジオローズ。ほら、もう見えてきたわ」
壁が一面薔薇色! なんてことはなく、外観はつまらないコンクリートの建造物でしかなかった……などとスタジオピンクの時と同じ感想を抱く。要するに何の変哲もない、風景レベルの建物だった。
運転手さんにお礼を言って車から降り、ミツルさんの後についてスタジオに入る。ロビーには、僕のご主人様がいた。
「乃木坂おかえりーっ!」
それまでは隣にいる色川社長と話をしていたようだが、話を打ち切って僕のところまで走ってきた。小さな身体がドレスと一緒に跳ねて、得も言われぬ可愛らしさを振りまいている。――あれ、止まらない? ぶつかるぶつかる!
「ぐぇ」
東条さんは僕に頭突きをかましてフンと鼻を鳴らした。
「見つかっても大したことにはならないっていったくせに! 捕まるなんてうそつき! ばーか!」
「ごめんね」
「ボクは怒ってるよ。だけど」
彼女は僕にしか聞こえない低い声で、こう続けた。
「帰ってきてくれてよかった」
「……うん」
どうしよう、嬉しくてちょっと涙が出そう。帰りを待っていてくれる人がいるというのは幸せなことだ。
東条さんは藤巻さんを見て、「おねえちゃん」と呼びかけた。くるたんとしての口調では、同年代の相手でもおねえちゃん扱いらしい。
「おねえちゃんは、もうボクたちを襲ったりしない?」
その目は、疑っていると言うよりは、純粋な子供の目をしていた。しかし、彼女は肉体的には幼女でも、中身は天才女子高生だ。きっと頭の中では、複雑な思考処理が行われているのだろう。
「ええ。絶対に」
「そっか。パパがおねえちゃんに話があるって。行っておいでよ」
色川社長が手招きをして、藤巻さんを呼び寄せた。三十秒ほど喋った後、二人はエレベーターの前まで歩いていった。あの二人が並ぶと、何だかシリアスな雰囲気ができあがる。
「何か用があったら、私たちは社長室にいるよ」
「乃木坂さん、東条さん、また後でお会いしましょう」
きっとディーヴァがどうとかノクターンがどうとか、込み入った話をするのだろう。二人はエレベーターの向こうに消えた。
「乃木坂、さむいのか?」
「え?」
「震えてるから」
確かに、館内に入ってからというものうすら寒く感じる。クーラーが効きすぎているのではなく、僕が寒がりになっているのだ。手で腕を擦りながら正直に答えた。
「実は向こうで風邪引いちゃってっくしゅ」
「カゼ!? そーいえば脚もケガしてるんだったな。ボクの許可なく体調を崩すとは、この不届き者っ」
うわ、思ったより反応大きい! しかも怒られた!
「罰としてスタジオローズの医療室でのキンシンショブンに処す!」
あれ。
「もしかして、治療してくれるってこと?」
「当たり前だろ。主たるもの下僕の健康を守るべし! さあ、話はあとにして、とりあえず今はあたたかいカッコして寝てろ」
東条さんの取り計らいによって、僕はしばらくスタジオローズでお世話になることになった。一人暮らしの身にはありがたい。ただ……。
家に置いてきた開封済みの牛乳が腐らないか心配だ。
医療室の責任者である東条博士に案内されて、僕は入院部屋のような部屋に入った。東条さんもついてこようとしたが、博士に「風邪が移ったらどうするの! ライブが近いのよ」と言われて渋々自室に戻っていった。そう言えば、東条さんの部屋はこの建物でもやはりモノトーンなのだろうか。
「何ボーっとしてるの。はいこれ体温計ね。着替え持ってきてあげるから、その間に計っとくのよ」
「あ、はい、ありがとうございます」
東条博士が出て行った後、体温計をわきの下にはさみながら部屋を観察した。ベッドが四つ、それぞれカーテンがついていて、しかも憧れのテレビまで置いてあるという素晴らしい設備だ。小さいころ肺炎にかかって地方の病院に入院したことがあったが、その時はテレビのスイッチのつけ方が分からなくて悲しい思いをしたことを、今でもよく覚えている。今度こそ何か見よう。特にアニメ!
「なに物珍しそうにテレビなんか見てるのよ」
ちょうど体温を計り終えたころ、東条博士が荷物を持って帰ってきた。彼女は冗談のつもりだったのかも知れないが、実際に僕は物珍しそうにテレビを見ていたので、一瞬挙動不審になってしまった。おそらく何らかのツッコミを期待していたのだろう、博士は僕の反応に不満げな顔を見せた。
「ノリ悪いわね……。体温何度だった? 三十八・六? 結構あるじゃない」
僕から体温計を受け取り、引き換えに荷物を押しつける。
「着替え。それとあなたが置いていった学生鞄。とりあえず脇に置いといて、ワイシャツ脱ぎなさい」
「え、何で博士の前で……」
「診察! 私は医者でもあるの。医療室の責任者ってことから察してよ」
あ、ああ、そっか。彼女は変な人というイメージがあって、つい身構えてしまった。
風邪の具合と脚の銃創を診た後、東条博士は薬を調合しに再び出ていった。窓越しに、白衣の姿が足音と共に遠ざかって行くのを見届ける。遠い後ろ姿であっても、博士の美しさは輝いていた。だが、それを綺麗と感じる前に、僕はこんなことを思った。
成長後の自分の美しさを毎日見せつけられていながら成長できない東条さんは、どれほど切ないだろう、と。
一人きりになった僕は、ほとんど無意識のうちにベッドに倒れ込んだ。全身に安心感が広がる。体重と言うよりも、存在そのものをベッドに支えてもらっている気分だ。銃で撃たれたり、監禁されたり、人の首を切ったり……。今日一日で受けた刺激はとっくに僕の許容量を超えていた。僕にはもう、自分を支えるだけの力がなかった。
恐れ、不安、そして喜び。処理しきれないごちゃまぜの感情が今になって押し寄せてくる。仰向けになってこらえようとしたが、突然目頭が熱くなって涙が溢れ出た。
「……ふぇっ……」
昨日限りで僕の「日常」は終わったんだと、今になって真に理解した。例えこれから学校でいじめられたとしても、そんなことは些細な問題になってしまうような、大きな世界に僕はいる。ちっぽけな僕には大きすぎる世界だ。でも、耐えられるかどうかじゃない。僕は東条さんの下僕なんだから、一緒に歩くんだ。
僕は顔に腕を押しつけ、声を殺して泣いた。泣けば泣くほど軽くなるような気がして、ひたすら泣き続けた。
やがて、安らかな眠りが僕を包み込んだ。
***
吟くんがスタジオローズの医療室で寝息を立てているのを見つけた時、私は安堵のあまりその場にくずおれてしまった。
私が貴方を探している間に帰ってきてくれたのね。
貴方を失うことになったらどうしようかと、ずっと怯えていたのよ。
私の手が、実体と温度を持って彼の額をなでる。久しぶりに触れる人の肌は熱っぽかったが、それが正常の範囲なのかそうでないのか、三十六度を忘れた私には判断できなかった。
色素の薄い髪は父親譲りだが、無垢な寝顔はあの方によく似ている。そう気づいただけで私は幸せな気分になる。彼にとって私は高野透という素性の知れない女でしかないけれど、私にとって彼は望みそのものだった。
私は吟くんに会ってはならないと、彼の父親から言い含められてきた。そしてそれを律儀に十年間守ってきた。
けれど昨日、私たちは出会ってしまった。それだけではない。彼は東条胡桃と出会い、次いでノクターンの少女とも出会っている。
彼の父親から、吟くんに情報を与える許可は得た。
明日彼が目覚めたら、私とあの方の話をしなければ。
――彼が「調律者」である以上、「騎士」との遭遇は避けられないのだから。