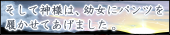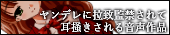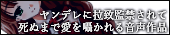第二章 ぴんく
虹高から歩いて十五分という便利な1Kアパート。その二〇二号室のドアの前に、着物を着た女性が立っていた。表札をじっと見つめる様子はまるで静止画のよう。背筋をぴんと伸ばして、微動だにしない。
問題は、そこが僕の部屋であるということだ。
何故彼女はあれほどまでに僕の名前を凝視するのだろうか。見知らぬ来訪者に戸惑い、階段の下で足を止めてしまう。
その時僕は、このアパートの家賃が破格の安さになっていた理由を思い出した。ここでは、外出している間に勝手にシャワーを使われたり、冷蔵庫に覚えのない食品が保管されていたり、まるで誰かに寄生されているような現象がたびたび起こるのだという。大家さんはタチの悪い悪戯だと一蹴していたが、そのうち幽霊の仕業だと噂されるようになり、借り手がつかなくなってしまったらしいのだ。
あんなに明瞭に見えている彼女が幽霊だとは思えないが、たとえ幽霊であろうと無視するわけにはいかない。僕は幽霊と違って、ドアを通らなければ部屋に入れないのだから。
「あの」
内心どきどきしながら声をかけると、女性は能面のような顔をこちらに向けた。
「貴方はここの住人なの」
ひどく抑揚のない喋り方だったので、疑問形で訊かれたことを理解するのに二秒を要した。空気に溶け込んでしまいそうな声質なのに、階段下の僕まで不思議とはっきり声が届く。
「そうです。僕に何かご用でしょうか?」
「ええ」
急いで階段を上がり、改めて彼女と顔を合わせた。
歳は十代後半。おかっぱがよく似合う、日本人形のような綺麗な人だ。身長は僕よりずっと高く、一六七センチくらいだろうか。こんなに近くにいるのに、ひどく存在感が欠けている。失礼ながら、幽霊の方がまだ存在感があるかも知れない。
「私は高野透(たかのとおる)。以前この部屋に住んでいた者よ。実は忘れ物をしてしまって」
「ああ、もしかして着物ですか?」
「話が早くて助かるわ」
このアパートにやってきた初めの日、荷物の整理をしていた僕は、押し入れの隅から着物と……女性の下着を数着見つけた。何と言っても下着なので、人生経験の浅い僕には大家さんに「僕の部屋にブ○ジャーが」なんて言う度量はなく、見て見ぬふりをしていたのだ。持ち主が見つかってよかった。
「上がって忘れ物を確認してください。引っ越してきたばかりで、まだダンボールだらけなんですけど」
「お邪魔します」
高野さんを引き連れ、居間兼寝室へと向かう。布団は綺麗に畳んでしまってあるので、人を入れることに抵抗はない。
「その押し入れの隅に置いてあります。き、着物が」
「あったわ私のパンツ」
僕の配慮は全くの無駄だった。
「ありがとう。てっきり廃棄されてしまっているかと思っていたのに」
無表情に見えるが、彼女なりに喜んでいるのだろう。
「この柄、気に入っていたの。いちご柄」
と言って指差すのは可愛らしいパンツ――ってうわ、見ちゃだめだ!
「迷惑をかけてしまったわね」
「い、いえ」
そう思うのならせめて下着を着物の下に隠してほしいです……。
用事が済んだ高野さんは、衣類を大事そうに抱き直し玄関の方へ歩いていく。帰るのだと思って後についていくと、彼女はドアの手前でふと立ち止まった。
「一つお願いがあるの。もしどこかで手書きの地図を拾ったら、切り刻んで捨ててほしい。詳しくは言えないけれど、人の手に渡ってはいけないものなの。それと……」
……あれ?
待てども待てども続きが来ない。たっぷり五秒が経過し、僕の方から何か言うべきなのかと焦り始めた頃、ようやく彼女が口を開いた。
「これを貴方に言っていいのかどうか、今すぐには判断できない。一日待ってちょうだい。もし必要なら、また貴方の前に現れましょう」
それだけ言うと、高野さんはドアノブに手をかける。長居をして追求されたくないのだろう。言外に、質問しても無駄だと告げていた。
「都会暮らしは危ないわ。吟くんは特に、気をつけて」
「あっ……」
別れの言葉を言う暇もなく、高野さんはするりと外に出ていってしまった。あまりに静かに動くものだから、ドアの開閉音さえ聞こえない。
残ったのは、彼女がいた時とそう変わらない静寂だった。
僕は困惑していた。しかし不思議と嫌な印象はなかった。彼女は表情に乏しい人だったが、一貫してどこか僕を気遣っていたように感じる。
ひょっとしたら、僕たちは以前会ったことがあるのかも知れない。例えば、僕が覚えていないくらい小さい頃に。高野さんの態度は、初対面の人に対するそれではないような気がするのだ。
とは言え、いつまでも彼女のことを考えていても仕方がない。そろそろ僕の日常を再開させなければ。
一人になった部屋で着替えをすまし、七時まで予習。それから晩ごはん(今日は鯖の味噌煮、ほうれん草のおひたし、きんぴらごぼう、フルーツヨーグルト)を作り、おいしくいただいた。家族で暮らしていた時は父と交代でご飯を作っていたけど、毎日一人で作るのも意外と苦ではない。むしろ料理の腕が上がっていくのが分かって楽しいくらいだ。
十時まで実力テストの見直しをしてお風呂に入り、十二時まで『スーパー下僕道』を読む。
『下僕たる者、常にご主人様の状態を把握していなければなりません。身体の調子はもちろん、些細な気分の変化も察知し、ご主人様の健やかな生活をお守りしましょう』
ふむふむ。
『下僕式健康チェック!
主人様のいとしい御足を軽く支え、円を描くようにお舐め申し上げます。足を舐めることでご主人様に満足感をご提供できるばかりか、味でご主人様の健康状態も分かるのです』
足を舐めるって健康チェックのためだったのか。勉強になるなあ。
十二時になったらすぱっと読書をやめて寝た。翌朝は六時に起きて朝ごはんとお弁当を用意し、七時半に家を出た。
我ながらよく出来た生活スタイルだ。
教室に入ると、栗本さんの伸びやかな声が迎えてくれた。
「おはよう、乃木坂くん」
僕が教室に来るのも大分早いけど、一番に来ているのはいつも栗本さんだ。さすがクラス会長。
席に着き、机に勉強道具を広げる。暇さえあれば勉強してしまう自分は、すっかりガリ勉が板についてしまっているようだ。栗本さんはちゃんとライトノベルを読んでいて偉いなあ。
彼女が読んでいる『なんだただのクロマニョン人か』は最萌(さいも)えSF大賞受賞作らしいし、僕も読んでみたいのだが……やっぱり無理だ。昨日『スーパー下僕道』を買ったから、娯楽費はもう出せない。しかし後悔の気持ちは一切なかった。立派な下僕になることは、僕の最優先課題だからだ。
カリカリ。ペラリ。カリカリ。しばらく二人きりの空間ができる。手を止めたら栗本さんと何か話さなくてはいけない気がして、僕は一心不乱に問題を解き続けた。栗本さんはいい人だけど、本当は僕のことをウザいクタオだと思っているんじゃないかと思うと、少し怖いのだ。
八時になると生徒も増えてくる。人のひそひそ声が自分の悪口に聞こえてしまうようなネガティブな僕なのに、今日は何故かこの人口増加にほっとした。きっと、栗本さんに嫌われたくない、真実を知りたくないという気持ちが、昨日優しくされたせいで大きくなってしまったのだろう。自分が自分で情けない。
「乃木坂ぁ」
幼い声に振り向くと、東条さんが教室の入り口からひょっこり首を出して手招きをしていた。こそこそした様子からすると、他の生徒に見られないように注意しているらしい。それはそうだ。世界一のアイドルと、国賊のクタオが一緒にいるところなんて見られたら、スキャンダルになってしまう。
「どうしたの?」
東条さんは僕を人気(ひとけ)のない廊下に連れ出すと、嬉しそうに話し始めた。
「今日のほーかご、乃木坂をスタジオピンクに連れてきていいって、パパから許可もらったんだ!」
「スタジオピンク?」
「世界征服のアジトのことだ。昔はディーヴァの研究所だったけど、今はボクの芸能活動全般をとーかつするスタジオになっている。一部の関係者以外には場所も教えてないんだぞ。よろこべ乃木坂!」
くいっと胸を張る様子に、自然と頬が緩む。一般人が立ち入れないようなすごいところに行けるのはもちろん、彼女が僕のためにいろいろ工面してくれたことが嬉しかった。
「でも、乃木坂にMPが効かないのは、ボクたちだけのヒミツだぞ?」
東条さんは急に真剣な表情を作る。
「MPが効かない人間なんて、パパたちにとっては危険因子だからな。乃木坂を捕まえて解剖しようとするかもしれないし、刺客を送ってアンサツしちゃうかも」
「ふぇっ!?」
一瞬驚いたが、よくよく考えてみればクローン人間だって平気で作ってしまうのだ。こんな高校生一人、簡単に殺せるだろう。
僕の不安を払拭するためか、東条さんは一段と明るい声で言った。
「だいじょーぶ! 乃木坂のことは、とってもアタマがいいから下僕にしたって言ってあるから!」
「そんな勝手に……。もしカラプロの人に『それほどじゃない』って思われたらどうするの?」
「んー、萌やしてごまかす」
行き当たりばったりとはまさにこのこと。
こうして僕は、スタジオピンクなる秘密機関に足を踏み入れることとなった。
虹間区の郊外に、スタジオピンクはあった。
壁が一面桃色! なんてことはなく、外観はつまらないコンクリートの建造物でしかなかったが、この中に世界征服の夢が詰まっているかと思うとわくわくする。
幼少期に「世界征服による救世」に憧れた人は少なくないだろう。僕もその一人だった。世界を僕のルールで統制すれば、誰も意見の相違で争うことはない。僕が正しいルールさえ作れば、世界は平和になるんだ――。そんな短絡的なビジョンで満足するのは最初だけ。正しいって何? 全人類が納得できる法律なんてありえない。逆らう人が出たら殺す? それでは救世にならない。魔法でも使わないと、世界平和なんて望めないのではないだろうか……。
子供たちはそこで壁にぶつかり、そのうち世界征服なんて馬鹿な夢はすっかり忘れてしまう。しかし、僕はこの目で魔法(MP)による平和的世界征服を見届けるチャンスを得た。封印されていた夢が、ようやく叶うのだ。
感慨にふけっている僕を出迎えてくれたのは、背の高い男性(?)だった。
「はぁい、坊や」
「こ、こんにちは」
スタジオの扉から出てきたのだからカラプロ関係者に間違いはないだろうけど、それにしてもこの格好は何だ。金髪リーゼントにサングラス、ピンク色をした女物のフリルつきブラウスに白いスラックス、なよなよした仕草に厚化粧……。がたいがいいので、ただの女装趣味者を通り越してオカマなヤクザにも見える。しかも年齢不詳と来た。人の好みに口を出す気はないけれど、これで外を歩いていたら通報されそうだ。
気おくれしている僕に、東条さんが営業ボイスで説明を入れる。
「ボク専属のスタイリスト、ミツルだよ。今日はオフだからボクたちについてくるって」
「そうでしたか。よろしくお願いします」
警戒を解いた僕に、ミツルさんはぐいっと顔を近づけて、品定めをするように眺めまわした。香水のにおいがする。
「あらー、可愛い子ね」
「いえ、とんでもありません」
「あたしと同じニオイを感じるわ」
「いえ、とんでもありません!」
「謙遜しなくていいのよ。うふふ」
ミツルさんはアクセサリーをじゃらじゃらさせながら、ついてくるように合図した。変わった人だけど、悪い人ではなさそうだ。
後を追って歩き出すと、東条さんが小さな声で言った。
「ミツルには、乃木坂にMPが効かないこと教えてあるよ」
いいの? と振り返る僕に、彼女はこくりと頷いた。
「ミツルは信頼できるよ。ああ見えてしっかり者だし、こどもを大切にしてくれるから。もし乃木坂がカラプロから狙われるようなことがあったら助けるようにって言ってある」
そっか、悪い人じゃないどころか、いい人なんだ。
そう考えると、あのピンクのひらひらも頼もしく見えてきた。
「ところで、スタジオピンクってピンクの服を着るのが決まりなの?」
「えっ?」
東条さんはミツルさんのピンクな後ろ姿を見て笑い出す。
「きゃははっ、あれはミツルの個人的好みだよ。『スタジオピンク』って呼ばれてるのは、ボクが桃色を名に負うディーヴァだから!」
なるほど、そういうことか。
最初に向かったのは衣装部屋だった。東条さんが普段着のように着ているドレスを始めとして、スクール水着、猫耳メイド服、巫女装束など、萌え要素の詰まった品々が並んでいる。
「好きな服をえらんで! 記念にそれを着たボクのブロマイドをぞーていするよ」
そう言われても、何千着という衣装を前にして、何を選んだらいいというのだろう。困った僕は、ぱっと目についた薔薇色のドレスを指差した。
「じゃあ、あれで」
「んまー、吟ちゃんいいセンスしてるわねぇ! ピンクは女を美しくする色なのよ」
ミツルさんが腰をくねらせながらドレスを手に取る。
「十分だけ待っててちょうだいね。胡桃ちゃんをちゃちゃっと可愛く飾ってくるわ」
「なに言ってるのミツル。ボクはもとから可愛いよ」
「確かにそうだわね」
二人は戯れながら更衣室に入っていった。僕はぼーっと二人が消えた扉を見つめていたが、東条さんだって同級生の女の子だということを思い出し、慌てて目線を逸らす。することもないので、暇つぶしにブレザーを脱いで鞄にしまった。別に暑くはなかったが、脱いでも寒くない快適な室温だったのだ。今度こそ手持ち無沙汰になって部屋の中をうろうろしていると、やがて更衣室のドアが開いて、二人が戻ってきた。時計を見るときっかり十分。東条さんは完璧にドレスアップされている。普通なら数十分はかかりそうなものだが、さすが世界的アイドルのスタイリスト。ミツルさんのスピードは並みじゃないらしい。
「乃木坂はしあわせものだね! こんな可愛いご主人様の下僕になれて」
東条さんはくるりと一回転して見せた。ふわふわのドレスと、薔薇をモチーフとした髪飾りが、爛漫と咲き誇る花を彷彿とさせる。
「ミツル、インスタントカメラ出して」
そう言いながら、東条さんはその辺にあった椅子の上で体育座りになった。右肩を背もたれにつける形で、顔だけこちらに向けて座っているので、髪もドレスもよく見える。身に染みついたポージング技術なのだろう。
ミツルさんがインスタントカメラを構えながら、優しい声で言った。
「天下のくるたんが、撮影室でもないところで、適当な椅子に座って、安物のインスタントカメラで写真を撮られるなんて。不思議な光景ね」
「うん、でもそれでいいの」
東条さんは瞳を閉じて膝に頭を預けた。
「今ボクは、ひとりの女の子として写真を撮るんだから」
薄く目を開けて微笑む彼女の様子は、姿こそまさに天使や妖精といった類の存在に見えるが、中身は普通の少女なのだと改めて実感させた。天使や妖精なら、本当の自分が出せないなんて小さなことで悩んだりはしないと思うから。でも、そんな小さなことで悩むからこそ、人間は可愛らしいのだとも思う。
写真撮影はあっけないもので、ミツルさんがパシャっとやってそれで終わり。写真の出来も庶民レベル。
でも、ここに写っているのは本当の東条さんなんだ。
衣装部屋から出る前に、東条さんは学校に来ていた時のドレス姿に着替えなおした。
「どっちにしてもドレスなんだから、そのままで良かったんじゃない?」
「む。いちおーボクにだって、私服と衣装の区別はあるんだよ」
確かに、さっきの薔薇色のドレスよりは、今着ているオフホワイトのドレスの方がいくらか質素には見えるけど……。どっちにしろ私服とは言い難いと思うのは僕だけだろうか。
廊下に出たところで、白衣を着た眼鏡の女性と出会った。
「ママ姉(ねえ)!」
東条さんが嬉しそうに駆け寄る。
「あら、胡桃、おかえりなさい」
顔を見て、一瞬で分かった。この人は東条さんの遺伝子的オリジナル、東条胡都博士なのだと。
絶世の美女とはまさに彼女のことを言うのだろう。東条さんが成長してスタイル抜群になったらこんな感じかな。いや、逆か。東条博士の幼女バージョンが、東条さんなのだ。すごい研究者なんだからお年も召していると思っていたが、びっくりするくらい若く見える。
「いつ見ても胡桃は可愛いわね。まあ私(わたし)の遺伝子使ってるんだから可愛いに決まってるけど」
「ボクもママ姉みたいなびゅーてぃーになりたいよぅ」
「何言ってるの、女はつるぺたのうちが華よ」
東条博士はさりげなく東条さんの胸を撫で始めた。こ、これはスキンシップの一環だよね? 東条さんは特に気にしていないようだし。
「ちょっとママ姉、こんなところで健康診断なんかしないでよ」
「すぐ終わるからね。ハァハァ」
なんだ健康診断かぁ。……なわけない!
固まっている僕に、ミツルさんがそっと耳打ちした。
「東条胡都はナルシストで真性のペドフィリアなの」
東条博士の大きな目がこちらを睨んだ。美人が睨むと迫力が半端ないって言うけど、本当だったんだ。ミツルさんも毅然とした態度で博士を見返す。これは……女の戦い!?
「何かおっしゃいましたか、ミツルさん?」
「さあ」
サングラスの奥で敵意が光った。さすがの東条さんも、二人の間に流れる険悪な空気におろおろしている。
「私(わたくし)は胡桃の『母』です。しがないスタイリストのあなたに指図される覚えはありませんわ。いつもいつも口を挟まれて、私、そろそろ限界です」
「博士の可愛がり方は、はっきり言って異常だわ」
「この子はいずれ平和な世界の頂点に立つのよ。可愛がって当然じゃありませんか」
「胡桃ちゃんはあなたじゃないのよ!」
「胡桃は私の最高傑作です! 我が身と変わりありませ――」
「やめーっ!」
東条さんの甲高い叫びと同時に、博士とミツルさんの表情が急に緩んだ。
「……萌えー」
MPを使ったらしい。さっきまでの剣幕はどこへやら、二人はデレデレと笑っている。
「今日は胡桃の可愛さに免じて許して差し上げますわ、萌えー」
「く、胡桃ちゃん、ごめんね、あたし、守ってあげたいのに、どうしても萌えちゃうの、何でこんな、あたしは……萌えー」
二人とも萌えたくて萌えているわけではない。大の大人が強制的に萌やされている光景は、あまりに凄絶だった。
誰も東条さんにはかなわない。最強幼女東条さん。
「ふぅ。二人ともボクの大切な人なんだから、なかよくしてよね」
呆れたように溜息をつくと、東条さんは博士に声をかけた。
「ママ姉、これがボクの下僕の乃木坂だよ」
「あら」
MPの余韻が抜けきらない顔で、博士は僕を見つめる。
「高校生って聞いてたけど、中学生だったのね」
「いえ、高校生ですよ」
「男の子って聞いてたけど、女の子だったのね」
「いえ、男ですよ」
「……リアル男の娘(こ)って初めて見たわ」
この歳になって初めて男子を見たらしい。女子高出身なのだろうか。
「これなら私(わたし)の胡桃が穢される心配もなさそうだし、安心だわ。せいぜい胡桃の役に立ってよね」
妖艶な笑みを残して、博士はすたすたと去っていった。うーん、穢すって……?
「ママ姉は、いい人なんだよ?」
僕のワイシャツの裾を引っ張って、東条さんは呟いた。
「いつもボクの身体に気を遣ってくれるし、こーねつ出したときも徹夜で看病してくれたんだから。そりゃあ確かにカホゴだけど、どうしてミツルがあんなに怒るのか、ボクには分からないよ……」
悪いけど、僕はミツルさんに同意する。東条博士は東条さんのことを「最高傑作」と言った。彼女にとっては、東条さんのパーソナリティーよりもその性能、つまり容姿やアイドル性、そしてMPの方が大事なのだ。東条さんをディーヴァとしてしか見ない博士は、悪い人ではなくても好きになれない。もちろんこのことは東条さんには内緒だ。曖昧な笑みでごまかすと、東条さんも曖昧に笑い返して、声を張り上げた。
「よーし、気を取り直して、次はパパに会いに行こー!」
パパということは、色川社長か。つまり一番偉い人。少し緊張してきた。
「色川社長って、どんな人?」
「んー、ボクには優しいよ」
「『には』……」
「功績重視だから、失敗したらこわいんだ。あと二次元に目がない」
話を聞いたらますます緊張してしまった。クタオだなんて知られたら、即刻首を刎ねられかねない。
階段を上がって右に曲がったところに、『社長室』はあった。
「本社じゃないのに、社長室?」
僕の素朴な疑問に、ミツルさんが答えてくれた。
「まあ、実質的にこっちが本社みたいなもんだからねぇ。世界に三十億のファンがいるくるたんのプロデュースは、世界平和計画を抜きにしても最優先事項だもの」
確かになあ。ちょっと他のアイドルさんがかわいそうな気もするけど。
「パパー、乃木坂連れてきたよ」
東条さんがドアをノックすると、中から貫禄のある温かい声が聞こえてきた。
「おうおう胡桃か、入りなさい」
「はーい」
僕の緊張を知ってか知らずか、東条さんは気兼ねすることもなくドアを開ける。
「あたしはここで待ってるから、頑張ってきなさいよ」
ミツルさんが応援してくれるけど、手に滲む汗は引くことを知らない。
校長室みたいなイメージの部屋の奥で、色川社長は机に向かっていた。六十代半ばの、温厚そうなロマンスグレーの男性だった。
「よく来たね、乃木坂くん」
「おっ、お会いできて光栄ですっ!」
「そう固くならなくてもいいのだよ」
柔らかく微笑む社長は、優しそうな人に見える。と、安心したのもつかの間。
「君は、何ができるんだい?」
「え?」
「胡桃は君を右腕として使いたいと言っているが、君にはそれだけの価値があるのかな?」
よく見ると目だけ笑っていない。やはり成果主義の実業家、僕を審査しようというわけか。社長は組んだ手に顎を乗せて僕の返答を待っている。
「えっと、家事一般は得意です」
「それだけかね」
社長の冷たい視線が僕を射抜く。怒鳴られているわけでもないのに、蛇に睨まれた蛙のように脚がすくむ。これが萌え文化の立役者、色川社長の迫力……!
「多忙な胡桃に仕えるなら、仕事上の人間関係やスケジュールを完璧に記憶できる能力が欲しいところだね。ここは一つテストをしてみようか」
彼は机の引き出しから一枚の紙を取り出した。
「まあこれでいいか……。社員の名簿の一部だ。一分あげるから覚えてみなさい」
手渡された名簿を見ると、百個ほどの名前がずらりと並んでいる。え、一分?
「はいスタート」
容赦なく始められる試験。
「はい終わり」
一分のあまりの儚さに涙が出そうだ。
「覚えている名前を言ってごらん」
「あ、相川みなえ、青山しゅ、俊二……」
しどろもどろで名前を言っていく。他の人と競争したことがないから分からないが、記憶力はある方だと思う。それでも答えられたのはせいぜい半数。難しそうな顔をして僕を見やる色川社長を正視できなかった。
「それで全部かね」
「……」
挫けそうになって目を逸らすと、心配そうに僕を見ている東条さんと目が合った。
そうだ。僕を必要としてくれた彼女のためにも、ここで諦めるわけにはいかない。
無能だと軽蔑されてもいい。生意気だと罵られてもいい。東条さんの下僕として、何としても認めてもらわなければ!
僕は顔を上げ、色川社長を真っすぐ見据えた。
「第三次世界大戦から四十四年経った現在、世界は痛みを忘れ、紛争も増えてきました。カデニアとファンゼル連邦なんか冷戦状態です。そんな現代において、カラープロダクションの萌え布教活動は素晴らしいと思います。でも、今のままでは東条さんにかかる負担が大きすぎます。僕は少しでも東条さんを支えたいと思うんです! もっともっと優秀になって、必ずお役に立ってみせます! だから、僕を東条さんの下僕でいさせてください! お願いします!」
勢いで頭を下げる。珍しく熱くなってしまった。自分の意思ををこんなにも押し通そうとしたのは久しぶりかも知れない。
……恥ずかしい。
「顔を上げなさい。何か勘違いしているようだが、私はテストの結果に満足しているよ」
「でも、僕、半分しか」
社長は僕の顔を見て笑った。余程情けない面をしていたらしい。
「いや、だって、半分も覚えてたら普通にすごいでしょう。私は感心したくらいなんだが」
「じゃあ……!」
「心意気も気に入った。君を胡桃の部下として正式に認めよう」
「ありがとうございます!」
とん、と背後に軽い衝撃を感じて振り向くと、東条さんが僕に抱きついて「よかったね!」と言ってくれた。僕も、すごく嬉しい。
「パパ、神聖アキバ帝国のことも、話していいかな?」
「うむ。もう彼はカラプロの幹部同然だ」
幹部同然ってあわわわ!
感動に打ち震える僕に、新たな驚愕の計画が説明された。
神聖アキバ帝国――世歴二〇四三年四月二十七日(日)建国予定。
それは、国土を持たないネット国家である。
国際条約において正式に認められた国ではない。いわば仮想国家なのだ。
初代皇帝は幼女帝くるたん。首都は幻の都市、秋波原(あきはばら)。第三次世界大戦中に消滅したオタクの聖地が、今ネット上に復活する。
国民になるにはややこしい手続きは一切必要ない。萌えを愛し、くるたんを愛すること。それだけでどんな人間でも国民になれる。自分の中の妄想では飽き足らず、国民としての目に見える証がほしい者は、メールで申し込みをすれば簡単にデータ状の国民証が手に入るという仕組みだ。
形を持たない神聖アキバ帝国は、現存するどの国家よりも自由に広がり続けるだろう。人種を越え、思想を越え、萌えが人類を一つにする。略奪や支配を経ず精神世界を征服する可能性を秘めた、カラープロダクション渾身の壮大なプロジェクト。
アキバの平和(パックス・アキバーナ)。
誰一人犠牲にしない、世界で一番平和な世界征服。
「というわけだよ、分かってくれたかね、乃木坂くん」
「二十日には建国記念ライブ、建国トージツには祝典が開かれるんだよ! もちろん乃木坂も手伝うんだからね」
改めて、東条さんたちがやろうとしていることの大きさを知る。僕みたいな一般人が首を突っ込んでいいのかという戸惑いと同時に、この新しい波の中で僕の力を試してみたいと言う不遜な欲求も湧いてきた。
クタオで引っ込み思案な自分でも、今なら変われると思ったから。
「じゃあパパ、そろそろおイトマするねー」
「ああ。乃木坂くんも、気をつけて帰るんだよ」
色川社長に見送られて社長室を後にし、ミツルさんと再会した。
「あら、その顔は、上手くいったのね」
「はい!」
「あの厳しい社長に認められたってことは、誇りにしていいのよ」
ミツルさんも喜んでくれているようだ。期待に応えられてよかった。
「乃木坂、帰る前にボクが住んでる部屋に寄ってかない?」
「って、このスタジオに住んでるの?」
「言ってなかったっけ? ここはまるっとボクの家でもあるんだよ」
当然行くに決まっている。東条さんも、素で話したいことがあるのだろう。東条さんの部屋がどんな風なのかも見てみたいし。
「じゃあ、あたしはここでお別れするわ」
「そうですか。今日はお世話になりました」
ミツルさんに会釈をして東条さんについていこうとすると、小声で呼び止められた。
「ちょっとだけ、あたしの戯れ言を聞いてくれない?」
どんどん先に行ってしまう東条さんを気にしながらも、彼に耳を貸す。ミツルさんは身をかがめて僕に身長を合わせると、オカマ声なのに何故か神妙に聞こえる調子で話し始めた。
「誰一人犠牲にしない、世界で一番平和な世界征服――。それが色川社長のコンセプト。でもね、誰一人犠牲にしないなんて嘘。胡桃ちゃんだけが、一人犠牲になってる。吟ちゃんにも分かるでしょ?」
小さく頷くと、ミツルさんは寂しそうな笑みを浮かべて言葉をつないだ。
「あの子には今まで友達なんて出来なかった。そしてあたしは、どんなに頑張ってもMPには敵わなかった。本当はあたしがあの子の一番になりたかったんだけど……。吟ちゃん、それはあなたに任せるわ。胡桃ちゃんを支えてあげて」
「何やってるの? はやくはやくー!」
向こうから、東条さんの無邪気な呼び声が聞こえる。
「さあ、お行きなさい」
ミツルさんはそれだけ言って、ぽんと僕の背中を押した。
東条さんは彼の心中など知るよしもなく、あどけない顔で「なに話してたんだ?」と訊いてくる。僕は胸にじんと染みるものを感じた。その正体はよく分からないけれど。
振り返ると、すでにミツルさんはいなくなっていた。
東条さんの部屋はピンクでフリフリしているのかと思いきや、モノトーンでシックなコーディネートだったのでびっくりした。東条さんが得意げに言う。
「意外だったか? ボクは可愛いのも好きだけど、かっこいいのも好きなんだ。くるたんとしてのイメージがこわれないように、メディアにはダミーの可愛い部屋をしょーかいしてるんだが、やっぱりこっちが落ち着くな」
確かに、この空間はおしゃれなのにすっきりしていて、実に住み心地がよさそうだ。
「こんなにかっこいい部屋なのに、誰にも見てもらえないなんて」
……まずい。ただもったいないと思って口にしただけだったが、友達も作らないで頑張っている東条さんに向かって「誰にも見てもらえない」だなんて。傷つけてしまっただろうか。
しかし取り越し苦労だったようで、当の東条さんは別段気にしている様子もなく話を続けてくれた。よかった……。
「ひとりで楽しむのもオツなものだぞ。それに、今は乃木坂が見ててくれるじゃないか」
「っ……うん!」
こともなげに嬉しい言葉を言ってもらって、僕は少しどきっとする。こんなふうに同世代の人と素で会話できるなんて久しぶりだ。
「まあ座れ」
顔が赤くなるのを感じながら床に正座すると、東条さんは先ほど撮った写真を見せろと催促してきた。意図は分からないが素直に差し出す。
「んー、やっぱりボクはいつ見ても可愛いなー。ポーズもバッチリだ」
ただの自慢話かと思えば、ふと彼女の表情が曇った。
「本当はお前といっしょに写りたかったんだけどな……」
「どうしてそうしなかったの?」
東条さんは呆れ顔で僕の頭を小突いた。予想外に痛い。
「ばーか。ボクとのツーショットを持ってるなんて誰かに知られたら、妬まれて殺されるぞ。ボク一人の写真なら、万が一見つかってもごまかしが効くだろ?」
「あ、そっか」
幸い、地味な僕に注目するような人もいないし、黙っていれば僕たちの関係はばれないだろう。
「写真、大切にしろよ」
そう言って東条さんは写真を僕に返した。僕はそれを、傷つかないように『スーパー下僕道』に挟んでおく。しまい終わると、東条さんはもじもじと膝を抱え直し、何故かためらいがちな瞳を向けてきた。
「あの、さ。さっきはちょっとかっこよかったぞ」
「さっき?」
「ほら、パパに向かってタンカを切ったときだよ! なんていうか、初めて乃木坂が『男』に見えた」
初めてって……。
褒められたのに若干落ち込むという不思議な状態に陥ったので、話題を転換してみる。
「ネット上とは言っても、国を作っちゃうなんてすごいよね! 忙しくなると思うけど、高校にはちゃんと来られるの?」
「なめるなよ、ボクはせーきの大天才だぞ! 国務も学校もりょーりつさせてやる」
東条さんは不敵な笑顔で言い放った。その自信に満ち溢れているところが堪らない。
「第一、虹高に通っているのは将来有望な人材により濃くMPの効果を植えつけるためだ。学校に行かないわけにはいかないんだ」
「そうだったんだ」
これが世界一のアイドルがわざわざ高校に通っている理由か。何とも合理的だと感心していると、東条さんの勝ち気な表情がふっと緩んだ。
「でも本当は、ボクも学校に行ってみたかっ――」
彼女が何か言いかけたその時。
突然、何者かによって窓ガラスが蹴破られた。
「わああっ!?」
割れた窓から乗り込んできたのは、高校生くらいの女の子。とても今の蛮行を行ったとは思えない華奢な体躯に、機能性の高いタイトな黒服を纏っている。粉々になったガラスのかけらと共に長い髪が舞っている情景は、ファンタジックですらあった。だが、破片が足元に降ってきて、現実に引き戻される。
少女は蹴破った勢いでひらりと床に着地すると、茫然としている僕たちに顔を向けた。風貌は清楚でおとなしげなのに、こちらを見やる目つきには隙がない。そして、その手には拳銃。
何だこの状況。
「こちらOp.1(ワン)。東条胡桃を確認。捕獲します」
耳に付けた小型通信機に話しかける少女の後ろで、窓ガラスが元通りになった。……え? 僕は我が目を疑った。床に落ちていた破片がきらきら光りながら浮き上がって、窓枠まで飛んでいったかと思ったら、窓が再生したのだ。まるで継ぎ目のないパズルのように。
どういう仕組みかは分からないが、今は呆気に取られている場合ではない。抜けていた腰を奮い立たせ、固まっている東条さんの手をとって駆け出す。
「逃げるよ!」
彼女も余裕がないのか、素直に僕についてくる。とりあえずドアの向こうへ!
「行かせません」
パン、という狙撃音と同時に、右足に熱い痛みが走った。
……撃たれた?
「いっ、いたっ」
「乃木坂っ!」
銃弾はかすめただけのようだが、結構血が出ている。銃に撃たれたのは初めてだ。当然だけど。っていうか何で僕こんなに冷静なんだろう。状況が非現実的すぎて、逆に理性がフル回転しているらしい。
「安心してください、傷はすぐに治ります。さあ、東条胡桃さん、私と共に行きましょう。あなたはノクターンの力になる」
言っている意味が分からない。傷が治る? ノクターン? 東条さんは半ばパニック状態だ。
「乃木坂をいじめるな! くらえ、にゅーんっ!」
泣き出しそうな顔でMPを放つ。これで助かった――はずだった。しかし黒服の少女は顔色一つ変えない。平気なのか?
「私はあなたには萌えません。諦めてください」
「そんな……っ」
東条さんは驚愕に目を見開いて立ち尽くしている。
「東条さん、逃げて!」
足を押さえながら必死で叫ぶ僕を、少女は訝しげに見据えた。
「あなたも萌えないのですか? それに、まだ傷が治っていないなんて。あなたは一体……。いえ、今は任務が最優先です」
少女の手が東条さんに伸びる。
もう駄目だと思った瞬間――信じられないことに――何者かが壁を通り抜けて出現し、その手をつかみ取った。
あれは、昨日の高野さん!
よく分からないけどありがとうございます!
「どこから……!?」
さすがの少女も動揺している。高野さんは手をつかんだまま少女を振り回し、ベッドに叩きつけた。少女はわずかに呻いたが、すぐに起き上がって状況を確認する。
「消えた!?」
何を言っているのだろう。高野さんは目の前にいるのに。
だが、少女にはまるで見えていないらしく、焦燥感を露わに辺りを見回していた。その間に、相変わらず無表情な高野さんが僕に声をかける。
「今、貴方以外の人間は私の存在を感知できない。東条胡桃と共に早く逃げなさい」
感知できないってどういうことだろう。しかしそんなことに構っている暇はない。高野さんのご厚意に甘えて、一刻も早く逃げなければ。
「東条さん!」
「う、うん!」
東条さんも我に返ったのか、幼女とは思えないパワーで僕を引っ張って駆け出した。
廊下に出て非常ベルボタンを押し、また走り出す。
「世界征服目指してると、こんなのよくあること?」
「いや、これが初めてだ。何なんだよあいつは……!」
「高野さんって、昨日言ってたカラプロの刺客?」
「たかの? 誰だそれは」
「さっきの着物の人だよ」
「あんな超能力者は知らない!」
正体不明の高野さんだが、いちご柄パンツの縁がある僕にとっては赤の他人ではない。いくら超能力らしき力が使えると言っても、相手は拳銃を持っているのだ。無事だといいのだけれど……。
十字路に差し掛かったところで、向こうから誰かが走ってくるのが見えた。
「ミツルさん!」
異様にスピードの速いオカマ走りで彼はやってきた。
「二人とも大丈夫? 何があったの? ……って、吟ちゃん、怪我してるじゃない!」
「あ、うっ」
指摘されて痛みがぶり返す。必死になっていて忘れていたが、そう言えば僕は怪我を負っていたのだった。……怪我?
恐ろしい可能性に気づいて振り返ると、血の跡が点々と僕に続いていた。
やってしまった――。
「ミツルさん、僕はいいから東条さんを安全なところへ」
「何言ってるのよ、怪我人を置いていけるわけないでしょう!」
「東条さんは拳銃を持った女の子に追われています。僕はこの通り、血の跡で居場所が分かってしまいますから、早く逃げてください」
拳銃という言葉を聞いて、ミツルさんもことは一刻を争うのだと悟ったようだ。だが、東条さんは営業ボイスも忘れて反対する。
「ばか! 血なんて垂れないように布でも巻けば……」
「処置してる間にあの子が来ちゃったらどうするの」
「それは……そうだけど」
彼女も僕の言葉で納得せざるを得なくなり、黙ってしまった。目を潤ませる東条さんを安心させるために、あえて軽口を叩く。
「向こうも僕なんか目当てじゃないから、見つかっても大したことにはならないよ。殺意はないみたいだったし」
自分でも怖いほど、僕は冷静だった。
ミツルさんに手を引かれて走り始めた東条さんは、名残惜しそうに僕の方を振り返った。
「死んだら殺すからなっ!」
こんな時なのに、つい笑ってしまった僕がいる。だって東条さんがあまりにも可愛いんだもん。
さてと。まずはどこかに隠れよう。そう思った矢先、右の道から足音が聞こえてきた。
これが後ろから聞こえてきたなら恐怖するけど、おそらくスタジオピンクに勤めている人が非常ベルを聞きつけて来たのだろう。助かった。足の血をハンカチで押さえながら、右の道を進む。
やがて見えてきたのは、黒いジャージをラフに着崩した男性だった。やはり緊急事態においては、近くに大人の人がいてくれると安心する。あの人なら運動神経もよさそうだし、一緒に避難してくれたら頼もしい。
男性は僕に気がつくと、にこやかに声をかけてきた。
「東条胡桃は、どこにいるかな?」
――おかしい。スタジオピンクの従業員なら、東条さんのことを呼び捨てにしたりはしないはずだ。ということは、この人……。
声にならない悲鳴を上げて、来た道を駆け戻る。けれど、どんどん差を縮められていくのが感覚的に分かった。僕の五十メートル走のタイムは八秒九二。どうしてこんなに脆弱なのだろう。追いかけっこにすらならない。
軽く肩に手を置かれた。
「捕まえたぞ、中坊」
「ひゃあっ!」
恐る恐る振り向くと、ひょうきんそうな若い男性がにこにこ笑っている。怖い人じゃ……ない?
「そんなにビビるなよー。別に俺、中坊には用ないからさあ。それより、東条胡桃がどこ行ったか教えてよ」
中学生だと思われていることが、今は救いだ。もし僕が大人っぽい容姿だったら、容赦なく尋問されていたかも知れない。
「と、東条さんは、秘密の地下道を通って逃げましたぁ」
我ながら見え透いた作り話だと思うが、「知らない」が許されるとも思えなかった。僕の返事を聞いて、男性は眉を吊り上げる。
「アホな嘘つくなよー」
おちゃらけた声とは裏腹に、彼の手は拳銃に伸びていった。
「俺はOp.1とは違って、人殺しに全然抵抗ないんだよね。あ、Op.1っつーのはさっき中坊を撃ったねーちゃんな。あいつノクターンのエージェントのくせにさ、超能力で敵の怪我治してやるんだぜ。優しいよなあ。中坊は何故か治らなかったけどなー。ああ、で、結局何が言いたいかっていうと、正直に答えといた方がいいよってこと」
頭に拳銃が当たってる……。
この人、さっきの女の子よりもヤバい!
「本当ですっ! 僕は地下道の入口も出口も分からないです! 嘘ついてないです!」
半狂乱のふりをして嘘をつく。僕にはもしかしたら演技の才能があるかも知れない。涙目なのは演技じゃないけど。
「ふーん、そっか」
僕の芝居を信じて男性が銃を下ろしてくれた直後、彼の通信機に着信が入った。
「はーい、こちらOp.4(フォー)。え? Op.1が勝てない相手がいるぅ? ははは、あの化け物が勝てないなんて冗談でしょう! ……分かりました。あ、今目の前にさっきの萌えない中学生がいますけど、どうします? あ、はい分かりましたー」
誰かと話し終えた男性は、ふと真面目な面持ちで僕を見おろした。
「悪いけど、予定変わったわ」
「え?」
足が床から離れ、身体がつんのめる。一瞬遅れて、男性の肩に担がれたのだと分かった。
「やっ、何するんですか、降ろしてください!」
「無理だよ、命令だもん」
男性がさくさく歩いていく中で、僕はまるで鞄のように呆気なく運ばれていた。抵抗して転がり落ちようにも、がっちりと身体を押さえられている。何とかしなくては。このままでは本当に拉致られてしまう。
「じ、自分で歩きます! ほら、お兄さんも人一人抱えてたら大変でしょ?」
「いや、いつもの訓練の重りの方が重いし」
こんな怪力からどうやって逃げろって言うんだ。必死に頭を働かせてはじき出した答えが、これ。
「トイレ! 僕トイレ行きたいです! トイレ行かせてください! 早くしないと漏れちゃうトイレぇ!」
恥を忍んでの迫真の演技。ところが男性は、動じることもなく僕の妄言を一蹴した。
「うるせー中坊だぜ。勝手に漏らしてろよ。まあそれも可哀想だから、ちょっと寝かせてやるか」
何だか悔しい。せめて慌ててほしかった。
そう思ったのも束の間、身体中から力が抜ける。
「あ……」
彼に何かされたみたいだけど、ふわふわして……なにもわからない……。
なんで――。
目の前が真っ白になった。