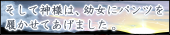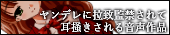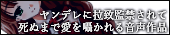第一章 もやし
僕の家にはテレビがなかった。
目の見えない母を気遣って、父がそう決めたのだ。
わがままを言えばお母さんを傷つけてしまう。そう思って、僕はずっと我慢してきた。アニメの話題についていけなくて学校で仲間外れにされたことも、声優を知らなくて馬鹿にされたことも、家族には言わなかった。
世界は今、萌えを中心に動いている。
第三次世界大戦終結後の萌え文化の広がりは、戦後四十四周年を迎える今日(こんにち)になってもとどまるところを知らない。戦前は萌えの愛好家を「オタク」と呼んで差別していたそうだが、今はオタクであることが当然の世の中。わざわざ名称を必要ともしないほどのマジョリティーだ。あえて挙げるとすれば、萌えの発信地である日本が自らを誇る際に、しばしばオタクという言葉が使われる。大和魂はオタク魂へ、大和撫子はオタク撫子へと進化を遂げたのだ。
反対に、萌えをたしなまない僕のような人間は「クタオ」と呼ばれる。ただ単にオタクを逆さまに読んだだけではない。萌えの対義語である萎えから「クタっと萎れる」というイメージが生まれ、「感性がクタっと萎れている人」という悲惨な意味でクタオと呼ばれるようになったのだ。小四の時、初めてクタオと言われた日のことは今でもよく覚えている。だって泣いたもん……。
萌えは平和の象徴だ。戦時中、彗星のごとく現れた謎の歌姫が萌え萌えなアニソンで人々の心を和ませ、それが世界規模の厭戦気分を作りだし、結果的に戦争が終結したという都市伝説がある。そもそも「謎の歌姫」って辺りから怪しいし、いくらなんでもこれはあり得ないと僕は思うけど、世界中に目撃者がいるのは変えようのない事実。だから萌えが世界中から支持を集めているのは当然だと思う。
僕だって、家に映像媒体があったらきっと立派なオタクになっていただろう。せめてパソコンくらいあったらよかったのだが、新聞すら買わないでお金を節約する家計状況で、おねだりなんてできるはずがなかった。働く時間を惜しんでラブラブする両親を見ていると、本当に幸せそうで、僕が二人の生活を乱すのは許されないような気がした。
チャイムの音が昼休みの到来を告げた。
生徒たちは教科書をしまい、あるいは机上に放置して、各自気の合うクラスメートと昼食を共にするべく散らばっていく。
みんないいなあ、もう友達できたんだね。今日もアニメの話で盛り上がるのかな。クタオの僕には友達がいないから一人でお弁当だ。寂しくない寂しくない。今日のお弁当は僕が腕によりをかけて作ったもやしチャーハンだよ! ……さみしい。
高校入学からわずか四日。僕は早くも浮いていた。
ここ、都立虹間(にじま)高校(通称虹高)は、世界屈指の進学校として有名だ。
僕はクタオクタオと虐げられているうちに、どんどん内気な性格になっていった。アニメも見ない、友達とも遊ばない僕は、見事なガリ勉になった。そんなイタくてクタオな僕に、中学の先生は優しく「虹高、受験してみたら?」と言ってくれたのだ。虹高に行くとなると、実家から離れて都会で一人暮らしをすることになる。両親は反対したけど、僕は先生の期待に応えるため、虹高を受験した。そして今に至る。
虹高なら、もしかしたらみんなもガリ勉かも知れない。そんな期待もあったけど、現実はそう甘くなかった。やっぱりみんなはちゃんとしたオタクで、僕だけが感性の萎れたクタオだった。
さすがにまだいじめられたりはしなけど……あれ、女の子がこっち見てる。
「あの子、乃木坂さんだっけ? 今日も一人でごはん食べてる」
「輪に入れてない感じだよね。きっとクタオなんだよ、そういうオーラ出てるし」
「しーっ、かわいそうでしょ。声かけてあげた方がいいのかな?」
「はぁ? 男子に?」
「男の子だったの!?」
チャーハンこぼした。
「テラワロスww 腹筋返せww」
「男子の制服着てコスプレしてるんじゃないの!?」
「いや、男子の制服着てたら普通男子でしょ」
「声も可愛かったし!」
「でもあたし、男子トイレに入ってくところ見たもん」
「うわー、鬱だ」
「メシウマww」
黄色い声を上げる女子二人。僕は恥ずかしくて、聞えないふりをしてお弁当を食べ続ける。こんな体はもういやだ。いつになったら成長期が訪れるのだろうか。クタオで成長不良なんて、コンプレックスを持つなと言う方がおかしい。
惨めな気持ちでブロッコリーを口に放り込んだ時、一際大きな笑い声が上がった。クラス会長の栗本さんがジョークを言ったようだ。その周りで男女十名弱の生徒が笑いこけている。
栗本木梨枝(きりえ)――全ての漢字に「木」が入った特徴的な名前を持つクラス会長は、早くもクラスのアイドル的存在になっていた。彼女はまさにオタク撫子の鏡のような人で、式典の日以外私服着用が認められていることを最大限に活用し、流行最先端のメイド服を着て登校してくる。制服を着ていた入学式の日でさえ輝いて見えたのだから、メイド服を装備した栗本さんは僕には眩しすぎるほどだ。しかもとてもフレンドリーで、クタオの僕にも分け隔てなく接してくれる。僕とは違う世界に……僕が憧れる世界に住んでいる人なのだ。
青臭いブロッコリーを飲み込んだ時、担任の先生が教室に入ってきた。
「実力テストの順位が小広間に貼ってあるぞ。確認しておくように」
実力テストとは、入学早々行われた残酷な学力試験のことだ。中学で優等生だった僕たちに、虹高での自分の位置を把握させるという目的らしい。地元では万年トップだった子が突然最下位になったりするんだから、恐ろしい話である。
生徒がぞろぞろと廊下に出ていく。結果が気にならないでもないけど、どうせ今行っても人混みでストレスがたまるだけだろう。そう思って、僕はもやしチャーハンを食べ続けることにした。うん、我ながらおいしく出来てる。
「行かないの?」
ふいに声をかけられて顔を上げると、栗本さんが机の前に立って僕の顔を覗き込んでいた。大きなリボンで飾られたサイドテールがゆらゆらと揺れる。
「えっと、僕はあとで……」
栗本さんは気配り上手な人らしく、僕が孤立しているとちょくちょく話しかけにきてくれる。それがクラス会長としての義務的行為だと分かっていても、僕は嬉しかった。今僕に話しかけてくれるのは彼女だけだし、彼女の明るい笑顔には人を元気にする力がある。だけど、僕の存在が迷惑をかけているようで、心苦しくもあった。
「人混みが苦手なの?」
「まあ」
「そっか……」
栗本さんは残念そうに肩を落とすと、去――っていかずに手をもじもじさせた。ためらうようにこちらを見ている。何だろうと思っていると、突然右手をつかまれた! えっ、何!?
「じっ、自分からみんなの中に入っていかないとダメだよ! き、き、キリエも行くから、乃木坂くんも一緒に行こう?」
右手越しに栗本さんの手が震えているのが分かる。出会ったばかりで素性も知れないクタオの手をつかむのは、相当勇気のいることのはず。それでも彼女は僕をクラスに溶け込ませようとしているのだ。僕は少し感動した。
「分かった、行くよ」
「わあ、よかった!」
そう言う栗本さんは、本当に嬉しそうである。きっと彼女は、少しでも早く僕が高校生活に馴染むことを、心から望んでくれているのだろう。僕も嬉しくなって笑顔を返すと、栗本さんはおひさまのような笑顔をくれた。
まだ僕がクタオと呼ばれる前、確か小学一年か二年の頃だと思うけど、学級委員長になった年があった。その時の僕は、いじめられっ子の手を取って一緒に歩くような、紛れもない優等生だった。それが今では逆の立場。何とも言えない無力感を覚える。
廊下を抜けて小広間に出ると、そこはすごい人だかりだった。一枚の順位表をみんなが見ようとするので当然だが、自分も今からその中に入っていくのかと思うと憂鬱だ。
「うわぁ、思ったより混んでるよ。やっぱりあとにする?」
僕のことを気遣ってか、足を止める栗本さん。そんなに僕って気弱に見えるのかな。これ以上心配をかけるわけにはいかない。
「せっかく来たんだし、今見てくるよ。栗本さん、ありがとう」
感謝をこめて微笑むと、栗本さんは「ううん」と言ってはにかんだ。教室ではいつも溌剌としているけど、素は案外照れ屋さんなのかも知れない。それとも、やっぱり僕がクタオなのが原因? きっとそうだ。迷惑かけてごめんね。
僕は人山の後ろに立つ。テレビを見ずに育った僕の視力は軽く二・〇を超えるが、人の頭で順位表自体が見えない。頑張ってつま先立ちを試みていると、誰かが「あっ」と声をあげて、後ろを指差した。それにつられて他の人も後ろを見る。僕の足の痺れと比例するように、ざわめきが大きくなっていった。
何だろう。
振り返ると、そこには六歳くらいの女の子が立っていた。フリフリのドレスにウェーブのかかった長い髪。まるで絵本から飛び出してきたお姫様みたいだ。非現実的なくらい愛くるしい姿をしている。
「ふみゅ?」
一瞬の静寂。
小さな口から漏れたその声が引き金となって、群衆は歓声を上げ始めた。
「萌えーっ」
「本当に虹高にいたんだ!」
「くるたんマジ萌えるううう」
目を輝かせてうっとりするみんなの様子は、明らかに尋常ではない。超人気子役か何かだろうか。ここでドラマの撮影するなんて聞いてないけど……。
女の子がてけてけ歩いてくるのを見ると、生徒たちは順位表から離れて拡散していった。僕は意味も分からず押し流される。女の子が順位表に近づくのを見て初めて、彼女に道を空けたんだと気づいた。
女の子は順位表を確認すると、その可憐な横顔に笑みを広げる。
くるりと振り向いて一言。
「ボクいちばーんっ!」
生徒は一斉に拍手を送った。つまりこの子は虹高の生徒なの? 幼女なのに?
女の子が愛想を振りまいている一方で、僕は混乱していた。
「みんなありがとー! ところで、二位の乃木坂吟(ぎん)ってだぁれ? いたら手あげて」
あ、それ僕……。
手を挙げるべきかどうか迷っていると、クラスメートの池田くんと目が合った。
「こいつですよー」
「うわっ」
ニヤニヤ顔で幼女に突き出されてしまった。
女の子は興味深げに僕を見上げる。新しいおもちゃを見つけた時のような顔だ。
「せーきの大天才であるこのボクと僅差で二位につけるなんて、アタマいいんだね! ごほうびに、にゅーん!」
両腕を上に突き出して満面の笑みをプレゼントしてくれた。状況が把握できない。可愛いんだけど、今の僕には苦笑いが限度だ。
その反応に、何故か幼女はかなり驚いた表情を浮かべた。
「もしかして、乃木坂は感じないの?」
何を?
きょとんとしていると、女の子は僕にしゃがむように合図した。そして、僕の耳に手を当てると、今までより幾分か低い声でこう囁いた。
「放課後、体育館裏に来て。誰にも見つからないようにね」
それだけ言うと、僕に質問させる間も与えずその場を離れる。
「ボクはB組に帰りまーす! みんなもベンキョーがんばってねー!」
この声はきっと営業ボイスなんだろうな。後ろ姿を見ながらそんなことを思った。
謎の美幼女が立ち去った後、僕は名前も知らない生徒たちからものすごい非難を浴びた。
「萌えに対する冒涜だ!」
「何で呼ばれたときすぐに返事しなかったんだよ!」
「あんな至近距離から『にゅーん』してもらっておいて苦笑いなんて! ふざけてんの?」
「嫉妬した! 氏(し)ね!」
みんなすごい剣幕だ。死ねとまで言われてしまった。
怖気づいていると、ずっと僕のことを待っていたらしい栗本さんが、よく通る声で助け船を出してくれた。
「よってたかって責めたら乃木坂くんがかわいそうだよ。話を聞いてあげようよ。ね?」
彼女の優しさに免じてか、みんなは黙って僕の言葉を待つ。
えっと、何か言わなきゃ。言わなきゃ殺される。
「あ、あの子誰なんですか?」
「はぁー!?」
全員が叫ぶので、思わず肩をすくめてしまった。こういうおどおどした態度が馬鹿にされる原因なんだって分かっているのに……。
栗本さんの隣にいた人なんか、真っ青になって――えっ、気絶した!? 僕そんなひどいこと言ってないよね!?
池田くんが呆れたように言う。
「いや、だって毎日CMに出てるじゃん!」
「僕んちテレビなかったから……」
「世歴二〇四三年のこの時代に、テレビがないだとっ!」
今度はショックを受けている。よく表情が変わる人だ。
「そうか、いろいろ大変なんだな……。まあ、家帰ったら『くるたん』でネット検索してみろよ」
「……実はパソコンもないんだ」
「えええええ!?」
池田くんは悲痛な面持ちで僕を見た。何かもうすっかり憐れまれている気がする。
「じゃあ教室のパソコンで見せてやるよ! いくらクタオでも、くるたん知らないなんてかわいそすぎるぜ」
そういうが早いか、池田くんは教室に戻っていった。慌てて追いかける僕。
みんなが夢中になる『くるたん』とはいかなる人物なのか。
これはクタオから卒業するチャンスなのかも知れないと、少し胸を弾ませた。
パソコンが立ち上がるまでのわずかな間に、池田くんから聞いたこと。
「俺のフルネームは池田綿三(めんぞう)! 略してイケメンと呼んでくれ」
えっと、遠慮しておくね。
「くるたんは通称で、本名は東条胡桃(くるみ)。ああ見えても俺らと同い年。何でも、昔かかった病気で成長が止まったとか……」
かわいそうに。辛いだろうなあ。
「くるたんは国民的、いや、世界的アイドルなんだぜ! 三十億人のファンがいる」
さ、さんじゅうおく……。
「ちなみに俺はオフィシャルファンクラブ会員七四八番だ!」
三桁ってさりげなくすごい。
「くるたんはいろいろやってるけど、一番目に挙げるとしたら歌手だな。声優俳優モデル作曲作詞、一通り経験あるはずだ。ネットでの活動が大半で、世界中に萌えを配信しているってわけ」
そんな偉人を知らなかった自分の無知に呆れ果てる。故郷は本州西端の岩口県、バスも通らない田舎で、テレビも新聞もない世間離れした生活を送っていたため、僕は流行や大衆娯楽に疎い。それは覚悟していたつもりだけど、こんなに常識がないとは思っていなかった。
「芸能活動も忙しいだろうに進学して大丈夫かって噂もあるけど、まあくるたんは天才だから、両立していく自信があるんだろ。というわけでパソコン立ち上がったぞ」
池田くんは僕に席を譲った。座りながら画面を見ると、『くるたんのおもちゃばこ』というサイトが表示されている。
「これが公式サイトだ。なぁ、萌え萌えだろー?」
桃色を基調としたファンシーなデザインだ。東条胡桃を模した萌えキャラのイラストが貼ってある。普通の芸能人だったら「イタい」と一蹴されてしまいそうだが、彼女に限っては元がアニメ的容姿なので違和感がない。アクセスカウンターを見ると、今日だけですでに六億のアクセスがあった。
「これが……萌えか……」
これは確かにハマりそうだなんて思っていると、後ろから栗本さんに声をかけられた。
「はい、もうおしまいだよー」
「へっ?」
「昼休み終了十分前にはパソコンの電源を切り、元通りカバーをかけておくこと。って書いてあるでしょ?」
壁にかかっている『パソコンの使い方』には確かにそう書いてある。そんなところまで熟読しているとは、さすがクラス会長。僕と池田くんはその手順に従ってパソコンをしまい始めた。
「乃木坂くんは、東条胡桃のファンになった?」
栗本さんは唐突にそんなことを訊いてきた。
「え……ううん、まだだけど」
ためらいながらも正直に答えると、彼女は静かに「そう」とだけ呟いた。生温かい笑顔からは感情が読み取れない。てっきり「ファンになってないなんてありえない!」とか言われるんじゃないかと思っていたので、この反応は意外だった。
「いいんだよ、乃木坂くんは乃木坂くんのままで」
なにその意味深なセリフ。
戸惑う僕を置いて、彼女は自分の席に戻っていった。
放課後、僕は言われた通りに一人で体育館裏に向かった。体育館裏と聞くと、中学校で「国賊(クタオ)」と罵られてリンチされたことを思い出す。嫌な響きだ。いくら僕が運動音痴でも、 幼女に負けたりはしないはずだけど。
約束の場所に彼女はいた。フリルやレースで飾られた少女の存在は、薄汚れた体育館裏には驚くほど場違いだった。そこだけぼんやりとした光に包まれているような錯覚に襲われる。東条さんは、僕の方を見て小さな手を振った。
「ボクが乃木坂を呼んだのは、テストをするためなの」
「テスト?」
「そ。テストはトクイでしょ? 今からボクがすることを、目を離さずにずっと見ててね!」
そう言うと、彼女は「みゃー」とか「ぴよぴよー」とか、可愛いんだけど意味の分からない奇声を発しながらポーズを取り始めた。正直、どんな反応をしたらいいのか分からない。
三分くらい経っただろうか、東条さんは疲れた顔に喜色を浮かべた。器用な顔だな。少し息が上がっている。
「乃木坂は、なんともない?」
「えっと……どうなると『なんともある』状態なの?」
「ボクのことが可愛すぎてほっぺた落ちそうになったら。よーするに、ボクに萌えたら!」
「なんともないよ」
僕はその時の彼女の顔を一生忘れないだろう。
くりくりした大きな瞳をさらに大きく見開いて潤ませたかと思うと、次の瞬間には泣き出しそうな笑みを称えて、今までとは違う口調でこう言ったのだ。
「ボクはずっと、お前のような人間がほしかった」
第一に、東条胡桃は「ディーヴァ」という人造人間である。
第二に、東条胡桃は世界征服を目指している。
第三に、歌姫救世伝説は事実である。
まず僕は、上記の三つを前提として話を聞くことを強要された。
「そうじゃないと全然話なんかできないからな。あ、あと、この話は他言するなよ、いちおー秘密事項なんだから」
「分かったけど……東条さん口調変わってない?」
「これが素だ」
素の東条さんは、見た目に反してふてぶてしい喋り方をする。
「乃木坂にしか素で話せないんだからな! ありがたくハイチョーしろ!」
少し舌足らずなところが可愛らしい。
世歴一九九七年、戦前から萌え産業の頂点に立っていた大手企業カラープロダクションの色川社長には、二十歳になる息子がいた。
息子――色川拓也はニートだった。
彼は孤児院を運営する叔母夫婦のもとで非生産的な生活を送っていた。
そんなある日、彼は近くの雑木林に謎の発光体が落ちるのを目撃した。叔母に話してもアニメの見すぎと言われる始末だったが、気になった彼は一人で確かめにいく。そこには、この世のものとは思えないほど美しい黒髪の少女が倒れていた。まだ十にもならない子供だった。
少女はアニメの展開のように記憶を失くしていた。色川拓也は彼女を「かぐや」と名づけ、孤児院で面倒を見てやった。無気力だった彼の生活に、色彩が戻ってきた。
「何だその顔は」
東条さんは僕の怪訝そうな顔を見て話を中断した。
「ウソだとでも言いたいのか?」
「……言いたいけど、やめとく」
「ウソだったらもっとうまい話を作るぞ」
「それもそうだね」
かぐやの声、特に歌は不思議な効能を持っていた。
歌を聴いた者は皆萌えたのだ。
萌えを軽蔑する者も、怒り狂った者も、たちどころに萌えてしまう。
色川拓也は、物理的要素以外の何かが働いていると仮定し、その力をMP(Moe Power)と名づけた。
そして第三次世界大戦勃発。
色川拓也はかぐやに、戦地で歌を歌って世界を平和にする計画を提案した。始めは渋っていたかぐやだったが、自分だけが世界を救えるというロマンに惹かれたのだろう、ついに計画を実行に移した。
色川はかぐやを愛していた。それは父性愛でも少女愛でもなく、純粋なる「萌え」の魂だった。強すぎる萌えは崇拝心を生む。彼は己の中で、かぐやを神に近しいものへと昇華させていた。世界を救えば、彼女は救世主として崇められる。新世界の神にもなれる。皆が共通してかぐやという一人の美少女を崇める世界――。アニメ的楽園を、彼は夢見ていた。
しかし悲劇は訪れる。終戦間際、かぐやと色川拓也は錯乱した民間人に銃撃された。色川が目覚めると、そこは病院だった。かぐやも一命を取り留めたが、目覚めることを忘れたように眠り続けた。
かぐやの寝顔を見つめながら、色川は誓った。
MPを使って世界を統治しよう。
かぐやが果たせなかった夢を、この命が尽きるまでに必ず実現させよう、と。
それはかぐやの夢などではなく自分の願望でしかないのだと気づくのは、まだ先のことである。
「萌えというのは、ひじょーに便利な位置にある」
「どういうこと?」
「人類の戦いの歴史にはシューキョーの影が見え隠れしているだろ? 信念の相違、これこそが人類の脅威。でもこればかりは抑えつけて統一することもできない。じゃあどうするか。そこで萌えの出番だ。戒律の厳しい一神教でも、萌えはシューキョーじゃないから気兼ねなく夢中になれる。萌えは、シューキョーの異なる人間が神を越えてつながれる、新しい概念なんだ。浅く広く世界中を包み込む新素材、人類の進化によって生み出された最終自己防衛装置、それが萌えなのだ!」
幼稚園児の声で壮大な話してる……。
亡くなった父からカラープロダクションと莫大な財産を受け継いだ色川は、企業の再興を図るかたわら、優秀な研究者を雇い、かぐやのクローンを作ろうとしていた。
だが、色川が結婚して子供をもうけるほどの月日が経っても、かぐやのクローンは生まれなかった。研究者が出した結論はこうだ。
かぐやは地球の生命体ではない。
だから地球の重力下ではクローン胚は成長しない。
研究者たちはやけになって言ったのかもしれないが、色川は大真面目にこれを受け止めた。すなわち、空から落ちてきた発光体はやはりUFOだったのだと。
「ええ!? かぐやさんは宇宙人だったってこと?」
「あくまで仮定だがな。まあ、うちゅーじんくらいいないとMPの説明がつかないし、いいじゃん、うちゅーじんってことで」
真実はどうであれ、物理法則では説明のつかない力を持っていることは信じよう。かぐやさんは実際に、萌えで戦争に対抗したのだから。
かぐやが眠りについてから十年経った。
かぐやのクローンを諦めた色川は、新たな計画を立てた。かぐやの細胞からMPを発生させる特定の遺伝子を抽出し、それを組み込んだ美女のクローンをかぐやに代わる歌姫として誕生させるというものである。彼はこの人造人間をディーヴァと呼んだ。
もちろんクローン人間生成は大罪である。これを揉み消すだけの資金と人脈があったからこそ、この計画は成り立ったのだ。カラープロダクションの裏社会での影響力は、すでに揺るぎないものとなっていた。
その間にも、カラープロダクションは、戦争で破壊された世界中の文化の隙間に萌えを浸透させていった。
「これ、犯罪だよね」
「そう、犯罪だ」
「……」
「告げ口したら、カラプロの刺客がお前を消すだろう」
「……聞かなければよかった……」
「ボクはずっと誰かに言いふらしたかったんだ。あーすっきりするー」
後戻りはもうできない。
誕生したディーヴァたちには、カラープロダクションの名にあやかって、色名が入った名前が送られた。だが、計画発足から十数年が経過しても、MPを持つディーヴァは現れなかった。失敗作のディーヴァたちは、何も知らないまま三歳で一般人へと回帰した。これは、人道的視点を捨て切れなかった色川の配慮でもあった。
そんな中、二十三年の眠りを終え、かぐやが覚醒した。実年齢は三十を越えるはずの彼女の身体は、十代後半の若さを保っていた。
色川は狂喜乱舞して、これでディーヴァなどという紛い物を使わなくて済むと安心した。ところが、かぐやは身体は大人でも心は十歳のままだった。
――どうしてまた歌わなければならないの? あんなに痛い思いをするのに。
その言葉に、色川は嘆き悲しんだ。神々しいあの歌姫はもういない。今ここにいるのは、ただの臆病な少女だ。
色川は、後遺症が残るかぐやを幽閉し、再びディーヴァの製造にいそしんだ。
――今度はもっといい子に育てよう。
それでもかぐやを自由にしなかったのは、まだ彼の中に理想の萌えとしてのかぐやが残っていたからかも知れない。
数年後、かぐやは色川の一人息子純人(すみと)と駆け落ちし、姿をくらました。
「え、そこさらっと通り過ぎたけど、駆け落ちしちゃったの?」
そんなあっさり駆け落ちされて、色川さん、いたたまれない感じ。
「うん。それでかぐやを使った世界征服は完全に不可能になって、ディーヴァを作るしかなくなったんだ。パパ……あ、色川しゃちょーのことな。パパはすっごく落ち込んだらしい。でも、その次の年、ボクという希望の星が生まれたんだ!」
東条胡桃は、研究員東条胡都(こと)のクローンから作られた最終世代のディーヴァだった。この世代が駄目なら、この方法はいたずらに人造人間を作ることと変わりないとして、一時中断さえ考えられていた。
彼女も他のディーヴァと同様に三歳の時点ではMPが見られなかったが、東条博士が親として世話をしていたため、六歳になってからMPが発現したことが分かった。
他のディーヴァも六歳になればMPを得たのか、それとも胡桃だけが特別だったのかは分からない。ただ一つ色川に言えたのは、胡桃を世界的アイドルに育て上げ、萌えで世界を統制するという目標ができたということ。それは一種の世界征服。誰一人犠牲にしない理想的手段。
計画発足から、二十年近くが経過していた。
胡桃は東条博士に似て聡明で、色川の大志をすぐに理解した。類まれなタレント性が、かぐやより弱かったMPを見事にカバーし、彼女はあっという間に大スターの座にのし上がったのだった。めでたしめでたし。
「最後の方はただの自画自賛だったような……」
「何を言っている、事実を述べただけだ。で、今から本題に入るが」
「今までのは前置き!?」
これ以上どんなファンタジーが待ち受けているというのだろう。うろたえる僕に、東条さんはビシっと指を突き付けた。
「ボクはお前がほしい」
その声がやたらと真剣だったので、思わずリアクションも忘れて彼女を見つめる。東条さんは僕の視線に気づくと、真っ赤になって手を振り回した。
「な、何見てるんだバカ! 変な意味で言ったんじゃないぞバカ! 期待するなよバーカ!」
一人でぱたぱた慌てふためいている東条さんは、腕が回るぜんまい仕掛けの人形のようで、見ていて面白い。やがて動き疲れたのか、ぽてっと腕を落として項垂れた。垂れかかった髪の奥から、外見年齢にそぐわない物憂げな表情が覗けてどきっとする。
「ボクの周りの人間は、MPを使うとすぐにのぼせて、まともに話だって出来ない。でも乃木坂にはMPが効かないだろ? ボクはずっと願ってた。誰かとふつーにしゃべってみたいって」
誰かと普通に喋ることが、世界に三十億のファンを持つスーパーアイドルの願い。
そっか。僕と同じなんだ。
ただ輪に入れてほしくて、きっかけを探してる。
遠い世界で威張っていると思っていた彼女が、すぐ近くに感じられた。
「つまり、友達になれってことだね!」
「ともだち?」
東条さんは、初めてその単語を聞いたかのように繰り返した。
「そっか。ボク、ともだちがほしかったのか」
そう呟いて、大きな瞳で見上げてくる。
「乃木坂、ボクのともだちに……」
おずおずと差し出される小さな右手。僕も手を伸ばして――
「やっぱりだめええぇぇ!」
――思い切りはじかれた。
「アイドルはみんなのものだ! 一人の人間をひいきするなんて許されない! ……でも、下僕ならだいじょーぶだ」
それはつまり、僕に下僕になれと? 大真面目に言っているのが怖い。
「この学校、バイト禁止だよ?」
「下僕はバイトではない。なぜならムキューだからだ」
無給の下僕って……それは奴隷って言うんだよ。
「もう逃げられないぞー。秘密事項をベラベラ喋ってやったからな!」
「あの前置きは拘束手段!?」
勝ち誇ったようにけらけら笑って、東条さんは僕に抱きついてきた。身体が幼児だから、異性に対する意識とかもないんだろうか。僕は戸惑ったが、彼女を突き放したりはしなかった。
だって東条さん、本当に幸せって顔してるんだ。
「MPは効かない、アタマはいい、最高の下僕じゃないか! 乃木坂、ボクのげぼくーっ!」
どうして僕にこの笑顔を無下にすることができようか。
世間の鼻つまみのクタオに会えて喜んでる。
僕なんかでいいのなら。
違う。僕じゃないと駄目だから。
下僕にでも何でもなってやる!
「乃木坂ーっ、ばいばーい!」
それから数分後、東条さんは精悍なガードマンに連れられて帰っていった。ガードマンの前ではぱっとアイドルモードに切り替わるあたり、プロの心意気を感じる。
そう言えば、ガードマンでもMPにかかればデレデレになってしまうのか。それを考えると、東条さんはよく今までそんな環境で耐えてきたと思う。自分を囲む人々が皆デレデレしている光景なんて、想像するのも恐ろしい。
校門へ向かいながら、「下僕」の仕事について考えてみた。
跪いて主人の足をなめる。
鞭で打たれる。
過労死する。
……。
下僕の何たるかを学ぶため、帰りがけに本屋で『スーパー下僕道』(七四〇円)を買った。これで少しでもいい下僕になって、東条さんを支えてあげるんだ。