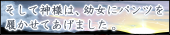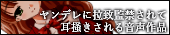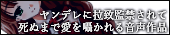第七章 はあと
――食べられた!
僕は瞬時にそう思った。
朦朧とする意識の中で、口内を貪る栗本さんの存在だけが浮き彫りになっている。こんなに乱暴ってことは、すごく怒ってるんだ。恐怖で息ができなくなる。酸素が欲しい。心臓の音が耳の奥で聞こえる。体が熱い……。
何も考えられなくなったころに、ようやく僕の唇は解放された。新鮮な空気を求める体は、自然と小刻みに喘いでしまう。口呼吸できるようになっても、栗本さんが腰にまたがっている以上、肺の圧迫感は癒えない。
栗本さんは頬を赤らめて僕を見下ろしていた。憤怒の形相かと思いきや、満ち足りた幸せそうな顔だった。人差し指でうっとりと唇をなぞる。
「乃木坂くんは、これがファーストキスだよね? キリエもこれが初めて。まあ、キリエにキスなんかされたら、普通の人は即死だけど。どうだった? 気持ちよかった? 毎日イメージトレーニングしてるから、結構自信あるんだよ」
「ふぇ……? いまの……キス?」
ぼんやりとしていた僕は、つい思ったことを口走ってしまった。
「違うよ、キスっていうのは、お父さんとお母さんがチュッてするあれでしょ? 今のは全然違う。栗本さんは僕のことを食べようとしたんじゃないの?」
僕はすぐに後悔した。こんなことを言って下手に刺激したら、また乱暴されるかも知れない。おそるおそる栗本さんと目を合わせると――。
何故か彼女は照れていた。
「やだー、乃木坂くん、どこでそんな言葉覚えたの? ふふ、大人のキスも知らないくせに。そんなに言うなら食べちゃおうかな? そしたら乃木坂くんはキリエのものだもんね」
確かに、僕を食べて消化吸収すれば栗本さんの骨肉になるんだから、その理論は間違ってないけど……。交際を断られただけでそんな極論に達するなんて、そんなに僕のことが好きなのかな。人から好かれるのはありがたいことだけど、彼女はまず病院に行くべきだと思う。
栗本さんは僕の頬から胸にかけてをそっと撫でた。今度は何をするつもりだろう。先ほどの恐怖がよみがえって涙がにじむ。
「世界で一番乃木坂くんを愛しているのは、絶対にキリエなんだから」
「いやぁ……食べないでぇ……」
食い殺されて終わりなんて嫌だ。怖い。
「誰にも渡さない」
低い囁きが、僕には死刑宣告のように聞こえた。
その時、誰かがドアを開け放った。
「あ……」
僕からは見えないが、来訪者は僕と栗本さんの態勢を見ているのだろう。驚くのも無理はない。人が食べられる瞬間なのだから。
「あなた一体何を……!? 乃木坂さんから離れてください!」
それは、聞き覚えのある澄んだ声だった。
栗本さんは立ち上がって、来訪者――藤巻さんを睨みつける。
「あーあ、せっかくいいところだったのにぃ」
体が自由になった僕は、肩で息をしながらよろよろと立ち上がった。
「ふ、藤巻さん……怖かったよぅ……」
思わず泣き出しそうになりながら、栗本さんから距離を取って壁沿いに後ずさる。本当は藤巻さんの方へ行きたいが、今はできるだけ栗本さんを刺激しない方がいいだろう。
藤巻さんは気遣うように栗本さんを見ていた。
「栗本さん……どうしてこんなこと……」
「うるさい! 雪菜ちゃんにはキリエの気持ちなんて分からないよ!」
栗本さんは隠し持っていた喫茶店用のナイフを藤巻さんに投げつけた。ナイフは標的に突き刺さらんと飛んでいったが、藤巻さんの指の間に軽く挟まれて動きを止める。
「いけませんよ、危ないじゃないですか」
藤巻さんは穏やかに言ったが、目は笑っていない。
「ふぅん? その危ないモノを簡単に止めちゃう雪菜ちゃんは、もっと危ない人なのかな? 最初会った時から普通じゃない感じはしてたけど」
「奇遇ですね。私もです」
二人の間に異様な緊張感が流れた。お互い本能的に、ルルティナから受け継いだ『力』を感じ取っているのかも知れない。
「藤巻さん気をつけて! 栗本さんはディーヴァだよ! 常人の力じゃない!」
「分かりました。乃木坂さんは、東条さんのところへ行ってあげてください」
頷いて駆け出す僕の行く手に、栗本さんが立ちはだかる。
「行かせないもん!」
しゅん、と風を切る音と共に、藤巻さんの手刀が栗本さんの頭上を通り過ぎた。栗本さんが回避していなければ、首筋にクリーンヒットしていたところだ。
「ひっどいなあ。首は急所なんだよ?」
「あなたが私と同じなら、そう簡単には死なないはずです」
藤巻さんはそう言うが、きっと一般人に当てても致命傷にはならない程度に加減していただろう。藤巻さんが狙っているのは、おそらく栗本さんを無力化してできるだけ穏便に事態を収束させること。力になりたいのは山々だけど、栗本さんが激情に駆られているのは僕のせいだ。今できることはない。
「ありがとう、藤巻さんっ」
対峙する二人を残して、僕は栗本家を後にした。
***
二人の少女が対峙していた。
一人はメイド服、もう一人は機能的な黒服を着ている。張り詰めた空気の中、木梨枝が先に口を開いた。
「始めに教えてほしいな。どうしてここに来たの?」
雪菜は落ち着いた調子で答える。
「もはや隠すこともないでしょう。私はカラープロダクションの協力者です。イノセンスの動きを警戒してパトロールを行っていた時に、開け放しのドアの向こうに見覚えのある靴が転がっていたんです。確認したら、かかとに乃木坂さんの名前が書いてありましたよ。あの人らしいです」
「でも、ただキリエの家に遊びに来ただけかも知れないじゃない。それを詮索するのはどうかと思うな」
「開け放しのドア自体が尋常ではありませんし、よほどのことがない限り、乃木坂さんが靴を乱れたまま放置するということはあり得ません」
木梨枝は興味深げに雪菜を眺めた。目の奥に暗い光を宿して。
「そっかぁ、よく見てるんだね、乃木坂くんのこと。好きなの?」
「……尊敬しています」
「それだけ? 雪菜ちゃんを見てれば分かるよ。無関心を装って、学校ではいつも乃木坂くんのこと気にかけてたよね」
木梨枝の精神状態に危うさを感じた雪菜は、努めて穏やかに振る舞う。
「落ち着いてください。私はただ、乃木坂さんの意思を尊重していただきたいだけです」
「そんなこと言って、ほんとはキリエから乃木坂くんを取り上げようとしてるんでしょ? 騙されないんだから!」
叫びざまに木梨枝は雪菜に組みついた。彼女の能力が雪菜から体力を奪う。
「……っ」
「あははっ、どう? 苦しい? 苦しいよねぇ、キリエの体は人を殺すんだよ」
雪菜は苦悶の表情を浮かべたが、すぐに木梨枝を体から引きはがした。荒く息をつく雪菜を見据えて、木梨枝はふんと鼻を鳴らす。
「口ぶりを聞いてると、藤巻さんもディーヴァなんだよね。さすがに普通の人みたいに一瞬で卒倒とまでは行かないなぁ」
傷を負えば自動的にルネサンスで再生する雪菜の体だが、今のダメージは自動修復の対象外だったらしい。自らの意思でルネサンスを発動させ、体調を整える。その様子を見ていた木梨枝は黄色い声を上げた。
「すごーい! 雪菜ちゃんはキリエと逆で、治す超能力をもらったんだね。いいなぁ、うらやましいよ」
普通に教室で談笑しているかのような話し方だが、ところどころに暗い感情が見え隠れしている。雪菜はいつでも反撃できるように警戒を強めた。
「雪菜ちゃん、タナトスって言葉知ってる?」
「死への欲求、ですね」
「そう。キリエは別に命を『吸い取っている』わけじゃない。それなら、みんなが死に向かうのは、キリエにさわられると肉体が持つタナトスが目覚めるからなんじゃないかって思うんだ。世界の仕組みがそういう風にできてる。キリエはきっと、世界そのものから嫌われてるんだね。雪菜ちゃんも、教室では仲良くしてくれたけど、本当はキリエが嫌いなんでしょ? だから邪魔をするんだ」
「それは違います。友達だから、止めるんです」
それを聞いて木梨枝は高らかに笑い声を上げた。ひとしきり笑いを吐き出してしまうと、ふっと表情を破棄する。そして、蔑むような視線で雪菜を射抜き、低い声で言い捨てた。
「偽善者のくせに」
「……!」
「ふふっ、その善人面剥いだら、何が出てくるんだろうね!」
彼女は前進し、勢いを乗せて手刀を打ち込む。雪菜は予想外の素早さに一瞬たじろぎながらもバックステップで回避し、間合いを取った。木梨枝はテーブルの上に置いてあった皿を雪菜に投げつける。高速の飛び道具と化したそれを雪菜はたやすく受け止めるが、短く呻いてうずくまってしまった。皿の割れる音が響く。
「そのお皿にはタナトスの力を纏わせてあるんだよ。雪菜ちゃんの体、いつまで持つかなぁ?」
再生する間もないまま、続けて飛んできたフォークが雪菜の右胸に突き刺さる。
「くっ……ぅ」
「あぁ、ごめんね? 女の子の大事なところなのに」
雪菜は激しく肩を上下させながらフォークを抜き取った。血が流れ出すが、ルネサンスの光と共に傷は塞がる。しかし、彼女には目に見えないダメージが蓄積していた。脳の状態を「再生」すると記憶が飛んでしまうため、脳だけはルネサンスの守りから外れてタナトスに蝕まれているのだ。
廊下へと続くドアの向こうに駆け込む雪菜を、木梨枝の狂気じみた声が追った。
「どうしたどうした! 逃げるしか能がないの?」
木梨枝は部屋にある限りのフォークを服に忍ばせてから部屋を出る。廊下は複数の部屋につながっているが、物音がしたのですぐに行き先は分かった。店の方だ。
愛しいあの人を手に入れる、その前に邪魔者を排除する。何かに追い立てられるように、彼女の心はそれだけを考えていた。
扉を開けると、そこには誰もいなかった。可愛らしい丸テーブルがいつも通り静かに並んでいるだけ。油断して三歩進んだところで、
「かはっ」
床にひれ伏してから状況を把握する。扉の影に隠れていた雪菜に、モップで殴り倒されたのだ。
雪菜は木梨枝に直接触れないように、モップで背中を押さえつけた。
「待ち伏せなんてずるいよぉ……」
「すみません。でも、再び乃木坂さんを襲う可能性がある以上、あなたを放っておくわけにはいかないんです」
雪菜の顔を見上げた木梨枝は、今にも泣き出しそうな声で哀訴する。
「あの日からずっと、乃木坂くんへの想いがキリエを支えてきた。乃木坂くんがいなかったら、キリエはきっといじめられっ子のまんまだったよ。ねぇ、分かるでしょ? キリエには乃木坂くんしかいないの。こんなに好きなのに、何で邪魔するの? そんなにキリエのことが嫌い?」
「そういう問題じゃありません。栗本さんは一方的すぎます。本当の愛というのは、相手のために行動するものではないのですか? 先ほどのあなたの行為は乃木坂さんを怯えさせただけです」
「そんなの分かってるよ!」
木梨枝は声を荒げると、続けて憎々しげに呟いた。
「雪菜ちゃんにはキリエの気持ちなんて分からないよ。可愛くて優しくて、何でも思い通りになりそうな雪菜ちゃんには」
雪菜は答えなかった。
重苦しい沈黙を破り、遠くでファンファーレが鳴り響く。
「東条胡桃のトークライブが始まるね。雪菜ちゃんはMP効く?」
「いいえ」
「なぁんだ。キリエも効かないから、雪菜ちゃんが骨抜きになったすきを突いてやっつけようと思ったんだけどなぁ。ディーヴァにはMP効かないのかもね――残念!」
木梨枝は袖から取り出したフォークを上方に放った。
雪菜はとっさに身をかわすが、同時に木梨枝を解放してしまう。木梨枝はにやりと笑い、五本連続でフォークを投げた。雪菜はモップでそれらを弾き飛ばし一気に間合いを詰める。木梨枝は素早く新たなフォークを構え、得物を振り上げる敵の脇腹を狙った。が、雪菜の方が早かった。
キン! 冷たい金属音を残して、彼女の手からフォークが叩き落とされる。
雪菜はそのまま大きく踏み込み、熾烈な突きを繰り出した。モップの柄が木梨枝の腹部にめり込み、体を吹き飛ばす。木梨枝は手前の丸テーブルにぶち当たってうずくまった。
「最後のチャンスです。落ち着く気はありませんか」
雪菜の問いに、ゆらゆらと立ち上がった木梨枝は迷いなく答える。その瞳は信念と言うよりは妄信に彩られていた。
「ないよ。雪菜ちゃんに勝たなきゃ、キリエは幸せになれないもん」
雪菜はその意味を測りかねたが、すぐにこの場に意識を集中させた。木梨枝が放った二本のフォークがまっすぐ雪菜に飛んでくる。しかし彼女はよけるでもなく、さらにモップを手放した。
雪菜は左右の手を交差させてフォークを掴み取り、平然とした顔で木梨枝を見やる。ワンテンポ遅れて、モップが音を立てて床に倒れた。
「どうして!?」
「遅まきながら気づきました。このフォークだって、過去の状態に戻せばただのフォークになるんです」
木梨枝は狼狽していた。相手は素手では自分に触れてこない。投擲物にタナトスの力を込めても、ルネサンスで「なかったこと」にされてしまう。戦闘技能そのものは雪菜の方が一枚上手。タナトスの力が届かないなら、自分は圧倒的に不利になる。
「わああぁぁっ!」
彼女は倒れている丸テーブルを掴み、叫喚しながら力任せに投げつけた。雪菜は大きく跳躍して宙を舞う。美しい髪を翻しながら空中で身をひねり、フォークを構えて、ある一点に狙いを定めた。
弾丸のような勢いで、フォークはシャンデリアの基部を破壊した。
豪奢なシャンデリアはダイアモンドのように輝きながら木梨枝の上に落下する。
――。
ガラスが粉々に砕け散り、再び静寂が訪れた。
動かなくなった木梨枝に雪菜は話しかけた。
「痛いでしょうが、意識はありますね?」
かすかにすすり泣く声が聞こえる。シャンデリアの破片は木梨枝の肌を切り裂き、体中に裂傷を作っていた。
「目は醒めましたか?」
「ごめ……んなさい……」
木梨枝は今までになく弱々しい姿を見せた。心の奥底に隠れていた弱い本性が、砦を失って外の世界に現れたのだ。
「怖かったんだ……。初め会った時から、雪菜ちゃんが怖かった。キリエは全部負けてるって思った。雪菜ちゃんが放課後乃木坂くんに会ってるとこもこっそり見てた。雪菜ちゃんはいい子だから、きっと乃木坂くんはすぐに好きになっちゃう。キリエは焦ってた。一度他の女の子とつき合い始めたら、乃木坂くんは一生キリエになんか振り向いてくれないんじゃないかって。雪菜ちゃんは悪くない。悪いのはわがままなキリエの方。ごめんね、タナトス、苦しかったよね……」
雪菜は静かに彼女の懺悔を聞いている。
「あんなことしたら乃木坂くんに嫌われちゃうだろうなって、分かってた。だけど、他にどうしたらいいのか分からなかったの。だって、乃木坂くんを失ったら死んじゃう。キリエにも居場所があるって、そう信じさせてくれたのは、乃木坂くんだけだったから。でも、違うって分かったよ。キリエの居場所なんて、ないんだ」
木梨枝は嗚咽に声を詰まらせた。
「世界はキリエが幸せになることを許さない! キリエが欲しいものは、全部手からこぼれ落ちていく。大好きだったお父さんはキリエを気味悪がって家を出て行っちゃった。お母さんはびくびくして、キリエに近づこうともしない。クラスのみんなも結局は東条胡桃に夢中。乃木坂くんだって、いつかは……」
雪菜は彼女の上のシャンデリアをどかし、上半身を抱き起した。そして優しく抱きしめる。柔らかな感触に驚いた木梨枝は小さく声を上げた。
「えっ、な、何して……?」
「安心してください」
彼女の体はまばゆい光を帯びていた。連綿とルネサンスを身に纏って、木梨枝の体から滲むタナトスの力を相殺しているのだ。それだけではない。木梨枝は自分の傷までもが癒されていくことに気づく。我が子を慈しむような雪菜の細腕が、木梨枝に安心感を与える。
見渡せば、辺り一面が温かなルネサンスの光に包まれていた。範囲が広いため一瞬でとは行かないが、ゆっくりと店が元の姿を取り戻していく。壁に刺さったフォークは抜け落ち、その歪みさえ正された。二人の周囲に散らばるガラスのかけらは、煌めきながら浮き上がり、天井でシャンデリアとして結合する。幻想的な情景に、木梨枝は夢を見ているような気分になった。
「栗本さんなら大丈夫です。今からでも手に入りますよ。ぬくもりも、幸せも」
それは雪菜自身が身をもって知ったこと。
命と心があれば、未来は切り開ける。
「乃木坂さんとは、ゆっくり親交を深めてください」
「応援してくれるの? キリエ、あんなひどいことしたんだよ?」
雪菜はにっこり笑って見せた。曇り一つない、澄み切った笑顔だった。
「もう仲直りです。だって私たち、友達じゃないですか」
木梨枝は自分から雪菜に抱きつき、幼子のように泣きじゃくった。胸に抱えていた苦しみが、全て流れ出てしまうくらいに。
***
僕は栗本さんに連れられてきた道を引き返していた。
途中で華やかなファンファーレが鳴り響き、びっくりして飛び上がるが、すぐに東条さんのトークライブが始まる合図なのだと気づく。急がなくちゃ。道順は全部覚えていたので、迷うことなくポスターの位置まで戻ってこられた。
『神聖アキバ帝国建国祝典開催! くるたんの路上トークライブはあちら→』
ついさっき見たばかりなのに、このポスターがやたら懐かしく感じられるのは何故だろう。僕は矢印の方向に小走りで進む。
あの二人、大丈夫かなあ……。栗本さんは何だかすごく思い詰めている感じだったし、藤巻さんもあの状態の栗本さんを放っておくとは思えない。非力な女子高生同士ならまだしも、二人は高い運動能力の持ち主だ。殴る蹴るの喧嘩になったらお互いただでは済まされない。藤巻さんにその気がなくても、栗本さんが暴走したら乱闘に発展する恐れがある。
栗本さんは、きっと何かショックなことがあったんだよね。明日になって、心が落ち着けば、いつも通りの元気なクラス会長に戻ってくれる。ずっとあのまま治らないなんてことはない、よね。
僕はもう一度平和な日々を取り戻したい。でも、今僕にできるのは、東条さんのライブを遠くから見守ることだけ。僕は非力だ。トークライブには大勢の観客が来ているから、最前列まで行って東条さんに会うこともできない。
それでも0と1は違う。
僕はあきらめない。できるだけ早く色川社長の信頼を取り戻して、東条さんと絆を結び直す。そしてもう一度下僕にしてもらった暁には、今日の話をするんだ。素晴らしい祝典だった、僕は見ていたよって。そのためには、いてもいなくても変わらないような人混みの中であっても、僕はそこにいるべきだ。
ようやく僕は会場らしきビル街についた。と言っても、人が多すぎて東条さんの姿はおろか、前方三メートルさえ見通しがつかない。何万人あるいは何十万人いるのか分からない人々の背中のずっと向こうから、東条さんの可愛い声だけが聞こえてくる。
「このなかで、もう国民証もらったよーってひと、どのくらいいますかー?」
はーいと声を上げ、僕の周りの人が一斉に手を上げる。すごい、もうこんなに!
「はーいっ!」
ひときわ威勢がよく、その上聞き覚えのある声がした。何と、すぐ近くで池田くんが手を挙げていた。ちょうど隣にいた人の影で隠れていたようだ。
「池田くん、こんにちは」
声をかけたら、「おお」と嬉しそうに笑ってくれた。
「お前も来たか! やっぱり、くるたんのよさを知るにはライブが一番だよな! つっても、この位置からじゃよく見えねぇけど。なあ、俺よく見える場所知ってんだけど、乃木坂も一緒に行くか?」
あまりの幸運にびっくりして、思わず訊き返す。
「いいの!?」
「いいとも!」
「行く! ありがとう!」
僕は池田くんの親切に甘えて、彼の後についていった。
***
ぼくはノクターンの一員としてではなく、イノセンスの代表者として角谷さんとOp.4を出迎えた。Op.4は布でくるまれた大きな荷物を肩に担いでいる。
「おお、持ってきてくれましたか。ご苦労さま」
荷物を受け取ろうとしたら、彼は「重くて朝比奈さんには持てないよ」と笑って、部屋の中まで持っていってくれた。
「彼が持つと軽そうに見えるんですがねぇ」
「当然さ、あたしが鍛えてるんだから」
角谷さんはOp.1に逃げられたというのに、何故かあれ以来ぴりぴりとした雰囲気が抜けて、何歳も若くなったようだった。
「最近機嫌がいいですね」
「そうかい? まあ、ふっきれたって言うかね……」
やけに艶っぽい反応をされて戸惑っていたところに、Op.4がやってきて茶々を入れる。
「角谷さん、本当にやりたかったことが分かったんだって。結婚して子供生みたいんだってさ」
「ば、馬鹿! そんなこと人に言うんじゃないよ!」
「これから合コン行って、いい男ゲットしてくるんだって」
「やだ、やめなって!」
ぼくは愉快な気分になった。これこそが自然な人間の姿。望みを持つ者はみんな美しい。
「はっはっは、なら早く行ってください。あなたの望みが叶うことを祈っていますよ」
「あ……ありがと……」
顔を真っ赤にした角谷さんと、ちょろっと舌を出しておどけるOp.4を見送ってから、ぼくは届いた荷物の布をはぎ取った。
現れたのは不思議な機構が仕込まれた装置だった。ノクターンの資金と技術力を借りて開発してもらった、ぼくの望みを叶える鍵。初めは東条胡桃に萌えなくなる装置が欲しいと思っていたが、偶然の発見から生まれたこの装置はそれ以上の価値を持っている。
このスイッチを押せば、東条胡桃は地獄を見ることになる。彼女の心には大きなトラウマが残るはずだ。ひょっとしたら死ぬかも知れない。少なくとも、芸能活動を続けていくことはできなくなるだろう。
秋波原跡に集結した何十万という人々は、この歴史的瞬間の当事者になるのだ。ぼくは心の中で、恍惚と彼らに語りかけていた。
東条胡桃がいなくなれば、彼女に支えられている脆弱な平和などあっという間に崩れます。そうしたら、みんなで人類の無罪と自由を謳歌しましょう。法律なんて東条胡桃の萌えに比べれば大した枷にはなりません。世界中の人間が、東条胡桃から解放された反動でそれに気づくでしょう。ぼくはその時が楽しみでなりません。人類の向かう先は平和か滅亡か、命ある限り見届けようではありませんか。
さあ、東条胡桃さん。
ぼくは本当のあなたを知りませんが、普通の女の子として生きるのも一興ですよ。これを機会に引退を考えてみてはいかがでしょうか。
――スイッチ・オン。
***
僕たちはデパートの屋上に向かっていた。
「俺の兄ちゃんここのそば屋で働いてるから、このデパートにだけは詳しいんだよ。屋上からならバッチリくるたんを見られるはずだ!」
何でも池田くんの家系は代々麺類の老舗を受け継いでいて、綿一(めんいち)お兄さんと綿二(めんじ)お兄さ んはすでに修行に出ているそうだ。移動している時に話してくれた。
ほどなくして僕たちは、さわやかな風の吹く屋上に到着した。早速フェンスの方に寄っていって下を見る。東条さんの衣装は天使のコスプレで、ステージの装飾も天国風だった。色とりどりの風船や、東条さんがトーク中に座るための大きな雲形クッションが見る者を和ませる。
装飾はステージ上に留まらなかった。ステージの周りのビルとビルにかけてはロープが数本張り巡らされており、旗や造花などの飾りが吊るされている。このビルの二階からもロープは伸びていた。旗は神聖アキバ帝国の国旗だろうか。白地の中心に天使の環を冠した桃色のハートが描かれており、その上部からは環をくぐるように新芽が萌えている。ハートの両脇にはデフォルメされた天使の羽根が添えられていて、とてもキュートなデザインだ。
「ありゃー、高すぎてよく見えねぇ」
僕は目がいいので、そんな旗の柄までばっちり見ていたのだが、池田くんには遠すぎたらしい。
「ま、何も見えないよりはいっか! 音も聞こえるしな。おーし、くるたんの萌え萌えなトークを聞こうぜ!」
東条さんは、歌とトークを繰り返して会場のボルテージを上げていった。今日は『ひとりぼっちの僕らは』のようなしんみりした曲は封印し、ポップで可愛らしい曲を中心にプログラムを組んでいる。とにかくみんなで盛り上がろうということだ。
東条さんがトーク中にMPを使ったり、MPを帯びた歌声が聞こえてきたりすると、池田くんは僕の隣りで「萌えー」と喜んだ。
「ほら、乃木坂も言ってみろよ、萌えーって」
脇から小突かれて、恥ずかしながらも言ってみる。
「えっと……もえー」
「そうそう、その調子だ! 『萌え』って口に出すと、世界が楽しく見えてくるから不思議だよな。生きてることが嬉しくなるっていうかさ。ってうをおおぉぉ! 今くるたんが手ェパタパタ振ったぁ! 萌えぇェぇうおおぉぉあぁぁ」
ものすごく萌えているのだと思っていたら、様子がおかしい。よく見たら、池田くんは人とは思えないほど滑稽な表情を浮かべて「うぼぁー」と奇声を発していた。
「えっ、どうしたの? 大丈夫!?」
滑稽と言うのはどの程度かと言うと、もはやお面であると言われた方が納得できるくらいである。具体的に示すと、顔をしかめたアルパカが大きく口をあけているような顔だ。
これは尋常じゃない。
滑稽を通り越して怖い!
彼は僕の言葉も理解していないようで、ひたすら呻きながらフェンスにガシガシぶつかっている。下に興味があるようだ。つられて見下ろすと、ビル街では凄絶な光景が繰り広げられていた。
観衆が全員池田くんと同じ状態になって、低い声を漏らしながら東条さんに向かって歩いている。まるでゾンビの波が押し寄せているようだ。東条さんは怯えて後ずさりするが、マイクを握り直して観衆に語りかけた。
「みんなぁ、どーしたの? ステージに来ちゃダメだよ! みーん」
MPを使えば使うほど、人々はよりゾンビのように蠢く。これはどうしたことか。MPの効用が変化している? 何故?
唯一分かるのは、MPの使用は逆効果だということ。しかし、東条さんはそれに気づいていない。MPを使えば人々をなだめられると思い込んでいる。
きっとミツルさんや色川社長もアルパカゾンビ状態だろう。東条さんを助けられるのは僕しかいない。
だがどうする。ここからでは無論声は届かない。あの群衆を掻き分けて東条さんのもとまで辿り着くだけの体力も、僕にはない。何とかしてステージ上に行けないだろうか……。
ステージ周辺を見渡すと、神聖アキバ帝国の国旗を吊るすロープが目に留まった。
一応、このビルから出ているロープはステージの上を通っている。
理論的には、あのロープを伝っていけばステージに行ける。
……。
近くで見てみて、それから考えよう。
池田くんをこの状態でほったらかしにしておくのは忍びなかったが、フェンスもあることだし屋上から落下するということはないはずだ。
「ごめんね。何とかするから」
僕は池田くんを残して階段を下りていった。
屋上から見た位置関係の記憶を頼りに、ロープのつけ根が外側にありそうな場所を割り出す。
窓から外をのぞくと、あった! 留め具は割としっかりしているように見える。人間がぶら下がっても耐えられるかどうかは甚だしく心配だが、これしか手は思いつかない。
……僕は体重軽いし、うん、きっと大丈夫。
僕は窓を開け放し、窓枠によじ登った。うわぁ、これだけでも怖い。少しでも足を踏み外したら、転落するか股を窓枠にぶつけるかして悲惨なことになる。僕は慎重にロープへと腕を伸ばした。試しに引っ張ってみるが、びくともしなかった。
ぶら下がりながら進む方式は、僕の腕力では無理だ。十数秒で落っこちる。となれば、ロープの上に胸も腹も乗せ、しゃくとりむしのように前進するのがいいように思える。それでもバランスを崩して落っこちそうだが、何もせずに東条さんがゾンビの波に呑まれていくところを見ているなんてできない。
僕は意を決して窓から足を離し、ロープに抱きついた。勾配の関係上、頭が下でお尻が上という向きに体が傾く。頭に血が昇るし、ロープが体に食い込んで痛い。
「ひえぇ」
手と足を使って進もうとするが、少し進んだだけで体の向きがくるりと反転しそうになった。何とか持ちこたえているのは、ひとえに集中力のおかげだ。
アルパカゾンビたちは僕の行動に全く気づいていない。でも、彼らは着実に東条さんに近づいており、すでに二十人くらいはステージに乗り上がって東条さんに迫っている。その二十人の中にミツルさんと色川社長が入っているのを目にして、僕は足を滑らせそうになった。やはりあの二人もこの謎の現象には逆らえなかったか。
ステージまであと二十メートル。東条さんはゾンビに追い詰められ、悲鳴を上げながらMPを放出している。
「東条さーん!」
ここからなら声も届くはずだが、東条さんには聞こえていないようだ。目の前に迫る危機で精一杯になっている。
「MP止めて!」
もう一度叫んだとき、東条さんの大きな瞳が僕を捉えた。唇が小さく動く。
『……乃木坂?』
気づいてくれた! そう思った矢先、出発点側のロープの留め具が弾け飛んだ。
「ぇ……ふぇええぇぇっ!?」
僕の体は振り子のように弧を描いて、一気にステージまで飛んでいく。近道できたなんて喜んでいる場合じゃない。このままでは床に大激突だ。あ、手からロープ抜けちゃった。
死ぬ――――――――!!
息の止まるような衝撃が僕を襲った。
……あれ、生きてる?
恐る恐る目を開けると、僕は淡いピンク色のクッションに埋もれていた。雲型クッションが衝撃を受け止めてくれたのだ。驚くべきことに、骨一つ折れていない。
「だいじょーぶか!?」
東条さんが駆け寄ろうとするが、群衆に取り囲まれてしまう。倍に増えたゾンビたちは大きく口を開け、奇声を上げながら東条さんに手を伸ばした。
近くで見ると迫力が違う。彼らは虚ろな目で東条さんをじっと見つめ、嫌がる彼女の体中を撫で回した。
「ぐヴぉおォォォ」
「さわるなっ! にぅにぅーっ」
すっかり取り乱した東条さんは、MPを乱発した。
「MP使っちゃだめ!」
僕は全力でゾンビを一人押しのけ、東条さんの前に体を割り入れる。相変わらず他の方向からは人々の手が伸びてくるが、僕が視界に入ったことで東条さんは少し落ち着いてくれた。
「どーしてだ? MP使わなかったら、みんなますます言うこと聞かなくなるんじゃ……」
「逆だよ、MPがこの人たちを錯乱させてるんだ。目的は東条さんを撫で回すことみたいだね」
「MPのせい? ボクの力が穢れちゃったのか?」
東条さんは目を潤ませた。僕は彼女が心を痛める前に否定する。
「ついさっきまでは普通にみんな萌えてたから、違うと思う。イノセンスがMPに対抗しようとしてるって話、藤巻さんから聞いてるよね?」
「うん。雪菜はイノセンスの動きをケーカイしてパトロールに行ってる」
「イノセンスは、MPを消すんじゃなくて、別のベクトルの力として働かせるような装置を作ったんじゃないかな。それを今どこかで使ってる。根拠はないけど……。少なくとも東条さんの力は穢れてなんかないよ!」
東条さんは少し自信を取り戻した様子で、僕の言葉に頷いた。
「ん。ボクは乃木坂のいうことを信じる」
まさか久しぶりの会話がこんな内容になるとは。でも無事で何よりだ。僕がくるのがあと一分でも遅かったら、もっと大勢の人が東条さんに押し掛けてきて、小さな彼女の体はつぶれてしまっていたかも知れない。
「ほら、しばらくMP使わないでいたら、みんな元に戻ってきたよ」
人々はごく普通の顔になり、自分が東条さんを撫で回していることに気づくと慌てて距離を取る。お互いに顔を見合わせ、とんでもないことをしてしまったと顔面蒼白になった。
「俺たち何やってんだ?」
「ごめんね、くるたん!」
「ごめんなさい!」
次々に上がる謝罪の声。東条さんは地獄から解放されたことで呆けながらも、すぐにアイドル精神を奮い立たせてファンたちに笑いかけた。
「いいよ! ゆるしてあげる!」
おお、と、数秒前までアルパカゾンビだった人々は涙を流して喜んだ。あれほどショックを受けていたのにもかかわらず、ファンの前では気丈に振る舞う東条さんを見て、僕も心動かされずにはいられない。
「もしかして祝典は打ち切り?」
ファンの一人が呟いたその言葉をきっかけに、ざわめきが広がっていった。
「えっ、そんなのヤダ」
「くるたん、続きやってよ」
「私たち、本当にくるたんのこと大好きなんです」
「お願いします!」
ファンの熱烈な要望に応えて、東条さんはマイクを握った。そして高らかに宣言する。
「祝典はまだまだつづくよーっ!」
人をがっかりさせるようなことはしない。それでこそ僕が慕ってやまない東条さんだ。
***
雪菜と木梨枝が外へ出ると、ライブ会場の方から異様な叫び声が聞こえてきた。ファンが胡桃に萌えている、どころではない騒ぎだ。二人は顔を見合わせてライブ会場へ走る。
そこで目にしたものは、自我を失った人々が何かに操られているかのように、ひたすら胡桃を目指して蠢いている光景だった。
「なに、これ……」
「イノセンスが、動き出したんです」
後方にいたファンが直進してきて木梨枝にぶつかり、タナトスの力で意識を失う。どうやら障害物をよける判断力すら奪われているらしい。
「これじゃあ乃木坂くんまで巻き込まれちゃう!」
焦燥感を募らせる木梨枝に、雪菜は冷静に尋ねた。
「栗本さんは前にイノセンスと接触したことがありますよね。どこに団員がいるか、心当たりはありませんか?」
木梨枝ははっとして、あるビルの最上階を見つめる。
「キリエがイノセンスからチラシもらった場所……。もしかしたらそこかも」
「行きましょう。迷っている時間はありません」
そこに解決の糸口があると断定できたわけではないのに、雪菜はファンをかわしながら疾走し始めた。後から追ってきた木梨枝はからかい半分に声をかける。
「雪菜ちゃん、冷静なふりしてるけど、ほんとは結構慌ててるでしょ」
「えっ……」
図星を突かれて、雪菜はさっと顔を赤らめた。ノクターンのミッションではそのようなことはなかったのに、どうして今に限って、という思いがよぎる。
「いいよ、キリエがちゃんとフォローしてあげるから!」
雪菜は予想外の申し出に驚いたが、すぐに微笑みを返した。
「頼りにしてますよ」
木梨枝は頷くと、目指す部屋の窓を凝視した。胡桃のライブにも行かず屋内にいる人影があったなら、そこでイノセンスの活動が行われているという確証が持てる。
「――いた! 雪菜ちゃん、人いるよ!」
雪菜は木梨枝を信頼していたため、あえて確認はしなかった。二人は常人の目には止まらぬ速さで駆け出す。彼女たちの絆は固く結ばれ、友達から親友へと変化を遂げていた。
「朝比奈さん……」
「また会えるとは思っていませんでしたよ、Op.1」
ビルの最上階で、彼らは出会う。
朝比奈は嘲笑うように雪菜の姿を眺めた。
「今度はカラープロダクションの人形になったわけですか。せっかくノクターンを抜けたというのに夢がありませんね。人形の相手には、人形がふさわしい」
そう言うと彼は、ポケットから象牙色のリモコンを取り出した。見覚えのあるその形に、雪菜は歯噛みして身構える。
「ウェポンロイド……っ!」
「え? 何?」
朝比奈がボタンを押すのと同時に、壁際に並んでいた数体の等身大人形が動き出し、少女たちに飛びかかってきた。
雪菜はOp.4から譲り受けた夜色の銃を抜き、木梨枝に襲いかかる自動戦闘人形(ウェポンロイド)の四肢を 打ち抜く。アームに損傷を受けた人形は、ぎこちない動きながらも立ち上がり、得物を倒そうと暴れ始めた。一瞬遅れて状況を把握した木梨枝は、構えを取って高らかに叫ぶ。
「お母さん直伝のメイド拳法、見せてあげる!」
彼女は突っ込んできた人形の腕を掴み、その勢いを活かして床に叩きつけた。その衝撃で床板はあっけなく砕け散り、コンクリートにまでひびが入る。しかし、ウェポンロイドはいまだ活動を続けていた。
「ブレーンは硬い外殻に覆われていて攻略が困難です! 手足を狙ってください!」
「分かった!」
木梨枝が投げたナイフは計算し尽くされた角度で関節部に刺さり、人形の回路を断ち切った。その様子を見ていた朝比奈は、興味深げに微笑んだ。
「ほう、その技……。もしかして、君のお母さんは先代Op.1ですか?」
「オーパス?」
「カラプロから大金を得たのではないですか?」
「あっ、そうだよ! それでキリエが生まれたんだもん」
朝比奈にはその言葉の意味は理解できなかったが、先代Op.1が娘を持って自由に暮らしていると考え、にたりと笑みを浮かべた。
確実にウェポンロイドの動きを止めながら、雪菜が釘を刺す。
「それを知ったところで、あなたには栗本さんやご家族をどうにかすることはできませんよ。今ここで、私が止めます」
「いや、先代Op.1には敬意を表しますよ。望むままに生きる、まさに理想の生き方だ。それに比べて君は……。君にはこの装置に秘められた未来の価値も分からないでしょうね」
雪菜は開け放した窓に向けて置かれた装置を一瞥し、それから静かに一言、現実を教えてやった。
「朝比奈さん、外を見てください。もうその装置の意味はありませんよ」
反射的に朝比奈は窓の外に目をやる。
装置の作用で胡桃を撫で回そうとしていた人々が、我に返ってステージから拡散していくところだった。
「なっ……東条胡桃が人を萌やすのをやめた!?」
木梨枝も事態の変化を知り、手を叩いて喜ぶ。その歓声が朝比奈の神経を逆なでした。
「乃木坂くんがやめさせたんだ! さっすが乃木坂くん!」
「くっ……」
気がつけばウェポンロイドも全滅。朝比奈は窮地に追い込まれていた。迫りくる絶望に、彼は初めて怒りを見せる。
「望みを持たない君がぼくの邪魔をするなんて、ちょっとばかり癪ですよ!」
腰から拳銃を抜き、雪菜目がけて乱射した。しかし一発たりとも彼女を傷つけることはない。雪菜は銃身で弾を弾きながら朝比奈との間合いを詰めていく。そのような芸当に耐えうる銃を、朝比奈は一つしか知らない。
オーパスだけが持つことを許される夜色の銃、夜の女神(ニュクス)。
特別仕様の外装の前では、普通の弾丸などあられのようなものだ。
「望みなら、あります」
「へぇ! 何ですか、君がやっと手に入れた望みとは!」
銃口が朝比奈の額を捉える。
「大切な人たちと、一緒にいること」
彼は薄く笑い、弾の尽きた銃を床に投げ捨てた。
「ぼくを警察に突き出しますか? そんなことをすれば、この装置のことも明るみに出ますが。東条胡桃の萌えが機械で操作できるものだと民衆に知られては、神聖さが失われますね。ならばいっそ、ここでぼくを殺しなさい」
「……」
「どうしたんです、ほら」
朝比奈が自ら額を銃口に押し付つけたとき、一体のウェポンロイドがわずかに機能を回復した。動かぬ右脚を引きずり、かろうじて動く左手でもって、主人を害そうとする少女を排除しにかかる。
雪菜が気配を感じた時、すでに人形は腕を振り上げていた。
――その腕は、銀の矢と化したナイフによって跳ね飛ばされる。
「フォローするって言ったでしょ?」
背後で木梨枝が親指を立てていた。雪菜は微笑みをもって感謝の意を示し、その表情を保ったまま朝比奈に向き直る。
「あなたの身柄はカラープロダクションが管理します。命の安全は保証しますよ。『誰一人犠牲にしない、世界で一番平和な世界征服』なんですから」
「……いいでしょう。ぼくは弱者として、強者である君の望みに従いましょう」
朝比奈は手を上げて、二人のディーヴァに投降した。
夢が破れた彼の口元には、しかし満足げな笑みが湛えられていた。
***
東条さんが僕に相談があると言うので、一度ステージから降りた。ステージ上での輝きはどこへやら、彼女はすっかり参ってしまっている。
「なあ乃木坂。イノセンスの装置が実際にあるとして、それはまだ稼働してるんだろーな、きっと」
東条さんは彼女らしくなく、頭を押さえて重苦しいため息をついた。
「きょうの祝典はぜったいに成功させなきゃいけないのに……。MPなしでどーしたらいいんだ」
「MPなしで、いいじゃない」
僕は軽い調子で言った。本音だからこその言い方だ。
「東条さんならMPなしでもみんなを萌やせるよ」
「そんなカンタンに言うな」
むっと膨れる東条さんが可愛かったので、僕は幸せな気分で微笑んだ。
「僕のこと、信じてくれるんでしょ?」
「う……」
東条さんは、ついさっき自分で口にした手前、肯定せざるを得なかったようだ。こくりと頷いて、颯爽と舞台に駆け上がる。
「できるだけのことはやる。乃木坂はいちばん前で見守ってろ」
仕切り直しのファンファーレが鳴り、トークライブは再開された。
東条さんは本物のアイドルだ。
MPに頼らず、声と身振りだけで観客を虜にしている。
「今日のくるたん、何かいつもと雰囲気違うね。夢の世界から現実界へ降臨したって感じ」
「うん。でも、これもイイ!」
不満を漏らす観客は一人もいない。あんなに人を楽しませようと努力している人が、愛されないわけがないのだ。
夢のような時間はあっという間に過ぎ、トークライブは幕を閉じようとしていた。しかし儚いとは感じない。充実した数時間は、忘れることができないほど心に深く刻み込まれていた。この感動は聴衆の心に永遠の炎として宿るだろう。つらいことがあっても、今日を思い返せばまた立ち上がれる。
「さみしいけど、おわかれの時間が近づいてきました。これがさいごの演目です。神聖アキバ帝国国歌、『パックス・アキバーナ』! みんなもいっしょに歌ってねー!」
争い絶えぬ大地に
萌えいずる愛の新芽
泣いてる子も 泣かせた子も
いたいのいたいの飛んでけ
みんなで平和になろうよ
願えば 望めば きっと叶うから
パックス・アキバーナ
全てが萌えに包まれたなら
パックス・アキバーナ
みんな笑顔でいられるよね
萌えは世界を救う
笑顔が絶えぬ大地に
咲き誇る愛の花
元気な子も おとなしい子も
笑い合ったらなかよし
世界は思っているより
ずっと 楽しい 遊び場なんだよ
パックス・アキバーナ
どんなにつらいことがあっても
パックス・アキバーナ
愛するこころ 忘れないで
萌えはあなたを救う
パックス・アキバーナ
世界をもっと楽しくしよう
パックス・アキバーナ
みんな笑顔でいられるように
萌えは世界を救う
世界の果てまで届きそうな盛大な拍手がビル街で巻き起こった。
その迫力に誰よりも驚いていたのは、当の東条さんだった。光に満ちたステージの上で、温かな歓声を浴びる。柔らかな頬に、一筋の涙が流れた。
「乃木坂!」
東条さんは気づいたのだ。
「ボク、MPなくても愛されてる!」
神聖アキバ帝国――世歴二〇四三年四月二十七日(日)建国。
祝典終了後、僕は色川社長に呼び出された。
東条さんに僕を解雇させ、刺客を使って始末することまで考えたという彼を前にして、緊張しないわけがない。しかし社長は丁寧な物腰で僕にこう言った。
「君は胡桃の命の恩人だ。礼を言おう。そして……乃木坂くんにはすまないことをした。胡桃に君を解雇させたのは私なんだ。私情に走って君と胡桃を傷つけてしまった。大人げない私を許してくれないだろうか」
深々と頭を下げられて、僕はびっくりする。世界に名立たるカラープロダクションのトップが僕に頭を下げているなんて。
「考え直したよ。胡桃は世界平和を望んでいて、君は胡桃の力を引き出してくれる。君たちは世界のためにも二人そろっているべきなんだ。もう一度、胡桃の友達(げぼく)になってやってくれないかね」
僕は東条さんと顔を見合わせ、同時に顔を輝かせた。
「はい、喜んで!」
ミツルさんは僕の下僕復帰を聞くと、祝福のウインクをくれた。
「吟ちゃん、これからもよろしくね! また女装させてくれると嬉しいわぁ」
そこへ東条博士が息を切らせて駆け込んできた。彼女は一直線に東条さんのもとへ行き、小さな体をぎゅっと抱きしめる。
「胡桃! ああ、よかった……」
僕の位置からはよく見えなかったが、博士は肩を震わせて泣いているようだった。その姿は僕にとって意外なものだった。まるで本当の親子のように、博士と東条さんは抱き合っている。
「ママ姉……」
東条さんは博士の腕の中で安心した様子を見せた。やっぱり東条さんにとって、お母さんは博士なんだ。
東条博士のこと、まだ好きにはなれないけれど、彼女は彼女なりに東条さんのことを愛しているのだということは認めようと思った。
藤巻さんが栗本さんを連れてカラプロ関係者のところにやってきたのはその後だった。なんと二人で協力して朝比奈さんを捕まえたらしく、手続きをしてカラプロのエージェントに引き取ってもらったそうだ。
話を聞くと大変な喧嘩があったように思うのだが、帰ってきた二人は仲が悪いどころか親友になっていた。
「雨降って地固まる、ですよ」
「ねー」
息までぴったりだ。それに、栗本さんはいつもの元気な彼女に戻ってくれていた。僕にはそれがとても嬉しかった。
栗本さんは僕の方に来て、うつむきながら言葉を紡ぐ。
「……乃木坂くん。昼はあんなことして、ごめんね。今日のことは忘れて、友達からやり直させてくれないかな」
僕が頷くと、栗本さんは切なげに睫毛を揺らして笑顔を作った。
「ありがとう」
それから栗本さんは、自分もディーヴァの一人として世界平和計画に携わりたいと言い出した。僕は驚いたが、栗本さんと初対面の東条さんは特に疑問も持たず、彼女を色川社長のところに連れていく。
栗本さんの姿が見えなくなってから、僕は藤巻さんに訊いてみた。
「栗本さんは萌えを嫌ってたはずなんだけど……どうして気が変わったのか知ってる?」
「私がお勧めしたんです。彼女は萌えを嫌っているように見えましたが、それは実際には東条さんがMPを持っていることに対する嫉妬だったようで、世界平和計画には大変興味を示されましたよ。それに何より、乃木坂さんの近くにいられますから」
藤巻さんはくすりといたずらっぽく笑ったが、やがてその笑みは深みのある微笑に変わる。
「またみんなで家族のように笑い合える日々が戻ってきます。私にとってこれ以上の幸せはありません。あなたが戻ってきてくれて、よかった」
僕は少し照れてしまって、ごまかしに夜空を見上げた。
冴えわたる群青の空に、星たちが仲良く並んで瞬いていた。
翌朝、教室に入った途端に僕は喝采を浴びた。
「え? え?」
状況が飲み込めない僕の周りに、クラスメートがどんどん集まってくる。
「池田くんからチャットで聞いたよ! 乃木坂くんはくるたんを救ったヒーローだって」
「勇敢にもロープを使って混乱の中に飛び降り、くるたんを守ったんでしょ?」
「かっけぇ!」
「今まで乃木坂って陰気なヤツだと思ってたけど、ほんとはすげーヤツだったんだな」
「くるたんの救世主は俺たちの救世主だぜ!」
ぽかんと口を開けて驚いている僕を、栗本さんと藤巻さんが笑って見ていた。栗本さんはおもむろに立ち上がると、よく通る元気な声で提案する。
「今日のお昼はみんなで輪になって、乃木坂くんとお話ししよっか!」
僕はその日、文字通りクラスの輪に入ることになった。
と言っても、僕はあまりしゃべらずに、主に栗本さんが盛り上げてくれたのだけれど。僕は話すより、聞いている方が好きなのだ。
――クタオと呼ばれた日からずっと続いてきた、馬鹿にされているんじゃないか、嫌われているんじゃないかという不安な気持ちは、もう感じなかった。
高野さんは、ちょくちょく僕の家に遊びに来るようになった。僕と話していると楽しいそうだ。そう言ってもらえると、僕も嬉しい。
「不思議ね。初めは貴方に付随する要素が目当てで話しかけていただけなのに、今は純粋に貴方という人格と話をしたいと思っている。きっと東条胡桃も同じ気持ちだわ」
高野さんは感慨深げに語った。表情はほとんどないに等しいのだが、接しているうちにわずかな雰囲気の変化を感じ取れるようになったのだ。
「初めは孤独からくる依存関係であっても、人は新たな関係を築いていける。相手の心を愛するようになった時、初めて真の絆は結ばれると私は思うの。そして、その絆は世界を織りなす」
高野さんはまっすぐ僕の目を見据えた。
「今度世界を動かすのは、貴方たちの絆かも知れないわね」
「えへへ……」
僕は照れてうつむいてしまった。
でも、きっと本当にそうなのだ。世界で一番平和な世界征服を達成するにはまだまだ時間がかかるけど、日々確実に世界は動いていっている。カラプロのみんなと、東条さんと、その下僕である僕が、動かしている。
「今日は貴方の家族の話が聞きたい。貴方の父親と、母親のこと」
高野さんのリクエストを受け、僕は自分自身懐かしい気持ちでお父さんとお母さんのラブラブな話をしてあげた。
考えてみれば、お父さんとお母さんに絆があったから僕が生まれて、その僕が東条さんたちと絆を結んで、世界を動かしているんだなあ。それって何だか壮大かも。
そんなことを言うと、高野さんはほんの少しだけ笑っていた。