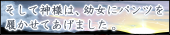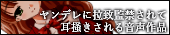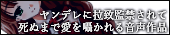第五章 ひいろう
ライブは大成功のうちに幕を閉じた。
僕は一刻も早く東条さんに会ってこの感動を伝えたいと、小走りで楽屋に向かう。ホール内は観客でごった返していたが、関係者用通路を通ればスムーズに行けた。
楽屋の前にはミツルさんと色川社長が立っていて、困った様子で楽屋の扉を見つめていた。ミツルさんなんか頬に手を当ててため息をついている。
「何かトラブルでも?」
心配になって尋ねると、社長がそわそわしながら答えてくれた。
「胡桃が楽屋に籠ってしまってね。帰ってくるなり、一人にしてくれと……」
どうしたんだろう。何か気に病むようなことがライブ中にあったのだろうか。僕が見ていた限りでは、これ以上ないというほどの大成功だったと思うのだが。
立ち尽くして閉ざされたドアを見つめていると、ほんの二センチばかりドアが開き、その隙間から東条さんの声が聞こえてきた。
「乃木坂? そこにいるの?」
いつも強気な東条さんのものとは思えない頼りなげな声だ。
「いるよ。大丈夫?」
「……乃木坂だけ来て」
横目で社長を見ると、彼はやや迷ってから頷いた。僕はドアを少しだけ開けて、静かに入室した。
東条さんは部屋の片隅に置いてある椅子に、ライブの衣装のまま腰かけていた。脚の長さが足りず、力の抜けた小さな足が宙に浮いている。僕が楽屋に入ってきても項垂れたままで、顔すら上げてくれない。本当に、どうしてしまったのだろう。
「東条さ――」
声をかけようとしてやっと気づく。彼女は小さな肩を震わせながら、声を抑えて泣きじゃくっていた。
「うっ、うえ……ひっく……ぇぅ……」
「うわわ、何があったの!?」
東条さんはごしごしと目を手で擦って、やっと僕を見た。しかしすぐに目に涙が溜まり、ぽろりとこぼれ出す。
「……なあ、乃木坂。お前はボクのことを可愛いと思うか?」
突然何を言い出すのだろう。そんなのは自明の理だ。
「可愛いに決まってるでしょ」
「どこが? 具体的に答えろ」
「えっ、うーんと……」
どうして主人の長所くらいぱっと言ってあげられないんだろう。東条さんのいいところはたくさんあるはずなのに、いざ訊かれると答えられない。東条さんの魅力は、どこがいいとかそんな局所的なものではないのだ。決して彼女に魅力がないから答えられないのではない。でも答えないわけにも……。
「ははっ、ムリいってごめん」
東条さんは気まずい雰囲気を吹き飛ばそうとしたようだが、僕にはその笑みが痛々しかった。不甲斐ない自分が恨めしい。
彼女はふと悲しげな顔に戻って、僕をつぶらな瞳で見上げた。
「アイドルだって、たまには甘えてもいいかな? 下僕にくらい悩みをうちあけても、許されるかな?」
「何でも話してよ! 僕はそのためにいるんだよ」
クタオで孤独だった僕は、東条さんが必要だと言ってくれたおかげで救われた。彼女の支えになりたいという気持ちは、出会ったあの日から変わっていない。
「……ありがとう」
東条さんは切なげに目を伏せると、自らの苦しみを吐露した。
「ボクは世界一のスターで、たくさんの人から愛されて、だれもがうらやむ人気者。拍手も歓声も、ぜんぶボクのもの。デビューしてから数年、しょーがっこうの高学年くらいまではそう思ってた。でもちがった。ボクはある日、MPのない自分がどれだけ価値のないものか気づいたんだ。
認めるしかないから認めるが、ちいさいころからMPに頼ってきたせいで、ボクは対人コミュニケーションがうまくない。くーきが読めなくたってMPがあれば可愛がってもらえる、そんな人生だったからな。MPがなかったら、ボクはつまらないガキでしかないんだ。それを自覚したとき、ボクはとてつもない虚脱感におそわれた」
自信に溢れた言動も、少し強引なところも、自分に自信のない僕からすれば頼もしいし、可愛らしくもある。しかし本来、出る杭は打たれるものだ。たとえ東条さんにどれほどの実力があったとしても、世間はその立ち振る舞いを批判する。「空気を読め、出しゃばるな」と。今はその勢力がMPで骨抜きにされているから、叩かれずに済んでいるだけなのかも知れない。
愛されて当然、萌えられて当然という態度を、MPなしで続けていくことは可能だろうか。今の僕には、客観的な判断など下せなかった。だから何も言えなかった。
「そんなボクがみんなから萌えてもらえるのは、ひとえにMPのおかげだ。MPがあるからボクは存在を許される。必要とされているのはボクじゃない。MPがないボクなんて、パパもママ姉もファンたちも、いらないんだ」
「でも僕は」
「わかってる。乃木坂がボクのこと大切に思ってくれてるのは、わかってるよ。でもそれは、乃木坂が特別だから。乃木坂にはきっと、ひとを大切に思える才能があるんだと思う。雪菜もおんなじだ。あいつはすぐにボクとなかよしになってくれたけど、それも雪菜がやさしいからだ。すごいのはお前たちだよ。ボクはなかまに恵まれているんだな」
自嘲的な笑みを浮かべる東条さんを見ると、僕まで悲しくなってしまう。でも、反論したって彼女の神経を逆なでするだけだ。MPがなくても東条さんは一流のアイドルだと僕は思うけど、それを証明するすべはない。
「ちゅーがくせいのときに、成長促進剤をつくって飲もうとしたことがあったんだ。でも、それがママ姉に見つかって……ママ姉、怒って薬をぜんぶ捨てたんだ。あなたは幼女だから価値があるのよ、可愛くなければ意味がないのよ、って……」
「何、それ……ひどい」
東条さんが東条博士のことを慕っていると知っていても、非難の声を禁じえなかった。東条さんの劣等感は、この発言でさらに膨れ上がったに違いない。東条さんの成長する権利を奪い、その上彼女の心を傷つけてまで、博士は幼女だったころの自分の姿に酔いしれたいと言うのか。東条さんは僕には人を大切に思える才能があるって言ってくれたけど、東条博士のことは本当に許せない。
「いや、ママ姉のいうことは正しいよ。ライブやってたら、ボク、かなしくなっちゃった。みんなはボクに萌えてるんじゃない、MPに萌えてるだけなんだってな。ボクは『幼女』『ボクっ娘(こ)』という萌え記号でつくられたMP発生装置みたいなものなんだ。ちょっと前には、一生世界平和のために自分を押し殺さなきゃいけないのかと思って、かぐやみたいに逃げてしまいたくなったこともある。でもボクはそうしなかった」
彼女は自分に言い聞かせるように言い放った。
「自分に救える世界がそこにあるのを、放ってはおけないから」
――かっこいい!
僕は言葉を失った。何てかっこいいことを言ってくれるんだろう僕のご主人様は!
「……ん、ちょっとはずかしいこと言っちゃったかな」
「すごいよ!」
「え?」
「そんな風に思えるって、すごいことだよ! だって、世界のために自分は我慢って、普通の人にはできない決心だよ。そういう人のことを何て言うかくらい、クタオの僕でも知ってる。ヒーロー、英雄だよ! 東条さんはアイドルを超えて英雄なんだ」
東条さんは少し照れて目をしばたいた。
「そう、か? ボクとしてはとーぜんの選択なんだけどな。白人諸国が高いせーかつ水準に達した今でも、黒人による白人差別はつづいてるし、白人も黒人に植民地にされてた時のことをまだうらんでる。それを象徴するみたいに、カデニアとファンゼル連邦の冷戦はどんどんひどくなってる。でも、ボクががんばって戦争を食いとめることができるというなら、人生をかけるだけの価値がある。くるたんを演じつづけるのは苦痛だが、世界を救うこと自体はボクの願いでもあるんだ。だから、今日はちょっと弱気になっちゃったけど、ボクは逃げたりしない」
MP使いのアイドルである限り、東条さんは一生自分の虚像に全てを持っていかれてしまう。それを覚悟した上でのこの言葉は、ますます東条さんを好きにさせた。
「かぐやは自分と恋人の幸せをゆーせんしてカラプロを去った。ボクはそれを悪いとは思わない。むしろ、かっこいいとすら思う。逃げたりしない、なんてえらそうにいってるが、よーするにボクには世界を見捨てる勇気がないだけだ」
「それは違うよ」
僕は自信を持って断言した。
「東条さんは、優しいんだよ」
カタリ様――いや、かぐやさんと呼ぶべきか――と色川社長の息子さんとの大恋愛を軸に、ディーヴァたちの運命は回っていると言っても過言ではない。かぐやさんが世界征服をディーヴァたちに丸投げしたから、今の東条さんの苦悩があるのだ。かぐやさんが悪い人だとは思わないし、高野さんがあれだけ敬慕しているのだからむしろいい人なんだろうけど、それでもかぐやさんの恣意に僕たちが振りまわれている感じがするのは否めない。
世界平和を捨てて恋人との幸せをとったかぐやさんは、きっと個人に対する愛情が深い人なのだろう。反対に、自分よりも世界を優先する東条さんは、博愛精神の持ち主だ。かぐやさんと東条さん、どちらが正しいかと聞かれたら答えにくいけれど、個人的には東条さんの方が「偉い」と思う。僕はそんな東条さんが好きだ。高野さんがカタリ様を慕っているように、僕も東条さんを慕っている。
いつの間にか涙が乾いていた東条さんは、自分でもそれに気づいて一瞬驚いたように目の辺りに手を当て、それからにっこりと僕に笑いかけた。
「なんだか、乃木坂に話したらココロが軽くなったみたいだ。ありがとな」
救いも答えも、最初から東条さんの中にあったのだ。僕はただ、それを引き出す手伝いをしただけ。
「ボクのがんばりは乃木坂が見ててくれる。それに雪菜も。ミツルだって、MPには萌えちゃうけど、本当のボクを優先してくれる」
「うん」
「なーんだ、ボク、ぜんぜんひとりじゃなかったんだ!」
立ち直ってくれてよかった。東条さんは少し躁鬱質なところがあるけど、元気な方が彼女らしい。
「パパー、ミツルー、心配かけてごめんねー!」
てててとドアに飛びついて楽屋の外に踊り出す。あるいは、元気に振る舞っているだけで、内心ではまだ孤独感を感じているのかも知れない。それでも彼女にはいつまでも落ち込んでいる時間はないのだ。あさってにはカデニアでライブがある。心が落ち着いてきたことで、楽屋に籠っている場合ではないと思い出したのだろう。
その日の夜、東条さんは日本を発った。
翌日の月曜日、僕はいつも通り登校した。
僕と藤巻さんは、カデニアのライブと同時期に学校を休んだらさすがに関連性がばれるということで、日本での待機を命じられたのだ。
今日も多くの生徒が早朝登校して、東条さんのライブの感想を言い合っていた。栗本さんも女の子たちの中心で会話をしているということは、クタオであってもライブの中継は見たのだろう。この日本では、東条さんの話題抜きにはコミュニケーションが成り立たない。いや、テレビが買えないくらいの貧困地区に住んでいる人でもなければ、世界中の誰もがライブの話をしているはずだ。
藤巻さんは編入してきたばかりだが、彼女の人柄と、彼女をクラスに溶け込ませようという栗本さんの心配りが相まって、すでに栗本さんや他の女子と友達になっていた。藤巻さんは、あくまで一般人としてライブに行った時の感動を語っている。
「よっ!」
「ひゃっ」
突然後ろから小突かれてびっくりした。僕にこんな風に話しかけてくれるのは一人しかいない。池田くんは満面の笑みで僕に報告した。
「俺、くるたんのライブ行ってきたよ」
「うんうん、どうだった?」
「最高だった! やっぱりくるたんはネ申(かみ)だぁ! 笑い泣き感動泣き萌え泣き、俺泣いてない時間なかったからな!」
それからしばらく池田くんは東条さんを褒め称えていた。好きな人が褒められているのを聞くのは、自分が褒められるのよりも気分がいい。
「あ、あと、トイレの場所分からなくて困ってたら、女の子が教えてくれたんだけどさ」
それ僕だけど、全然気づいていないみたいで安堵する。
「何とそれ、くるたんの秘書だったんだよ! 俺すごい人に会っちゃったよマジで!」
ちょっと待てー!
「何でその人が秘書だって分かったの!?」
「録画しといたテレビのくるたん特集で、出てたんだよその人が! ライブの舞台裏を取材しに行った時にその女の子が出てきてさ。まあ取材は断られてたけど。いやー、まさかくるたんの秘書に会えるなんて俺はラッキーだな!」
「そ、そうだね……」
どうしようどうしよう、テレビに映っちゃった!
でも、凄腕スタイリストのミツルさんが変装を手掛けたんだから、そうそう簡単に男だとは見破られないはずだ。大丈夫、と信じたい。
僕と東条さんの関係に気づく人が出るのではないかと思うと、授業中もそわそわと落ち着かなかった。誰かが僕を見ているような気がしたのだ。
そして、その嫌な予感は当たってしまった。
またもや僕は、放課後栗本さんに呼び止められた。何となく、この時点で「ああ、ばれたな」と悟った。彼女は僕にクタオ仲間であることを望んでいるので、監視の目を光らせているのかも知れない。
「乃木坂くん、テレビに出てたよね」
「何のこと?」
手遅れだと分かっていても、一応しらばっくれておく。
「はぐらかそうとしたって無駄。キリエには分かるよ。変装したって、乃木坂くんのことなら見破る自信あるもん。まさか東条胡桃の秘書をやってたなんて……」
怒ってはいないようだ。どちらかと言うと、悲しげな顔をしていた。暗い声で呟く。
「残念だよ。乃木坂くんは嘘をつくような人じゃないと思ってたのに」
「ご、ごめん……。あのっ、このことは秘密にして! お願い!」
手を合わせて懇願すると、栗本さんはその手を押さえて優しく言った。
「最初からそのつもりだよ。バラしたら乃木坂くん、妬まれて殺されちゃうかも知れない。キリエはそんなの嫌だから」
てっきり厳しく咎められるのではないか思っていたけど、案外許してもらえるのかな。なんてほっとしたのも束の間、栗本さんは引き続き優しげな声で、恐ろしい言葉を口にした。
「やっぱり東条胡桃のせいだよね。あの子が乃木坂くんに悪い影響を与えてる。乃木坂くんは悪くない。そうだよね?」
どう返すべきなのだろう。いいえと答えて栗本さんの機嫌を損ったら、「乃木坂くんなんかもうクタオ仲間じゃない!」とか言われて、秘密をばらされてしまうのだろうか。でも下僕自ら主人の悪口を肯定するわけにもいかないし……。
迷っていると、栗本さんは東条さんの批判を付け加えた。
「東条胡桃は世界中のみんなに愛されなきゃ気が済まない気違いだよ。ネット国家なんか作っちゃってさ、女王様気取りにもほどがあるよね。だから乃木坂くん、もうあの子には近づかないで」
「ぅ……」
嘘でもうんと言えばいいのに、僕は首肯さえできなかった。怯えた僕のそぶりを見て、栗本さんはふっとコケティッシュな笑みをこぼす。
「ごめんね。でも、キリエは乃木坂くんのことを心配して言ってるんだよ? あいつといたら洗脳されちゃう。クラスのみんなはもうダメ。乃木坂くんだけは守りたいの!」
「……」
返事をしない僕に痺れを切らしたのか、栗本さんは自分の鞄の方に歩いていった。よかった、帰ってくれるんだ。と思いきや、彼女は鞄から一枚のチラシを取り出して戻ってきた。手渡されたままに受け取る。チラシの最上部には、「イノセンス」の文字があった。これって――。
「ネットでクタオ専用スレッドにいたら、アンチ東条のグループがあるって書き込みがあってね。メールしたら集合場所教えてくれて、行ったらこのチラシもらったの。ねえ、乃木坂くんも一緒にイノセンス入らない? 東条胡桃から解放されるいいチャンスだよ!」
「やだよ」
ほぼ無意識のうちに言い切っていた。強い調子ではなく、臆しながら出した声ではあったが、栗本さんに意思表示するには十分だった。彼女は予想以上に決然とした僕の態度に動揺しながら、明らかに気落ちした様子で作り笑いをする。
「そっか……。だよね、乃木坂くんは優しいから、アンチ団体なんて合わないよね。今日はいろいろ強く言っちゃって、ごめん。キリエ、帰るね」
栗本さんは今度こそ本当に荷物を持って帰ろうとした。でも、このまま帰らせてはいけないと思った。
「栗本さん!」
「なに?」
「イノセンスには入らないで!」
東条さんはもちろんだけど、栗本さんだって僕にとっては大切な人だ。彼女はF組の最高のクラス会長で、思いやりのあるいい人なんだ。その二人が敵同士になるなんて僕は嫌だった。駄目元でも頼んでみなければ、後悔することになる。
僕の決死の必死な気持ちとは裏腹に、栗本さんはあっさりと頷いた。
「乃木坂くんがそう言うのなら」
よ、よかったぁ。
安堵して、僕も帰ることにした。
昇降口を出て歩いていくと、校門のそばに藤巻さんが立っているのが見えた。視力がいいのは、僕の希少な取り柄の一つだ。藤巻さんも、かなり遠くからだが僕の気配を感じたようで、振り返って小さく手を振ってくれた。
「どうしたの? 誰か待ってたの?」
近づいてから訊いてみると、「乃木坂さんを」と意外な答えが返ってきた。
「私が編入してきた初日も、一週間目の今日も、栗本さんはあなたを放課後に残してコンタクトを取っています。それに、彼女は授業中、ずっと乃木坂さんを見ていました。その……プライベートな人間関係に口を挟むつもりはありませんが、何か問題が起きているのではないのかと思って」
「プライベート」の辺りで語調が乱れた。彼女の中では、必要な相談か余計なお世話かという葛藤があったらしい。結果として、僕は話しかけてもらって助かった。栗本さんの話の内容をかいつまんで説明する。
「それから、こんなチラシをもらったんだけど……。ちょっと読んでみよう? 僕もまだ怖くて見てないんだ」
僕は栗本さんからもらったイノセンスのチラシを藤巻さんと一緒に覗き込んだ。リーダーである朝比奈さんからのメッセージを除いて、あまり情報は記載されていない。おそらくイノセンスにとってはほとんどの日本人が敵(東条さんのファン)であるため、電話番号や拠点の住所は仲間内にしか知らされていないのだろう。そもそも朝比奈さん自身が裏社会の人で、身柄を明かすわけにはいかないのだ。名前すら書いていない。
『こんにちは。アンチ東条団体イノセンスの代表です。
始めに言っておきますが、ぼくは萌え自体を批判しているのではありません。ぼくはあくまで、アイドル東条胡桃をはじめとするカラープロダクションについて、異議を申し立てたいと思うのです。
東条胡桃の声を聞いていると、否応なく萌えてしまうことはありませんか? これは決して気のせいではなく、カラープロダクションが科学技術を使って我々に催眠術のようなものをかけているのではないかと、ぼくは推測します。彼らは「東条胡桃は素晴らしい」という画一化された価値観を世に定着させ、また東条胡桃に平和を訴えさせることで、強制的に争いをなくした疑似平和をもたらそうとしているのです。
しかし、東条胡桃の言うことだから争いはやめよう、そんな考えで作られた平和は、果たして真の平和と言えるでしょうか。
少しばかり、ぼくの昔話を聞いていただきたいと思います。
ぼくは第三次世界大戦時、戦場となった地区に住んでいました。当時小学四年生でした。
街が壊滅し、ぼくの親が殺された頃になって、「歌姫」が現れました。そう、みなさんがご存じの、歌姫伝説の幼き歌姫です。彼女はどこまでも響き渡る不思議な歌声でカデニア軍を萌えさせ撤退させると、満足そうに笑っておりました。ですがぼくとしては笑っている場合ではありませんでした。なぜなら、ぼくの親はもう死んでしまったからです。
ぼくは復讐を誓いましたが、できませんでした。歌姫のせいで戦争が終わってしまったからです。そこでぼくは思いました。これは正しい終末なのか、と。
もともと第三次世界大戦は憎しみの連鎖で始まりました。第三次世界大戦はご存じの通り、ファンゼル連邦が黒人諸国に対する攻撃の機会を狙っているという情報を得たカデニアが、ファンゼル連邦に軍を派遣し、兵器の存在を探し続けた末に一人の青年を誤って射殺してしまったことが原因です。ファンゼル連邦は、長らく黒人国家からの支配を受けていた白人諸国が第二次世界大戦後に独立し、集結した国家ですから、黒人の大国カデニアに対する憎しみは相当のものだったでしょう。
ところが「歌姫」が中途半端なところで戦争を終わらせてしまったせいで、この憎しみは発散させられないままとなってしまいました。これは冷戦状態の一因でもあります。
本来であれば、憎しみが憎しみを呼んで、もっと悲惨な戦争へと進んでいったはずです。ぼくも成長して兵士になって、親を殺したカデニアに報復をしてやったはずなのです。争いの末に得た真の平和でなければ、ぼくは認めません。最終的に平和が得られず、人類が滅びるのであっても、ぼくは自然な終末として受け入れます。
人に罪はありません。
人は常に無罪です。街を破壊しても、人の親を殺しても、です。
したいと思ったことをするのが自然な姿ではありませんか? 自然に善悪はないのですから、自然に従うことが罪になるなど有り得ません。カラープロダクションの人類洗脳計画も無罪です。しかし、イノセンスが抵抗運動に出ることもまた無罪です。ぼくたちは正義を決することを目的としてはいません。やりたいことをやるのです。
ぼくと同じ考えを持っている方は、他にもいらっしゃるはずです。その方は是非、イノセンスに力を貸してください。東条胡桃による平和の押し付けを食い止められるのは、今しかないのです。
あなたが我々の朋となる日を楽しみに待っています。
イノセンス代表者』
文章はところどころ子供っぽいが、朝比奈氏の思想はしっかり伝わってきた。この論理は正しいとも間違っているとも言いがたい。平和を絶対的な善とするか否かという根本的思想が、僕たちとは違う。
「藤巻さん、これどう思う?」
聡明な藤巻さんは、つかえることなく自分の意見を述べた。
「カラープロダクションと融和することは不可能でしょうね。話し合いで解決する問題ではありませんし、バックにはノクターンがついています。この理念からすると、国家の法律もあまり重視していないでしょう。しかし、表立ったテロ行為は行わないはずです。朝比奈さんもノクターンの一員である以上、身元が露呈してノクターンの存在が明るみに出ることは避けなければなりません。よほどのことがなければ、彼らは少数派、東条さんの世界征服には支障をきたさないとは思いますが……」
「そっか」
有用で申し分ない意見を聞いたのにも関わらず、僕はどこか物足りない気持ちでいた。もっと何か、他に言ってほしいことがあるような。
そんな僕の様子に気づいたのか、藤巻さんは微笑んで言葉をつないだ。
「このチラシを読んだ今でも、世界平和計画を支援しようという意志は変わっていませんよ。私は東条さんの味方です。乃木坂さんも、そうでしょう?」
「うん!」
僕は何となく嬉しくなった。
東条さんがカデニアでライブをやっている頃、僕は日本で高校の授業を受けていた。いくら東条さんのライブがリアルタイムで中継放送されていると言えど、さすがに学校側も授業をさぼらせてはくれなかったのだ。当然と言えば当然だが、「くるたん」の影響力を考えると、むしろ意外ととらえる人もいるだろう。池田くんとか。
古文の先生の講義をメモしていると、前方から僕を呼ぶ声がした。
「こんにちは、吟くん」
「え? ――!?」
高野さんが前の席の人と同じ場所に、透過した状態で立っていた。
『どうして授業中に来るんですか!』
ノートの隅にそう書いて見せると、高野さんは悪びれた顔一つせずに要件を告げた。
「貴方の主人が、今大変なことになっている。早くテレビを見た方がいい。事は一刻を争うわ」
『どうしたんですか』
「とりあえず仮病を使って外に出て。今ここでそれを言ったら、貴方はクラスの真ん中で挙動不審になって担任の目に留まるかも知れない」
ただ事ではないと言うことは分かった。僕は演技をする緊張感から震えつつ、すっと手を挙げる。
「あの、先生。気分が悪いので保健室に行ってきます」
「私が付き添います」
クラス会長として、すかさず栗本さんが立ち上がった。気持ちはありがたいけど、今は一人にしてほしいのに!
狼狽していると、僕の焦りを察した藤巻さんも立ち上がる。
「いえ、私が行きます。保健委員になったことですし、お仕事したいんです」
そう言えば、彼女は編入してきた翌日に保健委員になったのだった。先生もその言葉に納得したらしい。
「保健委員か」
「はい」
「じゃあよろしく頼むよ。栗本は授業受けてていいぞー」
栗本さんは何故か顔をしかめて藤巻さんを一瞥した。藤巻さんは構わず僕に「行きましょう」と声をかけ、僕たちは静かに教室を後にする。「僕たち」の中に高野さんも含まれているのは、僕だけが知ることだ。
「坂の下のビルの壁に、大きなテレビが貼りついてるのを知ってるわ。あそこなら三分で行ける」
高野さんが教えてくれたが、リアクションを示すわけには行かないので表面上は無視した。教室から離れたところで、藤巻さんは怪訝そうに訊いてきた。
「どうしたんですか? 本当に具合が悪いのではないように見えましたが」
「うーんと、やっぱり東条さんのライブが気になっちゃって。坂の下のビルの壁面ディスプレイをちょっと見てこようかなーと……」
自分でも苦しい言いわけだと思う。池田くんのようなキャラだったら言い出してもおかしくない話だけど、普段律儀な僕がこんなことを言うなんて不自然だ。だが藤巻さんは不思議そうな顔はしながらも、深く追求はしないでくれた。
「そうですか。乃木坂さんがそうおっしゃるなら、私は文句は言いません」
僕たちは三人で坂の下まで降りていった。
「え、うそ……」
ディスプレイを見て初めに口にした言葉がそれだった。
『ミレニアムタワーにテロ攻撃予告!』
道行く人が皆足を止め、画面に釘づけとなる。
ミレニアムタワーって、東条さんのいるところだよね……?
『繰り返します。先ほどカデニア政府に、ファンゼル連邦のテロ組織シャデニールからテロの犯行予告がありました。爆薬を積んだ戦闘機でカデニアの首都サンデシアのミレニアムタワーに突っ込み、自爆テロを行うというものです。戦闘機はすでにサンデシアの上空を飛行しており、防衛隊の出動も間に合いません。ミレニアムタワー最上階のホールで行われていた東条胡桃さんのライブは中止となり、現在避難活動が行われていますが、全員が一階まで下りて脱出するには時間が足りません! サンデシアは嘆きに包まれています。ファンゼル連邦国務長官ゲルド・ネスマン氏は、「国家としては全く関与していない、この件については我々も非常に心を痛めている」とのことです。引き続きこのニュースについてお伝えします』
何だそれ。全員は助からない?
行き場をなくして逃げ惑う東条さんのファンたちを想うと、それだけで泣きそうになる。東条さんの安否だって分からない。無事に逃げてほしいと願うことしか、僕にはできない。
僕たちのそばにいた女性が金切り声を上げた。
「テロリストは何を考えてるの!? くるたんよ? くるたんがいるのよ!?」
「きっとテレビのない貧困地区の奴らなんだ。そうでもなければ、こんなの有り得ない!」
女性の肩を抱いて、恋人と思わしき男性も憤慨する。
ディスプレイに、実況中継でミレニアムタワーが映し出された。終戦直後に建設が決まり、世歴二〇〇〇年、平和と未来の象徴として造り出された美しい高楼。
それが今、僕の手の届かないところで大量殺戮の舞台になろうとしている。
「見てるだけなんて、こんなのやだっ! せめて東条さんと話ができればいいのに!」
僕は堪らなくなり、半ば泣きの入った声で叫んだ。東条さんを失うかも知れないという恐怖が、僕の心をこれまでにないほど蝕んでいた。
「私の携帯、使いますか?」
藤巻さんが差し出した携帯電話を、反射的に受け取る。
「番号の前に08をつければカデニアにある携帯電話にかけられます。東条さんが現在携帯電話を所持しているかどうかは分かりませんが……」
「ありがと、試してみる」
僕はできるだけ冷静になって電話をかけた。こちらの混乱が向こうに伝わってしまったら、東条さんにも迷惑をかける。
トゥルルルル。トゥルルルル。
コール音が耳に痛い。もし電話がつながらなかったら、そしてもし東条さんがテロに巻き込まれてしまったら、僕は二度と東条さんとしゃべれなくなる。お願い、つながって……!
僕の願いが通じたのか、東条さんは電話に出てくれた。
『もしもし雪菜!?』
「乃木坂だよ」
『乃木坂か、ちょうど声を聞きたいと思ってたんだ。今こっちは大変なことになってて』
「うん、テレビで中継見てる。東条さんはもう避難した?」
『避難するつもりはない』
「ど、どうして」
『みんなが助からなきゃ意味がないだろ! ボクはいま、塔のてっぺんの展望台に向かってる。そこから歌って戦闘機にMPをぶつける。テロリストの気が変われば、みんな助かるんだ』
「そんな、無謀だよ。死んじゃう、やめて!」
『やめてって言うな!』
怒鳴りつけられて、僕は口をつぐむ。
『ほんとうにボクのこと大切に思ってるなら、がんばれって言え!』
この言葉が、僕に大事なことを思い出させてくれた。
そうだ、東条さんは英雄になる人だ。他の人を見捨てて逃げるようなことはしない。だからこそ僕は東条さんのことを慕ってやまないんだ。
「がんばれ! 東条さんならできる! がんばれ――」
僕は力の限り東条さんを応援することに決めた。
***
俺と相棒は、シャデニールの仲間全員の希望を背負って旧式の戦闘機に乗り込んだ。資金のない俺たちにとっては、裏ルートで手に入れたこの戦闘機が唯一の攻撃手段だった。この攻撃が失敗したら、それはシャデニールの敗北を意味する。
――戦争はまだ終わっていない。
それがシャデニールの合言葉だ。
第三次世界大戦が始まった責任は、明らかにカデニアにある。勝敗のつかない不完全燃焼の戦争ではあったが、カデニアは我々に謝罪すべきなのだ。それなのにカデニアは、戦時中に占領したファンゼル連邦の領土を返還しようともしない。全て「終わった」ことにしてやり過ごそうとする。
シャデニールの構成員の大半は、占領された領土を故郷とする者だ。俺もその一人。できることなら、カデニアの謝罪声明と領土復帰の朗報を聞きながら、美味い酒を飲みたかった。だが、行動を起こさぬ限りそれは無理だと悟った。
だから俺と相棒は空を飛ぶ。
たった二つの命でカデニアに間違いを思い知らせてやることができるなら、お安いものだ。
「タワーが見えてきましたよ」
感慨にふけっていると、相棒が目を輝かせて告げた。
第三次世界大戦を経験した俺と違って、彼はまだ若い。自爆テロなんかにつき合わせるのは、正直俺は反対だった。だが、その嬉々とした表情を見て、俺は考えを改める。こいつも祖国のために立ち上がった立派な勇士だ。
「あれ。誰かいます、塔のてっぺんに」
「何だと?」
目を凝らすと、確かに人影がある。……子供?
子供は大きく腕を広げ、そして胸の前で手を組んだ。祈りでも捧げているのだろうか。
どこからか、美しい歌声が聞こえてくる。無論この戦闘機にラジオなどついていない。旋律の流れは子供の動きと一致しているが、この距離で、それも戦闘機越しに人間の声が聞こえるわけがない。ではこの声は何だ。心に直接響いているとでも言うのか。
今まで感じたことのない、表現しがたい情動が押し寄せる。全ての苦しみを洗い流してくれるような、夢にいざなうような歌声が俺たちを包容する。
天使の歌を、俺たちは聴いた。
***
僕は電話をしながら、ずっとディスプレイを見つめていた。そこにはすでに、シャデニールの戦闘機が映し出されていた。
『もう外に出るぞ。ケータイはつけっぱなしにしておくけど、話はいったんやめだ』
「うん」
『……ぜったい帰るから、ボクのがんばりを見てて』
「うん!」
その会話から数秒後、画面がミレニアムタワーの展望台に切り替わり、小さな東条さんの姿が現れた。桜をモチーフにした薄い桃色のドレスに身を包み、僕のご主人様は輝かしいほどの美しさを湛えて人生最大の舞台に降り立った。
レポーターが何か言いかけたが、すぐにやめた。東条さんが澄み切った声で歌い出したからだ。彼女にしては珍しいオペラ調の曲。マイクも使わないのに、物理的制限を超えてカメラのところまで声が届いている。これも女王の『力』だろうか。
戦闘機は止まらなかった。
止まらずにタワーの脇を通り抜け、そのまま空の彼方へと消えていった。
――助かったんだ。東条さんも、ファンのみんなも、戦闘機のパイロットも。
僕の周りにいた視聴者は歓声を上げた。僕は笑いながら泣いた。
『あれは……天使でしょうか?』
のちにこのレポーターの言葉は、東条さんの偉大さを物語る一つの名文句となる。
僕は誇らしかった。
***
最近胡桃が自分の意志を押し通そうとすることが増えたように感じる。
少し前までは、不服そうな顔は見せても、最終的には私の言う通りにしていたのに。
私は胡桃を愛しているということ、私がいなければ胡桃は生きていけないということを、幼い頃から教え聞かせてきた。胡桃は聡い子だから、すぐにそれを理解して「いい子」に育ったと思っていた。
多少の自立は、年齢的に仕方ないと認めてきた。例えば勝手に下僕をつくるなど、そのくらいのことは。しかし今日のことばかりは黙過できない。胡桃は制止する私をMPであしらって、独断で展望台に行ったのだ。結果的に大勢の命を救うことができたが、一歩間違っていたら死んでいた。
やはり乃木坂くんが来てからだ。胡桃が変化を見せたのは。
かぐやの時もそうだった。かぐやの心に純人が入り込みすぎた結果があれだ。最初は微笑ましい友人関係でしかなかったのに、一体いつの間に恋愛関係に移行したと言うのだろう。東条博士によれば胡桃は恋愛をするような精神発達をしていないとのこと。だが、恋愛をしないにしても、乃木坂くんとの生活が彼女の独立を促すものなら?
私自身、乃木坂くんにはつい心を許してしまうところがある。それが同年代の胡桃だったら、どれほど彼に影響されることか。
私は萌えの普及の立役者だ。私がニートだった頃に馬鹿にされていたオタク文化は、正義になった。今や私は誰にも蔑まれることはない。それでもなお感じ続ける、この敗北感はなんだ。純人にかぐやを取られ、今度は乃木坂くんに胡桃を取られてしまうのではないかと、私は怯えている。
胡桃の中に私以上に大きな存在があるなんて、これは危惧すべきことだ。
何とかしなければ……。
***
東条さんから帰国したとの知らせを受けて、僕たちは二十三日の夕方、僕が下僕になったあの体育館裏で待ち合わせをした。
早く東条さんに会いたくて、僕は二十分も前に体育館裏に来てしまった。待つこと二十分。定刻通りに東条さんはやってくる。
昨日の感動はお互い語り尽くしてしまっているので、まず言うべきことはこれだ。
「おかえり、東条さん!」
東条さんはにこにこ顔で僕を見上げた。
「乃木坂、今日はだいじな話があるの」
「うん、何?」
「乃木坂はもういらないよ。きょうをもって下僕リストラ!」
え?
一瞬言葉の意味が分からなくて、僕は首を傾げる。しかしだんだん頭の理解が追いついてきて……。
「ボクは乃木坂がいなくたってさみしくないんだ。だからもういらなーい」
ねえ。
「だってボクはほんとうのヒーローになったんだよ!」
何で二人きりなのに営業ボイスなの?
「MP抜きのボクの勇気を、みーんなほめてくれるんだ。乃木坂の意味なくなっちゃった」
やめてよ。
「いままでありがとーね」
いつもみたいに、ふてぶてしく喋ってよ。
「きょうからボクと乃木坂は赤のタニンです。あんまりボクに近づかないよーに!」
全く未練を感じさせない足取りで、東条さんは僕から離れていく。
――行かないで。
言いたくても言えない。僕には彼女を呼び止める権利がない。
だって、彼女に必要とされない僕は、ただのクタオなんだから。
東条さんの下僕をクビにされたら泣くと、過去の自分は言った。
でも違ったようだ。
本当にクビにされてしまった僕は、胸が痛すぎて、涙も出てこなかった。