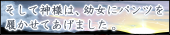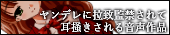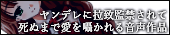第六章 おむすび
僕はクタオらしくクタっと萎れた心で、とぼとぼと帰路についた。
家に帰るなり鞄を放り出して、机の棚の中から適当に抜き出したワークブックで勉強する。精神を安定させるにはこれが一番だ。だが、手が震えて上手に字が書けなくなり、五分くらいでやめてしまった。
僕は無気力に床に身を横たえる。いつもなら布団以外のところで寝転がったりはしないのだが、今日ばかりは布団を敷く気力がなかった。
寂しくなくなったからって、リストラすることないじゃないか。そんな未練がましい思いが募る。東条さんにとって、僕は使い捨ての下僕でしかなかったの? 心がつながっていると思っていたのは僕だけ? ……それじゃあまるで、馬鹿みたいだ。
僕はすっかり自分がカラプロの一員になったように錯覚していたが、結局は部外者だったのだ。僕は藤巻さんのように裏社会に通用する能力を持っているわけでもない。だから、用済みになったら置いておく理由がない。
ああ、僕はとんだ勘違い野郎だ。
自分には東条さんのそばに置いてもらえるだけの価値があると思いこんでいた。彼女は「僕」を下僕にしたんじゃない。MPが効かない人間を下僕にしただけ。そのくらいのこと、本当は分かっていたはずなのに。
悶々と思考のループに陥っていると、家の電話が鳴り出した。耳障りです。今は一人にしてください。そうは思うものの、出ないのも申し訳ないので、物憂い身体を起こして受話器を取った。
『もしもし? 乃木坂愛です。吟ちゃんのお宅でしょうか』
少女のような、ふわふわした声が耳に届く。母だった。
「僕だよ、吟だよ」
『あら吟ちゃん、久しぶり。さっきは間違い電話をかけてしまって、相手の人に怒られちゃったのよ。これからは気をつけなくっちゃ』
母は何も知らないで、いつも通りのほほんとしていた。
僕がいくら苦しもうと、世界は何事もないように回っていく。
母に心配をかけないために、僕は空元気を出して受け答えした。今の自分と過去の自分が重なり、暗澹たる中学生時代を思い出させる。お母さんが笑っていてくれることが、せめてもの救いだ。
『入学してから半月経ったわね。友達はできた?』
……できたよ。主人と下僕って名義だったけど。でも。
『できたのね、よかった。吟は引っ込み思案だから、私も純ちゃんも、心配していたのよ』
友達は、僕の届かないところに行ってしまった。
『高校生活は楽しい?』
本人が孤独じゃないと言うのなら。
『せっかく遠くまで通ってるんですもの、満喫してこないとね』
喜んで祝福しなければならないのに。
『元気そうで何よりだわ』
――どうして僕は喜んであげられないんだ?
人の幸せを喜べないなんて、そんな自分にますます嫌気が差す。
電話が切れてからも、僕はしばらく壁に身を預けてその場を離れなかった。もう何も考えたくない。一人で泣いていたい。けれど涙は出てこない。
四月二十四日、木曜日。くもり。
朝から陰鬱な雰囲気だったが、ルーチンワークは乱さなかった。六時に起きて朝ごはんとお弁当を用意し、七時半に家を出る。ただし、お弁当は手を抜いて塩のおむすびしか作らなかった。
今日の朝はまた栗本さんと二人きりだった。イノセンスに勧誘されたあの日以来、僕は気まずくて彼女とろくに顔を合わせられないでいた。栗本さんの方は、逆にちらちらこちらを見ている。何か言おうとしてためらっているような素振りだったが、僕は気づかぬふりをした。ごめんね。
心の傷が開くと嫌なので、極力無感情でいられるように生活していたら、帰りがけに校門で待っていた藤巻さんに呼び止められた。
「またこんなところで引き留めてしまって申し訳ありません。今日のあなたのご様子が気にかかったので。教室で堂々と話しかけられないのは不便ですね。そろそろ、教室でも交友関係を深めませんか?」
「ああ……うん……」
「やっぱり今日おかしいですよ、乃木坂さん。どうしたんですか」
藤巻さんは僕が下僕をリストラされたことをまだ知らなかった。東条さんもこの件については言い出しづらかったのかも知れない。簡単に説明すると、藤巻さんは信じられないといった風に驚愕の顔を見せた。
「そんな、何かの間違いです! お二人が離れ離れになるなんて。私、東条さんに話を聞いてみます。乃木坂さん、今日はくれぐれも注意して帰ってくださいね。落ち込んでいる時は注意力も散漫になりますから」
僕は藤巻さんに見守られて校門を後にした。
事故にこそ遭わなかったが、途中で雨が降り出したので濡れてしまった。僕の心のようにじめじめとしていて気持ちが悪かった。
四月二十五日、金曜日。雨。
雨の降りしきる校門で、昨日と同じように藤巻さんとお話をした。
「残念ながら、昨日話していただいたことは事実のようです」
藤巻さんは沈痛な面持ちで切り出した。
「それでも私は、乃木坂さんのお役に立つという指針を変えるつもりはありません。今すぐに東条さんを説得することはできないでしょうが、いつかきっと、再びお二人が一緒にいられる日々を取り戻しましょう」
「……ありがとう」
家に帰ってから、初めてカラプロに行った日にもらった東条さんの写真を眺めた。写真の中の東条さんは、僕に微笑みかけている。もうこの笑みは見られないんだと思うと、胸が締めつけられる思いだった。
気を取り直して晩ごはんを作ろうとしたら、台所になめくじがいたので塩をかけた。なめくじは小さかったので、すぐにしぼんでしまった。悲しくなった。いつもだったら絶対殺さないのに。何をやっているんだろう僕は。
四月二十六日、土曜日。晴れ。
家で勉強している最中に、高野さんが壁から現れた。一旦手を止めて身体を彼女の方に向ける。
「こんにちは。今日は東条胡桃のところには行かないの」
「行きませんよ。下僕を解雇されたので」
僕はこともなげに答えた。昨日の夜、僕は現実を受け入れて、もうこのことでうじうじ悩んだりはしないと決めたのだ。
「解雇……。貴方はそれでいいの」
高野さんは一つも表情を動かさずに問う。彼女と話していると、鏡に映し出されたように自分の心が見えてくるのはどうしてだろう。僕は高野さんに答えるというより、自分に言い聞かせるように述懐した。
「いいんです。東条さんはもう僕を必要としていません。僕を必要としていない人に取り縋ろうだなんて、見苦しいじゃないですか。僕と東条さんのつながりは切れてしまったんです」
「では、貴方を必要としない東条胡桃には、会うつもりはないというのね」
「そうです」
「気持ちの悪い依存関係ね」
高野さんは冷徹に言い捨てた。
「それでは東条胡桃自身よりも、東条胡桃に必要とされることが重要ということになるわ。貴方は自分が孤独から救われたいがために彼女の下僕をしていたの?」
指摘されて言葉に詰まる。
最初は、確かにそうだったかも知れない。あの時は東条胡桃というアイドルの存在さえ知ったばかりで、東条さんの人柄なんてほとんど知らなかった。僕が東条さんを支えようと誓ったのは、長年クタオと呼ばれ軽蔑されてきた自分が誰かに必要とされたことが嬉しかったからだ。
「本当に東条胡桃を愛しているなら、不要と言われたからといってあっさり諦められるかしら。貴方は主人がもう救済をもたらす存在ではないと判断して、自ら切り捨てているのではないの? 私には信じられない。吟くんが、切れたつながりを結び直そうとしないことが」
でも、実際に東条さんの下僕として過ごしていくうちに、僕は彼女のひととなりに触れた。そして心から彼女を好きになった。僕は自分の孤独を埋めてくれる人についていこうと思って東条さんの下僕をやっていたんじゃない。かわいそうなアイドルに同情して応援していたのでもない。世界のために頑張る彼女自身の魅力に惹かれて、彼女を支える存在でありたいと思ったんだ。
――僕はただ、友達でありたかったんだ。
「今でも東条さんは僕にとって大切な人なんだって、高野さんのおかげで気づきました。僕を必要としているかどうかは関係なかったんです。東条さんのことが好きだから、僕は彼女の近くにいたかったんです。リストラのショックでそんな単純なことを忘れてました。つながりは、結び直せるでしょうか」
心なしか、高野さんが笑ったように見えた。
「それは貴方次第。彼女に貴方の想いが伝われば、きっと」
役目は終わったと言わんばかりに、高野さんは壁際へと歩いていく。そうだ、高野さんは今でもカタリ様の騎士だ。自分のことを忘れてしまったカタリ様を、もう自分には何も与えてくれないかぐやさんを、人柄だけで愛している。高野さんの想いがかぐやさんに伝わることは、もうない。
僕は後ろから声をかけた。
「ありがとうございました!」
高野さんはわずかに顔が見えるだけ振り返り、また壁の方を向く。
「私は自分の意見を述べただけ」
表情は分からなかったが、何となく、満足げに微笑んでいるような気がした。
四月二十七日、日曜日。晴れ。
今日は神聖アキバ帝国建国の日だ。ネットでは大変な騒ぎになっているんだろうな、などと考えていると、インターホンが鳴った。
「はい」
玄関ドアの覗き穴から来訪者を確認する。黒いスーツを着た長身の男性だ。真っ黒なサングラスをかけているが、精悍な顔つきであることは分かる。誰だこの人。
「ど、どちらさまですか?」
少し気おくれして尋ねると、意外な声が返ってきた。ただし囁き声で。
「あたしよあたし! ミツル! 内緒で来てるから早く中に入れてちょうだい!」
えええええ。信じられない。
「ほんとにミツルさんですか?」
「ホントよ!」
「何で僕の住所知ってるんですか」
「胡桃ちゃんから聞いたのよ」
「じゃあ、一つ質問します。僕が女装した時の名前は?」
「いちょうちゃん!」
どうやら本物らしい。ドアを開けて招き入れると、彼はカツラをはずした。すると勢いよく金髪リーゼントが飛び出してきて、僕の頭上でぶるんぶるんと揺れた。サングラスも黒いものから薄紫のものに取り換え、スーツを脱ぐと下からはピンクのフリルつきブラウスが現れる。仕上げに彼は神速でメイクを施した。そこには見知ったミツルさんが立っていた。
「どう、あたしの変装」
「びっくりしました、さすがです!」
「お仕事してると、身分を隠して移動しなきゃいけない時もあるのよね。だから自分の髪の毛で最高のカツラを作ったわ」
先ほどまで装着していたカツラを自慢げに振る。市販のカツラで満足しないところがミツルさんらしい。
「そうそう、本題に入るわ。胡桃ちゃんがあなたをリストラするなんておかしいと思ったのよ。だから問い詰めたら、泣きながら教えてくれたわ。あれは色川社長に命令されて無理矢理言わされたことだったんですって!」
「……え?」
「だーかーらぁ! ホントはあの子、吟ちゃんをリストラしたくなんかなかったのよ!」
それが本当なら、心臓が爆発するくらい嬉しい。いや、心臓が爆発っていうのは言いすぎかもしれないけど、泣きたくなるくらい嬉しいのは確かだ。
それなのに、あの時心に深い傷を負った僕は、つい疑念を抱いてしまう。
「でも、あの鋭い藤巻さんでさえ、事実だって言ってたのに」
そんな僕の暗い気持ちを吹き飛ばすように、ミツルさんが勢いよく否定してくれた。
「胡桃ちゃんは俳優をもこなすトップアイドルよ。あの子の本気の演技は、雪菜ちゃんでも見破れないわよ。それに、胡桃ちゃんが自分の意思であなたを解雇したって考えるより、強制されたって考えた方がむしろ現実味があるでしょ? 胡桃ちゃんは優しい子だってこと、あなたなら分かってるはず。胡桃ちゃんには、逆らえない理由があったのよ」
ミツルさんはビシッと人差し指を立てて声高に叫ぶ。
「なんと、胡桃ちゃんが吟ちゃんを解雇しないなら、刺客に始末させるって言われたんですって! きっと社長は、あなたと胡桃ちゃんが仲良くなりすぎるのを恐れたのね。先代の歌姫さんの例もあるし。胡桃ちゃんは今でも吟ちゃんと一緒にいたいって思ってるわ。だから行ってあげて!」
「行くって……スタジオローズにですか?」
あの辺りはバスも走っていないし、徒歩で行くには遠すぎるな。でも、東条さんのためなら頑張れる。と思ったら、ミツルさんに突っ込まれた。
「神聖アキバ帝国の建国祝典によ!」
「そんなの開かれるんですか?」
「知らなかったのぉ!? 連日テレビで報道されてるのに」
記憶を辿ると、確かにそんな話があった。
『二十日には建国記念ライブ、建国トージツには祝典が開かれるんだよ!』
その後ノクターンの襲撃があったりして、すっかり頭から抜けていた。
「とにかく、行ってあげなさいよ。場所は秋波原(あきはばら)跡よ。バスに乗ればすぐだから! ああん、あたしそろそろ仕事に戻らなきゃ。じゃあね、吟ちゃんっ!」
あっという間に再変装して慌ただしく部屋を飛び出してくミツルさんを眺めながら、僕は心を躍らせていた。
――僕たちの絆は、まだ結び直せる!
最寄りのバス停から秋波原跡行きのバスに乗ること十五分。
秋波原跡はもともと観光地として有名で、人通りの多い地区だが、今日はことさら人口密度が高い。どこに行けば東条さんがいるのだろう。
『神聖アキバ帝国建国祝典開催! くるたんの路上トークライブはあちら→』
ふと目に入ったポスターに感謝して、矢印に沿って進もうとすると、誰かに突然右腕を掴まれた。
「どこ行くの?」
朗らかな声に振り返れば、小首を傾げる栗本さん。
「もしかして、神聖アキバ帝国の祝典に行くのかな?」
気のせいだろうか、僕の腕を掴む力がいっそう強くなった。一見含みのない笑顔に見えるが、これは絶対怒っている。
「ごめんね、栗本さん。クタオとかオタクとか関係なく、僕は東条さんに会いたいんだ」
僕は栗本さんを振り払って人ごみに紛れてしまおうとした。が、彼女の力はどんどん強くなっていく。何これ、女の子の力とは思えない!
「行かせない。東条胡桃になんか会わせないんだから!」
「うわっ」
怒気をはらんだ声でそう言い放ち、栗本さんは僕の腕を捕えたまま早足で歩き始めた。必然的に、僕は意志に反して彼女についていってしまう。
「痛いよ、離してっ」
いつもは思いやりのある人なのに、栗本さんは振り向いてもくれない。どこか分からない場所へ連れて行かれるのは怖いが、僕には為す術もなかった。彼女の顔が見えないのが余計に不安をそそる。
トークライブ会場から離れれば離れるほど人は減り、ついに僕たちは二人きりになってしまった。お店が立ち並んでいるところを見ると、本来はここも賑わっているのだろう。しかし今日ばかりは、みんな祝典に流れてしまっている。
栗本さんは『メイド喫茶ゆんゆん』という店舗の前で立ち止まった。小さな屋敷のような外観で、CLOSEDと記された木札がかかっている。
「キリエのお母さんはここの店長なの。今日は誰もいないよ」
彼女は裏口に回り、鍵を開け、僕を引っ張りながら中に入っていった。こちら側は栗本家の住宅になっているようで、靴脱ぎ場がある。慌てて靴を脱ぐが、栗本さんはそろえる時間まではくれなかった。歯痒い思いで乱れた靴を見ながら、僕はリビングへ引っ張り込まれていく。
「やっと二人きりになれたね」
やっと僕を放してくれた栗本さんは、柔らかい笑みを浮かべた。
「乃木坂くんは、キリエの気持ちに気づいてるかな? きっと気づいてないよね」
ふうっと深く息を吐き、彼女は艶っぽいまなざしで僕を見つめる。
「八年前から、乃木坂くんのことが好きでした」
「何でそんな前から……」
普通はもっと違った感想を述べるところなのだろうが、ぽろりと出た言葉がそれだった。僕が女の子に告白されているというこの状況も信じがたいが、それ以上に八年前というのが気になってしまった。
「やっぱり覚えてないよね。無理ないよ、小二の時の話だもん。
三年生になる前にお母さんがこのメイド喫茶を創業して、キリエは一緒に引っ越しちゃったけど、小二までは乃木坂くんと同じ岩口県に住んでたの。それも、同じ小学校の、同じクラスにいたんだよ。その時はキリエ、お菓子の食べすぎで太ってたから、見た目じゃ分からないのもしょうがないね」
小二の時の記憶を辿る。しかしその頃の記憶は曖昧で、よく思い出せない。僕が告白されるわけがないという思いが強かったため、冗談や人違いといった可能性ばかりが脳内を巡った。
「転校してからもずっと、キリエは乃木坂くんのことばかり考えてた。次に会う時は可愛い姿を見せたくて、ダイエットもしたよ。おかげで今はみんなから可愛いって言われる。ねえ、乃木坂くんが見ても、キリエは可愛いかな?」
僕は本心のまま答えた。ちょっと恥ずかしかったけど。
「可愛いよ。栗本さんはすごい美人だと思う」
「ほんと!? 嬉しい、乃木坂くんが可愛いって言ってくれた!」
泣きそうな顔で喜ばれると、逆に良心が痛む。僕は栗本さんが思っているような素晴らしい人間ではないのに。
「キリエね、何となく乃木坂くんには近い将来会えるんじゃないかって思ってたの。中学の時やった全国模試って、成績上位者の名前がカタカナで発表されるでしょ? それに毎回満点取って掲載されてる人がいたの。ノギサカギンってね。キリエは家がここだったし、乃木坂くんほどの学力があれば虹高に来るかも知れないなんて甘い夢見ながら、虹高を受験したんだ。そしたらほんとに再会できたんだよ! 毎日一番に登校してたのだって、乃木坂くんとできるだけ早く会いたかったから。それくらい、キリエは乃木坂くんが好きなの」
「何でそんなに僕のこと……」
くすりと笑う様は魅惑的で、普通の男子だったら迷わずつき合ってくださいと言っているところだ。でも僕はまだ、栗本さんに好かれているという事実を認めることができなかった。
「乃木坂くんはキリエのヒーローなんだよ。近寄ると病気になるって言われてたキリエに唯一優しくしてくれたのが、乃木坂くんだったの」
「……!」
思い出した。学級委員長になった年に、僕が手を引いて歩いた女の子のことを。彼女の近くにいた子が貧血を起こすことが数回あって、それ以来彼女はいじめられていたのだ。汚いとか、ばい菌が移るとか、心ない言葉を投げかけられて、その子はいつも泣いていた。
『なかないで。きょうしつにもどろう?』
『やだ、こわいよ』
『じゃあ、ぼくと手をつなごう。いっしょならこわくないよ』
あの怯えた目をした女の子が、溌溂とクラスをまとめ上げるクラス会長になっているなんて。時は人を成長させるんだなあ。
しみじみと過去に思いをはせていると、栗本さんは思いがけないことを口にした。
「でも、いじめっ子たちが言ってたことも真実なの。キリエに触れた人間は生命力を失って、最終的には死に至る」
「そんなことないよ! あれはただの嫌がらせで、栗本さんは病気のもとなんかじゃ――」
「乃木坂くんの気持ちは嬉しいけど、キリエは本当に疫病神なんだよね。ちょっと脅してやったら、お母さんが教えてくれたよ。キリエは造られた人間なんだって。乃木坂くんは東条胡桃の秘書だから知ってるかな? ディーヴァのこと」
何だこの展開。まさか、栗本さんが……?
「……知ってるよ」
「なら話は早いね。キリエは歌姫になれなかった最後のディーヴァ。もともとはキリエのキは木曜日の木じゃなくて、黄色の黄だったんだって。キリエはMPじゃなくて、もっと邪悪で使い道のない超能力を手に入れちゃったの。実は虹高に入学してからも、何人か保健室送りにしてるんだよね。気をつけてても、ちょっとさわるだけでもうダメ」
昼休みに、会話の中心にいながらも微妙な距離を保っていた様子を思い出す。僕はてっきり彼女が隠れクタオだからだと思っていたが、事態はもっと深刻だったんだ。
「実力テストの結果発表の日、乃木坂くんの手を取っても何も起きなかった喜びは、きっと他の人には分からないよ。だって、ちゃんと人に触れたのは八年ぶりだったんだよ? お母さんでさえ、近寄るな、さわらないでって忌み嫌うキリエの身体が受け入れられた、奇跡の瞬間なんだよ。ほんと、泣いちゃいそうだったんだから」
人に触れることを許されない栗本さんの心中は、察するに余りある。東条さんや藤巻さんと違って、栗本さんに備わったのは恒常型の力なのだろう。何十年も力の制御を訓練してきた高野さんでさえ、長い間姿を現していることはできないと言っていた。栗本さんはこれから何年費やせば人と触れ合えるようになるのだろうか。
「じゃあ、僕のことが好きって言うのは、僕しかさわれる人がいないから?」
栗本さんは首を横に振り、切なげに僕を見る。
「それは違うよ。例え乃木坂くんが特別な体質じゃなかったとしても、キリエは乃木坂くんを好きになってた。乃木坂くんは人を救うことのできる人だから。キリエは乃木坂くんの魂に恋をしてるんだよ。
ねぇ、キリエとつき合ってくれないかな。キリエの体は、言ってみれば乃木坂くん専用。浮気なんかできないし、できたとしても絶対しないよ。こんないい女の子、他にはいないと思うけどなぁ」
栗本さんは僕に迫ってくる。でも、駄目だ。栗本さんは僕を過大評価している。僕に執着しているから他の人の良さに気づけなくなっているんだ。
「僕なんか、駄目だよ」
「ダメじゃないよ。どんなに苦しい時だって、死にたくなるような孤独の中でだって、乃木坂くんのことを想うだけで救われたの。乃木坂くんのいるこの世界で、生きていようって思えたの! 乃木坂くんが思ってるよりずっと、キリエは乃木坂くんのことが好きなんだよ。この気持ちに嘘はない」
「うぅ……」
ここまで言われてどうしてつき合ってやらないんだと、誰かが見ていたら怒るかも知れない。しかし僕には、交際を拒否する真っ当な理由があるのだ。
「僕、好きな人いるし……」
途端に栗本さんの顔色が変わった。僕の肩を掴んで、ものすごい剣幕で問い詰める。
「誰!? 雪菜ちゃん? まさか東条胡桃とは言わないよね? 誰、誰なの!?」
「中学校の……先生……」
僕は栗本さんが怖くて震えていた。嫌でもつき合うって言うべきだったのかな? 今の彼女なら怒り狂って僕を殴るかも。藤巻さんと同じくらいの力だったらどうしよう、死んじゃう。先生、僕にご加護を……!
ところが、栗本さんはころっと落ち着いた態度になって、その上軽やかに笑い出した。
「あはっ、なぁんだ。それって子供の小さな初恋だよね。安心したよ」
よかった、怒られなかった。と気を抜いたのも束の間。
「でも、これで乃木坂くんも恋をするってことが分かっちゃったなぁ。どうしよう、うっかりしてると他の子に取られちゃうね。それくらいなら、今のうちにキリエのものにしておかないと」
よく意味は分からなかったが、どことなく危険を感じさせる言葉を口にして、栗本さんは僕の方へ歩み寄ってきた。僕が後ずさりしても、栗本さんは顔を上気させて近づいてくる。妖艶な笑みは僕に恐怖を与えた。
「やっ……来ないで……」
笑ってるけど、やっぱり怒ってるんだ!
恐慌状態に陥った僕の身体は言うことを聞かず、足がもつれて倒れてしまう。手を使って少しでも彼女から離れようとするが、奮闘むなしくすぐに追いつかれてしまった。
栗本さんは僕の腰にまたがって、上半身を押し倒す。
「怖くないよ。むしろ気持ちいいはず」
もう僕に抵抗する気力は残っていなかった。栗本さんの重みがおなかにのしかかって、息が苦しい。肺から空気が漏れる。誰か助けて。
栗本さんは僕の顔を手で優しく挟み込んだ。混乱した僕の思考に、新たな刺激が加わる。
「んっ……」
僕の唇に、栗本さんの唇が押し当てられた。