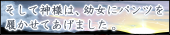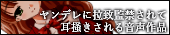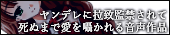卒業論文 日本人の「食」の思想
第二章 殺生と向き合う思想の欠如
第一節 「かわいそう」との出会い
近代まで肉食を忌避していたのにもかかわらず、これほど急速に肉食文化が受容されたのは何故だろうか。それは、日本では殺生の残酷さが問題とされず、ただ穢れるか穢れないかのみが関心の対象であったためと思われる。一度「肉食をしても災いは起きない」ということを知ってしまえば、穢れへの恐怖にも殺生への罪悪感にもとらわれることなく、平然と肉を食べることができたのだ。
岡田哲は、肉食解禁後すぐには庶民の食卓に肉が登場しなかった理由について、「①一二〇〇年にわたり忌避してきた臭い獣肉を、そう簡単には受けいれられない。②高価な西洋料理は、高嶺の花であまり縁がない。③獣肉の調理の仕方がまったくわからない。④獣肉を食べることで、心身がけがれることを恐れた」▼[35] とまとめている。やはり、動物がかわいそうだからという理由での反発は見られない。
そうした状況が作り出されたのは、日本人が動物の死を何とも思わない気質の持ち主だからというわけではなく、殺生について考える機会がなかったためだと考えるべきである。これは牧畜を経験しなかった日本特有の問題だ。
日本人は、獣肉は食べなくても、植物や鳥類魚類は殺して食べていた。しかしそれらは哺乳類ほどには人間に似ておらず、同情を引く程度も低かったと考えられる。また、狩りによって得た獣肉を食べることはあったが、野生動物を狩るのと、育ててきた動物を屠殺するのとでは感じ方が変わってくるだろう。動物の一生を人間の利益のためにコントロールする畜産と違い、狩りは野生動物と人間の勝負の結果動物が負けたというだけなので、「フェア」に感じられる。
仏教の理念により殺生が悪いことであるという認識はあったとしても、牧畜文化圏と比べれば、日本人は動物を殺すことについて何かを考えるという経験に乏しかったと言える。
畜産業が始まってからも、基本的には日本人は動物の死と身近ではなかった。牛鍋屋や洋食店がいくら増えたところで、出される動物はすでに生き物ではなく食べ物に加工された状態であり、客はそれを食べるだけだった。殺生をしているという意識は希薄だったと推察される。
しかし、次第に食べ物が生物の身体であることを意識する者も現れ始めた。日本を代表する菜食主義者である宮沢賢治は、友人の保坂嘉内に宛てた書簡の中で次のように記している。
又屠殺場の紅く染まつた床の上を豚がひきずられて全身あかく血がつきました。転倒した豚の瞳にこの血がパッとあかくはなやかにうつるのでせう。忽然として死がいたり、豚は暗い、しびれのする様な軽さを感じやがてあらたなるかなしいけだものの生を得ました。これらを食べる人とても何とて幸福でありませうや。▼[36]
宮沢は、殺される動物を憐れむと同時に、その肉を食べる人も不幸であると嘆いている。中村はこのことについて、「宮沢らのような富裕な高等農林の生徒が屠殺場に出向き、全身血だらけの豚を見るといった経験は、かつての浄/不浄の二項関係が崩れ出した近代に固有の現象である。近代とは、そういう意味で殺生の現実を剥き出しにし、またそれが肉食と不可分につながっていることを白日のもとにさらけだした時代である」▼[37] と分析している。
宮沢の悲しみは、『よだかの星』『なめとこ山の熊』といった作品からも窺い知ることができる。
屠畜を経験することで、日本人は殺される生物を「かわいそう」だと感じる機会を得た。しかし日本には、その感情に対応できる思想が存在していなかった。
【注意!】
専門家でも何でもない、一介の大学生の卒業論文です。
この論文を「参考文献」にしたり「引用元」にしたりしても、あなたの論文の信頼性を高めることはできません。ご注意ください。
ただ、引用元や参考文献一覧を見れば、参考になる情報が見つかるかも知れません。
論文の内容に関するご質問にはお応えできません。ご了承ください。
|
―― 【 目 次 】 ――
|
|
|
要約
|
|
| 序 | |
| 第一章 | 屠畜を経験しなかった日本 |
| 第一節 肉食禁止令の真意 | |
| 第二節 穢れ観の肥大化 | |
|
|
|
| 第二章 | 殺生と向き合う思想の欠如 |
| 第一節 「かわいそう」との出会い ★現在地 | |
| 第二節 西洋における屠畜の正当化 | |
|
|
|
| 第三章 | 殺生それ自体が残酷であるという意識 |
| 第一節 日本と西洋の動物観の違い | |
| 第二節 菜食主義に「偽善」を感じる日本人 | |
| 第三節 アニミズムと如来蔵思想 | |
|
|
|
| 第四章 | 現代日本人は「食」とどう向き合うか |
| 第一節 無意識の殺生から自覚的な殺生へ | |
| 第二節 人間、動物、植物を同じ次元に置く | |
|
|
|
| 結 | |
| 参考文献 | |
| 謝辞 | |
| 資料1 | ネット上での菜食主義議論 |
| 資料2 | 質疑応答(口頭試問) |