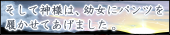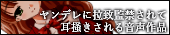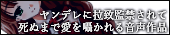卒業論文 日本人の「食」の思想
第三章 殺生それ自体が残酷であるという意識
第一節 日本と西洋の動物観の違い
鯖田は、「「残酷」という言葉の意味・内容が、日本人とヨーロッパ人とではまるでちがう」▼[54] ことを指摘し、次のように述べている。
動物愛護というと、日本人は、ともすれば、動物を人間と同じように扱い、動物を絶対に殺さないことだ、と考えやすい。なかには菜食主義を動物愛護の極致だと主張したりする人もたくさんある。
欧米諸国の動物愛護運動は、そうではない。そこでは動物を殺すこと自体はけっして残酷ではない。残酷なのは不必要な苦痛をあたえることである。▼[55]
動物を殺すこと自体は残酷ではない――日本人には奇妙に聞こえる言葉だが、キリスト教的世界観においては当然のことなのである。何故なら、人間の繁栄のために動植物を利用することは、神から与えられた正当な権利だからだ。動植物にとっては、人間の役に立つことが神から与えられた役目であるとも言える。人間と動物では存在理由が違うということを前提として世界を見る生き方は、日本人とは全く異なっている。
鈴木大拙は、日本人には珍しく人間と動物の役割の違いを論じた人物である。鈴木は1900年に「米国通信(僧侶の肉食に就きて)」を書き、食べられる動物に向けて次のメッセージを送った。
汝、哀れなる鶏(又は魚、何でもよし)よ、汝は吾々人間が生活する権利あるが如く、矢張り生活の権利を有せり。然るに吾々は無残にも汝の特権を蹂躙して今之を胃中に葬らんとするは、決して私欲の故にあらず。思ふに、宇宙は一大神秘の発現にして、吾も汝も皆其の一部を成せり、此の発現を完全にして、少なくとも意識ある生物(即ち人類)の心の上に完全なるものとなして、吾と汝とを悉く至美・至善・至真の郷に遊ばんと務むべきは一切万有の大責任と為す、汝と吾と皆此の責任を遁(のがれ)るべからず。然るに一大神秘は、吾に心を与へ、汝に肉を与へたり。乃ち其の肉を殺して、吾心の犠牲として此の心よりも大なる一大神秘を発表せん、是れ吾の責任なり。則ち汝が殺されて此の卓上にあるは、吾をして真理に至らしめん為め其の犠牲となりたるなり。(中略)汝、決して吾私欲の為めに殺されたりと信ずるなかれ、宇宙の生物皆各自に其の分あり、汝其の分を尽したり、吾亦豈に其の分を遂げざらんや。▼[56]
宇宙の一大神秘は、人間に「真理に至る責任」とそのための「心」を与え、動物に「人間を真理に至らしめるための栄養になる責任」とそのための「肉」を与えた。だから人間が動物を食べることは私欲による不当な搾取ではなく、お互いに自分の義務を果たしているだけなのだと、動物に語りかけている。
この文章について、中村は鈴木が「屠られていく動物たちの〝こころ〟」に呼びかけていることを指摘する▼[57] 。確かに、人間には「心」が、動物には「肉」が(肉のみが)与えられたと主張しているのにもかかわらず、鈴木は何故か動物の「心」を慰めるような物言いをする。本当に動物には「心」がないと思っているなら、慰安の必要はないはずだ。
このことは、日本人には人間と動物を「本質の異なるものである」と認識することは難しいということを示している。渡米して西洋文化に触れていた鈴木でさえ、霊肉両方が備わった人間と知性を持たない動物には別々の役割が与えられているというキリスト教的世界観に馴染めず、内心では動物にも心・霊・魂といったものがあると感じていたのだ。
引用部冒頭には、「お前(動物)は我々人間が生活する権利を持つのと同様に、やはり生活の権利を有している」とあり、人間と動物を平等の生存権を持つものとして扱う態度が見受けられる。さらに、後に続く「けれども我々は無残にもお前の特権を蹂躙し、殺して食べようとする」という懺悔めいた表現からは、鈴木も殺生への罪悪感に苛まれていたことが窺えるのである。
「人間と動物は役割が違う」説は、日本人の食の思想にはなれなかった。
日本とキリスト教圏の動物観の違いを示すエピソードに、日本では欧米と違って進化論が抵抗なく受け入れられたというものがある。明治政府の依頼で東京大学の教授に就任したエドワード・モースは、日本で初めてダーウィンの進化論についての講義を行った時のことを、次のように記している。
一八七七年十月六日、土曜日。今夜私は大学の大広間で、進化論に関する三講の第一講をやった。(中略)聴衆は極めて興味を持ったらしく思われ、そして、米国でよくあったような宗教的の偏見に衝突することなしに、ダーウィンの理論を説明するのは、誠に愉快だった。講演を終った瞬間に、素晴しい、神経質な拍手が起り、私は頬の熱するのを覚えた。日本人の教授の一人が私に、これが日本に於るダーウィン説或は進化論の、最初の講義だといった。私は興味を以て、他の講義の日を待っている。▼[58]
欧米で進化論が受け入れられにくいのは、サル▼[59] が進化してヒトになったとすると、人間は初めから人間として神に創られたという聖書の記述と矛盾してしまうからだ。鯖田は「地動説や進化論が大騒動をひきおこしたのは、結局、それらが、キリスト教のかげにかくれた伝統的な人間中心主義に挑戦するように思われたからである。人間も人間の住む地球も万物の中心でなくなることが、当時のヨーロッパ人に堪え切れなかったところに、真の原因がある」▼[60] と分析している。
一方日本には人間と動物を厳密に区別する思想がなかったので、人間はサルの子孫であると言われても抵抗感を示さなかった。進化論は先進国のありがたい学問として、拍手をもって歓迎された。このことは「差別主義の西洋人と平等主義の日本人」などという対比で見るべきではなく、「人間中心主義になる必要に迫られた西洋人と、その必要に迫られなかった日本人」という対比で見るべきである。
西洋の自然観が「縦の断絶」の構造であるのに対し、日本の自然観は「横のつながり」を有している。それはキリスト教と違い、主義として構築されてきたものではないが、日本人の心に深く浸透している。
日本人が「動物を殺すこと自体が残酷だ」という意識を持っていることは、仏教の不殺生戒の名残りであるというだけでなく、長年人間の命と動物の命を同質のものと捉えてきたことも一因であると思われる。
【注意!】
専門家でも何でもない、一介の大学生の卒業論文です。
この論文を「参考文献」にしたり「引用元」にしたりしても、あなたの論文の信頼性を高めることはできません。ご注意ください。
ただ、引用元や参考文献一覧を見れば、参考になる情報が見つかるかも知れません。
論文の内容に関するご質問にはお応えできません。ご了承ください。
|
―― 【 目 次 】 ――
|
|
|
要約
|
|
| 序 | |
| 第一章 | 屠畜を経験しなかった日本 |
| 第一節 肉食禁止令の真意 | |
| 第二節 穢れ観の肥大化 | |
|
|
|
| 第二章 | 殺生と向き合う思想の欠如 |
| 第一節 「かわいそう」との出会い | |
| 第二節 西洋における屠畜の正当化 | |
|
|
|
| 第三章 | 殺生それ自体が残酷であるという意識 |
| 第一節 日本と西洋の動物観の違い ★現在地 | |
| 第二節 菜食主義に「偽善」を感じる日本人 | |
| 第三節 アニミズムと如来蔵思想 | |
|
|
|
| 第四章 | 現代日本人は「食」とどう向き合うか |
| 第一節 無意識の殺生から自覚的な殺生へ | |
| 第二節 人間、動物、植物を同じ次元に置く | |
|
|
|
| 結 | |
| 参考文献 | |
| 謝辞 | |
| 資料1 | ネット上での菜食主義議論 |
| 資料2 | 質疑応答(口頭試問) |
【脚注】 ▲[番号]をクリックすると元の場所に戻ります。
▲[54] 鯖田豊之『肉食の思想―ヨーロッパ精神の再発見』中央公論新社,1966年,p.55
▲[55] 同上,p.55
▲[56] 鈴木大拙「米国通信(僧侶の肉食に就きて)」『鈴木大拙全集 第二十七巻』岩波書店,1970年,pp.416-417
旧字体は新字体に改めた。
▲[57] 中村生雄『日本人の宗教と動物観―殺生と肉食―』吉川弘文館,2010年,p.39
▲[58] E・S・モース著、石川欣一訳『日本その日その日 2 〔全3巻〕』平凡社,1970年,p.58
「宗教的の偏見」は原文のまま。
▲[59] 現生のサルのことではなく、現生のサルとヒトに共通する祖先のこと。
▲[60] 鯖田豊之『肉食の思想―ヨーロッパ精神の再発見』中央公論新社,1966年,p.67